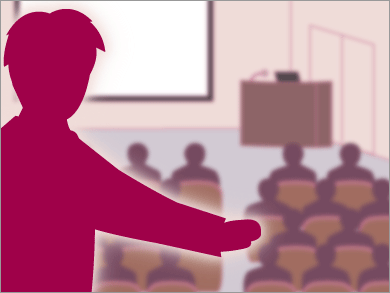メンター:感動のイルカ(1/2 ページ)
安易なコンサル頼みで利益を減らした主人公・猪狩浩の運送会社。経営に悩んだ浩は積極的に経営を学ぼうとするが――。
前回までのあらすじ
ビジネス小説「奇跡の無名人」シリーズ第3弾「感動のイルカ」は、アクティブトランスポートの代表取締役兼CEOである猪股浩行さんの実話に基づく物語である。
取り込み詐欺に遭い会社をリストラされた主人公の猪狩浩(いかり・ひろし)。独立して立ち上げた引っ越し屋は売り上げも順調。信頼できる税理士の助けもあり、社員も増やしてきた。そんな中、従業員の給料を少しでもあげようと安易に経営コンサルタントに依頼する浩。当初は好調だったものの、結果は価格競争に巻き込まれて利益も目減してしまった――。
会社経営に関して、何をしていいのか良く分からなくなってしまった浩は、そもそも自分が経営の勉強をしてこなかったことに思い至った。そこで、経営関係の本を読み漁り、商工会議所のセミナーなどにも積極的に参加するようになった。また、経営に関するメールマガジンなども購読するようになった。
冬になり、暦(こよみ)は2004年に変わっても勉強は続いたが、理屈ばかりが先行したものが多く、今の自分の悩みにしっくりくる内容のものには出会えないでいた。悶々としていたある日、商工会議所から来たファクスの大きな活字が目に付いた。セミナーのタイトルだった。
「感動経営だけが集客を可能にする」
商工会議所のセミナーには食傷気味になっていた浩だったが、このタイトルにはピンと来るものがあり、即刻申し込みをした。
会場は盛況だった。50人が定員の研修室では間に合わず、急遽倍の講演会場に変更したのだが、そこもいっぱいでキャンセル待ちが出たという。講師は、秋田正芳。最近、よく聞くようになった名前だ。『行列ができる会社になる感動と絆の経営』という本が売れているらしい。レジュメのプロフィール欄には、こうあった。
秋田正芳。起業マーケティングコンサルタント。
1945年生まれ。1968年龍命館大学卒。松平電気に入社。38歳のときにマーケティング戦略部の部長に就任。松平電気のマーケティング戦略に大きな改革をもたらす。1995年退職し、株式会社起業戦略研究所を創設。日本を代表するマーケティング理論家として、主に起業家の指導にあたる。「感動と絆の経営」を提唱し、コトラー博士らの欧米流のマーケティング理論に、行動心理学・認知心理学などの見地を付け加え、独自の秋田マーケティング理論を確立した。「あきらめたらあかん、これからおもしろくなる」「みんな生かされているんや」などの名言でも有名。
――正直良く分からない経歴である。なんとなく凄みは伝わってくるが、頭でっかちの人のようにも思えた。浩はあまり期待せずに秋田の話を聞き始めた。
開口一番、秋田はこう言った。「結局、モノを買うのは人や。そして、人は気まぐれなもんやで。自分のことを振り返ればよく分かりますやろう? あなたの買い物に法則性なんかあらへん。でも、いつも買う店ってありますやろ? 今日は、なんでそんなお店であるかというお話をさせてもらいます」
その後、ほかの人なら投げ出してしまいそうな制約条件だらけであるメーカーの日本法人を引き受けたのに、日本のトップシェアにしてしまった社長の話や、ホームレスだったのが現在は某県の県知事を目指している男の話などが続いた。そのすべてが、事業というのは意気に感じて応援しようと思う人が現れないと、絶対に成功しない。では、どうすれば応援してもらえるのかという話であり、およそ経営やマーケティングの話とは思えなかった。しかし、2時間後。浩の目は真っ赤になっていた。
感動という言葉では言い表せなかった。うちのめされた感じだった。うちのめされながらも、豊富な実例――ほとんどがどん底から立ち直った実例――が、浩の心に明かりを灯した。要するに心が揺さぶられたのである。
ああそうか、オレはお客さんのことを忘れていたのか。いや、それどころか、お客のいる現場から離れて、隔絶された奥の院で頭をひねることが経営だと思っていた。オレは、いつだってお客と向き合っていたときにだけ、うまくいっていたのではなかったのか?
社内で「食い逃げコンサル」とあだ名された浅田を雇おうとしたときに、アクティブ運送の関係者がいい顔をしなかった理由がようやく分かった。浩は、経営がうまくいく「正解」があると思い込んでいた。その正解を浅田がもたらしてくれるとも。しかし、そういうことではなかった。要するに自分らしくないことをやろうとしていたので、周囲が敏感に察知したのだろう。
「自分らしく」。これもキーワードだ。知識は重要だが、それに振り回されてはいけない。振り回されるときは、やはり「自分らしく」ないときなのだ。
秋田の話を聞き終わり、これだけのことに気づいた浩は、秋田にぜひ自分の師匠、いわゆる「メンター」になってもらいたいと思った。そこで名刺交換の列にならび、からからになった喉で、ようやくこれだけのことを言った。
「後日、この連絡先に連絡させてもらってもいいでしょうか?」
「ふん。君は本当に悩んでるようやな。面構えもええ。遊びにおいで」
浩は丁寧にお礼を言って、天にも昇る気持ちでその場を去った。
翌日、秘書あてに電話をすると、たまたまキャンセルになった用件があるので、3日後に時間が取れるとのことだった。浩は自分の予定表も見ずに、アポを入れてもらい、その後自分の予定表をチェックした。用事は入っていたが、無事調整できた。
約束の当日。浩は、九段下にある秋田の事務所に向かった。2月の晴れた日だった。興奮で寝不足だった浩の目に陽光が痛かった。浩はできるだけ日陰の中を、はやる胸を押さえて歩いた。小さなビルの4階に秋田の事務所はあった。質素だが清潔そうな建物である。オートロックの扉の外に無人の受付があった。受話器をとって、事務所の部屋番号を押すと、秘書が丁寧なあいさつをした。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 生成AIは検索エンジンではない 当たり前のようで、意識すると変わること
- “脱Windows”が無理なら挑まざるを得ない「Windows 11移行」実践ガイド
- VPNやSSHを狙ったブルートフォース攻撃が増加中 対象となる製品は?
- 大田区役所、2023年に発生したシステム障害の全貌を報告 NECとの和解の経緯
- ランサムウェアに通用しない“名ばかりバックアップ”になっていませんか?
- 標的型メール訓練あるある「全然定着しない」をHENNGEはどう解消するのか?
- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道
- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実
- 「Gemini」でBigQuery、Lookerはどう変わる? 新機能の詳細と利用方法
- PHPやRust、Node.jsなどで引数処理の脆弱性を確認 急ぎ対応を