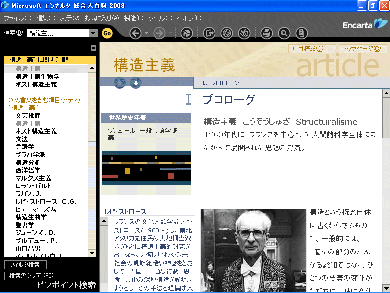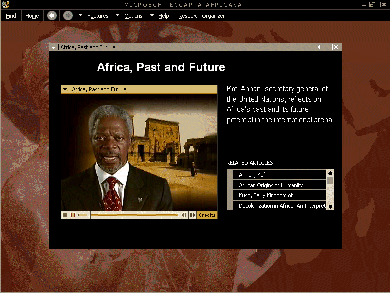| エンタープライズ:レビュー | 2003/06/23 14:58:00 更新 |
マイクロソフトの製品から
Microsoft Encarta総合大百科 2003レビュー (1/2)
マイクロソフトが発売する百科事典ソフトウェア「エンカルタ」は米国で1993年に発売されて以来、現在に至るまで改訂を重ねている。国内でも教育機関の学習用途に用いられているほか、家庭内での利用やビジネス分野でのユーザー数も多い。
最初のコードネームは「ガンダルフ」
マイクロソフトがPCの画面で読む百科事典の開発に着手したのは、1980年代の後半のことだった。誕生したばかりの画期的な記憶媒体「CD-ROM」の大容量と、急速に発達しつつあった「マルチメディア技術」の表現力とを最大限に活用して、来るべきデジタル書籍の市場を席巻し、同社にとっては未開拓の家庭および教育市場に食い込むことが狙いだった。
このプロジェクトには「マーリン」(アーサー王伝説に登場する魔法使いの名)というコードネームが与えられた。しかし、具体的な製品を生み出すことはできなかった。
1990年代に入ると、「マーリン」は新しいプロジェクト・リーダーとスタッフを迎えて刷新された。プロジェクト名も「ガンダルフ」(トールキン作『指輪物語』で活躍する魔法使いの名)に変わった。多くの技術的な困難を克服し、1993年に北米での初版発売にこぎつけた。「Microsoft Encarta」(以下、エンカルタ)の誕生である。「マーリン」と「ガンダルフ」を合わせると、開発期間は約8年。とんでもない難産だった。
マイクロソフトと消費者の双方にとって幸いなことに、エンカルタは成功した。伝統的な印刷物の百科事典と違って毎年改訂を受けるエンカルタは、年を追うごとにフランス語、ドイツ語、イタリア語など他言語へ展開し、1997年度版から日本でも発行を開始した。
だが、オフラインのデジタル書籍市場は、ビル・ゲイツや業界が期待したほどは成長しなかった。原因は複合的だが、インターネットの爆発的な普及が重大な阻害要因だったことは疑うまでもない。CD-ROMに収録された小説、年鑑、絵本、事典や辞典などの中には優れた製品も多くあったが、製品カテゴリー全体は小さく短く輝いてから萎んだ。しかし、エンカルタは生き残った。
何もかもがオンラインを志向するかに見える今日のコンピューティングにあって、このオフラインのデジタル書籍がひとりその質と地位を高め続けることができたのはなぜか。その理由を、最新国内版の「マイクロソフト エンカルタ 総合大百科2003」(以下、エンカルタ2003)の中に探ってみよう。
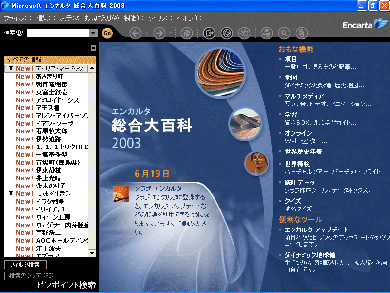
あなどれない日本版の血筋
エンカルタ2003の収録内容をざっと見てみよう。マイクロソフトの発表によれば、項目数は約3万9500点。これに約1万4000点の写真、2600点のイラスト、173点の動画、3000点の音声などを組合わせて、知識に臨場感と娯楽性を加えている。4万弱の項目数を、他の百科事典の項目数(例えば小学館『スーパーニッポニカ日本大百科全書』の13万項目)と比較することはあまり意味がない。解説文の短い百科事典は一般に項目数が多く(小項目主義)、長大な論文を集めた学術的な百科事典は項目数が少ない(大項目主義)。それぞれに良さがあり、数字の大小で内容の優劣は量れない。エンカルタは各項目の解説文が読み応えを感じる程度に長く、しいて言えば「中項目主義」で編まれていると言えよう。PCの画面で読むのに適した文章量とも言える。
マイクロソフトは全項目の約2割にあたる6300項目を追加・改訂したと誇っているが、これにはさほど感心しない。エンカルタ2003には自由国民社の『現代用語の基礎知識』(見たところ2000、2001、2002年度版)を統合して項目を補強しているので、6300という数字には説得力がないからだ。だが、この補強自体は成功で、身近な生活情報や実務的な新語の追加で百科事典の守備範囲を上手に拡張している。
エンカルタの対象読者年齢は、解説文の漢字使いからみると小学校高学年ぐらいが下限だろうか。加藤周一氏を編集長に迎えた平凡社『大百科事典』(のちに『世界大百科事典』)を読み慣れた方には、エンカルタは「ひらがなばかりの百科事典」に感じられるだろう。しかし、解説文の質は現行の国内百科事典の中でも第一級と言える。メニューの片隅に目立たぬよう設けられた「監修/執筆/翻訳者」リストを開けば、各方面で活躍中の国内学者・研究者の名前がずらりと並んでいるのを発見できる。どうやら日本のエンカルタ編集チームは、意図的に昭和30-40年代生まれの気鋭の学者たちを起用しているようだ。師匠や学会に内緒でエンカルタの執筆に加わった人もいるかもしれないから、ここでは具体的な名前を挙げることは差し控える。異業種から越境してきたこの百科事典は、気鋭の学者たちが無記名で寄稿できる、居心地の良い場所なのだろう。解説文の内容は総じて進歩的で、権威臭さがない。
だが、エンカルタを批判する人たちもいる。自然科学、殊に生物学や地理学の方面では安定した評価を得ているが、人文科学の方面では異を唱える声を耳にする。とりわけ、日本の近・現代史に関する記述に対して、扶桑社の『新しい歴史教科書』を支持する人たちが鋭く抗議している。言い換えると、エンカルタの「歴史認識」は、学習教材としては多数派に属す。本稿は個別の問題を論ずる場ではないので深入りを避けるが、百科事典に多様な価値観や見解を止揚する働きを少しだけ期待しても理不尽ではないと思う。
日本版エンカルタは初年度版からからすでに7版を重ね、毎年項目追加と改訂を受けて進化し続けてきたが、残念なことに手つかずで放置されたままの分野がある……衣・食・住関連の、日常生活に密着した情報がとても貧相なのである。「靴」「家」「家族」「料理」といった項目を調べるたびにがっかりする。日本版が生まれてからずっと、企業名、人名、地名、文化や出来事など日本固有の追加と改訂を意欲的に行ってきたのだが、かえって後回しにしてきた手薄な部分が目立ってきた。良い著者とめぐりあえない、読者からの要望がない、予算が足りない、忘れていたなど、理由は単純なのかもしれないが、家庭や学校での利用を重視した百科事典なのだからぜひ一考してもらいたい。
さて、さきほど言及した「エンカルタ編集部」について触れておこう。北米、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアなど、エンカルタを発行する国にはそれぞれエンカルタ編集部が設置されている。これら各国のエンカルタ編集部が毎年一回集まって国際編集会議を持ち、次年度版の編集方針を協議したり内容に関する情報交換をすると聞く。項目の設定や解説文を交換しあったりもするらしい。従って、エンカルタは百科事典の歴史に類を見ない国際編集体制を採用しているとも言えよう。
エンカルタの出発点である「マーリン」は、『Funk and Wagnalls』の大衆的な百科事典を電子データに変換するプロジェクトだった。その血を受け継ぐエンカルタも『Funk and Wagnalls』がベースになってはいるが、各国のエンカルタ編集部が合同で、あるいは国別に行う増補や改訂によって、オリジナルの痕跡を発見することはもはや困難だ。
日本にも、独立した出版社を起業できるほどの、大所帯の編集部が設置されていた。現在の編集部は、人づてに聞いたところでは、以前よりコンパクトになっているそうだ。日本のエンカルタ編集部の中核メンバーは、加藤周一氏が編集長を務めた平凡社『大百科事典』および『世界大百科事典』を編纂した人たちである。例えて言えば、秋葉原の電気街よりも神田神保町の書店街のほうが似合う大ベテランたちであり、日本の百科事典編纂の頂点である。大きく、重く、高価で、数年に一度しか改訂できない印刷物の百科事典ではかなわなかった願いを、彼らはいまビル・ゲイツの技術と資金で徐々に実現しているというわけだ。マイクロソフトの百科事典と聞いて、米国のデータを外注に出して翻訳しているだけと早合点している向きが多いだろうが、意外なことに、日本版エンカルタは我が国の百科事典編纂の血統を継承していると言る。
しかし、日本版エンカルタが平凡社『大百科事典』の直系の後継者と考えるのは短絡過ぎる。平凡社(およびすべての歴史ある百科事典出版社)は自らの思想と信条を持った文化的な集団であるのに対し、マイクロソフトは実用と実利を追求する経済的な集団である。従って、エンカルタには「問題を避けて通る」性質があって、それはエンカルタに収録された情報ではなくて、収録されていない情報に見て取れる。伝統的な出版社はタブーに挑むが、ソフトウェア会社はそれを迂回する。どちらが良いか悪いかではなくて、企業の根本的な成り立ちが違うのだ。百科事典は資金の潤沢な非出版系企業の支援なしでは存続そのものが危ういご時世だから、読者の側が百科事典とのつきあい方を変えるなければならないのかもしれない。
金銭で買えないもの
ここで、少し脱線。1999年、マイクロソフトは北米で「Microsoft Encarta Africana」(以下、エンカルタ・アフリカーナ)を発売した。アフリカ大陸の地理、歴史、文化と、アフリカにルーツを持つ人々を解説する特異な百科事典である。つまり、北米のアフリカ系アメリカ人を主な読者と想定していた。3361の項目、合計2341点の写真や動画や音声、簡潔でわかりやすい6種類の地図などを収録。この初版発行から二年の間に二回の改訂を受け、160冊にも及ぶアフリカ系アメリカ人の著作をまるごと収録した壮大な「Third Edition」にまで発展したのだが、現在はすでにマイクロソフトのカタログから落ちてしまっている。いずれの版も、日本国内では販売されなかった。
エンカルタ・アフリカーナは、ビル・ゲイツが発案したエンカルタと違って、外部からの持ち込み企画だ。最初に「Encyclopedia Africana」を着想したのは、ハーバード大でアフリカ系アメリカ人として初めて博士号を取得した社会学者・活動家のW. E. B. デュ・ボイス(1868-1963)で、それは1909年のことだった。アングロ・サクソンによる人種差別と戦う最も有効な方法は、アフリカを起源とする世界のすべてを網羅した総合的な百科事典を編纂することだと、ある朝突然悟ったとされている。二〜三冊は楽に本を書けるほどの紆余曲折を経て、結局アフリカーナのプロジェクトは頓挫し、彼は移住したガーナで帰らぬ人となった。
だが、デュ・ボイスの企画は彼の死後、ケンブリッジ大(のちにハーバード大へ)の二人の若い学者、ヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアとクワメ・アンソニー・アッピアーが再開した。1969年にエール大でデュ・ボイスの構想を知ったヘンリーは、1973年にケンブリッジでの師匠のウォレ・ショインカ(70年代後半にナイジェリアに帰国、1986年にノーベル文学賞を受賞)と先輩のクワメを誘ってアフリカーナ・プロジェクトを開始したのだ。デュ・ボイスはアフリカーナを人種差別に対抗する武器と考えたが、早い時期からCD-ROM化を前提としていたヘンリーたちは、それをデジタル・ディバイド解消の道具として期待していた。
デュ・ボイスが1909年に着想し、ヘンリー・ルイス・ゲイツ・ジュニアに1969年に取り憑いた「Encyclopedia Africana」のアイデアは、1999年の1月についに「Microsoft Encarta Africana」(以下、エンカルタ・アフリカーナ)として成就した。90年もの間、いずれの大手出版社もできなかったことを最後に実現したのは、文化や思想や言論と縁遠い裕福なソフトウェア屋だったというわけだ。エンカルタ・アフリカーナはアフリカ系読者や教師や牧師たちから歓迎され、北米の貧しいアフリカ系アメリカ人たちが住む地域のコミュニティー・センターに浸透し、不良少年少女たちの更正と自立に少なからず貢献したと聞く。
しかし、誰もがエンカルタ・アフリカーナを賞賛したわけではない。例えばテンプル大教授のモレフィ・ケテ・アサンテは、これを酷評した。「エンカルタ・アフリカーナはデュ・ボイスが目指したものとまったく違う。不充分かつ不正確な記述の寄せ集めにすぎない。」さらに、「音声、動画、バーチャル・ツアーといったインタラクティブな機能はすばらしい。しかし、そうした機能は金銭で買えるものだ。エンカルタ・アフリカーナには金銭で買えないものが欠けている−−正確かつ理性的な視点だ。」とも指弾した。
ここに、百科事典をマイクロソフトのような非出版系企業が出版することのジレンマがある。印刷物の百科事典は市場が枯渇し、伝統的な出版社には経済的な体力がなく、競争力のあるデジタル出版物を開発する技術もない。デジタル技術に長じた異種企業は資金が潤沢で、なおかつ「商品の製造と販売」に長けているものの、百科事典編纂に求められるような高度に文化的な「視点」を持ち合わせていない。モレフィ・ケテ・アサンテがエンカルタ・アフリカーナに感じた不満は、文化と経済の歪んだ関係に起因していると筆者は考える。この問題と、日本版エンカルタ2003は無縁ではない。伝統的な出版の価値観を現代的なIT産業の功利的な価値観で包み込んだために生じるほぐしがたい緊張を、エンカルタ・アフリカーナと同様に、日本版エンカルタ2003はその親しみやすい画面の下に隠しているということを読者は忘れないほうがいい。
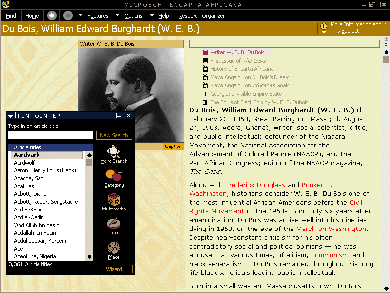
[江河 毅,ITmedia]