IT投資の特徴から見る測定手法の使い方:特集:いまから始めるIT投資効果測定(3)
前回までは、IT投資測定する手法とベンダが提供するサービスを紹介した。しかし、こうした手法を真に活用するためには、その前提としてIT投資の特徴を正確に理解し、それに対する“考え方”を身に付けておく必要がある。測定/評価の限界と、算出された数値をどのように読み取るかについてのスキルがなければ、IT投資評価そのものが無駄な作業になりかねないからだ
情報化投資の本質理解の必要性
このシリーズでは「IT投資」という言葉を使っているが、この回では「情報化投資」という表現を使う。IT投資は「情報化を含むプロジェクト全体」を指しているのに対して、本稿での情報化投資とは「情報システム」に限定したものを指すと解釈していただきたい。
投資の意思決定をするには、費用対効果を明確にすることが重要なのはいうまでもない。でも、なぜ情報化投資がことさらに問題となるのか? 経営状況が低迷している中で、情報化投資費用が増大していることもあろうが、経営者にとって情報化投資が分かりくいことも大きな原因であろう。
では、どうして分かりにくいのか? 経営者にとって最も基本的な情報リテラシーとは、情報化投資の費用や効果に関する知識のはずだ。情報化投資の特徴を理解するには、投資案件の作成や情報化の実施に従事した経験が有効だが、「日経情報ストラテジー」誌によれば、上場企業の3分の2では役員に情報システム部門経験者が1人もいないし、情報システム部門出身のCIOの割合はわずか20%程度だという。経営者は、ホンネでは情報は経営にとって重要だと思っていないのではないか? このような状況では、情報化投資の特徴を理解できないのは当然だ。
経営者が情報化投資の特徴を理解しないと、ことさらに情報化だけに関心を持ち、プロジェクト全体の効果や費用を見失う危険がある。また、数値的に精度の高い費用対効果の明確化を部下(情報システム部門管理者)に要求しがちである。そのために、部下は不毛な努力に時間を費やし、自分でも信じない検討書をでっち上げることになる。
このシリーズでは、前回まで多様な費用対効果測定の方法が紹介してきた。しかし、そこでも指摘されているように、それらの測定方法には限界がありそれで万事解決とはならない。ここでは、これらの方法を活用する前提となる情報化投資の特徴と費用対効果について考察する。
インフラ投資と個別アプリ投資
情報化投資は、インフラ投資と個別アプリ投資に区分できる。インフラ投資とは、1人1台のパソコン配布環境、ネットワークの整備、データベースの整備、標準化の推進、社員の情報リテラシー向上などのための投資である。他方、個別アプリ投資とは、販売システムや経理システムなど特定の業務アプリケーションを構築し運用するための投資である。
1. インフラ投資の重要性
インフラが充実していれば、個別アプリは比較的安価に短時間に構築できるし、関係者のリテラシーも高いので成功する確率も高い。成功して企業収益が増大すれば、その一部をインフラ強化に投資できる。また、ある個別アプリ開発で得たデータやプログラムなどを部品化することにより、インフラがさらに充実する。それが続くほかの個別アプリの投資を容易にする。好スパイラルの状況である。
情報化投資の成功事例といわれる企業の多くは、SIS(Strategic Information System)時代やBPR(Business Process Re-engineering)時代でも成功事例として取り上げられていた企業である。成功が継続しているのは、このような好スパイラルのサイクルを効果的に回しているからだ。逆にいえば、このような好スパイラルにすることが、情報化を成功させる秘けつなのだ。
それに対して、インフラが貧弱な環境では、個別アプリを開発するにはインフラ部分までも投資しなければならない。その費用の壁により投資案件が却下される。承認・実施されても、失敗する危険が多い。それらが続くと、情報化全体が消極的になる。悪スパイラルに落ち込んだのだ。
2. インフラ投資は戦略的判断で
インフラ投資はそれだけでは効果が発生しない。その上に構築される個別アプリが利益を生むのだ。ところがインフラ投資は個別アプリ投資に先行する。その時点で将来どのような個別アプリ投資が行われ、どのような費用や効果があるかを明確にするのは不可能である。
しかも、インフラ投資はハイリスクである。せっかく構築したネットワークとは異なるプロトコルが標準になると、既存環境があるために変更が大変である。インフラ投資がマイナスの結果になる危険もある。
このように、インフラ投資は個別アプリ投資と異なり、多分に戦略的投資なのである。すなわち、経営者が責任を持って決断しなければならない問題なのだ。
3. インフラ投資のタイミング
当然ながら、資金繰りに四苦八苦している経営環境では、ハイリスクであり効果が得られるまで長時間かかるインフラ投資はできない。そもそも、このような状況ではインフラ投資を考えること自体が間違いである。
どんな企業でも好況のときはある。成功企業はそのときにインフラを整備したのだ。この時期に社長室の絵画や銀座のクラブに散財したのでは、どうしようもない。しかし、そうはいってもそのまま放置すれば、悪スパイラルに陥る危険がある。それに、将来になって振り返れば、現在のがまだ余裕がある環境なのかもしれない。その見極めが必要となる。
評価方法の限界
投資の評価には多様な手法がある。それらを個別の投資に単純に適用できないのは、一般の投資でも同様である。しかし、情報化投資ではその限界が顕著に表れる。
1. 採算計算法の限界
ROI法などの採算計算では、現時点での投資額と毎年発生する利益の現在価値累計とを比較することが基本になる。この評価に最も大きな影響を与えるのが耐用年数である。耐用年数が非常に短いならば、よほど利益の高い投資でなければペイしないであろうし、耐用年数が長ければ、多くの投資案は有利になるであろう。
将来が不確実なのはどの投資でも同じであるが、特に情報化投資では耐用年数があまりにも不明確である。ある規模の情報システムでは、企画から実施までに数年かかり、ある程度長期間の利用が期待される。ところが、経営環境は激変するし情報技術の進歩は急速である。開発途中ですでに陳腐化する危険すらある。
情報化の効果は定量的効果だけでなく、定性的・戦略的な効果もある。しかも最近の情報化案件は定性的・戦略的な効果が主であり、定量的効果だけでは採算が取れない性格のものが多い。そのため、このような採算計算を適用する前提としての金額換算が厄介である。
2. 項目列挙法の限界
評価するべき項目を列挙し、それらの重要性に応じてウエートを付け、各項目について期待できる点数を与えて評価する方法を総称して“項目列挙法”ということにする。多くのベンダやコンサルタントが独自の方法を開発しているし、最近注目されているバランスト・スコアカードもこの一種である。
この方法では、定性的・戦略的な効果を評価に加えることができる。しかし、列挙する項目やそのウエート付けや評価に主観が入る。ときによっては、推進派と慎重派がそれぞれの立場を強化するために、自分に都合の良い項目を挙げてウエートを高くすることもある。そのために、この方法も客観的な評価にはならないのである。
そもそもこの方法は、評価するべき項目を多角的に網羅すること、関係者が共通の認識を持ちコンセンサスを得ること、実施結果とのチェックをして改善をしやすくするための方法なのである。そのような目的に優れた方法なのであり、客観的な数値的把握を目的としたものではない。
情報化費用の特徴
効果に比べて費用は比較的把握しやすいが、それでもかなり困難である。経営者に納得させるのに苦労することをいくつか列挙しよう。
1. ハードウェアの費用
1リットルの容器には2リットルの水は入らない。最大速度180km/hの自動車を300km/hで走行させたら故障してしまう。ところが、コンピュータは工夫次第でどうにでもなる。「データ量が急増しています。来年にはコンピュータの限界になります。早急に増強を」との要求を無視しても、たいていの場合は何とかなる。それは、ネックになるデータベースやプログラムに、標準化を無視したマニアックな工夫を施せば、処理能力を数倍数十倍にすることもできるからだ(当然このようなことをしたら、将来の改訂が困難になり、大きなシッペ返しを受ける)。それで経営者は「うまくいくじゃないか。とかく情報システム部門は……」と不信感を募らせる。
パソコンのリプレースも説得しにくい。Windows 95をXPにしたところで、いままでできなかった会計システムができるようになるわけではない。推進派がサポート打ち切りを理由にリプレースを主張すれば、消極派は壊れるまで使えばよいと反論する。価格低下を持ち出せば、来年になればもっと低下するという。これらの理屈は推進派も慎重派も理解しており、立場や都合によりどちらかの意見に傾くだけのことだ。決定的な尺度はないのである。
2. 見えない費用が多い
パソコン1台を運用するための全費用をTCO(Total Cost of Ownership)という。ガートナーグループの調査によれば、パソコン購入時のハードウェアやソフトウェアの費用は、全体の費用の約20%、情報システム部門での管理に関する費用が約30%、利用部門での各種作業の人件費が約50%である。情報化案件での検討時には20%に相当する費用しか計上しないのが通常であろうし、事後の評価でも50%を占める利用部門の費用まで測定するのはかなり困難であろう。
このような見えない費用は、情報システムの開発にもある。開発には利用部門から開発プロジェクトに参加する人もいるし、現状把握や要求定義などでヒアリングを受ける人は多い。それに、情報システムの効果の実現には、業務の改革をするための労力や費用も大きい。計画時にこれらの費用を組み込むことはむしろまれであろう。
3. 情報システムの費用
大規模なERPパッケージなら数億円になるが、同じくERPパッケージと名乗りながら数万円のパソコン用ソフトもある。データ量の違いや機能の違いもあろうが、数億円と数万円ではあまりにも差があり過ぎる。
自社独自のシステム構築では、人月を示されてもどうしてそれだけの労力が掛かるのか理解できないし、プログラムステップ数を示されてもそうなる理由は不明である。ファンクションポイントでもポイント単価は判定のしようがない。 これでは、開発費用が300万円とされても、3000万円とされても判断のしようがない。
自動車を購入する場合ならば、ショールームには実物があり試乗もできる。住宅ならば間取図を先に見せてくれるし、サービスが良ければ模型や3D画像、モデルルームが提供される。ところが情報システムでは事前に見本は提供されない。素人には外部仕様書を見ても実物が連想できない。しかも通常、松・竹・梅のオプションはなく、提案されるのは1案だけであり、出力帳票が10種類なのでそれを5種類にしても、データベースが必要だから費用が半分にはならないという。ではデータベースは導入しないというと、仕様の全面的変更が必要だという。
システム改訂の場合はさらに説明しにくい。西暦2000年問題というのがあった。単に2けたの年を4けたにするだけのために、数年間に数億円も掛かった。そのシステム開発をしたベンダに依頼したのにもかかわらず──である。
4. ベンダとの関係
どうも情報業界の常識は、自社の慣習的常識と異なる。納得できない費用を払わされる。しかも、この費用は目立たないが、社員の日常業務を犠牲にする機会損失は大きな額になる──と考えている経営者は多いはずだ。
- パソコンの利用では、ベンダが自社製品の使い方を教えるのになぜ有料なのか?
- ベンダが自社製品のバグを直すために、なぜ当社が保守料を払い、保守作業をするのか?
- ベンダは「ソリューションを提供します」というのに、なぜわれわれ素人が詳細な提案依頼書を作成しなければならないのか?
- 当社の業務をベンダのSEやコンサルタントに教えるのに、なぜ当社がカネを払うのか?
効果実現の不確実性
投資した効果が実現できるかどうかが不確実なのは、店舗や生産設備への投資でも同様である。しかし、情報化投資では効果実現に影響する要因が一般投資に比べて多いために、なお一層確実性が低い。
1. Many If
情報システムが期待した成果を上げるためには、「情報システムが期待した機能を実現できること」「利用者が期待した操作をすること」「関連する業務が期待したように改革できること」など、多くの条件をクリアする必要がある。情報システムが高度になるほど、条件は多く複雑になり、個々の実現確率が低くなるので、全体としての成功確率はかなり低くなる。ところが、提案時の効果推定にこれらの確率を乗じた期待値で示している事例はまれであろう。
2. 222の法則
現実問題として、情報システムが計画どおりに実現する確率は低い。スタンディッシュ・グループが米国企業を調査したところ、予算内・期限内で完了したのは16.2%にすぎず、計画が途中でキャンセルになったものや失敗になったものは、「情報システム開発では、計画した2倍の費用と2倍の時間がかかり、期待した2分の1の機能しか実現できない」という「2・2・2の法則」に近い数値を示している。
3. 2423の法則
提案時には、期待あるいは作為により物事を安易に考えがちである。情報システムへの要求でもそれがある。
提案依頼書段階でのシステム規模を「2」であるとする。それが実際の要求分析段階になると、見落とされていた条件の発見や便乗的な要求により、「4」の規模に膨れ上がる。追加費用を交渉しても認められず「2」の費用のままである。それで要求の一部を無視して「3」の規模のシステムになる。発注側は「4」の要求が「3」になったことで不満を持ち、ベンダは「2」の費用で「3」を構築させられたことに不満を持つというのだ。
プロジェクトの効果と情報化の効果
ここまで、「情報化の効果」が存在することを前提として話を進めてきた。ところで、情報化の効果とは何なのだろうか? ほとんどの情報化案件は業務改革を含むプロジェクトの一部である。プロジェクトを遂行するには、関係者の説得とか業務の改革などの活動が重要である。それをここでは「非情報系作業」という。実は、この非情報系作業がプロジェクトの費用対効果を左右しているのだ。
1. 非情報系作業の影響
架空の例として、顧客情報活用を目的とした自社クレジットカード発行の情報システムを考えてみよう。
当初は顧客購入動向と職業や年収による分析がマーケティング戦略に効果的であると評価され、そのための情報システム構築も承認された。
情報システムの完成のめどが立つ段階になると、顧客への加入勧誘とカード取扱店への協力要請が本格的に開始される。それが低調だと、母集団が少なく偏りがあるので、分析結果が経験とは相いれないものになってしまう。それで、カード加入数の目標達成が目的になる。年収や職業などのプライバシー情報も要求したのでは加入数が少ないことが指摘され、それらを加入申込書から削除してしまう。取扱店の増加のためには、多様な情報提供サービスが必要だとされる。このような経緯により、当初の目的であった“マーケティング戦略”は忘れられ、情報システムの規模は大きくなり複雑になる……。
このように、非情報系作業の活動が開発するべき情報システムの目的や要求機能に大きく影響を与える。しかも、多くの場合は情報システムの開発が始まってから非情報系作業が着手される。開発途中で目的や要求機能が変化するのだから、開発費用や開発時間が多大になり、当初の機能とはかなり異なったものになる。また、カード開始時期は事前に公表される。相次ぐ仕様変更により情報システムの開発が遅れても、顧客や取扱店への信用のために、実施を遅らせることはできないとの圧力が掛かる。それで、テストが不十分なまま実施に突入しトラブルが発生すると、情報システムが責任を取らされる。
ここでは失敗例を示したが、このように、プロジェクトに与える影響は非情報系作業の方が大きいのだから、初期の目的を実現できたときは、情報システムが成功したというよりも、非情報系作業が成功したことによる成果だと評価するのが妥当である。
2. 情報化の効果とは
プロジェクトの成否に与える情報システムの影響が少ないならば、プロジェクトの効果から期待する利益と非情報系作業に掛かる費用を差し引いた金額内で、非情報系作業からの要求を満たす情報システムが構築できればよいことになる。すなわち、情報化投資は費用だけを考えればよいのだ。
非情報系作業には多くの社員が参加する。上記のような例では、全社員によるカード顧客獲得運動になることすらある。その人件費や関連費用はあまり表に出ない。また、プロジェクトの内容によっては、販売価格や仕入れ条件の譲歩すら伴うこともある。このような見えない費用を洗い出せば、プロジェクト全体の費用のうち非情報系作業が占める割合はかなり高い。そのため、情報システムに与えられる費用は、通常考えられる額よりもかなり低いと考えられる。
ところで、情報化の効果として、情報システムがあるときと手作業で行うときの比較をすることがあるが、これは比較の対象を誤っている。現在、何かをするとき情報システムを使わないことは考えられない。最小限の情報化投資(“梅”のレベル)は費用対効果を問題にするまでもなく不可欠なのだ。
すなわち、情報化投資の費用対効果を検討するのは、その“梅”に追加投資して“竹”や“松”にするかどうかなのである。“梅”から“竹”に機能追加をするための費用と、それによる効果だけを考えればよいのだ。このように問題を整理すれば、情報化投資の費用対効果を測定するのは比較的簡単になる。
3. 混乱の理由と危険
経営者は非情報系作業に関心を持つべきなのだ。しかも、経営者にはプロジェクトの費用対効果の方が情報化投資のそれよりも理解しやすい。それなのに、なぜ「プロジェクトの効果」を「情報化の効果」と混同するのであろうか?
当然ながらベンダにとっては、情報化を提案するには、その情報化によって得られる効果を強調することが効果的である。それで、プロジェクトの効果を意識的に情報化の効果とすり替える。コンサルタント、行政、マスコミその他も大同小異である。これはビジネスなのだから批判するべきではない。
しかし、このような風潮が、「情報化=経営改善=善」という図式を関係者に刷り込んだことによる危険は大きい。そのために、「情報化は重要だ」の命題に疑問を持たなくなる。上記の例では、あえて情報システムにしなくても、顧客のヒアリング調査もあるだろうし、提携カードにすることも考えられるのに、「情報システムを構築する」ことだけが関心の対象になる。プロジェクト計画がいつの間にか情報化計画になり、情報化が手段ではなく目的になる。
経営者は「情報化=情報システム部門」という偏見も持っているので、本来は重要な非情報系作業にも関心を持たなくなる。その結果、プロジェクトが失敗する確率が高くなる。さらに、プロジェクトの失敗は情報化の失敗として情報システム部門をしかる。それで、情報システム部門はリスクを伴う情報化を避けたがる。インフラ投資もいい出さない。悪スパイラルへの入り口である。
精度ではなく正確度が重要
情報化投資について数値的に精度の高い費用対効果を求めて、例えば1億2345万円の利益があると算出したとしよう。しかし、その費用には、ガートナーグループがTCOで示したように「見えない費用」がその4倍掛かっているかもしれない。スタンディッシュ・グループの調査のように、期待どおりに実現する確率は約16%なのかもしれない。費用を4倍し効果を16%にすれば、この数字とはほとんど無関係な結果になる。1億2345万円としようと1億円としようと実質的には何ら違いはない。むしろ、見えない費用をどこまで組み入れたか、成功させるために、どのような対策(費用)を考慮したかという正確度の方が重要なのだ。
当然、「見えない費用」を精度よく見積もることはできない。逆にいえば、それを項目として検討することにより、「見える費用」にするプロセスが重要なのであり、それが「項目列挙法」のメリットでもあるのだ。
また、プロジェクトと情報化の関係で示したように、プロジェクトの費用対効果は非情報系作業を重視して検討するべきなのであり、情報化投資ではせいぜい梅→竹での効果だけであり、大まかには費用だけを考えればよい。
そもそも、経営者が個別アプリでの費用に関心を持つべき理由は2つある。その1つは、情報化投資の適正額の把握である。情報化投資に割ける金額が1億円あるからとはいえ、1000万円でできるものを“超松”の仕様にするのはばかげている。もう1つは、ベンダが過剰な金額を吹っ掛けてきたときのチェックである。
いずれにせよ、これらの目的のためならば、それに必要な見積り金額の精度は頭1桁程度で十分である。細かい数値を要求すると、上述のように担当者が苦労してでっち上げの報告書を作ることになる。「費用対効果を求めるための費用対効果」を考慮すると、細かすぎる精度の要求が正当化できるケースはむしろまれである。しかも、その要求を行う原因が経営者の基本的な情報リテラシーの欠如によるというのでは困る。
T効果測定手法の使い方
「IT投資効果測定」について、一見否定的とも思われる表現になったが、決して各種の測定方法を否定しているのではない。ガートナーグループの調査(2002年)によれば、IT投資効果を測定するための定量的な手法を持っている企業は全体の5%未満であり、測定手法は必要だと考えているが実際の開発検討には至っていない企業が過半数を超えるという結果が得られたという。
これは、少し難しく考え過ぎているのではなかろうか。ここでは、経営者が情報化投資に関してその特徴や基本的な考え方を理解していれば、あまり手法の細かなことにはこだわらずに、測定方法の採用を進めることができることをいいたかったのである。
なお、今回の主張の詳細は、「情報化投資の費用対効果をどう考えるか」にある。参考にしていただければ幸甚である。
(了)
Profile
木暮 仁(こぐれ ひとし)
東京生まれ。東京工業大学卒業。コスモ石油、コスモコンピュータセンター、東京経営短期大学教授を経て、現在フリー。情報関連資格は技術士(情報工学)、中小企業診断士、ITコーディネータ、システム監査、ISMS審査員補など。経営と情報の関係につき、経営側・提供側・利用側からタテマエとホンネの双方からの検討に興味を持ち、執筆、講演、大学非常勤講師などをしている。著書は『教科書 情報と社会』、『情報システム部門再入門』(ともに日科技連出版社)など多数。http://www.kogures.com/hitoshi/にて、大学での授業テキストや講演の内容などを公開している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実
- VPNやSSHを狙ったブルートフォース攻撃が増加中 対象となる製品は?
- 生成AIは検索エンジンではない 当たり前のようで、意識すると変わること
- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道
- ランサムウェアに通用しない“名ばかりバックアップ”になっていませんか?
- 大田区役所、2023年に発生したシステム障害の全貌を報告 NECとの和解の経緯
- 「Gemini」でBigQuery、Lookerはどう変わる? 新機能の詳細と利用方法
- PHPやRust、Node.jsなどで引数処理の脆弱性を確認 急ぎ対応を
- 標的型メール訓練あるある「全然定着しない」をHENNGEはどう解消するのか?
- 攻撃者が日本で最も悪用しているアプリは何か? 最新調査から見えた傾向
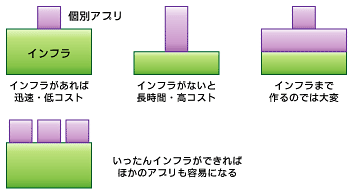 図1 インフラ整備が進んでいれば、個別のアプリ投資も効果的に行うことができる
図1 インフラ整備が進んでいれば、個別のアプリ投資も効果的に行うことができる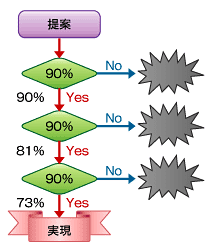 図2 企業の情報化の成功確率はプロジェクトの各フェイズの確率の乗数なので、意外に低くなる
図2 企業の情報化の成功確率はプロジェクトの各フェイズの確率の乗数なので、意外に低くなる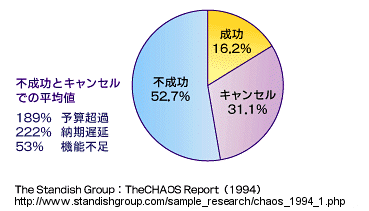 グラフ3 情報システムが予定通り導入される確率は決して高くない(出典:スタンディッシュ・グループ「The CHAOS Report:1994」)
グラフ3 情報システムが予定通り導入される確率は決して高くない(出典:スタンディッシュ・グループ「The CHAOS Report:1994」)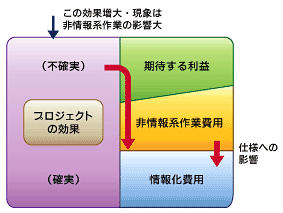 図4 非情報系の作業の費用は表に出にくいため、忘れられがちだ
図4 非情報系の作業の費用は表に出にくいため、忘れられがちだ


