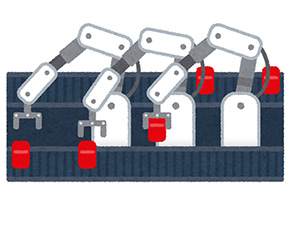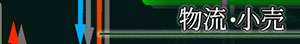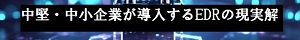「一度開発して10年塩漬け」は過去の話に アジャイルを加速させる「超高速開発」:本当はうさんくさくない、超高速開発のリアル(1/4 ページ)
AIや自動化の急速な進展とともに、超高速開発は最適な手法として利用が拡大し、2〜3年後には普及期に入ると予想できます。そのとき、SIerの在り方やSEの仕事はどう変わるのでしょうか?
超高速開発の「リアル」を解説する連載の第3回は、ジャスミンソフトの贄が担当します。私は「超高速開発」が当たり前になるであろう数年後の姿を描いてみたいと思います。
- 第1回 超高速開発の概要 (ルート42 高橋一成)
- 第2回 超高速開発のケーススタディー (SCSK 堀井大砂)
- 【本記事】第3回 超高速開発の最近の動きと展望 (ジャスミンソフト 贄良則)
2020年頃、超高速開発は本格的な普及期に
急激に社会に浸透しつつあるAIへの投資は今、「自動化」という大きな流れを作っています。
英国で最初の産業革命が起こってから200年近くが経過し、その間、私たちの社会は「機械化」による文明を享受してきました。これはどちらかというと、ハードウェア寄りの視点です。
今、起こっている自動化の波は、ソフトウェア寄りの視点といえるでしょう。この流れはもはや止めることはできず、これまでの機械化とは全く異なるスピードで加速度的に進んでいます。
その理由は、世界中の頭脳が集まってプログラミングに集中できる環境があること、そしてその知識と経験がインターネットによって瞬時に共有されるため、かつてないほど進化のプロセスが効率化されていること、それを支えるためのインフラストラクチャ(クラウド環境など)も日々、強化されていることにあります。
この記事のテーマである超高速開発は、この流れに乗っている技術です。もう、エンタープライズアプリケーション開発を「人海戦術で乗り切る」という発想では、昨今の急激な変化にはついていけません。
超高速開発が普及するとともに、この開発スピードが当たり前になり、超高速開発というキーワードそのものが死語になります。それが、「あと何年後か」と問われると答えるのが難しいですが、私見では2020年には本格的な普及期に入っていると予想しています。本記事の執筆時点から数えると、おおむね3年後です。この根拠を次に説明します。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
人気記事ランキング
- 生成AIは検索エンジンではない 当たり前のようで、意識すると変わること
- VPNやSSHを狙ったブルートフォース攻撃が増加中 対象となる製品は?
- 大田区役所、2023年に発生したシステム障害の全貌を報告 NECとの和解の経緯
- ランサムウェアに通用しない“名ばかりバックアップ”になっていませんか?
- 標的型メール訓練あるある「全然定着しない」をHENNGEはどう解消するのか?
- “脱Windows”が無理なら挑まざるを得ない「Windows 11移行」実践ガイド
- HOYAに1000万ドル要求か サイバー犯罪グループの関与を仏メディアが報道
- 「Gemini」でBigQuery、Lookerはどう変わる? 新機能の詳細と利用方法
- 爆売れだった「ノートPC」が早くも旧世代の現実
- 攻撃者が日本で最も悪用しているアプリは何か? 最新調査から見えた傾向