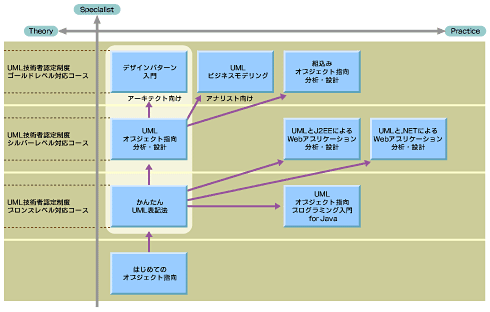オブジェクト指向開発の実践トレーニングはどこで受けられるのか? どのような講義、そしてトレーニングがあるのか? 今回のレポートでは、オージス総研、日本ラショナルソフトウェア、豆蔵、富士通ラーニングメディア、テクノロジックアートといったオブジェクト指向開発の学習、トレーニングで有名な企業のコース内容を紹介するとともに、トレーニングの現場から見た受講者の状況などを報告する。
【オージス総研】
初心者向けとして最適の講義内容が充実
オージス総研では、同社が制定したUMLの認定制度「UML技術者認定制度」に対応したトレーニングコースを提供している。「UML技術者認定制度」は、現在ブロンズ、シルバー、ゴールドの3資格があり、各トレーニングも対応した認定資格試験の合格を視野に入れた内容になっている。
オージス総研 eソリューション事業部 オブジェクトテクノロジー・ソリューション部 マネージャー 竹政昭利氏によると、認定資格の各レベルは「ブロンズはUMLの基本的な記述法をマスターするレベル。シルバーは記述法を活用して、オブジェクト指向の分析・設計などが行えるレベル。ゴールドはアーキテクトやアナリストなど上位の役職者に対応し、事業分野に特化したUMLの活用を方法論も絡めて適用できるレベル」ということになる。
トレーニングコースは、オブジェクト指向開発において、受講者がどのようなキャリアパスを描いているのかによって違ってくる。例えば、WebアプリケーションをJava言語で開発しようとする受講者の場合、入門編として「はじめてのオブジェクト指向」を受講した後、「かんたんUML表記法」「UMLオブジェクト指向プログラミング入門 for Java」「UMLオブジェクト指向分析・設計」「UMLとJ2EEによるWebアプリケーション分析・設計」の受講といったコースをたどることになるだろう。
ブロンズレベルあるいはシルバーレベルに対応したコースでは、UMLの表記法と分析・設計、プログラミング言語のマッピングが主な習得事項になる。開発全体を視野に入れた開発方法論の応用など、プロジェクトマネージャ的なスキルの育成はゴールドレベル以上のコースで行われるが、現在同社ではゴールド、さらにプラチナレベルのトレーニングプログラムの拡充・新設を急いでいる段階である。全体的に見て、初級から中級クラスのエンジニアがオブジェクト指向開発のスキルを磨く場として適しているだろう。
また同社では、これらのトレーニングを徐々にWBT(Web Based Training)へ移行させる計画もある。
【コラム:UML技術者認定制度】
UML技術者認定制度が開始されたのは1998年9月21日。同制度の認定機関であるオージス総研のeソリューション事業部 オブジェクトテクノロジー・ソリューション部 マネージャー 竹政昭利氏は当時を振り返り、「知名度はほとんどなかった」ともらす。同制度の立ち上げは、国内におけるUMLの普及を促す半ばボランティア的な活動意図から出発した。
一方、OMGでも世界各国統一のUML認定制度の設立に向けて動きをみせている。ただ、「現在は企業からの出資を募っている最中だと聞いているが、具体的にどのような活動をしているのかはわからない」(竹政氏)のが実情のようだ。つまり、現時点では、UML技術者認定制度が「世界で唯一のUML認定制度ということになる」(竹政氏)。
2002年10月現在公開されているUML技術者認定制度の認定レベルは、ブロンズレベル試験、シルバーレベル試験、ゴールドレベル試験の3レベルのみ。ブロンズレベル試験は初心者向けで、UMLモデルの表記法の意味や基本的な使い方を理解できるレベルをクリアしていれば合格が可能だ。このレベルであれば、書籍のみの独自学習でも認定資格を獲得できるだろう。
ただし、シルバーレベル試験以上となると、「実践の経験が必要となってくるかもしれない」(竹政氏)という。シルバーレベル試験では、開発グループの一員として、分析・設計を行う知識があり、UMLを使って自分でモデリングを行えるという能力が問われる。さらにゴールドレベル試験となると、オブジェクト指向技術の専門特化した分野のスキルを持っていることが求められる。位置付けとして、シルバーレベルとゴールドレベルに、大きな較差はないというのが竹政氏の見解である。つまり、知識レベルの深さや業務経験の豊富さにおいて、両レベルに大きな違いはみられず、その性質が異なるということである。シルバーレベルがジェネラリストを目指すとすれば、ゴールドレベルは専門領域のモデリングスキルに特化している。実際、ゴールドレベル試験で現在行われているのはアーキテクト向けのデザインパターン入門だが、今後、アナリスト向けとして、UMLビジネスモデリングや組み込みオブジェクト指向分析・設計など、さまざまな分野が拡張される予定である。
そして、シルバー、ゴールドより上級のプラチナレベル試験は準備段階にある。プラチナレベル試験の合格者には、UMLに関する知識とUMLを使った実際のモデリング業務の経験が必要で、さらにコンサルテーションの役割を担うことができる人材を想定している。ゴールドレベルまではWeb上の無料試験という形式をとっているが、プラチナレベル試験に関しては、「資格としての権威的な問題や試験内容の高度化を考えると、Web上で行うのは難しいかもしれない」(竹政氏)。またプラチナレベル試験では、有料化も検討されている。
UML技術者認定制度
http://www.ogis-uml-university.com/
【日本ラショナルソフトウェア】
RUPの全体像を押さえ、具体的なツールの活用法を学ぶ
日本ラショナルソフトウェアが提供するオブジェクト指向開発トレーニングの総称は「ラショナルユニバーシティトレーニングコース」である。その全体像は、大きく、「UML」「RUP」「ClearCase」「Rose」「RoseRT」「RationalSuite」「TestStudio」「AnalystStudio」「ClearQuest」のコースウェアに分割され、それぞれのコースウェアごとに、細かくコースが設定されている。例えば、「UML」では「ユースケースを用いた要求管理」「UMLに基づくオブジェクト指向分析設計実践」「オブジェクト指向入門」である。
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
同社は、オブジェクト指向開発方法論「RUP」(Rational Unified Process)の提唱企業であり、ビジュアルモデリングツール「RationalRose」のベンダでもあるから、トレーニングコースは必然的に、RUPに則した開発の流れで行われることになる。また、同社が提供するツールの実践的な使用方法にも、トレーニングの主眼が置かれることになる。
「ラショナルユニバーシティの受講者の内訳は、昨年末から今年にかけて大きく様変わりしている」と同社テクニカルコンサルティンググループ/ITチーム ソフトウェアエンジニアリングスペシャリスト 安竹由紀夫氏は言う。オブジェクト指向開発の初心者が急激に増加したのである。安竹氏はこのような状況について「受講者が増加すること自体に問題はない」としながらも「UMLの記述法だけを学びに来るのはあまり意味があることとは思えないし、できれば現場のエンジニアであっても、開発工程全体の流れを知っておくことは必要だと思う」と手厳しいコメントをしている。
UMLはあくまでモデリング言語にすぎないことはいうまでもない。オブジェクト指向開発の入り口にUMLの理解があることは確かであるが、安竹氏は「すべての受講者にまずは、RUPのオーバービューを受講してもらい、そのうえで、自分のキャリアパスに合ったコースを選択するのが望ましい」とアドバイスする。必ずしもRUPに限定されることではないが、UMLは開発方法論なくして機能しないともいえる。
なお、ラショナルユニバーシティは、ボーランド、NTTコムウェア、富士通ラーニングメディアなど多くの企業にOEMで提供されている。
【豆蔵】
オンサイトトレーニングの繰り返しで社内メンターを育成する
豆蔵の教育サービスは、定例コースと豆蔵仮想プロジェクトの2本柱で構成されている。このうち、定例コースは「オブジェクト指向言語Java入門コース」「オブジェクト指向入門 9Daysコース」「UMLモデリング入門コース」などの目的別総合セットコースと「オブジェクト指向オリエンテーション」「Javaによるオブジェクト指向設計実装入門」「UMLによるモデリング入門」といった目的別の単体コースに分かれて提供されている。しかし同社教育ソリューション事業部 コンサルタントの安田早苗氏によれば「受講はほぼ企業単位で、その多くは各カリキュラムを組み合わせ、カスタマイズしたオンサイトトレーニングを望む」という状況のようだ。カリキュラムを見ても分かるように、基本的にはオブジェクト指向開発の入門者向けの内容となっている。
*** 一部省略されたコンテンツがあります。PC版でご覧ください。 ***
定例コースをカスタマイズしたオンサイトトレーニングでは、顧客企業内に事務局を設置し、事務局を通して、教育サービスを提供するという形を取る。事務局の担当者は、豆蔵の教育サービスを受ければ受けるほど、スキルが上がっていく。つまり、顧客企業内でメンターを育成することにつながるため、受講者が毎回変わったとしても、社内メンターの実力が向上することで、教育効率は上がっていくという経験則がある。
もっとも、このことは受講者のレベルが均一に近い場合に効果を発揮するものであり、受講者のレベルがバラバラの場合、教育効率は著しく落ちていく。豆蔵でも日本ラショナルソフトウェア同様、昨年から今年にかけて受講者の質の変化が感じられるとしており、顧客企業内で増加したオブジェクト指向開発初心者と中級、上級者が混在する環境で、企業研修という形式でオンサイトトレーニングが行われるケースが多くなってきた。
そこで、同社では今後、オンサイトでトレーニングを行う場合、受講者の習熟度を測る仕組みを導入し、できるだけ均一のスキルと知識を持つ受講者に教育サービスを提供する体系を構築していく予定である。またこれに合わせて、コースの見直しも行い、実装寄りのコース、アーキテクト向けのコースなど、オブジェクト指向でシステム開発を行ううえでの目的別コースの厳密化を目指そうとしている。
豆蔵のトレーニングコースは、ラショナルと同様、多くの企業にOEMとして提供される。オブジェクト指向開発のノウハウに関して同社のソフトウェア開発業界に対する影響力は大きい。
同社の教育サービス2本柱の一方である「豆蔵仮想プロジェクト」は、業務ドメインに特化したシステムテーマを課題として設定し、仮想的な実践プロジェクトを体験しながら、実践的なスキルを身に付けるものである。期間は1〜3カ月間となっている。
【富士通ラーニングメディア】
eラーニングでオブジェクト指向を学ぶ
富士通ラーニングメディアでは、20種以上のIT研修コースの中に、アプリケーションシステムの企画・分析・基本設計を行う人材のための育成コースである「アプリケーション開発技術」を設けている。オブジェクト指向開発関連の研修項目は、このコースに含まれている。
オブジェクト指向カテゴリの各コースは、初級、中級、上級のレベルに分割されている。受講前には受講に必須となる前提知識の習得が不可欠だが、その知識学習も同社ではサポートする。
初級レベルでは、「オブジェクト指向入門」コース、中級クラスで、「UML〜表記法の習得〜」「C++によるオブジェクト指向プログラミング」などのコースで知識ベースの基礎固めをし、「オブジェクト指向技術:分析・設計基礎編」「UMLによるオブジェクト指向分析設計演習〜実践的開発技法とプロジェクト管理〜」で実践の基礎を築く。そして、上級レベルの「オブジェクト指向技術:デザインパターン/Java編」「オブジェクト指向技術:分析演習編」で実務経験に近い学習を行うことになる。
同社のオブジェクト指向学習コースは、その他にラショナルのラショナルユニバーシティも提供している。アカデミックコースとプロダクトコースの2つのコースの流れがある。
ラショナルアカデミックコースでは、「ラショナル社によるオブジェクト指向入門」から「UMLに基づくオブジェクト指向分析設計実践」「ユースケースを用いた要求管理」「ラショナル統一プロセス入門」「ラショナル統一プロセスの実装」「反復型開発のプロジェクト管理」と、オブジェクト指向開発の実践を系統立てたプログラムで学習することができる。
ラショナルプロダクトコースでは、ClearCase、Rational Roseを用いた実践コースを用意している。
講習会方式の学習以外に、同社ではeラーニングによるメニューを用意している。eラーニングコースには、「オブジェクト指向入門」「UML入門〜表記法の習得〜Part1」「UML入門〜表記法の習得〜Part2」など、知識ベースの学習が主流である。標準的な学習期間は約4時間に設定されている。ブロードバンドを利用した音声ナビゲーションによる学習コースである。
【テクノロジックアート】
エクストリーム・プログラミングの実践トレーニング
テクノロジックアートが提供するオブジェクト指向開発トレーニングは、「オブジェクト指向」と「エクストリーム・プログラミング」の2つのコースに大別される。エクストリーム・プログラミングの実践トレーニングを行っている企業は現段階ではまだ珍しい。
各コースはセミナー形式の講習を終えた後、トレーニングを行うという形式である。オブジェクト指向コースでは、「オブジェクト指向セミナー」や「管理者のためのオブジェクト指向セミナー」を受講した後、「コンポーネント開発実践トレーニング」「デザインパターン入門セミナー」を受講することになる。「コンポーネント開発実践トレーニング」では、カタリシス手法によるコンポーネントベース開発のメリットとUML表記法を解説していく。その後、同社のUMLモデリングツール「Pattern Weaver」を用いて、コンポーネントベースの開発を実践する。
エクストリーム・プログラミングコースは、「XP入門セミナー」受講の後、「XP TDD(テスト駆動開発)トレーニング」「XPリファクタリングトレーニング」を受講する。「XP入門セミナー」では、XPを適用したプロジェクト事例を元に、XPの概要の理解をうながす。「XP TDD(テスト駆動開発)トレーニング」は、ケント・ベック氏が作成したテキストを用いて、実践形式で学習を行うというもの。9月には実際に講師として、ケント・ベック氏自身が来日した。使用言語はJavaである。
オージス総研、日本ラショナルソフトウェア、豆蔵、富士通ラーニングメディア、テクノロジックアートの5社のオブジェクト指向トレーニングサービスを紹介した。各社それぞれに特徴はあるが、オブジェクト指向開発スキルの向上という目標は同じである。書籍だけでは身に付かない実践的なスキルを獲得するために、これらのトレーニングを活用してみるのはどうだろう。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.