「2025年の崖」は目前に 全社規模の変革を支えるために、IT部門はどうやって「システムの目利き役」になる?
レガシーなITシステムの刷新や、IT人材確保を喫緊の課題とした「2025年の崖」問題。経済産業省が2018年9月に『DXレポート』でこの問題を指摘して以来、あらゆる企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)に取り組んできた。
特にコロナ禍はITの意義を強く印象付け、DXの機運がさらに高まる出来事だった。しかし今でも、局所的なアナログ業務をデジタル化するだけの「デジタイゼーション」にとどまり、ビジネスの仕組みを変革する「デジタライゼーション」に至った企業は少ない。IT部門も既存システムの維持に多大なコスト、工数を割いており、変革につながる新たな取り組みには及び腰だ。だが「ニーズに応えるスピードと品質」が差別化要素となっている今、デジタルの力を有効に生かしていかなければ競争力は低下していくことになる。
では、デジタルを軸とした全社規模の変革に向けて、今、IT部門には何が求められているのか。インテル執行役員の上野晶子氏と、アイティメディア DX編集統括部 統括編集長の内野宏信が、“2025年以降”に向けて語り合った。
あれからどうなった? 「2025年の崖」問題の今
上野氏: 「2025年の崖」問題とDXを取り巻く状況を見ていると、2011年の東日本大震災直後に事業継続計画(BCP)の重要性が叫ばれたものの、その勢いが徐々に弱っていったのと似ているように感じます。昔も今も目先のITツール導入が優先されがちで、IT部門はインフラ管理に軸足を置いたままです。生成AIが登場して働き方とビジネスが大きく変化する可能性が見えてきた今こそ、IT部門の活躍が経営でも重要な意味を持つはずです。
内野: 背景にはよく指摘される「経営とITの分断」があると思います。IT部門がビジネス目的を十分に理解できていない、あるいは伝わっていないために、喫緊の対応やコスト削減などが第一義になってしまいがちなのですよね。
上野氏: 日本の場合、経営層もIT部門自身も「IT部門はコストセンター」だと見なしがちですね。IT部門に求められる役割はインフラ管理だけで、IT投資戦略は経営企画部のような別部門が担うケースが見られます。CIO(最高情報責任者)やCTO(最高技術責任者)が「いかに利益を生み出すか」を考えてIT投資の責任を負う海外の企業とは、この点が違います。
日本ではデバイス管理をアウトソースすることが多いという点も、意外に無視できない要因です。デバイスの利用状況から得られる知見や、管理業務に伴うノウハウが社内にたまらず、これらのデータを経営に生かせないという組織的な問題もあるように思います。
生成AI時代、IT部門はどうやって「システムの目利き役」になるのか
内野: やはり、IT部門が主体的に事業に関わる、事業に溶け込む体制の実現こそ喫緊の課題だと思いますね。その点、ツールの使われ方、すなわち社内のエンドユーザーのニーズは良い手掛かりになるのに、活用しきれていないというのももったいない話です。ただし昨今は生成AIの急速な浸透を受けて、経営層から現場層までデジタルに対する意識があらためて高まっています。これをどう変革に向けて巻き込んでいくか、リードしていくかが重要になるはずです。
上野氏: 同感です。そういう意味で、生成AIの登場はちょうどいいタイミングでした。インターネットが登場した時もさまざまな議論が巻き起こり、その後は予想もしないビジネスモデルが次々と生まれました。生成AIについてもそのような“変革の瞬間”を見逃さないことが大事だと思います。
内野: 実際、新しい技術が登場した時、身近に使いやすい環境があると発展が速いですよね。その意味では、社内で変革を起こすためには、生成AIをはじめ各種テクノロジーをいかに使いやすい形で提供するかが鍵になると思います。ちなみに「ITIL 4」では、IT部門の重要な役割はITのマネジメントではなく「ITサービスの提供」だという点が強調されており注目を集めています。これからのIT部門は「これが業務に役立ちますよ」とツールの目利きをしたり、サーバなどの安定運用にとどまらず、その上で動いている「ツールが快適、安全に使えているか」を監視したりする“サービスプロバイダー”としての視点を持つ必要があると思います。
DX推進に向けてインテルが支援できること
上野氏: そのお話は面白いですね。IT部門をサービスプロバイダーと定義すれば、おのずとサービス品質の維持と向上に向けて投資を続けるという考え方になりますよね。
内野: そうですよね。ビジネスを後押しするために、利便性とコストのバランスを考えながら主体的に手段を選び、提供する役割が求められていると思います。
上野氏: そこは当社としても同感ですし、IT部門には勇気を持って一歩踏み出していただきたいところです。内野さんは、どうすればIT部門が変わると思いますか。
内野: まずは現状の負荷を下げることが重要ではないでしょうか。アイティメディアの読者調査でも「人的リソースが足りない」「インフラが複雑化して安定運用に工数がかかる」などが例年課題として挙がります。背景には人手作業を軸とした非効率なプロセスと属人化の問題があります。運用プロセスを棚卸しした上で標準化と自動化を進め、単なる保守業務からIT部門を解放することが鍵となるでしょう。余裕を生み出した上で、IT部門内の効率化からステークホルダーの満足度へと視野を広げていく。特にDXはトップダウンだけではなくボトムアップも重要ですから、全社を巻き込んでいくという面ではPCという業務環境の整備、運用効率もポイントになるでしょうね。
上野氏: PCにおいては、業務を停止させない安定性が極めて重要です。そして、IT部門の運用の手間を減らすこと、エンドユーザーの生産性向上に寄与するパフォーマンス、強固なセキュリティも大事です。これらは統合型プラットフォーム「Intel vPro® プラットフォーム」(以下、vPro®)の強みですが、そもそもIT部門にこれらの技術を使いこなせる人が不足しがちなのは当社としても悩みどころです。どうすればもっと楽になれるか、使いこなしてもらえるかと常に考えています。生成AIの普及がこうした課題を改善する良いきっかけになってほしいと願っています。
内野: 実際、生成AIは「属人性の解消」という用途も大いに期待されていますしね。一方、事業部門にとっては生成AIを安定的かつ安全に使える環境が望まれます。その点、vPro®はIT部門の負荷を低減しながら、さまざまな場所で働く従業員の業務環境を守る一助になりますし、「インテル® Xeon® 6 プロセッサー」は生成AIをはじめ各種ワークロードに最適なインフラを整備する武器になります。さらに「インテル® Core™ Ultraプロセッサー」を搭載したAI PCを使えば生成AIはぐっと身近になる。これだけ手段が充実しているわけですから、IT部門の選び方、振る舞い方次第で、前述したインターネット黎明(れいめい)期のような「活発な議論や発展」を各社が起こすチャンスはあると思うのですよね。
上野氏: ただ、AIに関しては活用が期待される一方で、2025年以降、IT投資の考え方に変化が起きると予想しています。現状は「お金をかければかけるほど、すてきなことができそう」というイメージが先行し、自社にとって本当に必要な性能とコストが釣り合っていないケースは珍しくありません。
LLM(大規模言語モデル)に関しては成熟し、今後汎用(はんよう)化フェーズに入って「スペックはそれほど必要ない」という考え方が優勢になっていくと当社は見ています。生成AIを活用するユーザー企業がコストパフォーマンスをシビアに評価するようになった時、インテルは「AIアクセラレータを搭載したインテル® Xeon® プロセッサー搭載のサーバはいかがですか。高価なGPUにコストを割かず、電力消費も少なくて済みますよ」と新しい選択肢を示していきたいと思います。
内野: そこは重要なポイントですね。ビジネス目的によって投資対効果の観点や判断基準は変わります。その点、IT部門が「GPUを使わずAIが使える」というXeon®の情報を得て、性能を追求したPコア、電力効率を追求したEコアを軸に多様な選択肢があると知った上で何を重視するのか――「目的とROI(投資収益率)から最適な手段を選ぶ」目利き力が問われますし、こうした観点があれば、お付き合いのあるSIerに相談するにしても「事業に主体的に関わる」ことに他なりません。IT部門が変わるチャンスは身近にあるのかもしれませんね。
レガシーITからの脱却は「オープン」が鍵に
内野: では最後にあらためて、2025年以降に向けてIT部門が採るべき一歩について、上野さんはどうお考えですか。
上野氏: 私は「オープンかどうか」を基準に少しずつ変えていくアプローチをお勧めしています。重要なのは、属人化を防ぐためにオープンなプラットフォームに全てのシステムを載せていくことです。そうすれば、誰もが理解できで部分的な改修も簡単になります。そもそも「2025年の崖」は、自社好みのシステムを立てすぎた個別最適化の結果とも言えます。これからは全員で協力して崖を埋めていけるような仕組みを選ぶのがよいでしょう。
システムだけでなく組織もオープンになって、DXに関わるメンバー全員で話し合ってみるのがいいかもしれませんね。IT側はテクノロジーを、経営側はコストを語るとしても、コストパフォーマンスは共通のテーマになりますし、お互いフラットに語り合うことはできるはずです。崖を越えるためにも、2025年はそうした取り組みにぜひチャレンジしていただきたいです。
内野: 「目標は何か、どこまでお金をかけるのか」という議論自体が、IT部門と経営層の共通言語になり得るというわけですね。それにコスト効率とは、削減だけではなく投資すべきものには投資するということ。ここはぜひ“変革に向けた議論”をしていただきたいですね。
上野氏: 経営に対するインテルのメッセージも「コスト削減を」から「変革に向けた投資を」に変わりました。“ビジネスを止めない”パフォーマンス、管理機能、セキュリティ機能などを持つPC、コスト最適化に貢献できるサーバ、 ローカル環境でAIを使えるAI PC――これらについて「目的に対してコストパフォーマンスは適切か?」という観点を持ちつつ、企業各社で議論、選択、活用いただくことで、新しいビジネスモデルがどんどん生まれることを期待しています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:インテル株式会社
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia NEWS編集部/掲載内容有効期限:2024年12月23日

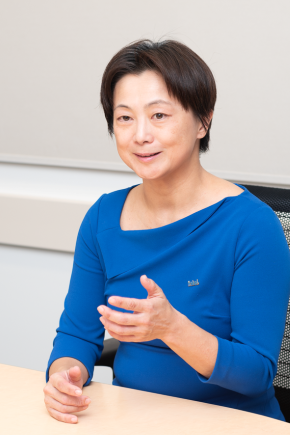 インテルの上野晶子氏
インテルの上野晶子氏 アイティメディアの内野宏信
アイティメディアの内野宏信











