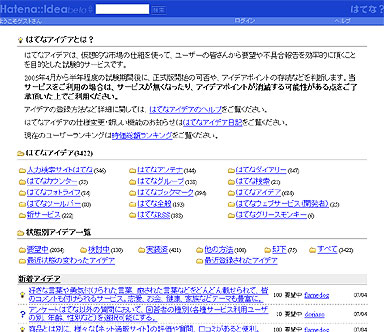「はてな」という変な会社(2/2 ページ)
ネット企業なのに紙で進行管理。社内会議はMP3でWeb公開。オフィスがあるのに仕事は図書館。旅先の宿で新サービスを開発――「はてな」はとにかく、型破りな会社だ。
「インターネットは、知能増殖装置」
はてなは、一部ユーザーに“露出狂”と言われるほどオープンな会社だ。ユーザーからの機能改善要望は、採否や進ちょく状況とともに「はてなアイデア」で公開。アイデアを検討する会議は、毎日録音してネット公開している。「会議をポッドキャスティングした企業って、多分世界初」
アイデアを公開すれば、競合に先を越されるかもしれない。会議を音声配信すれば、発言への批判を受けるかもしれない。それでもはてなは、情報を公開する。オープンにするほど、強くなれるという。
「情報をオープンにしなければ、自分が進む速度以上には進めない。でも、いったんネットに預けると、色々な人の力が加わって、一気に何倍にもなる。インターネットって、知能増殖装置みたいなところがあると思います」
はてなのサービスは、ネット上の知識増殖装置――ユーザーのアイデア――に育てられてきた。「ユーザーさんからは、僕たちの想像力の何倍というものが返ってくる。ユーザーと社員も、あんまり分けないほうがいいかもしれない」
「はてなっぽさ」を残したい
型破りでスピーディな経営。非常識なまでのオープン性。ユーザーとの距離――そんな“はてなっぽさ”が、会社が大きくなっても続けられるかが悩みだ。
「企画書にはんこを押してもらわないと何もできないような会社だったら、『はてなアイデア』みたいな訳の分からんサービスが通る訳がない」――少人数でやってるからこそ保てるものがあるのではないかと話す。
それでも、規模拡大にチャレンジするという。「今のユーザー数やサイトの質のままではいけない。世界に出て行けるサービスにしたい」。“はてなっぽさ”を保ったまま大きくなれるか。挑戦が始まる。
「はてなが残っていくには、宙に浮いた“はてなっぽさ”みたいなものが強くなっていくことが大事」――はてなっぽさが何かは、近藤社長にもよく分からない。ただ「はてな=近藤淳也」にはしたくないという。「『はてな=近藤』だと、ぼくがいなくなった終わり。ぼくの限界がはてなの限界になってしまう。それは避けたい」
社長を筆頭にしたトップダウン型の組織ではなく、“はてなっぽさ”という文化を共有し、継承し、大きくしていく、ユーザーまでもを巻き込んだ、対等でフラットな組織を目指す。「はてなという土台が活性化し、どんどん大きくなって、それを使っていろんなスタープレーヤーが生まれてほしい」
自分の名声には、こだわりがない。「はてなが大きくなって、かなり時間がたってから『あれ? そういえば最初って誰が作ったんだっけ?』という話になった時、『近藤という人らしいよ』と言ってもらえればそれでいい」
近藤社長は、会社の外でも“後世に続く何か”を残そうとする。自身が発案したサイクリングイベント「ツール・ド・信州」。1998年の第1回は、企画も運営も優勝者も近藤社長だったが、翌年からは選手をやめ、運営に専念した。
「選手として1等賞になる楽しさも確かにある。でも、次から次に何かが生まれていく土台みたいなものを作ってこの世に残す価値のほうが大きいと思う。自分が優勝することより、ツール・ド・信州が箱根駅伝くらいの国民的イベントになることの方が大切」
ネットという「パリのオープンカフェ」
近藤社長いわく、日本人にとってネットは、パリのオープンカフェだという。「パリのオープンカフェでは、大人たちが延々としゃべっている。『いつ仕事行ってるねん!』ってくらいに」――それがパリに住む人々の豊かさであり、人間らしさを獲得する場だという。
カフェで知らない人と話し込む図は、日本人同士では想像しにくい。しかしネット上ならありえる。「ネットでいろんな人と交流したり、知識を得ている人は出てきている。今まではテレビや本をただ見る、受動的な情報収集の時間だったものが、コミュニケーションに置き換わっているとすれば、それは豊かさを獲得していると思う」
コミュニケーションが文化を生む。近藤社長は言う。「文化のレベルは、街中であーだこーだ言っている人の会話のレベルによって決まると思う。文化のレベルの高さが感じられなくなっているとしたら、あーだこーだいってる人が少なかったり、まじめに聞いてる人自体がいないからかな、という気がしている」
はてなはそんな文化を、静かにサポートし続ける。「ぼくたちはノートPC 1台で、何もないところからWebサービスを作れる。たくさんの人に使ってもらって、便利さや豊かさを供給できるようなサービスを、ゼロから生み出していけるんです」
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
- 人力検索はてな、“4年目の正直”
- 自分の手でネットを“進化”させたい――「はてな」社長の夢
「インターネットは、人が本来持っている力を飛躍的に伸ばせる可能性を持った未完成の道具。この道具を進化させ、人間の生活を豊かにしたい」――そんな思いが「はてな」を生んだ。 - 「はてな」が東京に来た理由