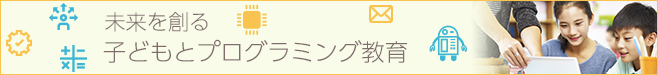「アバターのある日常」は日本から生まれ、世界を変えていく――大阪大学の石黒教授が見据える未来社会:「NEW EDUCATION EXPO 2025」特別講演(1/3 ページ)
TFTビル(東京都江東区)で6月5日〜7日に開催された教育関連の見本市「NEW EDUCATION EXPO 2025」では、さまざまな講演やセミナーが行われた。
その中でも注目を集めたのが、6月6日に行われた大阪大学大学院の石黒浩教授(基礎工学研究科)による特別講演「アバターと未来社会」だ。この講演の模様を2回に分けてお伝えする2回目は、アバターによって変わる社会や生活のありようや、大阪・関西万博への取り組みを語った後半部分をまとめる。
アバターが「教育」「仕事」「医療」「日常生活」を大きく変える
石黒教授はロボットと並行してアバターの研究にも取り組んでおり、コロナ禍をきっかけにアバターの開発を行うスタートアップ企業「AVITA」を創業した。
そんな石黒教授は、アバターによる社会の変化をこう語る。
教育、仕事、医療に日常生活――これら全てが、アバターによって大きく変わると私は確信している。教育ではAIアバターが個別指導を担い、難しい部分だけ人間の先生が対応する形になるだろう。学校そのものはなくならないが、友人関係(の構築/維持)や議論の場としての役割を持ちながら、アバターを通じて世界中の子どもたちとつながれる、インターナショナルな場になることが理想だ。
仕事も同様で、自宅にいながらアバターを介して専門家と議論でき、世界中の仲間とネットワークを築けるようになる。医療においても、病院に行くことなく、アバター化した医師が家庭に現れる未来が見えている。全ての診察をアバターが担うのは難しいが、検査機器の進化と組み合わせれば、遠隔診療は確実に進む。町の小さな病院にアバターを常駐させれば、都市部の専門医が乗り移って診察できるようになり、小さな病院でも高度な医療を提供できる。
このようにアバターが日常生活に浸透すれば、(誰かの)話し相手になったり、パーティーに参加したりする人も出てくる。こうした未来は、日本から生まれると私は考えている。インターネットやAIは米国が主導してきたが、アバターに必要なCGキャラクターや人間型ロボットの技術は、日本が得意とする分野だ。VTuber文化に代表されるように、日本には高度な技術と、アバターを生活の一部として受け入れる文化がある。欧米ではアバターは「道具」であり、AIによる自律型のものが主流だが、私は人が中に入るアバターの価値を重視している。実際、私の会社のアバターは、保険の販売やコンビニの年齢確認など、人間の介在が必要な場面で活躍している。
日本では人間とアバターが“対等な存在”として共存できる文化が根付いている。この文化と技術を生かせば、アバター分野で日本が再び世界の先頭に立つことができると、私は信じている。
本人の存在感をリアルに伝える「アンドロイドアバター」
これまでに、石黒教授はいくつかアバターに関する実証実験を行ってきたという。その事例について共有しつつ、課題も語った。
コロナ禍で外部との接触が制限されたとき、私は保育園や高齢者施設にアバターを導入する実験を行った。幼稚園にかわいらしいロボット型アバターを設置し、高齢者が遠隔から子どもたちと対話できるようにしたところ、子どもも高齢者も非常に喜び、毎日異なる人が交流を楽しんでいた。この取り組みは、今も続いている。
学童保育でもアバターが活躍しており、引退した先生がアバターを通じて子どもたちの相談に乗ったり、宿題を手伝ったりしている。子どもたちは全く飽きず、(コロナ禍によって)対話に飢えていたことがよく分かった。
他にも、さまざまな場所でアバターの活用を試みている。大阪の小さなアミューズメントパークでは、動物とふれあえる場にアバターを配置し、子どもたちが動物に関する質問をすると、必要に応じて飼育員がアバターに“乗り移って”リアルタイムで答えるという実験も行っている。こうした取り組みは、近いうちに実用化されると見ている。
医療分野でも(アバターの)活用が進んでいる、長崎県の二次離島では医師が1人しかおらず、専門外の診療に対応できない問題があった。そこで、アバターを島の医院に設置し、長崎大学の精神科医が“乗り移って”診療を支援している。医師免許は(専門領域を問わず)1種類なので、こうした形で他分野の医師がサポートすることは合法であり、非常に有効だ。ただし、ボランティアに頼り続けるわけにはいかず、今後は法整備が求められる。
政治の場でも、アバターは効果を発揮している。私たちは元デジタル担当大臣の河野太郎氏のアバターを開発し、(実証実験の一環で)商業施設において一般市民にマイナンバー制度の説明を行ってもらった。大臣がアバターに乗り移った瞬間、会場にはまるで本人がそこにいるかのような雰囲気が生まれ、多くの人が集まった。アンドロイドアバターは、本人の存在感をリアルに伝える力を持っていると実感している。
これからも、社会のさまざまな場面でアバターの可能性を広げていきたい。
 長崎県五島市の久賀島(ひさかじま)にある「久賀診療所」におけるアバター利用の例。久賀診療所にいる脳外科医や看護師が、コミュニケーションロボット「Sota」を介して長崎大学病院にいる精神科医から助言を受けるという形で、二次離島(本土から直接アクセスできない、近隣の離島経由でアクセスする離島)にありがちな「専門医がいない問題」の緩和を行っている
長崎県五島市の久賀島(ひさかじま)にある「久賀診療所」におけるアバター利用の例。久賀診療所にいる脳外科医や看護師が、コミュニケーションロボット「Sota」を介して長崎大学病院にいる精神科医から助言を受けるという形で、二次離島(本土から直接アクセスできない、近隣の離島経由でアクセスする離島)にありがちな「専門医がいない問題」の緩和を行っている関連記事
 「人間型ロボット」「アバター」がAIと出会うと何が起こるのか? 大阪・関西万博「いのちの未来」プロデューサーが語る“アバターと未来社会”
「人間型ロボット」「アバター」がAIと出会うと何が起こるのか? 大阪・関西万博「いのちの未来」プロデューサーが語る“アバターと未来社会”
6月5日から7日かけて行われた「NEW EDUCATION EXPO 2025」において、大阪大学大学院の石黒浩教授(基礎工学研究科)による特別講演「アバターと未来社会」が開催された。事前申し込みの段階で満員だった本講演の内容を、2回に分けて紹介する。今回は、人間型ロボットやアバターを研究/開発する目的、LLM(大規模言語モデル)が登場したことによるロボット/アバターへの影響と、これからのインターネットについて語った部分を紹介する。 Next GIGAの学習用/職員用端末を使うには環境整備も大事! 「NEW EDUCATION EXPO 2025」で見かけた周辺機器やソリューションをチェック
Next GIGAの学習用/職員用端末を使うには環境整備も大事! 「NEW EDUCATION EXPO 2025」で見かけた周辺機器やソリューションをチェック
6月5日〜7日にTFTビル(東京都江東区)で開催された「NEW EDUCATION EXPO 2025」では、Next GIGAを見据えた周辺機器やソリューションの展示も目立った。いくつか気になったブースを紹介しよう。 累計来場者数1000万人を突破した大阪・関西万博の「Mirai Meeting」で感じた驚き 実は会場の内外で触れていた日立製作所のテクノロジー
累計来場者数1000万人を突破した大阪・関西万博の「Mirai Meeting」で感じた驚き 実は会場の内外で触れていた日立製作所のテクノロジー
累計来場者数が1000万人を突破した大阪・関西万博。その中で、KDDIと共同展示している日立製作所のパビリオンに訪れた。 Z世代はオンラインと現実社会の人格ギャップに悩んでいる? レノボが「デジタルウェルネスキャンペーン」を展開する理由
Z世代はオンラインと現実社会の人格ギャップに悩んでいる? レノボが「デジタルウェルネスキャンペーン」を展開する理由
レノボ・ジャパンが、デジタルウェルネスをテーマにしたZ世代向けのキャンペーンを開催する。スペシャル動画を制作し公開する他、NPOと連携したチャット相談窓口も設ける。 「ノモの国」でパナソニックグループが次世代の子どもにアピールした理由 「大阪・関西万博」のパビリオン訪問記
「ノモの国」でパナソニックグループが次世代の子どもにアピールした理由 「大阪・関西万博」のパビリオン訪問記
ゴールデンウィークに入ってにぎわいを見せている「大阪・関西万博」。今回はパナソニックパビリオンを訪問した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- リフレッシュレート500Hz対応の量子ドット有機ELディスプレが店頭に! (2025年10月04日)
- Windows 10のサポートが終了する10月14日までに確認したいこと (2025年10月01日)
- 11型Andoridタブでプロジェクターも内蔵! タフ過ぎる「Blackview Active 12 Pro」を試して分かったこと (2025年10月02日)
- ゼンハイザーの完全ワイヤレスイヤフォンやヘッドフォンが最大58%もお得に買える! (2025年10月04日)
- ニトリから9990円のプロジェクター エディオンと共同開発、スタンド一体型 (2025年10月03日)
- ARグラスで仕事はできるか? スマホサイズの「XREAL BEAM Pro 5G」と老眼にやさしい「XREAL One」で試す (2025年10月02日)
- 新型「Fire TV Stick 4K」と「Fire TV Stick 4K Max」はどちらを選べばいい? ポイントをチェック! (2023年10月13日)
- 取り外せるモジュール型コントローラーが楽しい! Windows 11搭載のポータブルゲーミングPC「AYANEO 3」を試す (2025年10月03日)
- 保存するなら読み書きの速いフラッシュメモリへ! サンディスクのSSDやSDメモリーカードがお得 (2025年10月04日)
- 「Windows 11 2025 Update(バージョン 25H2)」の製品版が登場 Windows Updateを通して順次展開 (2025年10月01日)