ソーシャルDRMに合本機能――JTBパブリッシング「たびのたね」はこうして生まれた
JTBパブリッシングが10月にオープンした「たびのたね」。いわゆる電子書店に分類されるが、そこにはユニークな機能と信念が備わっている。開発チームの3人にたびのたね誕生の背景、そして今後の狙いについて聞いた。
『るるぶ』など旅行ムックなどを手掛けるJTBパブリッシングが10月に新たにオープンした「たびのたね」。
ソーシャルDRMの採用のほか、地域でのみ流通しているような出版物の取り込み、雑誌の第1特集などを抜粋したマイクロコンテンツの提供、そしてそれらのコンテンツをユーザーが自由に組み合わせて自分だけのガイドブックを作れる(合本機能)ことなどが特徴だが、複数の出版社が参加し、雑誌という権利関係が難しいパッケージでこれを実現したのは注目したい部分である。
ここでは、JTBパブリッシングのたびのたね開発チームの3人にたびのたね誕生の背景、そして今後の狙いについて聞いた。
パーソナライズ化されている旅行のニーズにどう応えるか
―― たびのたね、面白いサービスですね。これは電子書店と呼ぶべきでしょうか?
青木 実は、たびのたねの開発に当たっては、電子書店を作ろうとか、電子書籍の新しいことをやろうという思いからスタートしたわけではないんです。順番からいうと、“パーソナライズ化されている旅行のニーズに対応できるサービス”を生み出そうというのが先にありました。
―― JTBパブリッシングは『るるぶ』などの旅行ガイドブックも刊行されていますが、紙の旅行ガイドではそうしたニーズに対応するのが難しいのでしょうか。
青木 紙で買う顧客層とたびのたねのユーザー層は必ずしもイコールではないと考えています。
旅行ガイドブックの欲しい部分だけを取ってきたり、それを他社のコンテンツとまとめて自分だけのガイドブックにし、好きなデバイスで楽しむ、という体験をより多くの人にしてもらいたいと考えていますが、それは現時点で十分に簡単なものではありません。そして、そうした体験を志向する方々が今の紙の旅行ガイドブックがカバーできていないお客さまだとも感じています。
―― 「自分だけのオリジナルガイドブック」というのが細分化した旅行ニーズに応える部分だというわけですね。雑誌のコンテンツを抜き出してWebメディア化するアプローチもあったかと思いますが、電子書店のようになっていったのはなぜでしょう。
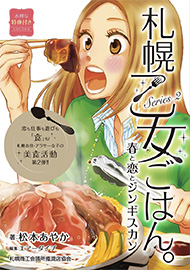 グルメ漫画は『孤独のグルメ』や『花のズボラ飯』だけじゃない! 北海道唯一のマンガ出版社「エアーダイブ」と、経済団体「札幌商工会議所」、札幌在住のマンガ家「松本あやか」さんの『札幌乙女ごはん』など、ご当地出版物には知られざる名作が多い
グルメ漫画は『孤独のグルメ』や『花のズボラ飯』だけじゃない! 北海道唯一のマンガ出版社「エアーダイブ」と、経済団体「札幌商工会議所」、札幌在住のマンガ家「松本あやか」さんの『札幌乙女ごはん』など、ご当地出版物には知られざる名作が多い青木 たびのたねに並んでいるのは、どれも編集というフィルターを介して制作されたコンテンツですが、わたしたちは、“編集されたコンテンツの価値”を高く評価しているということです。
Web上にはデータベース的に膨大な情報が存在します。旅行ガイドも、情報がさまざまな形で取得されている中、総量は減ってはいませんが、相対的に紙のシェアが減っているということなのでしょう。
しかし、情報が膨大にあればいいわけでもないというのがわたしたちの考えです。編集者が介在した意味や価値を伝えようとしたら、結果として今エッジが効いているのは本というパッケージでした。
ISBNのついてないようなディープな内容の本、あるいはその地域でしか流通していない面白い本はたくさん存在しますが、旅行先で地元の本屋に足を運ぶことは少ないですよね。面白いコンテンツを知ってもらえる機会がないわけです。そうした出会いの機会を作りたいというわたしたちからの提案は、地域の出版社さんにも好意的に受けとめてもらえましたね。
―― 「たびのたね」は旅行情報ポータル?
井野口 旅に行きたいなって思った時にじゃあまずここに行こうという代名詞的なサービスって実はまだないんじゃないかと思います。ただ、皆がいつも旅行に行っているわけではないですから、そのときにしか用がないサービスだと、接点が弱くなりますよね。そうではなく、いつきていただいても旅への興味を喚起する場でありたいです。
全部そろっているわけじゃないけど、自分が知らなかった見方や情報が入る面白さを味わえるような場所。インディペンデント系の書店さんの魅力は、そういうところなんだろうと思います。
たびのたねは、参画出版社にとっての自社書店になってほしい
―― 今回、北海道と沖縄の2地域のコンテンツからスタートしていますが、これは旅行者が多い場所から、という理解で正しいですか?
青木 それもあります。地理的に比較的独立した旅行先で、ある程度のボリュームでコンテンツをご提供できる場所、というところで優先順位を決めたというのが正確ですね。
―― 地域の出版社も含めるとどれくらいの出版社が参加していますか?
青木 現在は35社です。純粋な出版社に加え、出版物を出してるところ、というところもあります。
この取り組みで面白いと思ったのは出版社が出版社を紹介してくれるんです。北海道でラーメンに関する本を出している出版社さんが、スープカレーの本も出していたので、そのスープカレーの本もたびのたねで扱わせてもらいたいと申し出たら、「スープカレーはうちよりもこっちの方が面白い」って別の出版社を紹介してくれるんです。こうしたことは東京だとなかなかないような話だと思いますが、こうした横のつながりも大きな価値があると感じているところです。
―― 参加している出版社はコンテンツをEPUBで納品しているんでしょうか。
村上 出版社の負荷やリスク、手間は極限まで排したかったので、何らかのデータをいただければ、わたしたちの方でEPUBにしています。
実際のEPUBを作る作業は外部にお願いしていますが、固定レイアウトといってもデータを単純に左から右に送れば済むわけでもなく、想定以上に時間も掛かり、苦労した部分ですね。ただ、そこを丁寧にやったので、今回初めて電子化された作品なども少なくない数がご用意できました。
雑誌をデジタルで見せる、つまり、レイアウトを伴ったコンテンツの見せ方としてどういうものが最適かは今後も議論が必要だと感じています。制作のワークフローも、紙と電子ができるだけ重なった形で進むのが理想的ですが、実際には大変だな、と思うこともまだ多々あります。
一方で、先ほどお話したように、今回の取り組みの中で、たくさんの出版社が人レベルでつながっているように感じています。同じテーマや地域を紹介する中でも、アプローチが出版社、編集者で違いますが、気持ちの部分でつながるんじゃないかと思っていて、それをたびのたねという場で発信していければと考えています。
たびのたねは、参画いただいている出版社さんにとっての自社書店、もっといえば、一緒に運営してもらいたいというくらいの気持ちでいます。るるぶブランドを用いていなかったり、リアルタイムに販売レポートを確認いただけるようにしていたりするのも、そうした気持ちからです。
特徴的な「ソーシャルDRM」や「まとめたね」
―― 「たびのたね」は先行事例もよく踏まえた上で機能を検討されたのだろうと感じる個所が多々あります。例えばソーシャルDRMの採用もそうですね。
井野口 わたしどもも自社チャンネル、あるいは他社チャンネルでDRMが掛かったものを配信していますので、DRMを二元論で語るのは難しいですが、自分がユーザーとして考えたときに不便に感じる部分があるのも事実です。ですから、まずは(ソーシャルDRMで)やってみて、その反応を知りたいと考えています。
―― ソーシャルDRMは閲覧環境をユーザーが自由に選べますが、一方で、EPUBをダウンロードさせて後はお好きなようにというのは現状、ハードルが高い部分もありますよね。
青木 そうですね。将来的なことも見据え、今回まずは標準的なEPUBフォーマットの採用にこだわりました。閲覧環境はこれからどんどん変わっていくと思いますので、そうしたハードルも下がっていくことを期待しています。コンテンツやコンセプトが面白いと感じてもらえれば使って頂けるんじゃないかと思う部分もありますが、だからハードルを高くしていいのだというわけではないので、やはりそこは十分な説明が必要ですね。
―― 複数のコンテンツを1つにまとめる合本機能である「まとめたね」もユニークですね。雑誌は権利情報が複雑とよく言われますが、権利関連の苦労はありましたか?
青木 おっしゃるとおり、雑誌は権利関係が複雑なことが多く、それらを一気にクリアすることはなかなか難しいこともありますね。わたしどもはすでに旅行ガイドブックで権利関係をしっかりとやってきたので、そのノウハウが生きた部分は多々ありました。
例えば、権利をクリアしたもので新しいコンテンツを企画したり、あるいは、著者の方に許諾をいただくとバックナンバーに遡ってクリアできたり。制約があったからこそ生まれた商品もあります。もちろん著書や出版社さんのご意向で、抜粋版がないものも中にはあります。それはよしとして、ただ、その本がまとめたね機能の対象外になるのはナシとしています。
―― 抜粋版に対するユーザーの反応はいかがですか?
青木 抜粋版は、複数冊購入いただいている方が多いですね。抜粋版が受け入れられていること、そしてそれらをまとめるために横断的なチョイスをされているのは、たびのたねのコンセプトと比較的合致していて、手ごたえを感じています。
地域と連携し、人が訪れてもらえるようなきっかけを作るサービスに
―― では、これからの課題と感じる部分は?
井野口 まずはエリアのカバレッジ拡大。1月には九州、2月には関東、2015年度上期中には47都道府県、場合によっては海外もカバーしていきたいです。訪日旅行(インバウンド)でのニーズも見据えたいですね。
もう1つは、「○○さんがまとめた本」のようなCtoC的なまとめも提供できればと考えています。そこは先ほどお話したインディペンデント系の書店の考え方を実現できればいいなと。
―― 旅行した後にその人が撮った写真をまとめたねの表紙素材などとして提供してくれたらインセンティブを返すような仕組みもできそうですね。地域振興の観点から自治体との連携なども考えられるのではないでしょうか。
青木 そうですね。これはたびのたねと直接関係しているわけではないですが、今、JTBグループ全体では地域交流ビジネスに取り組んでいて、全国の各地域の課題を解決しようというようなこともやっています。
地域のコンテンツと出会ったり、それをまとめることで、旅のスタイルが全然変わって旅行がさらに面白くなる、たびのたねに出会わないとできない旅のスタイルがあるとわたしたちは考えています。それは網羅的なガイドブックだけでは味わえない体験です。
それがひいてはその地域、本来は訪れなかった地域に人が訪れるようになる可能性も秘めている。地域と連携した仕組みを作ることで、そこに人が訪れてもらえるようなきっかけを作るサービスにしていければと思います。
関連記事
 これからの旅の友――JTBパブリッシングが電子書店「たびのたね」をオープン
これからの旅の友――JTBパブリッシングが電子書店「たびのたね」をオープン
旅行ガイドブックや雑誌を1記事から購入できる電子書店。購入したものをまとめた自分だけのガイドブックの作成機能も。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

 左から青木洋高氏(情報戦略部企画課 課長代理)、井野口正之氏(執行役員 情報戦略部長 情報戦略部企画課長)、村上祐介氏(情報戦略部企画課)
左から青木洋高氏(情報戦略部企画課 課長代理)、井野口正之氏(執行役員 情報戦略部長 情報戦略部企画課長)、村上祐介氏(情報戦略部企画課) 誌面の特集などを抜粋版として提供するのはこれまでにもないわけではなかったが、複数のコンテンツを自由にまとめて1冊にする機能をストアサービス側で用意したのは珍しい(画像出典:たびのたね)
誌面の特集などを抜粋版として提供するのはこれまでにもないわけではなかったが、複数のコンテンツを自由にまとめて1冊にする機能をストアサービス側で用意したのは珍しい(画像出典:たびのたね)