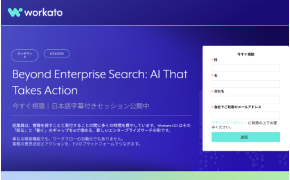3カ月で“形”にするAI実装 日本企業が継続的に価値を生み出すための実践法:鍵は「アジャイル」「トライ&エラー」「データ」
企業の生成AI導入が進む中、試用段階から抜け出して成果を創出するにはどうすればよいのか。ポイントは、AIと既存システムやデータを連携させて自動化する基盤にあると専門家は語る。
労働人口の減少が進む日本において、生産性向上の手段として期待される生成AI。アイティメディアの「生成AIの活用意向と課題」に関する調査(2025年2月)によると、生成AIを「利用している」と答えた回答者は38.4%に上った。
ただし、その利用範囲は狭く、一部の従業員が自身のタスクを効率化するケースが多い。生成AIを活用する米国などの他国と比較すると、PoC(概念実証)の域を出ずに期待するほどの成果を得ていない企業が多数だ。
なぜ日本企業のAI活用はPoCの域から脱却できないのか。真の業務変革を実現するために必要な要素は何か。エンタープライズオーケストレーションプラットフォームの「Workato」を提供するWorkatoの鈴木浩之氏と山川敦也氏に聞いた。
日本企業が陥る“PoC沼”
「ITmedia エンタープライズ」の読者調査(2025年4月)によると、AIの用途として多くの回答が集まったのが「業務文書作成」(36.1%)を筆頭とする個人的な作業で、「情報セキュリティ運用」(10.0%)や「工場などの製造プロセス管理」(3.9%)といった部門全体や全社に関わる業務での利用は少ない。
この背景について、鈴木氏は日本企業特有の取り組み方に問題があると指摘する。
「従来のアプリケーション開発は要件定義から始まり、ウォーターフォールのアプローチの実装が主流でした。しかしAI活用は性質が異なり、予測した通りの成果や品質を最初から完璧に達成することは困難です。実装自体は比較的簡単であるため、まずはスモールスタートで始め、トライ&エラーを繰り返しながら質や成果を高めていくことが不可欠です。成果が課題解決に結び付かないようでは経営層からGOサインは出ません。ビジネス課題を理解している人が主導してAI活用を進めることが、より良い結果を生む鍵となるでしょう」
鈴木氏は、日本企業の時間軸に対する考え方も問題だと続ける。
「米国の先進企業は、クラウドネイティブなSaaSやマイクロサービス(APIを含む)を活用したコンポーザブルなアーキテクチャとアジャイル開発がすでに標準です。Workato本社のCIO が語るように『3カ月を超えるITプロジェクトは成果の妥当性を判断できなくなるリスクが高まるため、原則行わない』という考え方が主流になりつつあります。一方で日本企業は『PoC(概念実証)』と称して運用に至らないまま数カ月から半年以上も検証フェーズにとどまり、意思決定や実装に遅れが生じるケースが散見されます。企業競争が激化する今、ITの在り方そのものを見直して“早く作り、すぐ動かす”という俊敏性をどう実現するかが経営と現場に問われています」
AI活用で日本企業は他の先進国企業に後れを取っている。しかし鈴木氏によれば、真面目にルールを整備して詳細なマニュアルなどを作る日本企業の文化は、AIが必要とする業務のコンテキストやナレッジなど重要なアセットが文書化されているケースが多いため、「日本企業にもAI活用が進む素地(そじ)はある」と同氏は指摘する。
「AIは脳」――機能するためには“神経”が必要
真の意味で「AIを業務に実装する」とはどういうことなのか。山川氏はこう説明する。
「AIはデジタルの“脳”です。判断や推論を得意としますが、それだけでは業務は変わりません。AIを業務に活用するには、AIが出す判断や命令をアプリケーションに届けて動かすための連携基盤が必要です」
AIとアプリケーションの間に入って、AIが出した指示を実際の業務アクションに変換する役割を果たすのがWorkatoだ。
「AIを“脳”とするなら、Workatoは“神経系”のような存在です。アプリケーションや業務システムで生じるデータは、人間の“五感”のように現場の状況を示しています。WorkatoはAIが正しいナレッジを通じて文脈を正確に理解し、適切な行動を判断できるよう情報の整合性を保つ役割を担います。AIの不確実性を低減して再現性を確保するために、Workatoはさまざまなアプリケーションの操作方法を複数の『スキル』として定義し、AIがそれらを利用できる状態にしています。当社のAIエージェント『Workato Genie』はもちろん、他社のAIエージェントとも連携できるのが特徴です」(山川氏)
データサイロ化の壁を越える統合戦略
AIを活用する上で、もう一つの課題がデータのサイロ化だ。生成AIの回答精度向上やデータ分析による意思決定の迅速化を求める企業は多いが、データの分散によって効果的な活用が阻まれているケースは多い。ITmedia エンタープライズの読者調査でも27.1%が「社内データと連携できない」と回答しており、生成AIの利用を意識してデータ基盤を整備している企業は15.1%にとどまる。
山川氏はこの課題への対策として、データウェアハウス(DWH)の構築だけでは不十分だと指摘する。
「DWHを構築してデータを1カ所に集める企業が増えていますが、ただ集めるだけでなく、いかに活用するかが重要です。集めたデータを分析して、その結果をAIやアプリケーションにフィードバックする必要があります」
DWHは基本的に、人がBIツールで分析、閲覧するためのデータを整備するシステムだ。つまり、人が「見たい」と思ったときにアクセスして使うものだ。一方で、データの変化に応じてAIやアプリケーションが自動でアクションを実行するような仕組みを実現するには、変化したデータをAIやアプリケーションにリアルタイムでフィードすることが求められる。
「Workatoの強みは、データの発生源であるアプリケーションやデータに接続できることです。24時間休みなく働くAIがそれらのデータをリアルタイムにモニタリングすることで、これまで見逃していたインサイトを察知し自律的なアクションにつなげられます」(鈴木氏)
セキュリティ対策とガバナンスを確保するAI活用基盤
AIを業務に実装する際に、企業が必ず直面するのがセキュリティ対策とガバナンスの課題だ。ITmedia エンタープライズの読者調査でも、AIサービス利用に当たっての障壁として「セキュリティリスクを評価できない」(42.6%)、「社内ルールを整備できない」(39.2%)という回答が上位を占める。
Workatoはこうした課題に対応するための機能を備えている。AIエージェントが動作する際に、人間のユーザー権限を引き継いでシステムにアクセスして操作する「ランタイムユーザーコネクション機能」だ。
「営業担当者がAIに『この商談情報を更新しておいて』と依頼すると、AIは担当者の権限で営業支援システムにアクセスするので、その担当者が直接操作した場合と同じ記録が残ります。AIが勝手に誰かの権限を使って操作するのではなく、依頼した本人の権限で処理するため、責任の所在が明確です」と山川氏は説明する。
Workatoは全ての処理のログをステップごとに記録しており、後から「なぜその操作が行われたか」「どのユーザーが関与したか」をトレースできる。このように、Workatoにはガバナンスや透明性を確保する機能が組み込まれており、企業規模で業務プロセスのコントロールとセキュリティガバナンスを実現する。
複数のシステムをつないで働くAIワーカー
Workatoを利用すると、業務をどのように効率化できるのか。山川氏がデモンストレーションを通じて紹介した一例が、デバイス紛失時の対応自動化だ。
「社用スマートフォンを紛失しました。どうすればいいですか?」と入力すると、Workatoで動作するAIエージェント「ITGenie」が紛失時の手順を案内して、手続きに必要な情報をユーザーに聞く。情報を入力すると、一連の対応――インシデント管理ツールのチケット作成やユーザープロファイルの取得、デバイス管理ツールでのデバイスのロック、ID管理ツールによる全アプリケーションのセッション切断、対処結果のレポート――を自動で実行する。
AIエージェントが対応する内容は、各企業のルールに基づいて構築される。単なるデータの検索や回答ではなく、深い業務理解と文脈の判断によって具体的なアクションを実行する「Deep Action」が可能だ。これを支えるのがWorkatoの特徴である「幅広いシステムへのアクセス」と「複数の業務プロセスを横断した自動化」「AIエージェントと業務自動化の融合」だ。
「ユーザーはAIエージェントがどのシステムとつながっているか、どういうデータが行き来しているのかを意識する必要はありません。操作マニュアルを見る必要もありません。複雑性は全てAIが吸収してくれます。その結果、全社でのAI活用のハードルが低くなります」(山川氏)
Workatoは、限られた内製リソースを生かして効率性や俊敏性、自律性を同時に実現するための、ノーコードによるワークフロー実装環境を提供する。2025年7月時点で世界1万2000社以上が導入している。そして、Workatoは日本市場特有のビジネス文化に大きな可能性を見いだしている。鈴木氏は次のように強調する。
「生成AIで成果を出すためには、単なる導入ではなく使いこなす力が不可欠です。日本企業は品質向上への強いこだわりと、地道なカイゼンで成果を積み重ねる文化を持っています。そこにAIを組み合わせれば、他国には真似できない高品質かつスピーディーな業務遂行が可能です。エージェンティックAI時代を迎える今こそ、日本企業は卓越したプロセス品質を武器に競争優位性を確立できるでしょう」
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:Workato株式会社
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2025年9月8日
 Workatoの鈴木浩之氏(創業者兼戦略&Field CTO)
Workatoの鈴木浩之氏(創業者兼戦略&Field CTO) Workatoの山川敦也氏(シニアソリューションコンサルタント)
Workatoの山川敦也氏(シニアソリューションコンサルタント)