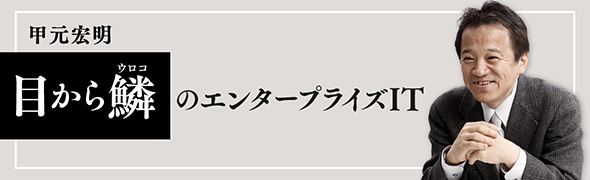「オンプレ回帰」なんて起きていない テクノロジー活用に“未来への想像力”が必要な理由:甲元宏明の「目から鱗のエンタープライズIT」
「オンプレ回帰」という言葉がメディアで踊る中、筆者は「オンプレ回帰は起きていない」と喝破します。次々と新しいテクノロジーが登場する中で、自社に導入すべきものをどう見分けるべきでしょうか。
この連載について
IT業界で働くうちに、いつの間にか「常識」にとらわれるようになっていませんか?
もちろん常識は重要です。一生懸命に仕事をする中で吸収した常識は、ビジネスだけでなく日常生活を送る上でも大きな助けになるものです。
ただし、常識にとらわれて新しく登場したテクノロジーやサービスの実際の価値を見誤り、的外れなアプローチをしているとしたら、それはむしろあなたの足を引っ張っていると言えるかもしれません。
この連載では、アイ・ティ・アールの甲元宏明氏(プリンシパル・アナリスト)がエンタープライズITにまつわる常識をゼロベースで見直し、ビジネスで成果を出すための秘訣(ひけつ)をお伝えします。
「甲元宏明の『目から鱗のエンタープライズIT』」のバックナンバーはこちら
最近、IT系メディアの記事やITベンダーの広告で「オンプレ回帰」というフレーズをよく見ます。この言葉を素直に考えれば、「クラウドからオンプレミスへの回帰が起きている」という意味に取れます。筆者が所属するアイ・ティ・アール(以下、ITR)にもユーザー企業やITベンダーから「『オンプレ回帰』というトレンドが起きているのか」という問い合わせがよく来ます。
「オンプレ回帰」はトレンドになっていない
ITRは各種IT製品の国内市場や、国内企業のIT導入の取り組み状況などを調査しています。調査結果から言えば、国内クラウド市場は極めて高い成長率で拡大しています。ITインフラ領域において国内企業の投資はクラウド系サービスに集中し、オンプレミス系製品やデータセンターへの投資は減少傾向にあります。
一方で、多くの国内企業がオンプレミスでさまざまなシステムを運用しており、オンプレミスを維持する意向を示す企業も多く存在しています。
ただし、クラウドで運用しているシステムをオンプレミスに戻したり、または戻す予定があったりする企業は非常に少ないのが現状です。
こうしたファクトから筆者が導き出した結論は次の3つです。
- 日本ではクラウド採用のトレンドが強く、今後も継続する
- オンプレミスでシステム運用している国内企業も多く、オンプレミスの運用保守市場はそれなりに大きいが、高い成長は期待できない
- クラウドからオンプレミスに戻る、いわゆる「オンプレ回帰」現象は起きていない
もちろん、一部ではいろいろな要因でクラウドからオンプレミスに戻すケースも発生しています。しかし、「オンプレ回帰」と言えるほどの大きなトレンドは起きていないというのが筆者の結論です。
テクノロジー活用には「未来への想像力」が重要
筆者は多くの国内企業にITコンサルティングを実施しています。顧客がクラウドのような新しいテクノロジーの将来性をどう判断すべきかと苦慮しているときは、「“未来”がどちらにあるのか考えましょう」と話すようにしています。クラウドに関して言えば、「オンプレミスにある各種ハードウェアやソフトウェアを自社で調達・保守するのと、クラウドサービスのどちらが“未来的”かを考えましょう」ということです。このように考えるとほとんどの人はオンプレミスよりもクラウドに未来があると感じると思います。
もっとも、実際の未来にどのようなテクノロジーが出現するのかを予測するのは困難です。革新的なテクノロジーが普及する時期を予測するのはもっと困難です。ただし、同じ領域の新旧テクノロジーを比較して、どちらに“未来”がありそうなのかを考えることはさほど難しくありません。
AI(人工知能)と手作業を比較したときに、「手作業の方に未来がありそうだ」と考える人は皆無でしょう。対話型生成AI「ChatGPT」をはじめとするAIテクノロジーが2023年に広く普及すると予測できた人は少ないでしょうが、「いつかAIが世の中を席巻する」と考えていた人は多いのではないでしょうか。
AWS(Amazon Web Services)が米国でサービスを開始したのは2006年でした。筆者は当時、ユーザー企業のIT部門でオンプレミスサーバ群に翻弄(ほんろう)されていたので、この革新的なテクノロジーにとてつもない未来を感じました。2011年に東京リージョンがオープンした後、AWSを利用する国内企業は徐々に増えましたが、それでもまだ少数派でした。筆者は多くの人から「日本企業はクラウドを使わないよ」という声を聞きました。
今思えば、そのような発言をした人はIT産業で既に成功し、従来型の価値観に縛られていたのでしょう。国内企業は世界に比べてクラウド活用で後れを取っています。クラウドに触れたときに感じた“未来性”を信じて突き進む人や企業が多ければ、このような事態にはならなかったのではないかと筆者は思います。
未来に備えるためのチェック・ポイント
それでは、未来を感じ、未来に備えるにはどのような点に着目すればよいのでしょうか。筆者は以下のポイントに注目すべきだと考えています。
- イノベーティブ:当たり前ですが、未来を創るテクノロジーはイノベーティブ(革新的)である必要があります。それも、「そこそこの革新性」ではなく「ぶっちぎりの革新性」が必要です。そのテクノロジーに初めて触れたり聞いたりしたときに「こんなことができるのか!」「なんと!」「やられた!」と感動を覚えれば、そのテクノロジーの未来は明るいといえるでしょう
- スケーラブル:将来性を考えれば、どのようなテクノロジーでも地球規模(または宇宙規模)で普及することが必須です。特定の国や地域だけで通用するテクノロジーには将来性はありません
- インターネット:スケーラビリティを十分発揮するにはインターネットとの親和性が高くなくてはなりません。インターネットも未来永劫(えいごう)存在するのではなく、別のネットワークテクノロジーに取って代わる可能性があります。どちらにしても、スケーラブルなネットワークテクノロジーと親和性を持つ、またはネットワークを使うことでポテンシャルがより発揮できるテクノロジーが未来を創るといってよいでしょう
- ソフトウェアセントリック:テクノロジーをユーザーに提供するにはハードウェアやソフトウェア、ネットワークが必要ですが、特定のハードウェアに縛られたテクノロジーはスケーラビリティに限界があります。ハードウェアへの依存性のない、ソフトウェアを中心とした「ソフトウェアセントリック」なテクノロジーに“未来”があります
これらの4要素を満たすテクノロジーには有望な未来が待っています。これらのポイントを押さえて、将来やってくる「新テクノロジーの波」に乗れるよう準備を怠らないことが重要だと筆者は考えています。
筆者紹介:甲元 宏明(アイ・ティ・アール プリンシパル・アナリスト)
三菱マテリアルでモデリング/アジャイル開発によるサプライチェーン改革やCRM・eコマースなどのシステム開発、ネットワーク再構築、グループ全体のIT戦略立案を主導。欧州企業との合弁事業ではグローバルIT責任者として欧州や北米、アジアのITを統括し、IT戦略立案・ERP展開を実施。2007年より現職。クラウドコンピューティング、ネットワーク、ITアーキテクチャ、アジャイル開発/DevOps、開発言語/フレームワーク、OSSなどを担当し、ソリューション選定、再構築、導入などのプロジェクトを手掛ける。ユーザー企業のITアーキテクチャ設計や、ITベンダーの事業戦略などのコンサルティングの実績も豊富。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 不確実な時代を勝ち抜く鍵は「ITインフラの近代化」 OracleとUberのCEOが語る
不確実な時代を勝ち抜く鍵は「ITインフラの近代化」 OracleとUberのCEOが語る
Oracleは「Oracle CloudWorld 2023」を開催している。サフラ・キャッツCEOがUberのダラ・コスロシャヒCEOと対談し「不確実な時代を勝ち抜く方法」を語った。 日立が国産のas a Service型IT基盤を発表 ハイブリッドクラウドの運用を効率化
日立が国産のas a Service型IT基盤を発表 ハイブリッドクラウドの運用を効率化
日立が「as a Service」型のIT基盤製品群「EverFlex from Hitachi」を発表した。パブリッククラウドとシームレスに連携可能なオンプレミス基盤を提供する。 「オンプレに投資は行わない」 SAPにおける生成AI、クラウド、日本の競争力強化への取り組み
「オンプレに投資は行わない」 SAPにおける生成AI、クラウド、日本の競争力強化への取り組み
SAPジャパンは「SAP NOW Japan」を開催した。同社の生成AIやクラウドにかける期待に加え、国際競争力が低下している日本が取るべき打開策が分かる。 経営層が誤解している「クラウド障害」の真実 ガートナーが提唱する復旧策
経営層が誤解している「クラウド障害」の真実 ガートナーが提唱する復旧策
クラウド障害によるビジネスへの影響が拡大する中、適切な復旧策を講じるためにはまず経営層の誤解を解くところから始める必要があるだろう。