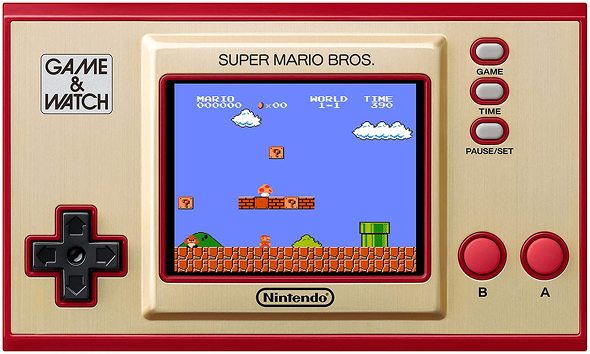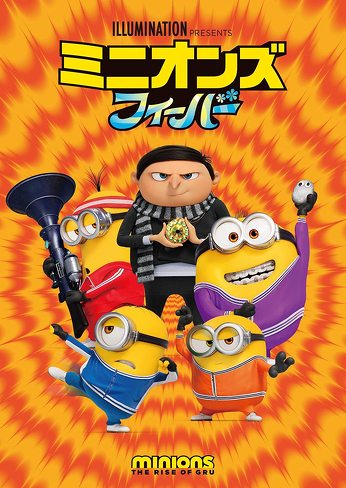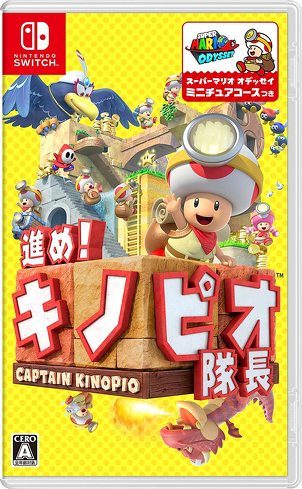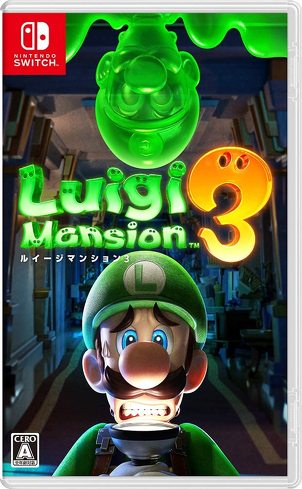興行収入1600億円突破! 「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」がヒットした3つの理由
全世界興行収入1600億円を突破し、いま乗りに乗っている3DCG映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」。日本でも公開からわずか17日間で80億円を超えるヒットを記録しており、これは今年に入ってからの最速となります。
「怪盗グルー」や「ミニオンズ」などで知られるイルミネーション・スタジオと任天堂により共同制作された本作。公開されてすぐ筆者も見に行きましたが、はっきり言って傑作でした。イルミネーション・スタジオと組んだことにも納得がいきましたし、世代を問わず評価が高い点にも合点がいきました。
なぜこんなにもマリオの映画がヒットしたのか? 実際に映画を見て思った3つのポイントについて紹介します。なお、本記事では多少のネタバレがありますので、その点はご了承の上でご覧ください。
木島祥尭
フリーライターとして、家電、家具、アニメ等の記事を担当。大学時代から小説や脚本などの創作活動にはまり、脚本では『第33回シナリオS1グランプリ』にて奨励賞を受賞、小説では『自殺が存在しない国』(幻冬舎)を出版。なんでも書ける物書きの万事屋みたいなものを目指して活動中。最近はボクシングをやりはじめ、体重が8kg近く落ちて少し動きやすくなってきました。好きなのものは、アニメ、映画、小説、ボクシング、人間観察。好きな数字は「0」。Twitter:@kirimachannel
→著者のプロフィールと記事一覧
原作ゲームのギミックと往年のヒット曲によって全世代が喜ぶ作品になっている
マリオの生みの親・宮本茂氏は本作について「ゲームを遊んでいただいた時の感覚までよみがえると思います」とコメントしていますが、まさにそのとおりの内容で歴代のマリオ関連ゲームを思い起こさせる作りになっていました。
マリオのジャンプやパンチ、スライディングを含めたアクションの数々、「ヤッフー!」やコイン、キノコでパワーアップするときの音など……世代を問わず誰もが知っているような要素が満載で、任天堂とかなり密なやり取りがあったことを感じさせますし、制作に6年かかったのもうなずけます。
こうしたマリオの基礎教養的なポイントをはじめ、映画の全編に渡ってマリオゲームのギミックが散りばめられており、どの世代でも反応できるよう構成・演出されている点が、今作がヒットした要因の1つと言えるでしょう。
例えば、配管工を営むマリオとルイージの2人がブルックリンの街を移動するシーンでは、3Dだった画面が突如2Dの画面に変化し、マリオでおなじみの横スクロールアクションが展開されます。左から右へマリオがギミックをうまく利用しながら進んでいく様は、まさにゲームそのものです。
これはなかなか憎い演出で、もともと横スクロールアクションは1985年の初代マリオから継承されているものなので、かつてファミコンを楽しんだ中年世代が「おっ!」と感激できるのはもちろん、20〜30代の若い世代も2006年発売の「NEWスーパーマリオブラザーズ」あたりを思い出すことができ、幅広い世代が懐かしさに浸れるわけです。
さらに音楽では、布袋寅泰の「BATTLE WITHOUT HONOR OR HUMANITY」やボニー・タイラーの「Holding Out for a Hero」、A-haの「Take On Me」など80年代から2000年代を彩った往年のヒット曲が使われており、当時青春時代を過ごしていた中年世代にとってのエモさが担保されています。
変身・戦闘シーンにおける全世代への目配せもすさまじく、まずはノーマルキノコでマリオが大きくなるところから描かれ、次にドンキーコングとマリオの戦闘シーンで食べると小さくなってしまうマメキノコが登場し、さらに窮地に陥ったマリオがベルを取ってネコマリオに変身するという流れで、マリオのさまざまなアイテムが登場します。
このノーマルキノコ→マメキノコ→ベルの順にアイテムを出していくあたりが見事でした。というのも、ノーマルキノコは1985年の初代から存在し、マメキノコは2006年の「NEWスーパーマリオブラザーズ」から、ベルは2013年の「スーパーマリオ3Dワールド」から存在するもので、リリースされた順に昔のアイテムから登場していることがわかります。初代を遊んだ中年世代も、「NEWスーパーマリオブラザーズ」を遊んだ20〜30代も、「スーパーマリオ3Dワールド」以降を楽しんださらに下の世代も巻き込んでどの世代も親しめるように工夫されているのです。
また、車での移動シーンも「マリオカート」の要素をこれでもかというくらいに詰め込んでおり、パーツをカスタマイズしてカートを作ったり、ノコノコの甲羅を投げて敵にヒットさせたりと、マリオカート勢もテンションの上がる演出が盛りだくさんでした。
マリオカートのコースはたくさんありますが、本作ではレインボーロードが使われており、このレインボーロードを選ぶあたりもファン心理をよく理解していると言わざるを得ません。レインボーロードはスーパーファミコンの初代マリオカートのときから最新作「マリオカート8」まで脈々と受け継がれてきたコース。昔のソフトを遊んだ世代も若い世代も共通して知っており、どの世代にとっても思い入れのあるコースなのです。
さらに本作では、カートから落ちたマリオが下のコースに移るという場面が用意されていますが、この下に落ちてコースをショートカットするという裏技は実際のマリオカートのレインボーロードにも存在します。最新の「マリオカート8」にも昔の「マリオカート64」にも存在する隠しルートで、プレイヤーなら誰もが一度は試したことがあるほど親しみのある要素なのです。
このようにマリオメインシリーズからマリオカートまで、あらゆるマリオ関連ゲームのギミックを使いながら、どの世代も取りこぼすことのないよう設計されている点は、本当に見事と言わざるを得ません。
異世界転生×少年マンガ×海外アニメの良いとこどりで、最強コンテンツに!
本作ではニューヨークでうだつの上がらない配管工・マリオとルイージの2人が、不思議な土管に吸い込まれて異世界に飛ばされ、最後には英雄として帰還するという、まさに異世界転生的なストーリーが展開されています。
そもそもマリオやルイージ、ピーチ姫といった人間と、キノピオやノコノコ、クッパなどの謎の生命体がなぜ同じ世界に存在するのかという素朴な疑問に「異世界転生したから」という形で答えている点も面白かったですし、異世界転生のプロットを使うことで今の時代にフィットしたものになっている点も興味深いところでした。
というのも、異世界転生は日本や韓国では今やメジャーなジャンルの1つで、受け入れられやすい物語形式です。特に日本では近年”親ガチャ”という言葉が流行っていることからもわかるとおり、時間をかけて積み上げていく努力論へのあきらめムードが強く、逆に運よく一発当てたいという”ワンチャン”的な思考や、時間をかけずに成功したいという”タイパ”的思考が支配的になりつつあります。
こうした時代状況を踏まえると、現実でうまくいかない主人公が異世界に行ってから”一発逆転する”という異世界転生もののストーリー展開は人々の心をとらえやすいと推測され、実際に日本や韓国で異世界転生ものは人気を集めている状況です。このように異世界転生ものを受け入れる土壌がしっかりある中で、マリオの映画を異世界転生ものとして仕上げたという点はマーケティング的に見ても英断だったのではないでしょうか。
上記は日本・韓国目線での解釈ですが、欧米的に見ても本作のストーリー構造は、冒険に出て何かを得て帰ってくるという”行って帰りし物語”として受け入れやすい内容だったと考えられます。これは”ヒーローズジャーニー”と呼ばれる西洋の神話などにもよく出てくる構成で、日常から出て別世界に行き変化して戻ってくるのが特徴です。
「スターウォーズ」をはじめ、「ハリーポッター」や「ナルニア国物語」、古くは「不思議の国のアリス」などがそれにあたります。特に土管を介して別世界に行くという展開は、駅の柱をくぐって魔法世界に行く「ハリーポッター」や穴に落ちて別世界に迷い込む「不思議の国のアリス」と、何かを介して移動するという点で似ており、欧米的にも慣れ親しんでいる展開だったと言えるでしょう。
さらに少年マンガ的な要素が盛り込まれている点にも注目です。本作においてドンキーコングとマリオは最初敵対関係にありますが、拳を交えてからは協力関係に変化し、クッパという共通の敵に立ち向かっていきます。初めは敵同士だった2人が共通の敵を見つけて仲良くなる構図は、少年マンガ(もっと言えば少年ジャンプ)に良く見られるもので、マイナスの関係からプラスの関係への変化という形でギャップが大きい分、観客の心を熱くさせる効果があります。
ヤンキーがネコを助けるというようにギャップのあるものに人は感動しやすく、それはキャラクター同士の関係性にも言えることです。「ドラゴンボール」で言えば悟空とベジータの関係性であり、「鬼滅の刃」で言えば炭治郎と柱の関係性と言えるかもしれません。こうした少年マンガ的友情劇としての魅力を持ち合わせているのも、コンテンツとしての面白さを支えている要素の1つだと解釈できます。
また、イルミネーション・スタジオとマリオゲームの相性が抜群だったという点も押さえておかなければなりません。イルミネーション・スタジオと言えば「怪盗グルー」や「ミニオンズ」などのヒット作で知られており、頭身の低いキャラクターを魅力的に描くことを得意としています。
小さな生き物たちが、わちゃわちゃとそれぞれ好き勝手に騒いでいる様子を描くのがうまく、ミニオンズはその最たる例です。この点から考えると、そもそもマリオ自身も頭身が低いですし、特にキノピオはミニオンズと似たようなサイズ感で、同じ形状の小さな生き物がたくさん集まっているという点でも似通っています。
ミニオンズで発揮された表現がキノピオやノコノコなど頭身の低いキャラクターの表現にそのまま生かされており、ディズニーでもピクサーでもなくイルミネーション・スタジオでなければならなかった理由が、ここにあるように思われます。
また、これはディズニーやピクサーにも共通する点ですが、説明台詞が続くシーンでもギャグやゲームのギミック、世界観の面白さなどを混ぜて展開し、ほとんど止まっている瞬間がなく飽きがこないよう設計されている点も見事でした。
このように本作は異世界転生や少年マンガ、海外のアニメ映画の持つ良いエッセンスを掛け算して作られており、隙のないエンターテイメント作品に仕上がっているのです。
”トロフィーガール”から”トロフィーブラザー”へのアップデート
本作ではジェンダー感が現代のものにアップデートされており、その点も多くの人に受け入れられた要因の1つと言えます。マリオと言えば、クッパにさらわれたか弱いピーチ姫をマリオが救出するという、いわゆる”トロフィーガール”的な展開がお決まりでした。もちろん、これはこれで悪くないのですが、現代の価値観としては受け入れられにくいのも事実です。
無力で助けられることが多かったピーチ姫のキャラクターイメージが本作では刷新されており、自主自立したパワフルな人物に生まれ変わっています。キノコ王国を守るために、勇猛果敢にクッパやその手下たちと戦いますし、類まれな身体能力や武器術、炎・氷などの魔法を操る術も身に着けており、マリオよりも強く好戦的なキャラクターとして描かれています。
劇中ではピンチになるシーンもありますが、あくまでも自分の身は自分で守る精神を崩さず、もはや受け身的なお姫様ではありません。「アナと雪の女王」以降の価値観で作られた新たな時代のヒロイン像と言って良いでしょう。
とにかく強いヒロインなので今回はトロフィーにされることもなく、代わりにルイージがクッパに捕らわれてしまうという展開になります。”トロフィーガール”から”トロフィーブラザー”への転換が図られたというわけです。
また、ルイージは「ルイージマンション」を思わせるような、おどおどした比較的女々しいキャラクターとして出てくるため、捕まってしまうという展開にも無理がなく自然と見られるのもうまいところです。
マリオとピーチの関係が”ラブロマンス”ではなく一緒に戦う戦友的な関係に近く、本作ではむしろマリオとルイージの”兄弟愛”にスポットが当てられています。”ラブロマンス”から”ブロマンス”へ変化している点にも現代的な調整が行われている印象を受けました。
ちょうど新海誠監督が「君の名は。」などで使っていたそれまでの”ボーイ・ミーツ・ガール”的な展開をやめて、「すずめの戸締まり」で”ガール・ミーツ・ボーイ”に切り替えたのと同じように、本作も”女の子は助けられる存在”という価値観から脱し、現代に合うようにアップデートされています。
原作リスペクトしつつも原作の設定をそのまま通すのではなく、時代に合わせて変化させるべきところは変化させるという柔軟性を持ち合わせている点も、本作のヒットを支えている要素と言えるかもしれません。
「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」の関連ゲーム
「マリオのゲーム」最新ランキング!
こちらの記事も要チェック!
関連記事
 ニンテンドースイッチ これから登場する新作ソフト4選&ランキング【2023年5月版】
ニンテンドースイッチ これから登場する新作ソフト4選&ランキング【2023年5月版】
人気ゲーム機「ニンテンドースイッチ」(Nintendo Switch)。これから発売される新作ソフトの人気作品を、Amazonの新着ランキングからピックアップして紹介します。 【ニンテンドースイッチ】新作ゲームソフト発売スケジュール【2023年5月版】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」いよいよ登場!
【ニンテンドースイッチ】新作ゲームソフト発売スケジュール【2023年5月版】「ゼルダの伝説 ティアーズ オブ ザ キングダム」いよいよ登場!
続々とリリースされるニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)の新作ゲームソフト。期待の最新作をピックアップして発売予定日順に一覧で紹介します。(2023年5月1日現在) 「クラシックゲーム機」おすすめ5選 懐かしいタイトルを手のひらサイズのゲーム機で【2023年3月版】
「クラシックゲーム機」おすすめ5選 懐かしいタイトルを手のひらサイズのゲーム機で【2023年3月版】
昨今注目を集めているのが、発売当時のゲームを遊べる「クラシックゲーム機」です。今回は、懐かしいゲームの数々を遊べるミニクラシックゲーム機を紹介します。 ニンテンドースイッチ「体験版が遊べるソフト」おすすめ5選 無料でも楽しめる人気作がたくさん!【2023年1月版】
ニンテンドースイッチ「体験版が遊べるソフト」おすすめ5選 無料でも楽しめる人気作がたくさん!【2023年1月版】
人気のゲーム機「ニンテンドースイッチ(Nintendo Switch)」。ソフトを購入する前に、まずはお試しで遊んでみたいという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、無料体験版が遊べる人気のソフトを紹介します。 「タグ・ホイヤー」と「マリオカート」が限定コラボ! カートに乗ったマリオ、キラーやバナナなどのモチーフが盛りだくさん
「タグ・ホイヤー」と「マリオカート」が限定コラボ! カートに乗ったマリオ、キラーやバナナなどのモチーフが盛りだくさん
タグ・ホイヤーは、任天堂とのコラボウォッチの第2弾として、人気ゲームシリーズ「マリオカート」をテーマにした限定モデル「タグ・ホイヤー フォーミュラ1 × マリオカート リミテッドエディション」を発表しました。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
- 大きすぎず使いやすい「キタムラのバッグ」おすすめ3選【2026年2月版】
- 今売れている「レトルトカレー」おすすめ3選&ランキング 無印良品の商品が1位【2026年2月版】
- 文句なしにカッコいいです。セイコーの「黒ウォッチ」3選【2026年2月版】
- 【無印】の高見えケースを「ショルダーポーチ」にしてみたら→身軽なお出掛けにぴったりだった! カスタムできる優秀アイテム
- デジカメ専門家が選ぶ、コストパフォーマンスが高い「ミラーレス一眼」3選(フルサイズ編)
- JAL×3COINSの「旅行で使えるコラボアイテム」3選 旅のプロが考える“あったらいいな”が形に【2026年2月版】
- ミニマリストさんにおすすめの「ミニ財布」3選【2026年2月版】
- 今売れている「コーヒーメーカー」おすすめ&ランキング【2026年2月版】
- 今売れている「インスタントコーヒー」おすすめ3選&ランキング ブレンディやネスカフェのものが人気【2026年2月版】
- 「全部で3色購入しました」【GLOBALWORK】の「あったかスッキリイージーパンツ」が大人気! 「上に着る服を選ばない」「動きやすい」