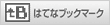| Mobile:NEWS | 2003年11月4日 00:55 AM 更新 |
BREW2.1で何が変わるのか?
auのA5500シリーズでは、アプリプラットフォームであるBREWのバージョンも2.0から2.1に上がった。BREW2.1のアップデートポイントは何か。そして、今後BREWはどんな方向に進化していくのか。
auのA5500シリーズ(10月6日の記事参照)では、アプリケーションプラットフォームBREWのバージョンが上がった。最新のBREW2.1では、何がどう変わったのか。
|
BREW2.1で大きく変わった点は「カメラ」「3D描画」「サーバ機能」の三つだ。
※もう一つ、「A5502K」(10月6日の記事参照)が搭載する地磁気センサーをサポートする「GetOrientation API」もBREW2.1で標準化された
各フレームをキャプチャ可能。自由度高いカメラAPI
一つ目はカメラだ。ドコモやボーダフォンでは、504iSシリーズ、J-SH53以降、Javaアプリケーションからカメラを操作できるようになっている(2002年11月の記事参照)。BREW2.1からは、BREWアプリからもカメラ撮影などが可能だ。
ただし、ドコモのiアプリからのカメラ操作がかなり限定されたものなのに対し(連載「エンタメiアプリを作ろう」参照)、BREW2.1からの操作はプリミティブだ。「カメラモジュールを起動して、各フレームを全部送ってくる。プレビュー表示や撮影もBREWアプリ側で処理する」とクアルコムジャパンのモバイル・アプリケーション・スペシャリストである久保雄介氏は話す。
ズームやブライトネス操作に関するAPIは標準化されており、そのほかカメラモジュール固有の機能もBREWから操作できる場合がある。「BREWはメーカーの組み込み用ソフトも目指しているので」(久保氏)という理由だ。
MSM6100の3D描画機能をサポート
二つ目に追加されたのは3D描画用のAPIだ。ボーダフォンやドコモ端末には、Javaアプリから利用できる3Dポリゴンエンジンが用意されているが、同様にBREW2.1でも3D描画が可能になる。
ただし注意したいのは、これが「MSM6100に用意された3Dアクセラレーション機能を動かすためのもの」(久保氏)であることだ。OpenGLなどと同程度にプリミティブな、Qualcomm固有のフォーマットの3Dデータに対応している。
A5500シリーズに搭載されたベースバンドチップ「MSM6100」は3D描画機能を持っており、それを利用するためのAPIとなる。そのため3D描画機能を持っていない一世代前のチップ「MSM5100では、ソフトレンダリング部を用意してもらう必要がある」(久保氏)。
国内ではエイチアイの3Dポリゴンエンジンがデファクトスタンダード的な位置づけにある。KDDIはBREW2.1以降、エイチアイの3Dエンジンを「BREW Extension」として利用できる環境を整えると話しており(2002年8月の記事参照)、MSM6100の3D描画APIは主に海外向けと想定される。
端末と端末がエンドツーエンドで接続
三つ目が、「TCPのサーバ側になる機能」だ。BREWは携帯向けJava(CLDC)とは異なり、TCP/UDPの多様な通信プロトコルをサポートする。ただし、これまでは対戦ゲームなどで端末同士が通信をしているように見えても、「ゲームサーバが真ん中にあって、そこと通信していた」(久保氏)。
BREW2.1以降はTCP通信を待ち受ける(listenする)機能が追加され、真の意味で“端末間同士”のTCP通信が可能になる。
A5500シリーズでは“KDDI独自拡張”も
上記の三つの新機能は、世界各国のBREW2.1端末がサポートする共通機能だ。これとは別に、A5500シリーズにはKDDI独自のAPI拡張も施されている。
- データフォルダへのアクセス
- アドレス帳への書き込み
- QVGA対応
BREW端末のスペック表でデータフォルダ容量とBREW保存容量が分かれて書かれているように、BREWは既存のauのデータフォルダとはファイルシステムが異なり、BREWが扱うデータ自体も別個に扱われていた。BREWからデータフォルダへのアクセスが可能になったことで、例えばゲームの賞品として特典画像をプレゼントする……といったことも簡単になる。
QVGA対応は、特に描画アクセラレーションなどが規定されたわけではないが、auA5500シリーズとして共通化された。
なお、BREW2.1は基本的に後方互換性を持っており、BREW2.0向けに作られたアプリケーションも動作する。ただし、画面解像度がQVGAになったため、全画面できれいに動かすには調整が必要な場合もある。
今後のBREWプラットフォームの進化
BREWというプラットフォームは、基本的にQualcommのチップに搭載された機能を活用するためのものだ。そのため、BREWの進化もMSMチップの機能追加をフォローする形で進む。
BREW3.0、4.0では「メモリリークの問題など、メモリ保護の仕組みを導入する予定。これまではネイティブアプリケーションとBREWのメモリ空間が一緒だったが、分ける形になる」と久保氏。
MSM6100がコアに持つARM9には(7月16日の記事参照)、ハードウェアとしてMMU(Memory Management Unit)が搭載されている。BREW2.1ではMMUを利用していなかったが、今後は「ハードウェアの管理を前提として」(久保氏)MMUを使ったメモリ保護機能が搭載されていくもようだ。
関連記事
特徴があまりに多いため、全貌を把握しにくい、今回のau冬モデル。CPUの違い、カメラ、音源チップなどから、各機種の違いを探っていく。
WIRELESS JAPANの講演で、KDDIがこの秋に予定している端末の姿の一端が明らかになった。ARM9コアのチップを使い高速化を果たすと共に、BREW2.1を搭載。液晶もQVGA化して、GPSを使ったナビゲーション機能の強化も図るという。
前回の連載では、BREW SDK 2.1をインストールするところまで解説しました。今回は実際にソースコードを書き、BREWエミュレータで動かしてみましょう。画面に "Hello World" と表示する簡単なBREWアプリを作成します。
auの「A5304T」が対応したBREW。しかしBREWとは何なのだろうか。Javaとはどこが違うのだろうか。一般ユーザーの視点と、携帯アプリケーションのビジネスプレイヤーの視点からまとめてみた
KDDIがBREW端末「A5304T」を発表した。BREWによって、アプリケーションの世界流通、企業向けアプリケーションの開拓、コンシューマ向けの快適なアプリケーション環境を狙う。Javaとは異なり、今後ローエンド機にもBREWを搭載していく予定
2003年第1四半期からの本格展開が待たれるダウンロード型BREW。ワールドワイドな展開をにらんださまざまな仕様が盛り込まれている
関連リンク
[斎藤健二, ITmedia]
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
モバイルショップ
 最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!
 最新スペック搭載ゲームパソコン
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!