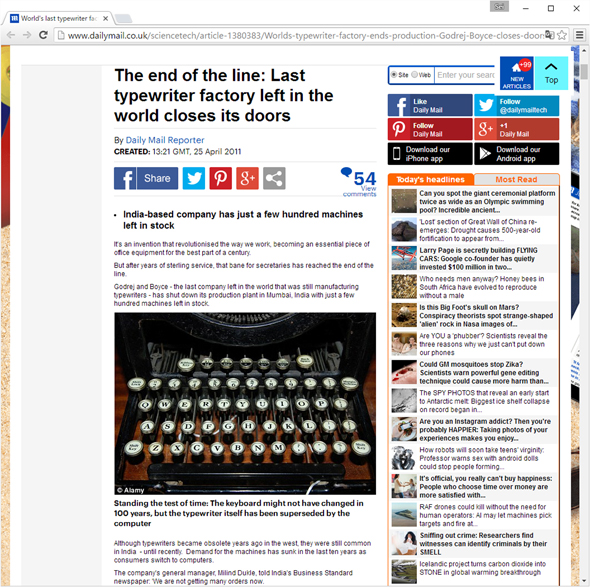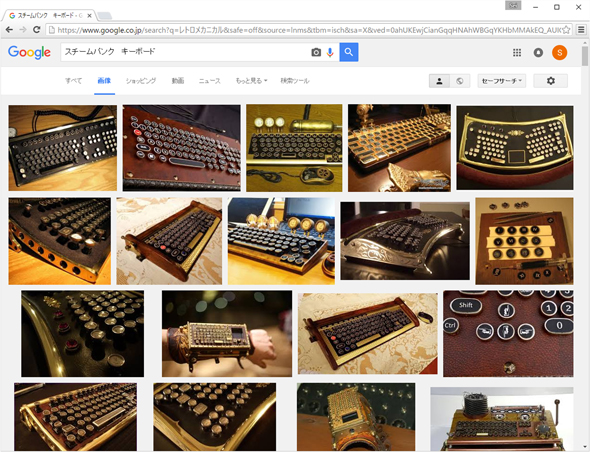タイプライター風キーボード「Qwerkywriter」でレトロメカニカルの雰囲気にひたる:リアルとイメージの絶妙なバランス(1/4 ページ)
デザインは? 使用感は? 細部までねっとりと評価する。
タイプライター、知ってる?
2011年4月、世界最後のタイプライター工場が閉鎖された。1867年に米国で生まれて以来、タイプライターは実に足かけ3世紀にわたって人々の文書作成を手助けしてきたことになる。
機械式タイプライターの基本的な仕組みはシンプルだ。タイピストがキーを押すとその力でハンマーが動き、インクリボンを紙に叩きつける。ハンマーの先にはキーに対応した活字が付けられており、打ったキーの通りに紙に印字される。現在のパソコンなどで使用されているキーボードの原型とも言えるもので、このころからすでに「QWERTY(クワーティ)配列」と呼ばれる現在主流のキーレイアウトが採用されていた。
筆者も中学のころ、家に転がっていたタイプライターを叩いたことがあるが、ともかくキーが重たかった記憶がある。なにせ、たかだか1センチ程度のキー押下げ動作で、10センチ以上もハンマーを動かさなければならない。テコの原理を考えても相当重たいことが分かる。しかも、キーを打つ力の強さが印字インクの濃さに直結するため、美しい仕上がりのためには強く、同じ力で打ち続けなければならない。
だが、タイプライターにはレトロメカニカル――スチームパンクにも通ずる古き良き機械の雰囲気がある。スチームパンクは蒸気機関が発達した時代を描いたSFジャンルの一つ。ヴィクトリア朝時代(1800年代)の雰囲気を持ち、当時入手可能な材料を用いて、当時の技術力で作り上げたかのような外見のガジェットが特徴だ。真鍮(しんちゅう)を用いた鈍い黄金色、蒸気圧計をはじめとしたアナログメーター、いくつもの管が並び、多数の歯車とボタンが並ぶなど、使いにくそうだけれども使うことが楽しいだろうな、と思わせるスタイルは作品を離れ、一つの様式として確立している。
もっとも、タイプライターはヴィクトリア朝後期に登場した(というのも驚愕だが)ものの、全盛期はそれから100年ほど後になる。レトロメカニカルなイメージが強いのは1920年〜1960年ころのモデルまでで、それ以降は現在のキーボードに近い造形に寄っていく。
Qwerky Toys, Inc.の「Qwerkywriter」はそんな初期のレトロメカニカルなタイプライターを再現したBluetoothキーボードだ。クラウドファンディングサイト「KickStarter」で出資を募り、9万米ドル(約962万円)目標のところを13万米ドル近く(約1380万)の調達に成功、2015年11月に製品化を果たしている。予約特別価格は329米ドルだったが、現在は通常価格の米349ドルで販売されている。そして2016年5月31日、フリーウェイが全国のPC専門店、ネット通販店で国内販売を開始した。
Qwerkywriterは想定価格5万9800円(税込)と、キーボードにしてはかなり高額な製品。外観写真やスペックだけでなく、実際に触ってみなければわからないところを重点的に見ていくことにしよう。
「打っていて楽しい」を実感するメカニカルスイッチ
Qwerkywriterの本体はがっしりとしたアルミ合金製。重量1.3キロで安定感がある。キーは83英語配列でキーピッチ16ミリ、キーストローク4ミリ。円形キートップは周囲をクロムメッキされており、黒い本体・キートップの中で光沢が映える。表面はなめらかな凹面仕様で、指に吸い付くような感覚が心地よい。
円形キートップを外すと本体から飛び出した青軸のメカニカルスイッチが見えるが、この青軸の打鍵感が実によくQwerkywriterのフォルムにマッチしている。
今のPCのキーボードはキーの押下げを電気信号として認識する。そのため、キーの打ち心地は機構的な必然性だけで決まるのではなく、むしろ逆に狙った打鍵感を得られるように「味付け」されたキースイッチによって決まる。廉価なキーボードと高級キーボードではこの部分に差があると言ってもよい。
現在主流のキースイッチ機構はメンブレンスイッチ、静電容量無接点方式、メカニカルスイッチの三つに分けられるが、もっとも「味付け」にこだわりを見せるのがメカニカルスイッチではないだろうか。
メカニカルスイッチはキートップと接点をスプリングで反発するように保持し、キートップが押下げられて接点同士が接触することでキー入力を検知する。スプリングの強さ、接点の位置などで打鍵感をさまざまに調整することができる。独Cherry社は打鍵感の異なるスイッチを多数出しており、それぞれを軸の色で区別している。今や黒軸、赤軸、茶軸、青軸という言葉が打鍵感を表す共通言語として使用されているくらいだ。
その中でもQwerkywriterに採用されている青軸にはカチッというクリック感があり、約50グラムという高めの押下圧と相まってしっかりした入力感がある。入力を楽しむユーザーには最適なメカニカルスイッチだ。
この青軸の採用はリアルとイメージの折り合いがとれた、実にバランスのよい選択に思える。タイプライターの押下圧をそのまま再現すると、重すぎてとても現代の実用に耐えるものではない。かといってカコポコという一般的なキースイッチの音ではピンとこないだろう。クリック感のある青軸だと「タイプしている」という感じが得られつつも、日常的に叩き続けられる押下圧だ。
もっとも、本来のタイプライターの音はルパン三世のタイトルコールのあの音。青軸のクリック音とは全然違うはずなのに違和感がないのは脳内補完されてしまうからなのかもしれない。
Bluetooth接続とスタンド
QwerkywriterはBluetooth接続のみ。背面にはmicro USBポートがあるが、これは内蔵バッテリーの充電用で接続用インタフェースとしては使用できない。スマートフォンやタブレットなど、モバイル機器が普及した現在ではUSB接続よりもBluetooth接続の方が利用範囲が広いのだろう。背面のプレートはスタンドにもなっており、厚さ12.7ミリまで対応できる。スタンド面の高さは低めだが、Qwerkywriter自体が重量があるため、大きめのタブレットを置いても安定している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.