成功企業の必要条件はスピード――統合型システムは業務部門の要求に応えられるか?:アナリストが語る!仮想化・クラウドの選択で考えるべきこと
IT部門に対するビジネス部門の期待度は年々高まりつつある。だが、既存業務をこなすだけでも手一杯の状況でIT部門がその期待に応えるのは簡単ではない。ITRシニア・アナリストの甲元宏明氏は、「テクノロジーを生かすことができる企業はビジネスも成長させている」と話す。ビジネスの期待に応えるためのテクノロジーとは具体的にどのようなものだろうか?
IT部門が日々抱えている業務は、システムの企画・開発から既存システムの安定運用まで幅広い。特にIT予算に占める割合が6割とも7割とも言われる運用・保守は大きな負担になっている。毎年のIT予算は横ばいか、良くても微増という企業も多い。IT部門としては「もっとビジネスに貢献し、企画や開発により多くのリソースを割きたい」というのが、本音ではないだろうか。
経営層や業務部門がIT部門に寄せる期待も高まっている。既存ビジネスを成長させることに加え、新規ビジネスを立ち上げ、一気に加速することで、競合よりもいち早く優位性を確保したいためだ。テクノロジーを駆使できるIT部門の役割は実に大きく、皆がその可能性に注目している。
つまり、業務部門とIT部門の思いは、本質的な部分では一致しているはずだ。しかし時にお互いのコミュニケーション不足から、同じ目標に向かって取り組めなくなるケースも少なくない。
業務部門とIT部門を取り巻く複雑な関係とは?
調査会社アイ・ティー・アール(ITR)でシニア・アナリストを務める甲元宏明氏は、このような状況を「不幸な関係」と表現したうえで、その要因となっている問題点を3つ指摘する。
1つ目の問題点は、日本のIT環境が“超”サイロ化しているという現実だ。システムのサイロ化は、昔から脈々と行われてきた個別の要請に応じてシステムをバラバラに構築するという、いわば悪しき慣習の結果であり、スピードや効率性が重視される今のITニーズにマッチしていない。それを解決するために「標準化」も叫ばれてきたが、全社的にサイロ化してしまった環境をIT部門単独で打破するのは容易ではない。
2つ目の問題点は、IT部門がテクノロジーを活用し、業務変革につながるような新たなシステムの提案をしようとしても、なかなか積極的な協力を得られないというもの。業務部門は、IT部門のサポートやテクノロジーに期待を寄せつつも、一方で「動いているシステムをなぜ変える必要があるのか」という意識も持ち合わせているため、特に業務部門にオーナーシップがあるシステムの場合、「みんなを巻き込み、時間や予算をかけてまで新しい環境を展開することは面倒だな」とIT部門が及び腰になってしまい、実現できないままのケースも多い。
3つ目の問題点はいわゆる「ベンダーロックイン」から逃れたいというマインドだ。経営サイドが意識しがちな点であるが、明確な根拠があるわけではなく、「特定のソリューションに依存するのは何となく不安だから」といった漠然とした不安に起因している。結果として選択肢を狭めてしまうことになるわけだ。
こうした3つの問題がそれぞれに作用することで、ビジネスに貢献する新たなテクノロジーの積極的な活用が思うように進まないというのが、甲元氏の指摘である。反面「徹底したコスト削減が至上命題になっている大手金融企業が、特定のベンダーと密接なパートナーシップを組むといったケースはある」(甲元氏)といい、こうした企業では強いコスト意識のもと、むしろベンダーロックインを積極的に活用して、乱立状態の多数のシステムを共通化・標準化させることにより、その目的を達成している格好だ。
繰り返し述べるが、IT部門は「ビジネスに貢献したい」という“正のマインド”を有している。それをいかんなく発揮するには、ここまで述べたような“負のマインド”を変えることが最初の一歩かもしれない。それにはIT部門自身が率先して、テクノロジー活用を妨げる負のマインドを捨て去るべきなのは言うまでも無い。
成功企業に共通するキーワード――それは「スピード」
ではIT部門は何を指針にすべきだろうか? このような状況を打破するヒントとして、多くのユーザー企業と向き合った経験から甲元氏が導き出したのは「例えばクラウドのような、新しいテクノロジーを積極的に活用している企業は、ほぼ間違いなくビジネスも成長させている」という事実だ。
例えばここ数年、企業の間で広く導入・活用が進んでいる代表的なテクノロジーが「仮想化」と「クラウド」である。仮想化の活用では、物理環境で稼働していた無数のサーバを集約することで、マシンルームもコストも非常にスリム化されるという恩恵をもたらした。見た目にもその効果を実感できることから、分かりやすいテクノロジー活用だといえる。
パブリッククラウドも、ITに要求するスピードや効率性を実現できる手段として、本格的に活用され始めた。当初は「業務データを外部サービスに預けても大丈夫だろうか」といった懸念を抱く企業もあったが、可用性や信頼性の向上にともない、基幹システムをクラウドで稼働させたり、クラウド上のシステムと連携したりというスタイルも珍しいものではなくなった。
「成功する企業と、そうでない企業の違いは“ビジネスのスピード”にある」というのが甲元氏の読みである。言いかえれば、クラウドや仮想化といった新しいテクノロジーを正しく提供できるか否かが、IT部門のプレゼンス向上につながるというわけだ。
そして、仮想化やクラウドと並んで圧倒的なスピードをもたらす“ビジネス貢献型テクノロジー”として注目したいのが、「統合型システム」と呼ばれる存在だ。
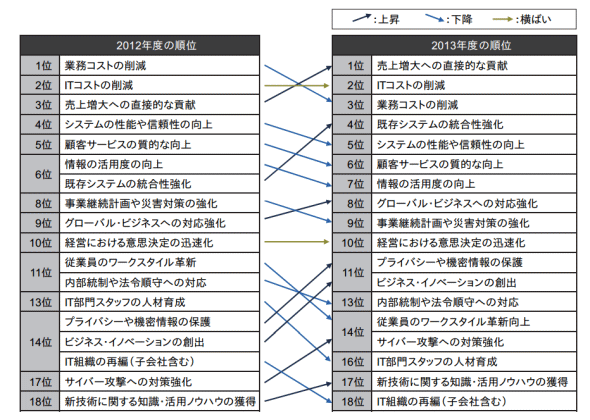 IT戦略において最重要視されるキーワード(2012〜2013年度) 出典:ITR「IT投資動向調査2013」
IT戦略において最重要視されるキーワード(2012〜2013年度) 出典:ITR「IT投資動向調査2013」ユーザー企業が自社のIT戦略で重要視する項目において、「売上増大への直接的な貢献」がコスト削減を上回った。このようにビジネスへの貢献をITに期待する意識が高まっている
仮想化、クラウドと並んでビジネスを加速するテクノロジー「統合型システム」
統合型システムは、サーバやネットワーク、ストレージなどのインフラシステムを、実績に基づく最適な構成で組み合わせたオールインワン型ソリューションである。ベンダーによる事前検証やノウハウを、ベストプラクティスとして反映した形で出荷されるため、手間暇をかけることなくすぐ導入でき、運用面でも標準的な手法を適用できる。
この統合型システムはどのようなシーンでの活用が期待されるのだろうか。甲元氏は、その一例として「垂直の統合や水平の連携を問わず、企業内に複数存在するシステムをつなぐ“センター”のような役割を担う」と話す。
ITインフラの領域ではクラウドのIaaSを活用する動きが本格化しているが、当然ながら、“超”サイロ化した既存インフラの全てをIaaSへと移行させることは容易ではなく、実際にはIaaSに構築したシステムと連携するハイブリッド型が主流である。ただし、既存インフラが“超”サイロ化したままでは連携すらもうまくはいかない。
しかし“超”サイロ化した既存システムの最適化は避けて通れない。そのファーストステップとして、これまで主に行われてきたのがサーバの仮想化である。
だが、インフラ最適化という視点でみると、サーバの仮想化だけでは十分ではない。本来はネットワークやストレージを含めたインフラ全体で取り組み、さらにはその先にある運用までも考えなくてはならない。その点で運用面までもカバーしている統合型システムは、「ビジネスに貢献するIT」を実現していくアプローチにおいて有望な選択肢になり得る。
また甲元氏は、新規ビジネスを迅速に立ち上げなくてはならない時のテクノロジーとしても、統合型システムがそのニーズに応える存在になるだろうと指摘する。
ビジネスの基盤となるシステムを導入する際には、設計・選定・調達・検証・設定・構築など、多くの工数を要する。例えばハードウェア調達に関わる負荷を解消したのがクラウドだが、セキュリティポリシーなどのさまざま条件からクラウドが使えない場合は確実に存在する。
そうした点でも統合型システムを活用すれば、IT部門としてはシステムの設計や開発にリソース集中させることができる。ビジネスを支えるためのシステム基盤をビジネスサイドへすぐに提供でき、その後の運用面における負担も小さくできるだろう。
このように統合型システムは、「ビジネスに貢献するIT部門」を実現する上での足かせを払しょくしてくれる、「スピード感にあふれた頼もしいテクノロジー」だと言える。
統合型システムが「開発生産性向上」と「意思決定の迅速化」もたらす
甲元氏が指摘するように、業務部門とIT部門のマインドが一致し、そこにテクノロジーという武器が加われば、ビジネスに計り知れない効果を生むことができるのは間違いない。「テクノロジーを活用しビジネスのスピード感を増した企業が成功する一方、運用コストばかりを重視しITに投資しない企業ではビジネスが成長していないという傾向がある」――これが甲元氏の指摘だ。
システムのお守りをするだけのIT部門から、ビジネスの成長に貢献できるIT部門に変革するには、スピード感が必要だ。それを実現する環境としては仮想化やクラウドに加えて、統合型システムが登場している。「IT部門の開発生産性を向上し、意思決定のスピードを圧倒的に改善できるソリューションとして、統合型システムに注目している」(甲元氏)。
この統合型システムは、ビジネスサイドが要求するスピードにIT部門が応えていく上で、どのようなメリットを提供してくれるのだろうか。次回は、その具体的な特徴や導入のポイントなどについて詳しく触れたい。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:日本電気株式会社
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2014年9月3日
 アイ・ティー・アール シニア・アナリスト 甲元宏明氏
アイ・ティー・アール シニア・アナリスト 甲元宏明氏