普及が進むデスクトップ仮想化――「仕組み」と「メリット」を知る:図解でわかるVDI
クライアントPCからデスクトップ環境を切り離し、サーバ上で稼働させる「VDI(Virtual Desktop Infrastructure:デスクトップ仮想化基盤)」が注目されている。決して最新技術ではないものの、ネットワークの大容量化や画面転送プロトコルの高速化などの技術革新により、ここに来て普及の兆しをみせている。
クライアントPCに課題あり
どの企業でも、数年おきにクライアントPCのリプレースが行われている。今まではハードウェアをそっくり入れ替えることが当たり前だったが、ここ数年は事情が変わりつつある。従来型のクライアントPCを導入するのではなく、VDIを導入する企業が急増しているのだ。
従来型のクライアントPCは、ユーザーにとって自由度や利便性が非常に高い。けれども、企業にとっては幾つもの課題がある。例えば、クライアントPCではHDDをはじめとする可動部品の故障が少なくない。HDDに保存されているデータを定期的にバックアップしておかないと、突然故障して大切なデータが消失し、ビジネスにおいて多大な損失を被るおそれがある。
クライアントPCの内部にデータが保存されていると、セキュリティ対策の面でも心配がある。万一ノートPCのような可搬型のクライアントPCが盗難に遭ったり紛失したりすれば、会社の機密情報が漏えいするかもしれない。
加えて情報システム部門にはもっと多くの課題がある。管理するクライアントPCの台数が増えると、障害対応に伴う負担は大きくなるし、統制をとることも容易ではない。ソフトウェアの不具合や脆弱性を修正するパッチを適用するような運用管理の負荷も高い。このようなクライアントPCの課題を解決する有力な選択肢として、VDIが注目されているのだ。
VDIが提供するメリットは何か?
VDIの技術自体は、決して新しいものではない。Windows NT Serverにターミナルサービス機能が搭載された1990年代から一部で利用されてきたものだ。しかし、当初のVDIはサーバ性能やネットワーク帯域の制約から、クライアントPCの代替として導入されることは少なかった。ここ数年になってサーバの高性能化、ネットワークの広帯域化、仮想化技術の進展といった技術革新が進み、ようやく実用段階になってきた(図1参照)。
現在のように、多くの企業が導入を検討するようになったきっかけの1つは、2011年3月の東日本大震災だ。震災直後に発生した交通網の大きな乱れや計画停電によって休業を余儀なくされた多くの企業が、どこからでもネットワーク経由で事業を継続できるソリューションとしてVDIに着目した。また、クライアントPCのOSに多く使われてきたWindows XPのサポート終了により、クライアントPCのリプレース需要が高まったのも、VDIが注目されるようになった理由の一つだ。
さらに、いつでもどこからでもネットワーク経由でデスクトップ環境を利用できるという特徴から、ワークスタイル改革に取り組む際の技術基盤としても注目されている。スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスからデスクトップを閲覧・操作できるため、その利便性は一段と高まっている。
情報システム部門の立場からもVDIは、セキュリティ対策や運用管理の面で有効な手段だ。アプリケーションやデータはサーバで一元的に集中管理できるため、情報漏えいやマルウェア感染のリスクを軽減できるし、新規提供時やアプリケーションの大幅な入れ替えの際に、端末の設置場所へ出向いて1台ずつ手作業をしなければならないといった負担から解放される。端末の故障による業務停止も極小化できる。
具体例としては、業務の一部を海外へ移管する場合などに、データ自体は日本国内に置き、業務での操作は現地で行うことようにして、厳格なセキュリティレベルを維持することが挙げられる。また流通業なら、店舗端末をシンクライアントにすることで、店舗のPC障害による業務停止の時間を短縮するといったことも期待できる。
VDIの主なメリットとしては以下の4つの点が挙げられる。
- 事業継続性の向上
- セキュリティ対策強化による安全な業務遂行
- クライアント端末の運用管理負荷の劇的な改善
- 外回りでの隙間時間を活用したタブレット端末などによる業務効率の改善、在宅勤務やリモートアクセスなど従業員の生産性が高まる新たなワークスタイル改革
つまりVDIは、「業務上のロスを稼働に変える」手段として、単なるコスト削減以上の効果と柔軟性をもたらすわけだ。
このようにVDIのメリットは多いが、コスト面では従来型のクライアントPCと比べても劇的に削減効果を得られるわけではないだろう。初期導入コストは、サーバとシンクライアント端末を用意しなければならないことで、むしろPCより高い。運用後の節電効果についても同様だ。
したがって、従来型のクライアントPCと「シンクライアント端末+サーバ」という初期費用の違いのみで判断するのではなく、業務上の効果を適切に数値化して導入検討を進めるのが肝要である。これは、同じ仮想化技術の適用となる「サーバ仮想化」のように、仮想化集約により物理サーバ数が減ることでのコスト削減を目的とするのとでは、大きな違いがあるといえる。VDIはコスト削減というより、事業継続性の向上、セキュリティ対策の強化、運用管理性の改善などを重視する場合に有効なソリューションといえるだろう(図2参照)。
適材適所で選ぶ3つの方式
VDIには、大きく分けて3つの方式がある。それぞれの方式の特徴に応じて、ユーザーが適材適所で選択することが望ましい。
1つ目の方式は「ターミナルサービス」である。この方式は、複数のユーザーが同じサーバ上のOS/アプリケーションを共用し、デスクトップとしてはユーザーごとに独立した環境が用意される。ユーザーの収容度が高く、システムを効率的に使えるというメリットがある。
ただし、クライアントOSではなくサーバOSを利用するため、業務上必要なアプリケーションがサーバOSで動作することが適用条件となる。アプリケーションさえ動作可能であれば、この方式は最もコストが安いといえるだろう(図3参照)。
2つ目の方式は「仮想PC」だ。これはサーバ仮想化技術を応用し、仮想マシン上にユーザーごとのデスクトップ環境を用意する。仮想マシンを利用するため、デスクトップ環境を作成や廃棄、初期化といった作業が簡単だ。ユーザーごとにOSが独立しているため、ユーザー個別のアプリケーションをインストールしたい場合は、この方式になる(図4参照)。
3つ目が「ブレードPC」方式になる。これは、1台のシャーシに数十台のブレードPCを格納できる機器を用意し、ユーザーごとに1台ずつブレードPCを割り当てるという方式だ。ユーザー数が多い場合は、ラック数が増加することなどにより、トータルコストが割高になる。ハードウェア/ソフトウェアはユーザーごとに完全に独立しているため、各ブレードPCが故障したり、負荷の高い処理を行ったりしても、ほかのユーザーに影響が及ぶことはない。
また既存環境がクライアントOS上で仮想マシンを作り、そこで古いクライアントOS上でしか動かないアプリケーションを動作させているような特別なケースの移行では、仮想PCやターミナルサーバ上に、さらに仮想マシンを作成することはできない。ブレードPCはハードウェア上で通常のクライアントOSが動作するため、このような移行の際に、有効な選択肢となる(図5参照)。
以上のように、VDIを適用する際に3つの方式が存在するが、VDI導入を成功させるためには自社の業務にあわせて使い分けることが肝心だ。例えば、営業やスタッフ部門のように資料作成と伝票入力などの定型業務のみを行うユーザーは、コスト効果の高いターミナルサービス方式が適している。個別のアプリケーション利用がある場合や、アプリケーションのバリエーションが膨大だったり、パッケージの提供元がサーバOSでの動作を保障していない場合など、サーバOSでの動作確認が難しい場合は仮想PC方式が必要になる。それに対し、開発部門や障害ログを解析するような保守部門など、データ量や負荷の高いクライアント処理が必要な場合は、ブレードPC方式が向いている。このように、適材適所のソリューションを選択することが望ましい(表参照)。
明確な目的を持って導入すべし
VDIの導入で最も重要なことは、目的をしっかり持つことだ。事業継続性の向上やセキュリティ対策の強化、クライアント端末の運用管理の改善、タブレット端末などによる業務効率の向上、ワークスタイル改革など、主眼を置く点を明確にする。併せて、実際に利用するユーザーの不安を事前に取り除き、どんな効果が得られるのかを理解してもらうことも必要だ。
VDIの導入後はユーザー側も運用側も、そこで得られるクライアント体験は今までとはまったく違ったものとなる。柔軟性・俊敏性・安全性・継続性を一気に得られるこの手段で業務をリ・デザイン(再設計)できる絶好の機会となる。コストの適切な把握と効果算定を着実に実施し、新しいユーザー業務の生き生きとした姿も描きながら、取り組んでいくことが成功への道となるわけだ。
・記載の会社名、製品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。
・記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。
関連記事
 将来的な環境変化も見据えてデスクトップ仮想化に挑戦 J-オイルミルズ
将来的な環境変化も見据えてデスクトップ仮想化に挑戦 J-オイルミルズ
BCP強化や運用管理コスト削減などを目的に、デスクトップ仮想化への動きが本格化している。製油業界の代表的メーカーであるJ-オイルミルズは、グループ企業約1400ユーザーのクライアント環境更改に当たり、日立の「デスクトップ仮想化ソリューション」を導入。モビリティの向上や将来のクラウド化も見据えた柔軟なIT環境の構築を実現した。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
提供:株式会社日立製作所
アイティメディア営業企画/制作:ITmedia エンタープライズ編集部/掲載内容有効期限:2014年2月5日
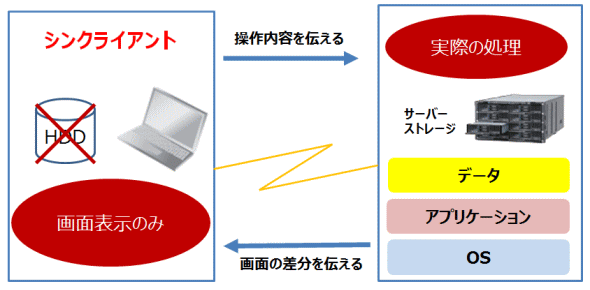 図1:VDIの概念。ユーザー側では画面データの表示と入力操作だけを行い、データの処理はサーバ側で行う
図1:VDIの概念。ユーザー側では画面データの表示と入力操作だけを行い、データの処理はサーバ側で行う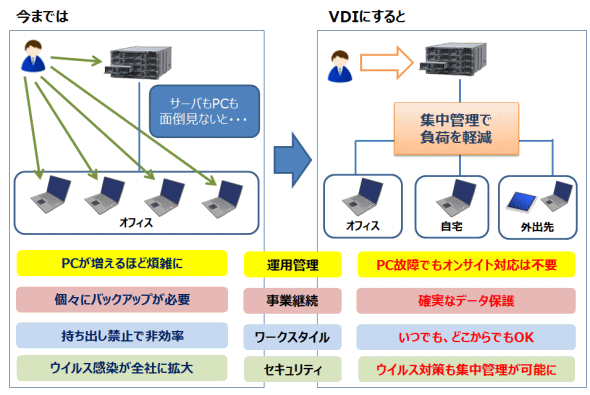 図2:VDIが提供する4つのメリット
図2:VDIが提供する4つのメリット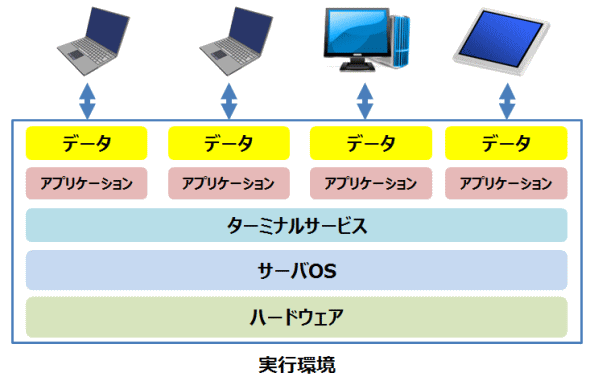 図3:ターミナルサービス方式による構成イメージ
図3:ターミナルサービス方式による構成イメージ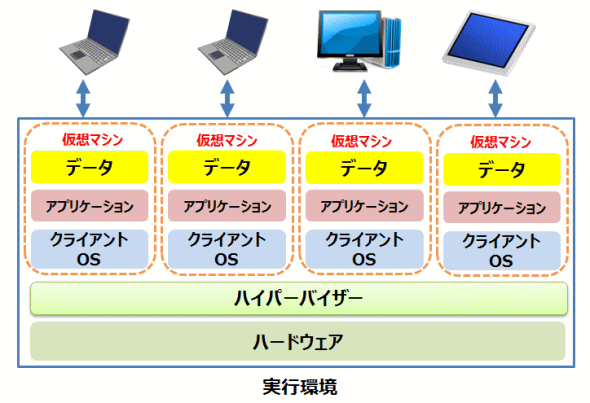 図4:仮想PC方式による構成イメージ
図4:仮想PC方式による構成イメージ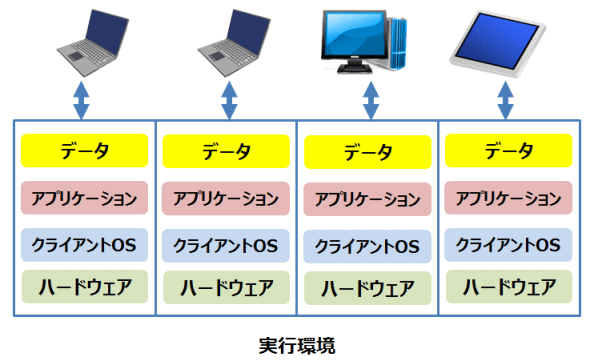 図5:ブレードPC方式による構成イメージ
図5:ブレードPC方式による構成イメージ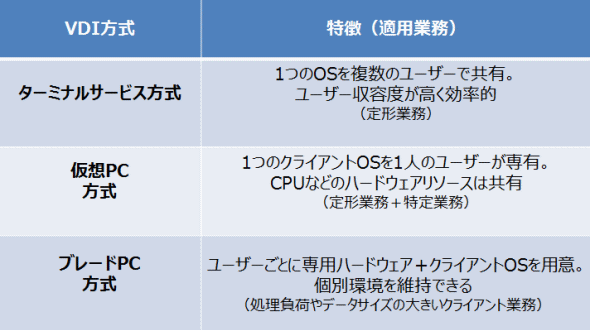 表:業務バリエーションに応じたVDI方式の選択
表:業務バリエーションに応じたVDI方式の選択


