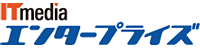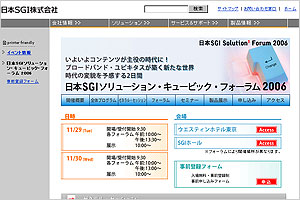
日本SGI ソリューション・
キュービック・フォーラム2006
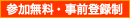
いよいよコンテンツが主役の時代に!
ブロードバンド・ユビキタスが築く新たな世界
時代の変貌を予感する2日間
2005年11月29日(火)、30日(水)
ウェスティンホテル東京/SGIホール
ただいま事前登録受付中!


日本SGI株式会社 代表取締役社長兼CEO 和泉法夫氏
コンテンツが主役になるとビジネスが変わる?
ハリウッド映画にCG革命を起こした米シリコングラフィックス社の日本法人として設立された日本SGIは、NECが筆頭株主になってビジネスを展開するようになって数年が過ぎた。その中で同社がフォーカスする方向性は、「コンテンツ」という存在の意義を改めて問うものとなっている。果たして同社がわれわれの良きナビゲーターとなり得るのか、和泉氏に話を聞いた。
日本SGIがソリューション志向のビジネスを展開するようになって数年が過ぎた。その中で同社がフォーカスする方向性は、「コンテンツ」という存在の意義を改めて問うものとなっている。
同社代表取締役社長CEOの和泉法夫氏はこれまで、折に触れてコンテンツが主役となる時代の到来について言及してきたが(関連記事参照)、いよいよそうした時代が到来したといっても過言でない今、果たして同社がわれわれの良きナビゲーターとなり得るのか、和泉氏に話を聞いた。
ITmedia:デビット・モシュラの著書である「覇者の未来」で述べられていたコンテンツの時代が彼の予想よりも早く到来し、その中での「勝ち組」というものが明確になりつつある感があります。
和泉:コンテンツの時代においては、ハードウェアや自社製品でのビジネスにこだわっていては成功しません。これは音楽業界におけるiPod (Apple)などを見るとよく分かります。iTunes Music Storeからのダウンロード件数はすでに5億曲を超えているようですが、実際のところ、ダウンロード販売で得られる利益自体は実に薄利なものでしょう。しかし、iTunesにコンテンツが集まるということがこの仕組みの重要なポイントになっています。またコンテンツとして音楽を提供する側は、利益を稼げるようなビジネスになっています。 iPodというハードウェアでもiTunesというソフトウェアでもなく、そこに集まるコンテンツが主役となってビジネスの方向性を大きく変えている象徴的なケースです。
ITmedia:そもそもコンテンツはなぜ主役となり得るのでしょう。
和泉:かつてブロードバンドの普及期には、「何のために」ということを説く必要性があり、そのための材料としてコンテンツが挙げられていました。つまり、そのころのコンテンツは完全に脇役だったのです。コンテンツを普及させるためにまずインフラを普及させるという考えからすると、ねじれが起こっていた部分もあります。
とはいえ、そのころにおいても双方向のコンテンツを提供しようという動きはありました。例えば、あるアーティストのライブを配信する際、そのアーティストの衣装をクリックすると、服や靴のブランドなどの情報が表示され、購入もできる――こういった取り組みも存在はしたのです。また、1990年代に千葉県浦安市で行われたNTTとの共同開発によるVODの実証実験で扱ったコンテンツは今見ても遜色ないものです。そのころ残念ながら花開かなかったのは、インフラの貧弱さによるものが大きいです。しかし現在、日本では通信インフラが安く広く整備され、ネットワークの部分では差別化できなくなっています。そうなると、かつては脇役だったコンテンツが主役となり、差別化のポイントになるのです
ITmedia:コンテンツ、という言葉にはさまざまな意味があると思いますが、日本SGIが考えるコンテンツはどういったものでしょう。
和泉:何がコンテンツかというのは定義が難しいところです。というのは、Blogやポッドキャストに見られるように、コンテンツそのものの定義がどんどん広がっているからです。また、これまではコンテンツだと思われなかったようなものが、コンテンツとしての価値が出てくるのです。その意味では企業内にはまだまだ多くの有益なコンテンツが眠っているはずなのです。
また、従来のコンテンツは変化が求められています。特に紙媒体はものすごい勢いで変わらざるを得ないでしょう。例えば新聞はその性質上、発行した時点で競争力を失います。情報をアップデートするには次の刷りで対応しなければなりませんからね。たとえば産経新聞が朝刊を「産経NetView」というサービスで動画や3Dを含めて有料配信していますが、わたしは非常に便利だと感じています。新聞はこの方向にシフトしていくでしょう。
同様に、ソフトバンク・メディア・アンド・マーケティングとアクセス・パブリッシングが創刊した無料月刊誌「Manyo−万葉−」は、クオリティの高い雑誌のコンテンツをどうネットと絡めるかといった点で興味深い試みですね。
産経新聞にせよ、Manyoにせよ、究極的には映像を含めたコンテンツと変貌を遂げるのではないかと思っています。
ITmedia:コンテンツが主役となる時代で、コンテンツを提供する側が考えるべきことは何でしょうか。
和泉:前の話に関連しますが、「コンテンツのクオリティ」が重要です。少なくとも今の時代、どこかのコンテンツホルダーを買収してそこのコンテンツを提供する、というのはレガシーのコンテンツであり、短絡的です。映画など万人に受けるコンテンツというものも確かに存在はしますが、多くの人に見てもらおうとするコンテンツの作り方からの発想を転換する必要があるでしょう。 これからは、個人の趣味や志向、また特定のターゲット層に合わせた情報発信を、インタラクティブにおこなうことが重要でしょう。ブログが300万人以上に使われていることを見てのその流れがわかります。
ITmedia:そのような理解が進むことで、今後、大幅な伸びが期待できる業種や職種といったものは存在するのでしょうか。
和泉:いずれの業種・職種においても当てはまるでしょうが、特にマーケティングには有益だと思います。というのは、社内に豊富なコンテンツを有しながら、コンテンツという発想がマーケティングの人に欠けているケースが散見されるからです。
自動車業界を例に挙げましょう。巨額の予算をかけて広告を作成し、それをショールームで流し続けているのを目にしたことがあるかもしれません。あるいは、営業の方にスペックを延々と聞かされたかもしれません。しかし、こうしたことはユーザーからすればそれほど意味がありません。
トヨタのレクサスに見られる販売戦略はその部分に目をつけた象徴的なものです。テクノロジーをことさらに語るのではなく、レクサスを購入しようとするユーザーに、「レクサスに乗るとこんないいことがある、こんなことができる」と訴えるアプローチ、これはAppleが「iPodとiTunesでライフスタイルが変わる」というメッセージを送るのに通ずるものがありますが、これはユーザーからすると非常に分かりやすい。マーケティングのスタイルが安さやスペックだけを訴えている限り、こうした発想は出てこないものです。
また自動車業界ではマツダが車の販売店で、お客様へCGを駆使して車の特徴を説明したり、開発者のコンセプトをインタビューして映像で伝えるような仕組みを始めており、
これは画期的な新しい試みと言えます。
かつては手段を提供することがユーザーから求められ、企業もそれを提供してきましたが、コンテンツが主役となる時代では「目的」にフォーカスする必要があります。日本SGIがコンテンツが主役と言っているのは、手段ではなく目的にしっかりフォーカスし、よりユーザー志向のサービスを提供するという意味なのです。目的と手段を混同してはなりません。
ITmedia:では、日本SGIがそこで果たす役割とは?
和泉:日本SGIはあくまでコンテンツの制作、アーカイブ、配信を支援するシステムのインテグレーションを生業とします。主役であるコンテンツをどう作るか、どうスムーズに活用するかといった企業の課題に対し、元々、映画やTV、ゲームなどのコンテンツ制作に関わってきて、メディアと通信の融合がわかる唯一の企業の立場で、コンサルティングをしながら、イノベーション・ナビゲーターとして役割を果たしてくのがわれわれなのです。
ITmedia:日本SGIは11月末に「日本SGIソリューション・キュービック・フォーラム 2006」を開催します。前回の同フォーラムでは、「CIOと呼ばれる人たちもERPやDBばかりに目を向けていてはならない」とおっしゃっていましたが(関連記事参照)、今回はどういったメッセージを送るのですか。
和泉:特定の人に向けてというよりは、製造、放送、医療、教育などさまざまな分野でコンテンツが主役となることで起こるビジネスの変化を体感してもらいたいですね。日本SGIのスタンスとして、実際に最先端でそれらを実践しているユーザーの方を講師として招いていますので、より具体的な話を聞くことができるでしょう。また、最先端のソリューションのデモも公開します。いずれにせよ、ありとあらゆる世界が変わってきたことを実際に体感できるようにお見せしたいと思います。
関連記事
- 「二足歩行で満足ですか?」ロボットの最先端を見せる日本SGI
- ブロードバンド・ユビキタス社会におけるアップルコンピュータと日本SGIの類似点
- 「ユビキタスへの進出も」選球眼を持って脱皮を図る日本SGI
関連リンク
提供:日本SGI株式会社
企画:アイティメディア 営業局/制作:ITmediaエンタープライズ 編集部/掲載内容有効期限:2005年11月30日