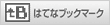| リビング+:連載 | 2003/06/30 23:59:00 更新 |
enjoy@broadband.home.net
DHWG設立で前進するか? ホームネットワークの楽しみ方
家電やPCベンダー17社が参加する「Digital Home Working Group」(DHWG)が発足した。目的はズバリ、ホームネットワークでさまざまなメディアを扱うために必要な“決めごと”を作ること。その背景にあるもの、そして見通しを、「VAIO Media」の企画を担当するソニーITカンパニー商品企画部の岸本豊明氏とのインタビューから探ってみよう。
先週、17社でDigital Home Working Group(DHWG)という組織を設立することが発表された。17社の中には家電、パソコン、携帯電話といったデジタル技術を応用した家電製品の主要ベンダーが含まれている。DHWGの目的はズバリ、ホームネットワークでさまざまなメディアを扱うために必要な“決めごと”を作ることである。
実は、以前にこの連載の中で紹介したSonicStage Mastering Studioを取材した時、ソニーにお願いして「VAIO Media」の企画を担当するITカンパニー商品企画部の岸本豊明氏に話を伺っていた。外からアクセスすることも可能になった、新しいVAIO Mediaについては同じ岸本氏に小寺氏がインタビューしているのでそちらを参照してほしいが、ここではその中で出た話をピックアップしながら書き進めていくことにしたい。
VAIO Mediaはつながるのか? つながらないのか?
VAIO Mediaをこの連載で初めて取り上げた時、見出しの件を一つの大きなテーマとして取り上げた。なぜならVAIO Mediaが投資(お金だけでなく、労力や時間などVAIO Mediaにコミットするために必要なリソースすべて)する価値のある対象なのかどうかを判断する上で、VAIO Mediaがオープンな接続性を目指しているかどうかが重要だったからだ。
たとえば、せっかくVAIO Media用に「SonicStage」で曲データを管理し、プレイリストを作ったり、ジャケット写真を取り込んで貼り付けてみたりしても、ソニーだけの世界でしか再利用できないとしたら努力も報われないだろう。ネットワークで色々なものがつながっていくからこそ、そこに広がりがあるのに、その広がりを特定ベンダーの中だけに閉じてしまうというのは、どうにも納得のいかない部分がある。
VAIOで管理しているメディアでも、NECや富士通のパソコンで管理しているメディアでも、ハイブリッドレコーダー内のビデオでも、さらにはネットワークエリアストレージ内にあるメディアデータでも。わが家の中にあるメディアは、等しくすべてのネットワーク対応プレーヤーあるいはパソコン上で再生できて欲しい。
将来、現在作り上げているメディアライブラリが、さまざまな場所、デバイスで再利用できるならば、その労を惜しむことなどしない。その逆ならば様子を見る。こうした考え方は何も特殊なものではないハズだ。これらの意見を前述の岸本氏にぶつけてみた。
本田:ソニーはGigaPocket/SonicStageをVAIOでやっていて、その一方でLinuxベースの「コクーン」シリーズがある。どちらもネットワーク指向を標榜しているのに、つながりそうな素振りもない。今後は「PSX」も加わってくる。ソニーの中だけでも、全然つながっていないのでは?
岸本:ソニーの歴史は、メディアでデバイスをつないできた歴史です。確かに個々の製品は発生が別々であるため、現状つながってはいませんが、ソニー全体がネットワークの方向に向かっていますし、当然その中でカンパニー間を超えた連携も行っていきますよ。社内的には、ソニー製品同士は全部つながるように話を進めています。
本田:その割には、今のところつながっているのはVAIO同士とルームリンクだけ。これではかけ声だけで、その実態が全く見えない。もう少し、外に向けてのアピールも必要ではないですか?
岸本:実はあまり知られていないんですが、昨年のソニードリームワールドでは、バイオとコクーンをUPnPでつなげて映像をネットワーク配信するデモをやっていたんですよ。アプリケーションプロトコルは独自、いわば“VAIO Media語”でやりとりしていたので、あらゆるデバイスとつながるわけではありませんが。
本田:ということは、ソニーのAV機器同士はつながる方向で間違いないと。では他社との接続はどうなんでしょう。ビデオケーブルをつないで他社のテレビにビデオ映像が映るように、ソニー以外の機器ともつながって行かなきゃならない。このあたりは、UPnP Forumでの動きも含めて、どのような状況なのでしょうか?
岸本:ソニー製AV機器とVAIO Mediaはつながるようになっていきます。これは間違いない。ほかのAV機器ベンダーとの話ですが、こちらも話が進んでいます。業界内で組織を作って、相互にメディアをやりとりするための取り決めを作っていくんです。
本田:それはUPnPベースで?
岸本:もちろんUPnPですが、UPnPはデバイス同士がつながる表面的な部分でしか機能しませんよね。その上のUPnPアプリケーションのプロトコルが、最近イロイロと揃いつつあるわけですが、通信手順だけを決めれば終わりというわけにもいきません。やりとりする情報、メディアのフォーマットやCODECをまとめなきゃなりませんから。
実は一番のネックがCODECの統一
冒頭で紹介したDHWGは、そうしたCODECやデータフォーマットまでをアプリケーションごとに定義し、ハードウェアベンダーを超えてつながる世界を構築するための、最低限の決めごとを作りましょうという組織だ。
DHWGのプレスリリースによると、パソコン、テレビ、セットトップボックス、プリンタ、オーディオ機器、携帯電話、PDA、DVDプレーヤー、デジタルプロジェクターなどを、有線あるいは無線のLANで結び、IPネットワーク上でコンテンツを簡単に共有可能になることを目指すという。基本となる技術にUPnPを用い、単につながるだけでなく、つながったあとに情報をやりとりする手順やフォーマット、CODECをも標準化するためのガイドラインを作業部会で策定する。
DHWGの策定したガイドラインに準拠する製品にはロゴが発行され、DHWGロゴを持つ機器同士を接続する際の互換性が保証される。ロゴプログラムに準拠した製品は、今後1年以内に登場する見込みだ。PC業界からはインテル、マイクロソフト、富士通、IBM、ヒューレット・パッカード、NECなどが参加し、家電業界からはソニーをはじめ、松下電器、シャープ、フィリップス、サムスンなど、そして携帯電話ベンダーとしてノキアが参加する。
これは、昨年後半あたりから話題になっていた、UPnPアプリケーションプロトコルの標準化から、さらに一歩前に踏み出したものだ。UPnPではIPネットワーク上でデバイス同士が互いの存在や機能を認知し、“つながるだけ”だった。その上で、アプリケーションを動かすための手順が策定されてきたが、データフォーマットの統一までには至っていない。しかしDHWGのガイドラインでは、データフォーマットまで踏み込んだ標準化や、相互運用に関する細かな取り決めまでが行われる。
今から思えば……だが、今年1月の「International Consumer Electronics Show」(CES)でソニー社長の安藤國威氏が「デバイス同士をネットワークで結ぶため、最低限の決めごとを作らなければならない。そのためにソニーは最大限の努力をしている」と話していた成果が、今回のDHWGだったのだろう。そのコメントと同時に、ソニーはフィリップスやノキアと、アライアンスを組むことを発表していた。3社ともDHWGの賛同ベンダーだ。
岸本氏に話を伺った時点では、まだDHWGについて発表されていなかったが、以下のようなやりとりがあった。
本田:オープンな接続環境でといっても、岸本さんが言うようにフォーマットの問題がある。しかしこの問題は、ホームネットワークに限らず、あらゆる分野で“笛吹けど踊らず”の状態でストップしていることが多い。本当に信用していいのでしょうか?
岸本:ソニーとしても、きちんとした業界団体を組織して標準化しようとしています(後に発表されるDHWGのこと)。口だけでは決してありません。現時点ではネットワークに通すAVデータのCODECを何にするのか、あるいはビットレートの設定をどのようにするかといった部分はまとまっていないのは想像される通りです。
パソコンは多くの提案の中からデファクトスタンダードが決定していきますが、家電は機能的な汎用性があまりありませんから、まずは規格ありき。そうした文化の違いによる“産みの苦しみ”を経験しているところです。
本田:CODECは本来、単なる圧縮フォーマットのハズなのに、実際には各社のデジタル著作権管理機能と深く結びついてそこに利権争いの種がある。CODEC統一と言われても、にわかに信じがたいでしょう。いっそのこと、圧縮フォーマットとメディアデータをカプセル化して、セキュアに配布するデジタル著作権管理機能を切り離して定義するべきじゃないですか?
岸本:実際には複数のCODECが標準として混在するようになるかもしれません。しかし複数のCODECであっても、標準が存在する意味は大きいでしょう。
本田:でもA社の製品はAACとMP3、B社の製品はATRAC3とMP3、C社はWMAとMP3、なんてことになると、事実上、選択肢はMP3になってしまうかもしれない。結局のところCODECにこだわる必要もないのでは?
岸本:現在、話すのが難しい問題もたくさんあります。しかし、オープンなインフラを作っていくという意味において、決して悪い方向には行ってません。それは断言できます。
もっともっと簡単、楽しく、便利に
実は、DHWGが発表されていないインタビューの時点で、岸本氏に深い話題を振ったのには理由がある。マイクロソフトがハードウェア開発者向けに開催したカンファレンス「WinHEC 2003」の会場で、UPnP Forumに深く関わる関係者から「UPnPに関して、ソニーはかなり本気ですよ。可能な限りの譲歩をしながら、フォーラムメンバーに対して早期の標準化を促し、率先して新しい提案をしています」と、事前情報をもらっていたのだ。
UPnP Forumは、標準化を行う業界団体の中でも、特にルールが厳しいことで知られている。たとえば、ロクに標準化作業に参加せず、情報だけを持ち帰ろうとするボードメンバーは、メンバー企業同士の投票でキックアウトされてしまう。キックアウトされた企業は半年間、標準化の会議に参加できない。半年後、復帰する際には再度、ボードメンバーによる投票が行われ、そこで復帰が認められないと標準化のグループに戻ることができないという。あるメンバー企業は「UPnP Forumが近年、急速に前進しているのは、そうした厳しい運営方針も大きく影響している」と話す。
別のDHWG参加ベンダーは「DHWGはもともと5月に発表予定だったが、予想以上に広範なベンダーが集まり、また内容的にも濃いものになることがわかり、ある日本の大手家電ベンダーが間際になって参加を決め、それに吊られるように数社の参加が決定した。そのため、再度参加ベンダーのコンセンサスを取るため、発表が6月に延期された経緯がある」と話す。
情報ソースは急遽参加を決めたベンダーの名前を明かさなかったが、DHWGメンバーにソニーと松下電器、両方の名が連なっていることは興味深い。DVD Forumの例にあるように、単に標準化に合意するだけでは前になかなか進まないものだが、とりあえずスタート地点に立ったことを現時点では評価すべきだろう。
本田:業界標準を作る動きが出て、その後にはメディアの扱いやすさについても、もっともっと進化してくれないと困りますよね。たとえば現在のVAIO Mediaは、異なるパソコンにあるメディアは一度に見ることができない。どのパソコンにメディアデータがあるかを意識せずに、フラットにメディアライブラリを参照できるようにディレクトリサービスを定義するなどの必要もあるのでは?
岸本:パソコンやデジタル家電のマニアではない、ふつうの人が簡単にメディアデータを管理できるようにするアイデアは、実は以前からあります。まだ実装できてはいませんが。ほかのアイデアとしては、QoSや帯域に合わせたビットレートの変換をユーザーが知らないうちにやれるようにしたい。
たとえば、ビットレートやフォーマットを変更するトランスコードを、機器の能力やサポートするフォーマット、回線の空き帯域などを見て自動的に決定するといった機能です。高品質なメディアデータをトランスコードしようと思えば、かなり高いパフォーマンスが必要になりますから、能力的にも、機能の汎用性という観点からも、パソコンの力が重要になるでしょう
本田:外出先からテレビや音楽を楽しむ機能が追加されたVAIO Mediaが、次に向かうところもそのあたりにある?
岸本:いえ、次のバージョンアップは秋を予定していますが、それまでに考えていることをどこまで詰め込めるかは現時点では何も言えません。しかし、秋は秋でスゴイ進化を予定しているので楽しみにしていて欲しいですね。われわれはひとつの場所に留まるのではなく、確実に前進することを目指しています。期待してください。
関連記事関連リンク
[本田雅一,ITmedia]
モバイルショップ
 最新スペック搭載ゲームパソコン
最新スペック搭載ゲームパソコン
高性能でゲームが快適なのは
ドスパラゲームパソコンガレリア!
 最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
最新CPU搭載パソコンはドスパラで!!
第3世代インテルCoreプロセッサー搭載PC ドスパラはスピード出荷でお届けします!!