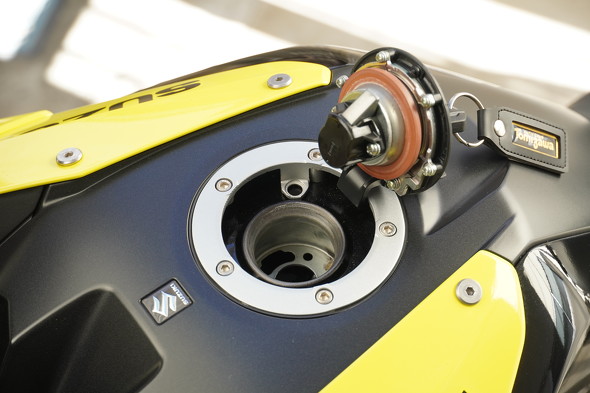【バイクの冬眠】放置して大丈夫? “バッテリーを外す”以外に注意すべきこととは
降雪地域に住んでいる、あるいは単純に寒いから乗りたくないなどの理由から、この時期はバイクの長期保管の仕方、いわゆる「冬眠」に関するノウハウが話題となります。
ここでは、車両メーカーが推奨している方法を元に、長期保管の方法や注意点を紹介します。
大屋雄一
モーターサイクル&自転車ジャーナリスト。短大卒業後、好きが高じて二輪雑誌の編集プロダクションに就職し、6年の経験を積んだのちフリーランスへ。ニューモデルの試乗記事だけでもこれまでに1500本以上執筆し、現在進行形で増加中だ。また、中学〜工高時代はロードバイクにものめりこんでいたことから、10年前から自転車雑誌にも寄稿している。キャンプツーリングも古くからの趣味の一つであり、アウトドア系ギアにも明るい。
→著者のプロフィールと記事一覧
洗車・ワックスがけが愛車を長持ちさせるコツ
国内4メーカー(ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ)が取扱説明書で推奨しているのは、長期保管前に洗車をしてワックスをかけることです。車体の表面に付着した汚れにはさまざまな有害物質が含まれており、それらによる悪影響を軽減するのが目的です。
なお、ツヤ消し塗装面へのワックスがけは不可。メッキ部分には防錆油(ぼうせいゆ)を吹き付けておくとさびの発生を軽減できます。
ワックスをかけた後は、バイクが倒れにくい平坦な場所に駐輪し、雨やホコリを防ぐためにボディカバーをかぶせます。ちなみにホンダでは、長期保管中でも雨上がりにはボディカバーを外し、車体を乾燥させることを推奨しています。
カワサキは、ボディカバーに加えてマフラーにビニール袋をかぶせるように指示しています。いずれも愛車を長持ちさせるのに有効な手段と言えるでしょう。
今売れているバイク用グローブをチェック
バッテリーは車体から取り外す
洗車・ワックスがけと並んで車両メーカーが推奨しているのが、バッテリーを車体から取り外すことです。バッテリーの自己放電と電気漏れを少なくするのが目的で、ほぼ全ての車両の取扱説明書には取り外し方が記載されています。
ただし、精製水の補充が不要なメンテナンスフリータイプが主流になって以降、バッテリーの搭載位置が車体の奥深くになってしまい、取り外すのが困難な車両も少なくありません。その場合は、最低でもマイナス側のターミナルを外すようにしてください。
取り外したバッテリーは完全充電した後に、風通しの良い冷暗所で保管してください。なお、ヤマハは3カ月に1回、カワサキは1カ月毎に補充電することで、バッテリーの劣化が抑えられると説明しています。
人気のフルフェイスヘルメットをチェック
オイルは交換するべき?
長期保管時のエンジンオイルについては諸説あります。「冬眠させる前に交換した方が良い」「春になってから交換すべき」「新しければそのままで問題ない」など、さまざまな意見が交わされています。
車両メーカーによると、ホンダとヤマハについてはオイルに関して直接の記載はないものの、「保管期間を考慮した上で、走行前には各部の点検を実施してください」とあり、この各部の点検項目にオイルのコンディションチェックが含まれる可能性が大です。
スズキは長期保管後における再始動の手引きとして、エンジンオイルとオイルフィルターを交換してからエンジンを始動するように記載。つまり、長期保管“後”の交換を推奨しています。これに対してカワサキは、長期保管“前”にエンジンオイルを交換するように説明しているなど、車両メーカーごとに見解が異なっており、ユーザーとしては非常に興味深いところです。
いずれにせよ、オイルは空気に触れることで酸化し、エンジン内部の結露による水分混入などで走行の有無にかかわらず劣化するので、これを踏まえた上で交換タイミングを検討してください。
タイヤの空気圧について
バイクの重さによる変形を防ぐため、「長期保管前はタイヤの空気圧を指定よりも高くした方が良い」などと昔から言われてきました。しかし各社の取扱説明書を調べてみると、ホンダとヤマハはタイヤについて直接の記載がありません。
スズキは「タイヤの空気圧は規定圧に調整」した上で、必要に応じてメンテナンス用スタンドなどで前輪と後輪を地面から浮かせるように指示しています。
興味深いのはカワサキで、空気圧を高くするのではなく、むしろ「2割減らした上で、前輪と後輪の下には防湿のために板を敷く」とあります。ちなみに、イギリスのトライアンフは「長期保管中も適宜空気圧を調整し、メンテナンス用スタンドなどで両輪を地面から浮かせる。それができない場合は、板を敷いてタイヤを湿気から保護する」ように記載しています。
タイヤの空気は徐々に抜けるので、変形を防ぐためには高めに入れて春まで放置するよりも、指定圧に適宜調整するのが効果的かもしれません。そして、湿気による劣化を軽減するには板が有効だということも分かりますね。
今売れている「バイク用通信機器」をチェック
ガソリンは満タン、それとも排出すべき?
そのほか諸説あるのがガソリンです。タンク内部のさび発生を防ぐためには空気に触れないよう満タンにすべき、いや完全に抜いて乾燥させた方が効果的だ、などと意見が分かれています。
ホンダ、ヤマハ、スズキについては取扱説明書に記載がなく、国内4メーカーではカワサキだけか「燃料を全て排出する」と指示。これに対しイギリスのトライアンフは「給油した上で、可能であれば燃料安定剤を注入」することを推奨しています。
どちらの意見にも相応の理由があるため、不安な人は愛車を購入したショップに相談することをおすすめします。
降雪地域では冬期保管サービスを利用する手も
以上のように、長期保管の方法については車両メーカーごとに見解が異なります。保管する場所が屋内なのか、屋外なのか。たとえ雨風がしのげるガレージであっても、地面がコンクリートではなく土や砂利の場合は湿気がこもりやすいなど、保管環境は人それぞれです。だからこそ、車両メーカーは詳しく記載できないという理由があるのかもしれません。
なお降雪地域を中心に、バイクの長期保管サービスを実施しているショップがたくさんあるので、そうしたシステムを利用してみるのもよいでしょう。
ライターおすすめのバイク用品はコレ!
無料でお試し 音楽聴き放題!
Apple Gift Cardで、楽天ポイントがたまる・使える!
Google Play ギフトコードで、楽天ポイントがたまる・使える!
関連記事
 ライダーにとって最強の「手の防寒アイテム」は? “アイテムの組み合わせ”がカギ
ライダーにとって最強の「手の防寒アイテム」は? “アイテムの組み合わせ”がカギ
冬でも走り続けるライダーにとって、敵は何といっても寒さです。特に手指は寒風が直に当たるので、対策をしていないとすぐにかじかんでしまいます。この時期に有効な手指の防寒アイテムをいくつか紹介しましょう。 バイクジャーナリストが試乗して「印象に残ったバイク」ベスト5 衝撃を受けたインパクト抜群なバイクとは?【2023年最新版】
バイクジャーナリストが試乗して「印象に残ったバイク」ベスト5 衝撃を受けたインパクト抜群なバイクとは?【2023年最新版】
現在、日本では国内外メーカーのバイクが600車種以上も購入できると言われています。四半世紀以上にわたって数多くのニューモデルに試乗してきたバイクジャーナリストが、ここ3年以内で特にインパクトを受けたモデルを5台紹介しましょう。 ビギナー向け「ロングツーリングを快適にするアイテム」おすすめ5選 最新のバイク用高性能モニターなど【2023年最新版】
ビギナー向け「ロングツーリングを快適にするアイテム」おすすめ5選 最新のバイク用高性能モニターなど【2023年最新版】
バイクの楽しみ方の一つが「ツーリング」ですが、移動距離や時間が長くなるほど、さまざまな予期せぬ問題が発生します。そこで今回は、そうしたトラブルを未然に防ぎ、ロングツーリングでのストレスを軽減してくれるアイテムを厳選して紹介しましょう。 はじめしゃちょーが購入した“近未来バイク”「ホンダ NM4-02」、発売当時は人気がなかった? バイクジャーナリストが解説
はじめしゃちょーが購入した“近未来バイク”「ホンダ NM4-02」、発売当時は人気がなかった? バイクジャーナリストが解説
チャンネル登録者数が1000万人を超える大人気YouTuber、はじめしゃちょーが購入したことで話題となったホンダの「NM4-02」。その近未来的なスタイリングに驚かれた方も多いことでしょう。 【関東近郊】行ってよかった「ツーリングスポット」5選 都心から日帰り・1泊で行けるスポットをベテランライダーが紹介
【関東近郊】行ってよかった「ツーリングスポット」5選 都心から日帰り・1泊で行けるスポットをベテランライダーが紹介
バイク趣味における醍醐味の一つが、景色の良い道路を利用しての「ツーリング」でしょう。他の交通手段で何度も訪れた場所であっても、自らバイクを操縦し、暑さ寒さをダイレクトに感じながらたどり着くと、風景の見え方も全く変わってきます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
- 「薄くて軽くて暖かい」【ユニクロ】の高機能な中綿アウターが人気「一着は持っておくと便利」「自宅でも洗濯できる」
- 「かわいすぎて毎日持ち歩きたい!」【タリーズ】の「バレンタイン限定ボトル」はデザインも機能も100点満点!
- 【しまむら】×「ちいかわ」の新作コラボアイテム おすすめ3選【2026年2月版】
- 暖かくて動きやすい「ゴルフパンツ」おすすめ3選【2026年2月版】
- 「高見えします」【ワークマン】の2900円「MA-1タイプジャンパー」が好評! 「めっちゃ暖かい!」「3枚購入」
- 今売れている「コーヒードリッパー」おすすめ3選&ランキング【2026年2月版】
- 宅飲みで本格的な焼き鳥を楽しめる「焼き鳥焼き器」おすすめ3選【2026年2月版】
- 【コールマン】の豪華付録! 「otona MUSE」4月号特別号に、ブルーとピンクがかわいい「便利グッズ4点セット」が登場!
- 【ワークマン】の「ワイドオープンリュック」は、耐久性・機能性・はっ水性に優れた秀逸リュックだった
- 今売れている「保温マグカップ」おすすめ3選&ランキング【2026年2月版】
 バイクの長期保管方法や注意点を紹介
バイクの長期保管方法や注意点を紹介

 バッテリーは車体から取り外す
バッテリーは車体から取り外す 長期保管時のエンジンオイルについては諸説あり
長期保管時のエンジンオイルについては諸説あり