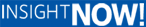プレゼンで想いを伝えるための“例え話三原則”(1/2 ページ)
著者プロフィール:木田知廣(きだ・ともひろ)
シンメトリー・ジャパン代表。米国系人事コンサルティングファーム、ワトソンワイアットで、成果主義人事制度の導入に尽力。欧州留学を経て、社会人向けMBAスクールのグロービスの立ち上げをリード。2006年、経営学の分野で有効性が実証された教育手法を使い、「情報の非対称性」を解消することをミッションとしてシンメトリー・ジャパンを立ち上げる。
筆者は仕事柄、セミナーの講師をすることがよくありますが、以前は「言いたいことが伝わらない」という大きな悩みを抱えていました。
参加者の方々は、そもそもセミナーに来るという時点で、そのテーマに関する知識はないわけです。つまりは「常識」を共有できてないわけで、いくら言葉を尽くして丁寧に説明しても、「なるほど!」とは思ってくれないのです。
例えば、会計セミナーなんかで、「決算書というのは、株主や銀行への報告のために使われるんですよ」「その中でも損益計算書は、過去1年間のお金の出入りをまとめたものです」「一方、貸借対照表は、ある時点での会社の財産一覧表です」という分かりやすい(つもりの)説明をしても、参加者が“ピンと来る”感じではありません。
これが「例え話」を使うだけで、まったく変わってきました。
「決算書というのは、人間にたとえれば履歴書のようなものですよ」「その中でも損益計算書は、いわば職務経歴。過去1年間何をやったかがまとめられています」「一方、貸借対照表は顔写真。撮影日の時点で、どんな人なのか表しています」という説明だと、履歴書という誰でも知っている(既知の)情報と新たなインプットが結び付けられるからでしょうか、「ああ、そう言うことか!」と感じてもらえるようです。
ただ、同じような例え話でも、キレが良いのと悪いのがあって、変な例え話を使ってかえってスベってしまったことも数知れず。会場がシーン……となると、かなり焦るものです。
「その違いは何か?」と考えてたどり着いた結論が「例え話の三原則」。すなわち、「1.整合性」「2.関連性」「3.多面性」があればあるほど、「なるほど!」の度合いが大きくなるというもの。
Copyright (c) INSIGHT NOW! All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング