東北大・大野英男総長に聞く 「10兆円ファンド」支援候補に選ばれた舞台裏:東北大学の挑戦(2/2 ページ)
政府が創設した10兆円規模の「大学ファンド」初の支援対象候補に、東北大学が選ばれた。東北大の大野英男総長に「国際卓越研究大学」の認定候補に選ばれた舞台裏を聞く。インタビュー全3回の1回目。
大野総長のリーダーシップ 何が奏功した?
――大きなビジョンを提示したことに加え、一致団結したチームを組めたことも、成功要因の一つだと感じます。総長はリーダーとして、どんな指示を出しましたか?
「横串を」と常に呼びかけています。縦割りにしてしまうと、大学の本来の力が出せないからです。これは学術的インパクトにも社会的インパクトにも当てはまります。人材を多様にして、いろいろな人をきちんと結び付けられる環境を作ろうとしています。
一方で今回の提案は、大きな反省に基づいてもいます。それは国立大学が法人になった20年前、法人化に伴ったさまざまな業務が発生しました。安全衛生管理や装置の見回りなどもあり、報告や記録の義務もあるのもあって、これは一例ですが、いくつかの委員会を立ち上げてこなしました。現場でこれらの業務を担当したのは、若手の教員や大学院生です。法人化に伴って発生した業務を引き受けるための予算や人員がついていませんでした。企業ではあり得ないことですね。
加えて運営費交付金の減額が始まりました。それらは本学だけでなく、国立大学全体に重くのしかかりました。このようにして研究時間、特に若手の時間を減らしてしまったことは、研究力低下の大きな要因だったと考えています。
今回の提案はそこを解放するものです。これにはリソース、すなわち予算が必要なわけですね。人を雇用するなどして、研究者でなくてもできる仕事から、研究者を解放しなければならないのです。今回の提案では、研究環境をきちんと整えることが大きな柱となっています。
――縦割りをやめることによって多様性のある有機的なチームを作り、組織的な課題を明らかにすることで本質的な問題を解決しようとしたのですね。
この20年間の日本の研究シーンで、インパクトをなかなか上げられなかった原因の一つがここにあったと考えています。また、本学においては東日本大震災の影響もありました。いずれにせよ忙しすぎるのです。
例えば新型コロナの件でも、それなりの研究者人口がいるはずなのに、日本の研究者による論文の数も被引用数も多くはありませんでした。この背景には、コロナの場合には医療従事者でもある研究者が主として関わりますが、診療と教育、研究の全てをやらなければならず、研究現場に余裕がなかったことがあると考えています。
他方、そのような中でも産学連携を近年は伸ばすことができました。関わった研究者の「産業に貢献したい」という熱意と、産学連携の仕組み作りの賜(たまもの)です。
30年に向けた東北大学のあるべき姿(ビジョン)と、その実現を目指した中長期の方針(重点戦略)や具体的なアクション(主要施策)を定めた「東北大学ビジョン2030」では「アンダー・ワン・ルーフ型産学連携拠点」の構築を掲げました。医薬品や材料科学などの分野で共同開発を推進し、30年までに産学連携による収入を、18年比で5倍の165億円へ拡大させることを目標にしました。
当初は「高い目標を掲げたが、どのような仕組みを作れば良いのか、何をやればできるんだろうか」と、担当は手探りの状態でした。そこから共創研究所などの仕組みも整え、社会に呼びかけたところ、産学連携経費は年率約13%の伸びを見せ、現在の収入は100億円を越えるまでになりました。大学として産業界の大きな期待とニーズに応えている実感があります。
――財務を意識している教員や職員は、それほど多いわけではないと思います。東北大の未来を考えて、そのような礎を築いてきたのですね。
研究者は、ある意味でジョブ型の職業です。従って財務を研究者が気にしなくても良いようにすることは重要です。研究者が思い切って研究と教育、そして社会との共創ができる環境をつくるのは、法人としての大学の仕事です。
今回の卓越大のスキームでは、授業料を除く国以外からの収入に対してマッチング支援が行われます。シンガポールでは同様のスキームがあり、それらをモデルにして、今回の大学ファンドの仕組みが作られたのだと思います。
産学連携から間接経費収入が得られますし、多くの方々からの寄付も増えています。これらの収入を、学生支援や産学連携に関わらない基礎研究の支援にまわすことによって、大学全体が発展していきます。大学債を発行して必要な事業を早期に開始することも進めています。バランス良く大学を発展させるためには、大学の本質を見据えつつ進める「大学経営」が極めて重要になります。
全ての教員に経営感覚が必要ではありませんが、大学内の資金循環の全体像について構成員が深い理解と見識を持つことにより、東北大はさらに発展すると思います。
――大野総長はスピントロニクス研究の第一人者でありながら、大学を経営する立場でもあります。いかにして研究と経営を両立してきたのですか。
両立したというより「いつの間にかこうなってしまった」ということですね(笑)。研究でも大きなプロジェクトをいくつかやると、どうしても経営を考えざるを得ないところが出てきます。
キャリアの前半は基礎研究に取り組みました。後半は徐々に応用も視野に入れた研究が増えていきました。応用になると、特に半導体の分野は「生き馬の目を抜く」ところもありますし、世界よりも早いスピードが研究開発に求められます。最終的には資金循環も含めた視点がないと発展していきません。
国立大学には、法人化前の国のブランチとして、与えられた予算を消化する組織文化が残っています。つい最近までは内部留保もできませんでしたし、投資もできなかったことも、組織文化が変わらなかった原因の一つです。そこに疑問を呈したのが、私の総長就任1年目のことでした。
資金循環を含めてエコシステムを作り、公共財として機能拡張をしていくことによって、一層大学らしい価値創造ができると考えたのです。出口を模索していたところに、このような動きを支援しよう、大学が独自の基金を形成できるようにしようと登場したのが大学ファンドの仕組みです。
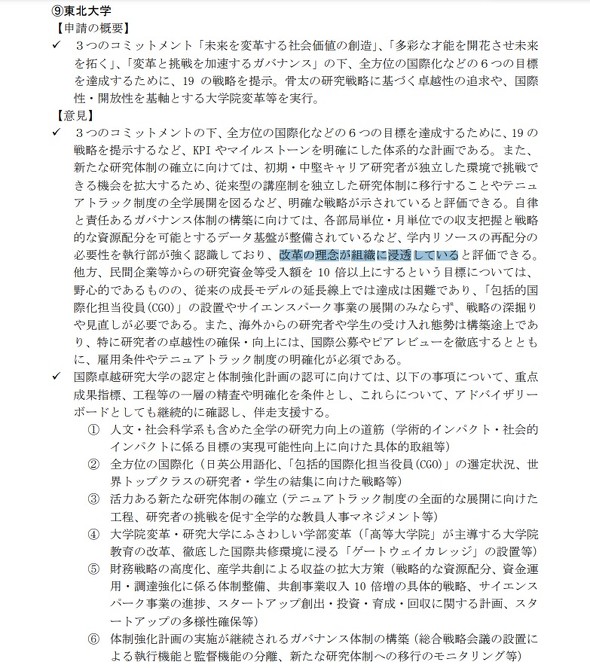
国際卓越研究大学の認定等に関する有識者会議による審査の状況では「改革の理念が組織に浸透している」と評価された。この背景に大野総長のリーダーシップがあったことは間違いない(文部科学省のWebサイトより)
――これまでの実績に加え、明確な変革への意思(ビジョン)とコミットメントが評価されたように感じました。「改革の理念が組織に浸透している」ことも評価されています。企業経営においても、経営層と社員の目線を合わせるのはとても難しいですね。冒頭の「インパクト・タレント・チェンジ」のうち、特に「チェンジ」が最も難しいと思われます。
多様な意見があるのが、良い大学の指標です。しかしその中で、方向性を共有することも重要です。行動変容やマインドセットの変化が一番難しいですね。いかに未来志向で、変わっていくか。これは非常に大きなポイントの一つだと考えています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 東北大が三井住友信託と仕掛けた産学のゲームチェンジ オープンイノベーションの狙い
東北大が三井住友信託と仕掛けた産学のゲームチェンジ オープンイノベーションの狙い
東北大学が産学連携を進めている。4月には、同大と三井住友信託銀行が共同で出資し「東北大学共創イニシアティブ(THCI)」を設立。設立発表会では東北大学の大野英男総長、三井住友トラスト・ホールディングスの高倉透社長、THCIの石川健社長の三氏が狙いを語った。 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」
富士通の時田社長「日本語の生成AI開発は重要」 改良を続けることに「ゴールはない」
富士通の時田隆仁社長に、2024年の展望を聞いた。生成AI、社員の行動変容、社会課題の解決に向けた新事業「Fujitsu Uvance」。同社はどこへ向かっていくのか――。 NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?
NEC森田社長に聞く「生成AIで優位に立てた」理由 NTTやソフトバンクとの協業は?
ECの森田隆之社長は12月12日、アイティメディアなどのグループインタビューに応じ、生成AIを開発する国内企業との協業について「競争するところと協調するところは常に意識しており、そういう(協業する)動きになると思っている」と説明した。
