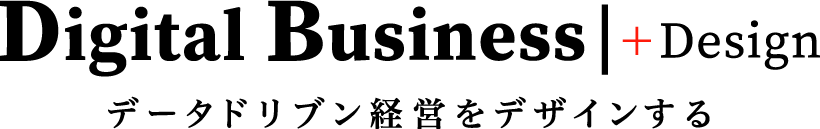Snowflakeは何がすごくて何ができるのか ITアーキテクトが見た技術的特性と可能性:Snowflakeで何ができる? 基礎情報解説(1)(1/2 ページ)
近年データ活用基盤を語る際、話題に上ることが増えたソリューションの1つにSnowflakeが挙げられます。単なるクラウドDWHではない先進的な設計思想やデータ処理の特徴に加え、既存の企業情報システムの課題解消にどう生かせるかを見ていきます。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
本連載は、昨今高い注目を集める「Snowflake」について紹介します。従来のビジネスやITが抱えていた課題、これからわれわれが直面する課題に対して、Snowflakeのテクノロジーがどのように貢献できるかを、数回にわたってアーキテクトの視点から見ていきます。
第1回の今回は下記トピックを中心にSnowflakeの基礎情報と直近の動向を整理ます。
- そもそもSnowflakeとは何か
- Snowflakeが注目を集める理由、3つの象徴的な特徴
- Snowflakeが目指す世界「Data Cloud」とは
筆者紹介:村山弘城(NTTデータ Data&Intelligence事業部 データマネジメント統括部ソリューション担当部長)
2000年にNTTデータに入社。入社以来、EAI/SOA/ESB/MSAといったデータ連携関連の製品調査・技術調査と関連プロジェクトに従事。 2014年頃よりビッグデータ基盤のアーキテクトとして金融・ユーティリティ・製造業などのプロジェクトに参画、その後2018年よりPMやアーキテクトとして全社規模のクラウドサービス型データ分析基盤プロジェクトに従事。現在は、NTTデータにおけるSnowflake事業の主幹責任者としてSnowflake社とのパートナーシップ・普及展開・お客様への導入支援に取り組んでいる。
そもそもSnowflakeとは何か 単なるDWHサービスではない機能の広がり
Snowflakeは、2012年にシリコンバレーで創業したSnowflake社(以降、企業名はSnowflake社と表記)が提供するクラウドサービスです。2015年に一般提供開始、2019年9月 日本法人設立、2020年2月にAWS Tokyoでもサービスが開始されました。筆者が所属するNTTデータでは、日本法人設立以前から製品調査をしておりましたが、AWS Tokyoでサービスが開始された2020年2月にパートナー契約を締結し取り扱いを開始しました。
もともとは「クラウド型のDWH(データウェアハウス)サービス」でしたが、最近は単にDWHの機能だけではなく、データシェアリング、データマーケットプレイイス、マルチクラウドレプリケーションといった機能拡充を経て「Cloud Data Platform」、さらには「Data Cloud」を標ぼうするデータ分析プラットフォームサービスへと進化を遂げました。
とはいえ「Data Cloud」といってもなじみがない概念のため、まずは基本的な機能やベーシックな特徴として「Cloud Native DWH」と考えていただけると分かりやすいでしょう。
多様な機能を持つSnowflakeですが、まず全容を理解するために把握しておくべき基本的な特徴は次の3つです。
- 標準SQLベースのデータウェアハウス
- クラウドテクノロジーをベースに構築
- サービス(Database as a Service)として提供
以前からさまざまなDWH製品を検討、導入されている読者の皆さまには、これだけでは何が従来の製品と大きく違うのかは分かりにくいかもしれません。
Snowflakeが注目を集める理由、3つの象徴的な特徴
昨今、さまざまな企業がデータ活用、分析のさまざまな施策においてSnowflakeに注目する背景には、この製品が持つ次の3つの特徴があります。
- ストレージとコンピュートを分離した「マルチクラスタ・共有データアーキテクチャ」
- データの一元管理が可能な高い拡張性と柔軟性
- ニアゼロメンテナンス
これらの詳細は次回以降で紹介していきますが、Snowflakeの登場は、さまざまなクラウドサービスや企業のDX推進施策に影響を与えるものだとわれわれは考えています。
Snowflakeが目指す世界「Data Cloud」とは
「Snowflakeの他サービスとの違いは?」とよく聞かれますが、実は、最大の差異は「Data Cloud」の考え方や目指している世界だと筆者は考えています。
Data Cloudは、インターネットを通じて顧客やビジネスパートナーとの間でライブデータを共有できる他、データコンシューマー、データプロバイダー、サービスプロバイダーとして事業を展開する組織や企業とデータを介して簡単に接続できる世界のことを指します。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場