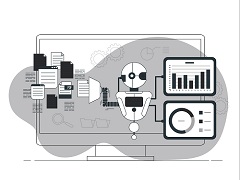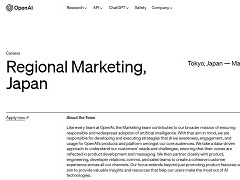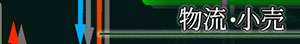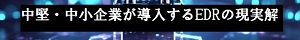【特集】エンタープライズ品質のAI活用
実用レベルの生成AIが登場したことで、改めて企業におけるAI活用が注目を集めている。すでにコンシューマ領域での活用を中心に盛り上がりを見せており、企業の生産性向上においても期待する声が増えている。 一方で企業が業務で利用するには幾つかのハードルがある。ユースケース検討の他、情報漏えい対策やガバナンス整備、ドメイン知識の学習や企業に特化したチューニングをどう実現するかが課題になっている。また、生成AIの利用に関する国内外の法整備はまだ途上であり、それらのリスクも考慮しなければならない。 とはいえ、学習やチューニング等の技術特性を考慮すると業務効率化や生産性向上につながるAIの利用は、いち早く取り組めた企業が成果を上げると考えられることから、現段階で企業が安全にAIの利用に着手する方法が求められている。 そこで本特集は生成AIを巡る国内外の議論のポイントや課題、実装実務の概要、企業利用の実務で求められる要件、情報システム部門が果たすべき役割等の情報を、企業が利用することを前提に解説する。
【特集】エンタープライズ品質のAI活用
【特集】エンタープライズ品質のAI活用:
生成AIブームをきっかけに改めて企業におけるAIの利用が注目を集める。全社規模で多様なAIモデルを扱い、成果を挙げるにはデータサイエンティストだけでなくIT部門の強いリーダーシップが必要になると目されているが、課題も多い。
OpenAIの「ChatGPT」をベースにしたAIアシスタントサービス「ConnectAI」を開発し、社内の業務改革を推進するパナソニック コネクト。2023年9月には、AIが自社固有の情報を扱えるようにするための開発・検証作業を新たにスタートさせた。どのような追加開発をしているのだろうか。
新着記事
ガートナージャパンが、生成AI頼りの顧客対応を続けると顧客離れを起こすとする予測を発表した。生成AIの品質が未熟であることが理由だという。
生成AIが登場して以来、これを「どう活用するか」という議論が盛んになっているが、「あるリスクが置き去りになっている」と松永 エリック・匡史氏は指摘する。生成AI活用が進むことでどのようなリスクが生じる可能性があるのか。
AIの活用や規制について包括的に定める「AI法」が欧州議会で可決された。今後のAI規制の世界標準となる可能性が高く、厳しい罰則もある。企業が留意すべきポイントとは。
日本プルーフポイントは日本企業の情報漏えいに関する調査レポートを発表した。データ漏えい対策の現状と内部脅威への対応、ユーザーの不注意や電子メールの誤送信、生成AIの影響などが分析されている。
生成AIの進化は早く、すぐに新しい最新のモデルが登場する。素早く導入に動く場合は投資リスクがあるが、それでも得られるメリットは大きい。リスクを極力減らして新しい技術を活用する方法もある。
一般提供が開始された生成AIチャットbot「Microsoft Copilot for Security」。これはセキュリティ業務の役に立つのだろうか。セキュリティ担当者が実際に使ってみたメリット/デメリットを語った。
経済産業省と総務省が「AI事業者ガイドライン」を公表した。生成AI普及前のガイドラインをアップデートし、AI開発者、サービス提供者、利用者向けに重視すべきことを説明している。
世間の注目が生成AIに集まる中、デロイト トウシュ トーマツが実施した調査によると、CFO(最高財務責任者)の3分の2近くが今後、生成AIへの投資を控えようとしているという。その背景にある「ある問題」とは。
Snowflakeの新CEOにスリダール・ラマスワミ氏が就任した。同氏はこれまでAI担当シニアバイスプレジデントを務めていた人物だ。同社はこれを受けてAI戦略に大きく舵を切る計画だ。
本格始動したOpenAI Japanが2件の人材募集要項を公開した。生成AI業界のトップランナーであるOpenAIが求める人材像とは。
Google Cloudは生成AI「Gemini」をBigQueryやLookerなどのサービスに実装することを発表した。新機能の詳細と利用方法を紹介する。
「ChatGPT」や「Gemini」のような生成AIを検索エンジンのように使う人も多いが、この2つは性質が異なるもの。混同していると、AIに「まぼろし」を見せられてしまう。
企業にさまざまなメリットをもたらす生成AIは、ハッカーの攻撃対象となったり、ツール自体のセキュリティや信頼性が問われたりとリスクもある。問題点と適切な管理のポイントをまとめた。
他のビッグテックが独自の生成AIを繰り出す中、慎重な姿勢を取ってきたApple。ついに同社の取り組みを明らかにする研究論文が発表された。他社のLLMを凌駕するApple製LLMの性能とは?
グーグル・クラウド・ジャパンとCSAは共同調査結果を発表し、組織の55%が今後1年以内に生成AIソリューションの採用を計画していることを明らかにした。ただし、この結果から、多くの専門家がAI導入に楽観的な姿勢を見せていることが分かった。
SentinelOneは生成AIプラットフォーム「Purple AI」の一般提供を開始した。セキュリティデータへのクエリ実行と結果の要約、調査の共有と保存を自動化し、セキュリティチームの効率化を支援する。
Microsoftは2024年4月1日から「Copilot for Security」の提供を開始した。Copilot for Securityは、新しいMicrosoft Entraのスキルを搭載し、IDとセキュリティインシデントの解決を支援する。マイクロソフトはプロンプトの実例も公開した。
「DIGITIZE YOUR ARMS デジタルを武装せよ」を標語に掲げてデジタルトランスフォーメーションを推進する日清食品グループ。この裏にはIT活用を安全なものとするため、グループ全体で総力を挙げたセキュリティ対策があった。
アクセンチュアがアドビの画像生成AI「Adobe Firefly」を自社のサービスに組み込む。企業のマーケティングへの活用を想定しているようだ。何ができるようになるのだろうか。
生成AIをどう業務で利用するかの試行錯誤が続く中で、ServiceNowは「ユーザーは生成AIを使っているという意識を持つことなく、いつの間にか使っているという状況が実現する」と言う。どういうことか、見ていこう。
人気記事ランキング
- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」
- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止
- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題
- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用
- 「欧州 AI法」がついに成立 罰金「50億円超」を回避するためのポイントは?
- 「プロセスマイニング」が社内システムのポテンシャルを引き出す理由
- 「SAPのUXをガラッと変える」 AIアシスタントJouleの全体像とは?
- “生成AI依存”が問題になり始めている 活用できないどころか顧客離れになるかも?
- 日本企業は従業員を“信頼しすぎ”? 情報漏えいのリスクと現状をProofpointが調査
- 検出回避を狙う攻撃者の動きは加速、防御者がやるべきことは Mandiantが調査を公開