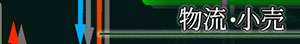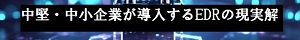DigitalNativeLeaders
最適なDX戦略を策定し、組織やチームを巻き込んで実行したいリーダー達のための知見を、事例や動向取材を通じて探る。
新着記事をもっと読む
人気記事ランキング
- 生成AIは2025年には“オワコン”か? 投資の先細りを後押しする「ある問題」
- 江崎グリコ、基幹システムの切り替え失敗によって出荷や業務が一時停止
- 「Copilot for Securityを使ってみた」 セキュリティ担当者が感じた4つのメリットと課題
- Microsoft DefenderとKaspersky EDRに“完全解決困難”な脆弱性 マルウェア検出機能を悪用
- 「欧州 AI法」がついに成立 罰金「50億円超」を回避するためのポイントは?
- “生成AI依存”が問題になり始めている 活用できないどころか顧客離れになるかも?
- 「プロセスマイニング」が社内システムのポテンシャルを引き出す理由
- 「SAPのUXをガラッと変える」 AIアシスタントJouleの全体像とは?
- 日本企業は従業員を“信頼しすぎ”? 情報漏えいのリスクと現状をProofpointが調査
- 検出回避を狙う攻撃者の動きは加速、防御者がやるべきことは Mandiantが調査を公開