生成AIは日本の人口減少社会を救う? 政治家、投資家、起業家がそれぞれの視点で語る
IVRyが自社主催したカンファレンスで、元デジタル副大臣で、自由民主党・衆議院議員 環境副大臣の小林史明氏、ALL STAR SAAS FUNDマネジングパートナーの前田ヒロ氏、IVRy創業者 代表取締役CEOの奥西亮賀氏が、AIが日本の社会課題にもたらす影響について話した。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
ビジネス電話の音声AI応答サービスを開発、販売するIVRy(アイブリー)は初の自社主催カンファレンスを都内で開催した。最終セッションでは「生成AIで変わる未来のシゴト」と題したトークセッションが開催され、元デジタル副大臣で、自由民主党・衆議院議員 環境副大臣の小林史明氏、ALL STAR SAAS FUNDマネジングパートナーの前田ヒロ氏、IVRy創業者 代表取締役CEOの奥西亮賀氏が登壇。AIが日本の社会課題にどのような影響をもたらすか、3人それぞれの立場から意見を述べた。
IVRyが2025年1月31日に主催した「シゴトシフト2025 - AIで、現場が楽(ラク)になる」の最終セッションとして「生成AIで変わる未来のシゴト」と題したトークセッションを基に編集部で再構成した。
人口が2割減る社会で同じ生産性を引き出すためには
最初のテーマは「日本の社会課題とAI活用の事例」。小林氏は、将来的に人口が大幅に減少する可能性が高い日本の未来を直視し、「人口8掛け社会」によって生産性を高めていかなければいけないと語る。「地方を回る中、今後20年で10人でやっていることを8人で回せる社会にしていこうと話している。これまでもあらゆる手を尽くしているのに、どうするのかと叱られるが、そのために政府が率先して変わろうとしている。その原動力がAIだ」と話す。
既に約1万件の国の規制を見直し、AIで自動化できるように改訂。2024年8月に完了したという。例えば、約3000条項に含まれていた「目視」という文言を全廃。人が直接見る代わりにカメラ、ドローンなどを使えるようにした。他にも「常駐」「専任」「有資格者」など、人が現場に張り付かなければいけない項目をカットした。
「現地で直接見ていた業務がオンライン化すれば、例えば、介護施設の責任者はオンラインで複数拠点を見ることができる。またセルフサービスのガソリンスタンドでは、必ず店舗内のスタッフが承認しないとガソリンが出ない仕組みになっているが、AIで処理すれば無人化でき、圧倒的な効率化を進められる」(小林氏)
規制の撤廃は新たな産業の支援にもつながる。小林氏は2020年の安倍政権時代に、コロナ禍で書類の「ハンコ廃止」のための法律の見直しにも関わった。「48の法律に書かれていたハンコという条件を消した結果、それ以降の3年間で電子契約の市場が4倍に拡大した」と話す。
目下政府が取り組んでいるのが行政の問い合わせ窓口の統合だ。千葉県で実施してる実証実験では、従来は各市町村単位で運営していた子どもの虐待に関する相談窓口を県が一つに集約する。大分県では介護について同様の取り組みをしている。これらがうまくいけば全国の都道府県に展開したいという。
「地域単位では年に数件の問い合わせでも、全国で集約すれば数千のビッグデータになり、分析して解決のサイクルを回せる。AIなどのテクノロジーを使ってアナログな業務から人を解放していく」(小林氏)
AIが日本企業のテクノロジー活用を加速する
続いて2つ目のテーマの「グローバルでのAI活用」について、前田氏が説明した。前田氏はベンチャーキャピタルでスタートアップを支援してきた。2015年からはSaaSとAIに特化して集中投資を進めている。その立場から、日本と海外、特に米国のテクノロジーの取り入れ方の違いを次のように語る。
「米国で『iPhone』が登場してから当時主流だった『ブラックベリー』のシェアは急落した。米国は技術者は常に『新しいテクノロジーに取って代わられる、ゆっくりしていたら食われる』という危機感を持って働いている」
日米のスピード感の違いについて3人の意見が一致していたものの、「日本も今後スピードが上がる可能性がある」と指摘するのは小林氏だ。「徹底的にテクノロジーを活用しなければ生き残れないというマインドは高まっている。日本もいよいよインフレ時代に入ったので、早く意思決定した人が得することになるため、スピードは上がるのでは」と期待を語る。
「日本のスピードアップを図るためにはどうすればいいか」という小林氏の問いに対して前田氏は「AIなどのテクノロジーは、コスト削減、効率化の領域で効果が出やすく、最初はそこに入っていく。やり尽くして限界になると、トップラインを伸ばす方向に向かっていく。米国はすでに効率化にメドが立ち、AIを活用した成長にシフトしているが、日本はこれからだ」と答える。
また前田氏は、海外と日本の違いとして、テクノロジー人材の動向についても言及する。
「米国ではエンジニアの約7割が非IT企業に就職する。Coca-ColaやP&Gなどの大手企業が大量にエンジニアを採用するが、日本は逆にエンジニアの7割がIT企業に就職してしまう。これは日本のDXが進まない課題かもしれない。逆に、社会課題の解決に集中できるスタートアップのサービスは一気に普及するチャンスにもつながる」
このコメントに対して奥西氏は、「AIが進化することで、これまで『ジュニアエンジニア』が担ってきた、簡単なコード生成などのITスキルをAIが代わりに担当できる。IT人材が不足している日本企業の構造的な問題は、AIをうまく使うことで解決できる可能性がある。ピンチに見えるようでチャンスなのかもしれない」と話す。
AIで日本のポテンシャルを活性化する
最後のテーマは「日本でAI活用する際のポイントと、これからの日本の課題」。奥西氏が口火を切った。
「インターネットの登場後、ITの側面の一つは『Web画面のユーザーインタフェース(UI)を改善する』取り組みだった。生成AIの登場で、そのパラダイムが動いた。画面に展開しなくても、いきなり会話でインタフェースが成り立つ時代が訪れている。データ活用も生成AIの登場によって従来のように構造化を意識する必要がなく、例えば会話の音声データをそのまま残しておけば、後でいくらでも分析できる」
奥西氏は、今後10年で、Web画面やキーボードといったインタフェースが博物館送りになるかもしれないと語る。「この視点でビジネスを見渡すと、イノベーションのタネはあちこちに落ちている」
これに対して小林氏は、「AIによってテクノロジー活用に専門性が必要なくなり、課題になるのは権限委譲と年齢のダイバーシティーだ」と述べる。
「例えば飲食店の業務の課題は、間違いなく現場で働くアルバイトが一番分かっているはずだ。その人に何を改善すればいいかを聞くことが、本部の人が時々店舗を回ってヒアリングするよりもいいはず。それが会社としてできるか。また、ITを若手中心で開発するケースが多く、高齢者はITが苦手というなら、シニアの従業員には課題を聞けばいい。AIがテクノロジーへのアクセスを楽にするというメリットを生かし、誰でも議論に参加する環境を作るべきだ」(小林氏)
AIによるテクノロジーの民主化に関して奥西氏は、IVRyは最先端のAIを活用するソリューションだが、「電話」という分かりやすいインタフェースを使っていることで、多くの企業が拒否反応を示すことなく検討していると説明する。
最後にセッションのまとめとして、3人がそれぞれ今後への展望と期待を述べた。
小林氏は、AIの普及で専門性の低いホワイトカラーの仕事はどんどん圧縮される一方、社会を支える専門人材の価値が高まり、「アドバンスドエッセンシャルワーカー」が存在感を増すと話す。「この領域にテクノロジーに理解のある人に参加してもらい、リアルな世界と接している人のアナログ仕事を変革してほしい。それが『8掛け社会』の日本を成長させる原動力になる」と語る。
前田氏は、「AIの精度は間違いなくもっと上がる。近い将来、『アイアンマン』のAIアシスタントが存在するような世界になると確信している。そういう時代に、私は日本が優位性を持てるポテンシャルがあると思っている。海外から日本に来た人が口をそろえて言う、食事やサービスのディテールは、AIでは提供できない。日本人が世界で活躍できる場は広がると思っている」と期待を述べる。
最後に奥西氏も、「紙からインターネットへの変革も、従来の価値観と戦った人たちの努力によって実現してきた。AIは思っているよりもできることが多い。みなさんが、目の前の一つ一つを変えていくチェーンをつないでいくことで、将来の日本をともに変えていきたい」と語った。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
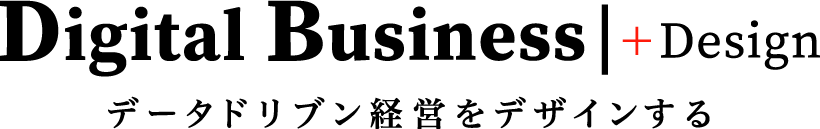
 左から奥西氏、前田氏、小林氏(提供:IVRy)
左から奥西氏、前田氏、小林氏(提供:IVRy)