ビジネスモデリングをプロジェクトに応用する:ビジネスモデリング事始(6)
ビジネスの機能、構造のモデル化に続き、「ビジネスの振る舞い」を表現する方法を解説しよう。これらの手法を身に付けることで、業務改革やIT投資効果の算出などのプロジェクトがスムーズに進められる。
ビジネスの振る舞いから何が分かるか?
第4回でビジネスの機能をモデル化する手法を、第5回でビジネスの構造を表現する方法を説明しました。最後に、ビジネスの振る舞いを記述する方法について説明します。各資産はどのようにしてプロセスを実現しているのか、その動きを明らかにする方法について見ていきます。
ここでは、ビジネスの振る舞いを「相互作用」「ワークフロー」「ライフサイクル」という3つの観点からとらえます。
ビジネスのメカニズムを検証する「相互作用」
まず、相互作用について説明します。UMLの相互作用図を作成することにより、プロセス構造で構成された各資産の役割分担が適切か否かを検証します。関連のある各資産の間でメッセージをやりとりさせることによって、各資産の相互作用をシミュレーションし、価値を産出するメカニズムが適切かどうかを確認します。
例えば「責務が集中しすぎている資産はないか」「同じ機能を実現している複数の資産、役割の重複はないか」「まったく何の役割も担っていない資産はないか」などをチェックします。すると同じ機能を実現している複数の情報システムや作業者が可視化されます。こうした重複資産もコンスタントにコスティングされていきますので、それだけ企業の利益を圧迫することになります。相互作用を検証することにより、ビジネスの構造を再編成して価値産出のメカニズムを効率化するなど、コストダウン対策を立てられるようになります。
ビジネスルールを明確化する「ワークフロー」
続いて、ワークフローについて説明します。プロセス単位にアクティビティ図を作成することによって、「誰が」「何を」「いつ行うか」という作業の流れの観点から、プロセスの実現を明らかにします。このとき、アクティビティ図のレーンに各資産を対応させ、1つ1つのアクティビティを資産の機能、つまりクラスの操作に対応させて考えます。
ワークフローによってビジネスルールが明確になり、さまざまなメリットが生まれます。例えばプロセス単位にアウトソーシングを考える場合、その単位でビジネスルールを指定することができます。また、ワークフローに対してABC分析を適用することで、プロセス単位のコスト(プロセスコスト)を算出できます。また現状のプロセスコストと改善後のプロセスコストを比較することによって、業務改善の妥当性を検証することができます。
ビジネスの振る舞いを可視化した結果を受けてビジネスの構造を洗練させます。相互作用によって見直された役割分担は、ビジネスの構造に反映されます。相互作用図でやりとりされるメッセージは、そのメッセージを渡された資産(クラス)の操作として割り当てます。また、ワークフローを構成する1つ1つのアクティビティは、それを実行する資産に対応したクラスの操作として割り当てます。
ビジネスや資産の繊維状態を表す「ライフサイクル」
最後に、ライフサイクルについて説明します。ビジネスや資産の状態が遷移する場合、それをUMLの状態遷移図を使って表すことができます。例えば、事業部(組織単位)がビジネスの単位であれば、その単位にライフサイクルを記述します。
このようなビジネスの振る舞いを表したモデルを「ビジネスビヘイビアモデル」と呼びます。
以上のように、UMLによってもうかる仕組み、
- ビジネスのプロセス
- プロセスを誰がどこで実現するのか:組織および資産とネットワーク
- プロセスをどのように実現するのか:相互作用とワークフロー
が可視化されます。また、プロセス体系、組織体系、ネットワーク体系によってビジネスアーキテクチャが構成されます。
ビジネスモデルを現場で活用する
ビジネスモデルをベースにして業務プロセスを改善する
ここでは、UMLで作成されたビジネスモデルを活用して業務プロセスを改善する方法について説明します。
・現状プロセスのコストを測る
業務プロセスを改善するには、(1)まずUMLで現状のビジネスを可視化する(As-Isモデル*1の作成)ことから始めます。(2)そして、その中から業務改善を行うプロセスを選定します。(3)続いて、選定されたプロセスのプロセスコストを算出します。プロセスのワークフローを表すアクティビティ図を見て、各アクティビティに対してチャージレートや時間、経費などを測ります。(4)それを合計してプロセス単位のコストを算出します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図3 As-Isモデルのプロセスコスト |
このときワークフローの流れの中に同期スレッドがあれば、最長のスレッドの時間をスレッド全体の時間にします。また、条件付きスレッドがある場合は、その発生率で重み付けをします。さらに、代替スレッドがあった場合も、その発生率で重み付けをします。
・各アクティビティの付加価値分析を行う
次に、アクティビティ図を見て各アクティビティのバリューランキングを行います。そして、付加価値が低いものに対する改善策を策定します。このとき、情報システムを導入することよる自動化など、ITを活用することを考えます。そして、その結果を受けて改善後のワークフローを作成します。(To-Beモデル*2の作成)。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図4 付加価値分析の例 |
・現状プロセスと将来像モデルのコストからROIを算出
続いて、ABC分析によってTo-Beモデルのプロセスコストを算出します。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 図5 To-Beモデルのプロセスコスト |
これによって、As-IsモデルとTo-Beモデルのプロセスコストの差分が分かります。例えば情報システム導入により、業務プロセス改革による削減コストを算出することができます。削減コストが算出できれば、それをベースに「情報システム導入による投資対効果」を算出できます。投資に対するリターンを見込むことができれば、情報システムを開発するなど、実際の業務改善が実施されることになります。
ビジネスモデルをベースにして情報システムを開発する
続いて、UMLで記述されたビジネスモデルをベースに情報システムモデルを作成する方法について紹介します。
まず、ビジネスモデルの中のどの部分を情報システム化するかを明確にします。
情報化対象の選定
- 情報化対象プロセスの選定
開発対象のプロセスを1つまたは複数選定します。
- 情報システムの選定
選定されたプロセスに対応するTo-Beモデルのプロセス構造を確認して、そこに参加する情報システムのうち開発対象となる情報システムを明確にします。
- 操作の明確化
対象となる情報システムの資産構造を参照し、開発対象となる操作を明確にします。To-Beモデルのプロセスの実現を確認して、相互作用やワークフローに関連している情報システムのメッセージやアクティビティに対応する操作を見つけ出します。
- 関連資産の明確化
To-Beモデルのプロセスの実現(ワークフローや相互作用)を確認して、開発対象の操作に関連する協調相手(コラボレーター)となる資産を見つけ出します。
- エンティティの明確化
To-Beモデルのプロセス構造を確認して、開発対象の情報システムや、その協調相手に関連しているエンティティを明確にします。
続いて、ビジネスモデルを情報システムモデルへ展開します。
サブシステムの作成
「情報システムの選定」で選定した情報システムをサブシステムに割り当てます。
ユースケースモデルへの展開
- 操作からユースケースへの展開
上述した操作の選定で選定された操作を1つの情報システムのユースケースに割り当てます。
- アクターへの展開
「関連資産の明確化」で明確にされた資産1つ1つを情報システムのアクターに割り当てます。
- オブジェクトモデルへの展開
「エンティティの明確化」で明確になった、開発対象プロセスのすべてのエンティティから概念モデル(*3)を作成します。概念モデルを作成する際は、実際にプロセスを運営する専門家にヒアリングをして概念構造を探っていく手段が大変有効です。システム開発が進んでいく中で、アプリケーション開発者は、概念モデルをベースにして、ソフトウェアの仕様を表す分析モデルを作ります。
データモデルへの展開
エンティティの明確化で明確になった、開発対象プロセスのすべてのエンティティからER(Entity-Relationship)モデルを作成します。
このように、UMLで記述されたビジネスモデルをベースに情報システムを開発することができます。
以上のように、UMLでビジネスモデルを作ることによって、それをベースに業務改善や情報システム開発をすることができます。
このページのポイント
▼ビジネスの振る舞いを、「相互作用」「ワークフロー」「ライフサイクル」でとらえる
▼「相互作用」「ワークフロー」「ライフサイクル」がそれぞれ何を明らかにし、どんなメリットがあるかを押さえよう
▼ビジネスモデルをベースに、改革すべき業務やシステム化の対象が見えてくる
▼ビジネスモデルをシステムの機能や操作、データモデルに展開することで最適なシステムを円滑に構築できる
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- 中国電力、RAGの限界に直面し“電力業務特化型LLM”の構築を開始 国産LLMを基盤に
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 「年齢で落とされる」は6割超 シニアエンジニアが直面する採用の壁と本音
- なぜ日本のITエンジニアは優遇されない? 「世界給与ランキング」から見えた課題
- 年収1000万を超えるITエンジニアのキャリアは? 経験年数と転職回数の「相関関係」が明らかに
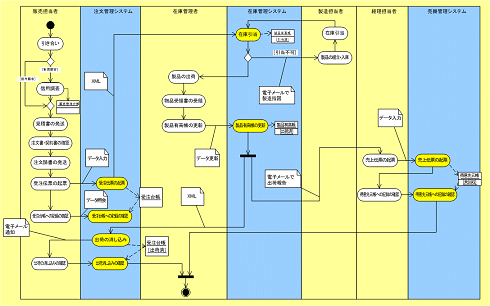 図1 プロセスの実現:ワークフロー(
図1 プロセスの実現:ワークフロー(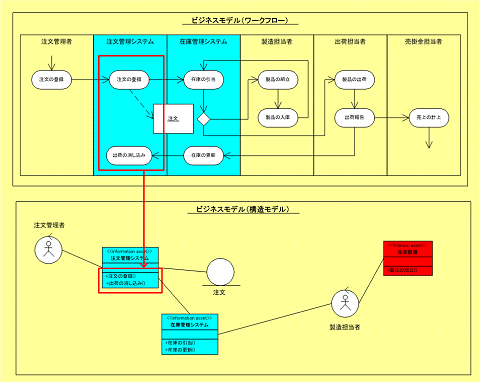 図2 構造モデルの洗練:ワークフローから(
図2 構造モデルの洗練:ワークフローから(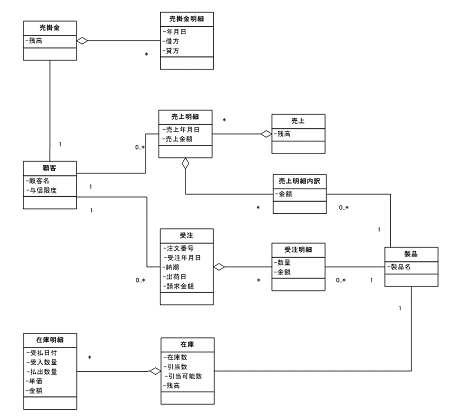 図6 概念モデルの例(
図6 概念モデルの例(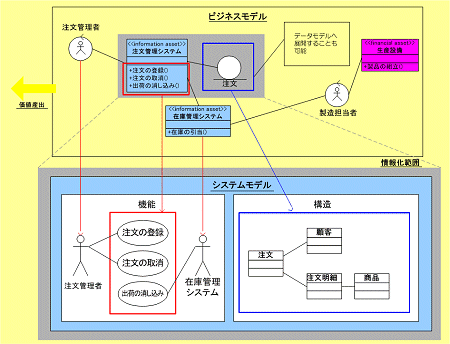 図7 ビジネスモデルから情報システムモデルへの展開 このように、UMLでビジネスモデルを作ることによって、それをベースに業務改善や情報システム開発をすることができます。
図7 ビジネスモデルから情報システムモデルへの展開 このように、UMLでビジネスモデルを作ることによって、それをベースに業務改善や情報システム開発をすることができます。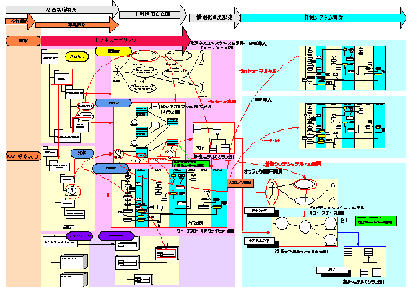 図8 UMLによるビジネスモデリングとその活用(
図8 UMLによるビジネスモデリングとその活用(