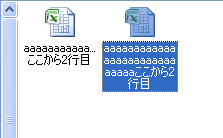理想のファイル名の付け方:3分LifeHacking
「あれ、あのファイルどこいったっけ?」という人に限って、いい加減にファイル名を付けていることが多い。ルールは複雑にしたくないが、どこに気をつければ後から活用しやすいファイル名になるのだろうか。
その昔、ファイル名が8文字+3文字だった時代は、ファイルの整理といえばフォルダを階層化してツリー状に分類していくことだった。ところがデスクトップ検索全盛の昨今は、フォルダの数を減らして多くのファイルを入れるやり方が増え始めている。
そこで問題になるのがファイル名の付け方だ。
まず上書きされないよう既存のファイル名と違う名称にしたい。できればフォルダ一覧画面からぱっと見つけられるような名前にしたい。同種のファイルをまとめて選択できるようにしたい。こんな希望を叶えるには、どんな名前の付け方にすればいいだろうか。
ファイル名は“タグ”である
ファイル名には、「何についてのファイルか?」を入れるのが一般的。つまり画像・動画共有サービスやソーシャルブックマークのように、そのファイルのタグに当たるものをどんどん入れてしまうのだ。
- 何についてのファイル──例えば「媒体資料.pdf」
- 関連する企業名──例えば「アイティメディア_媒体資料.pdf」
- プロジェクト名──例えば「bizid_媒体資料.pdf」
- 誰が作ったもの?──例えば「媒体資料_斎藤修正.pdf」
これまでフォルダ名として付けていた言葉を、ファイル名に入れ込んで、フラットに管理するともいえる。ただしあまり長い名前を付けるとエクスプローラで一覧できなくなる。
Windows XPで試したところ、下記のように、表示方法によって一覧できるファイル名の長さは異なった。最も長くても半角41文字。アイコン表示を普段使うなら、英数字で11文字、日本語で20文字が目安になる。
ファイル名を2行表示させるには?
デスクトップなど「アイコン」表示されているファイルのうち、ファイル名が2行に渡って表示されるものと、1行しか表示されないものとあるのにお気づきだろうか。
どうやらWindows XPでは、すべて英数字のファイル名だと1行表示だが、2バイト文字や半角スペースなどが含まれているとファイル名が2行表示されるようだ。しかも、頭が英数字で始まり途中から2バイト文字が入っていると、2行目は2バイト文字から表示されるという仕掛けになっている。
例えば、「07-03-15version00012_itmedia_アイティメディア.pdf」というファイルがあると、2行目は「アイティメディア」から表示されるのだ。
日付を入れ込む
さらにユニークなファイル名(同じフォルダに入れても上書きされない名前)にするには、作成・更新の日付を入れるとよい。また、バージョンを管理するのであればバージョン名を入れるのもアリだ。
- 作成、更新の日付──例えば「媒体資料070314.pdf」
- ファイルのバージョン──例えば「媒体資料ver2.pdf」
ちなみに、どんな要素をファイル名の頭にするかはよく考える必要がある。日付を頭にすれば、ファイルを名前で並べ替えたときに日付順に並ぶというメリットがある。逆に、後ろに入れておけば、関連する資料がまとまって並ぶ。要するに、何の基準でまとめたいかを考えておこう。
ただし日付順に並ばせたい場合は、「表示」から「詳細表示」を選んで、「更新日時」で並び替えればいいので、日付情報は後ろに入れるという考え方もある。
ファイル名のちょっとしたTips
ファイル名を付けるときに気をつけたい点を2つ。
1つは、連番の数字を付けていくときは桁数を揃えるということ。例えば10個以上のファイルがあって数字で区別する場合は、「6」ではなく「06」といった数字を付けたい。桁数を揃えないと並び替えをした時に“10のあとに2が来る”ということになってしまうからだ。※3月20日付記:Windows XPやMacOSでは桁数を揃えなくても、うまく並び変わります。ご指摘くださった皆様、ありがとうございました。ただアプリケーションによっては桁を揃えたほうがよい場合も多いので、推奨させていただきます
2つ目は、ファイル名の頭には日本語ではなく英字を付けたほうがいい。Windowsのエクスプローラは、ファイル一覧画面で英字キーを押すと、その文字のファイルにジャンプできるからだ。「b媒体資料.pdf」というファイル名にしておけば、[b]キーを押すだけで選択できる。
ファイル名の付け方について、いくつかTipsを紹介してきた。しかし最も重要なポイントは、シンプルで自分で守れるルールを使い継続するということだ。パーフェクトな管理法を編み出したとしても、それを守れなければ元の黙阿弥。これらを参考にしつつ、守れるルールを使ってみてほしい。
関連記事
- LifeHack
- 続・デスクトップを広く使う方法
解像度がXGAぐらいのノートPCを使っていると、デスクトップ上のアイコンがやたらと巨大に感じることがある。デスクトップのアイコンを、エクスプローラの「一覧」表示と同程度まで縮小してくれるのが「ぴたすちお」だ。 - Google Desktopをマスターする
Google Desktopを賢く使えば「ビルがスティーブに宛てた合併関連のメール」なども検索可能。(Lifehacker)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 悪いのは本当にVPN? 日本医科大武蔵小杉病院のランサムウェア事件をダークWebから解明
- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?
- アサヒGHDがランサムウェア被害の調査報告書を公開 152万の個人情報が漏えいの恐れ
- 関西電力が「AIファースト企業」化に本気 脱JTCを図る背景と全従業員“AI武装化”の全貌
- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ
- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認
- 東海大学、ランサムウェア被害を報告 19万人超の個人情報が漏えい
- 保守の「脱・人月ビジネス」化は進むか それでも残る仕事は何か
- そのセキュリティ業務、自前と外注のどちらが正解? 勘に頼らない判断のこつ
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
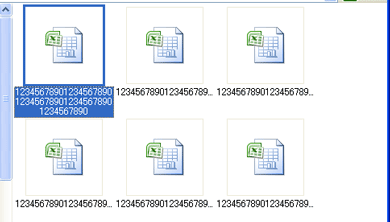 「縮小版」表示。選択されていないファイル名は、半角で19文字しか表示されない
「縮小版」表示。選択されていないファイル名は、半角で19文字しか表示されない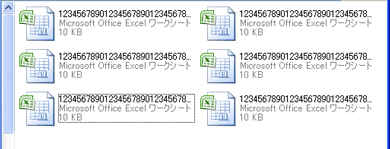 「並べて表示」。半角で28文字を表示
「並べて表示」。半角で28文字を表示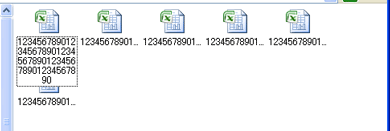 「アイコン」表示。選択されていないファイル名は半角で11文字しか表示されない。デスクトップがこの状態だ。ただし日本語ファイル名なら少々異なる(カコミ参照)
「アイコン」表示。選択されていないファイル名は半角で11文字しか表示されない。デスクトップがこの状態だ。ただし日本語ファイル名なら少々異なる(カコミ参照)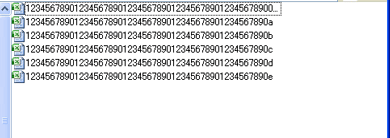 「一覧」表示。半角41文字を表示
「一覧」表示。半角41文字を表示 「詳細」表示。名前のカラムを広げなければ、表示されるのは半角25文字
「詳細」表示。名前のカラムを広げなければ、表示されるのは半角25文字