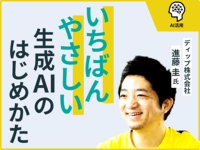東武ホテルが直面する人手不足 社長が提唱する「観光業界のAI活用」:東武ホテルの戦略【中編】
【Amazonギフト券プレゼント!】味の素の元CDOに学ぶ、全社DXの背景にある「パーパス経営」とは≫
- 【開催期間】2025年6月25日(水)13:00〜15:30
- 【視聴】無料
- 【視聴方法】こちらから無料登録
- 本セミナーに登録し、2つ以上の講演を視聴された方全員にAmazonギフトカード500円分をプレゼント
- 【概要】かつて5年連続の赤字に陥った味の素。しかし、2019年に福士博司氏がCDOに就任して以降、同社は次々に改革を実行し、時価総額を大きく伸ばしました。その原動力が、デジタルの枠を超えた「組織を180度変える戦略」だといいます。福士氏は何を見据え、どのように戦略を描いていたのか。DXの本質に迫ります。
コロナ禍を経て、観光業界はかつてない変革期を迎えている。日本政府観光局の調べによると、2025年3月の訪日外国人数は349万7600人と、前年同月比13.5%増で過去最高を記録。1〜3月の累計でも1053万人超と過去最速のペースで推移している。2024年のインバウンド消費額も8兆1395億円に達し、1人あたり旅行支出は22万7000円と過去最高を更新した。
こうした需要拡大の裏で、ホテルや鉄道など観光インフラの現場では、人手不足やコスト増、デジタル化対応が急務となっている。ホテル業界は人手不足やDXの課題にどう向き合えばよいのか。
前編に引き続き、東武ホテルマネジメントの三輪裕章社長に、ホテル経営の現場で直面する課題と、その打開策を聞いた。
タッチ決済普及とデータ活用が変える観光インフラ
――三輪社長の東武鉄道での労務経験は、現在の経営にどのように影響していますか。
経営層と従業員が向き合って話をする経験は、私にとって非常に大きかったです。組合と経営側は立場が違うので、どうしても対立する場面もあります。逆に立場が異なるからこそ、お互いにチェックし合える関係が生まれます。一方的にやりたいことだけを進めてしまうのは危険で、やはり自分の考えや方針をきちんとチェックしてくれる存在がいることによって、暴走や誤りを防ぐことができます。
他社の例では、JRは国鉄時代、組合がいきすぎてしまったこともありましたし、その後は当局側がやりすぎた歴史もあります。東武ではそうしたことが起きないよう、バランスを大切にしてきました。
例えば、JRでは組合が分裂しているため、同じ内容の交渉を何度もやらなければならない場面もあります。東武は単一労組でしたので無駄な手間を避け、しっかりと一つの方向性でやっていくことができたと思います。従業員も経営全般をよく見てくれるようになりますし、危機的な状況や事故、コロナ禍のような非常時にも、しっかりと理解して協力してくれる体制ができています。そのため東武は、コロナ禍からの回復も比較的早く進められました。
――具体的にどのような施策を実施したのでしょうか。
合理化の面でも、大きな変化がありました。東武鉄道は全線で約460キロありますが、そのうち180キロを除く280キロはすでにワンマン運行を導入しています。これはコロナ禍の2020年ごろから進めてきた取り組みです。ワンマン運転のための設備を整え、従来の運転士と車掌がいる体制の常識を大きく変えました。東京メトロ南北線や都営大江戸線など、今では都心の多くの路線でもワンマン運転を導入していますが、東武はローカル線を多く抱えているため、駅の無人化も積極的に進めています。
ホームドアの設置についても、主要な駅を中心に進めていますが、東武は200以上の駅があり、他の大手私鉄と比べても規模が大きいのです。利用者の少ない駅にまでホームドアを設置するのは現実的ではありませんので、主要な百数十駅については期限を設けて設置を進めています。例えば東上線60キロ、本線60キロ、野田線60キロといった主要区間で対応しています。
こうした合理化や現場の変革を進めるうえでも、労使の信頼関係や現場との対話の経験が今の経営に大いに生きていると感じています。
――ITやテクノロジーの活用について、社長はどのように考えていますか。
私は、今後のホテル経営や観光業において、ITやテクノロジーの役割はますます大きくなると考えています。現状では、経験や勘をもとに「こう動くだろう」と予測して動いていますが、今後はAIの活用によって、より高度なパターン分析や提案ができるようになると思います。実際、営業統括本部には20人ほどいますが、AIの導入が進めば、将来的にはそれほど多くの人員を必要としなくなる可能性もあると感じています。
ホテル業界で言えば、フロント業務が接客の中心ですが、オンライン予約の拡大によって、ホテル名や詳細を顧客に十分に伝えられないまま予約が入ることも増えています。また、海外からの予約では、現地アクティビティの手配を求められることも多いのですが、ホテル単体で全てを担うのは現実的ではありません。
地域の事業者とネットワークを組み、送客やサービス連携を進める必要があります。しかし、彼らはインバウンド対応でキャンセル料が取れないと、経営が成り立たない課題もあります。OTA(オンライン旅行代理店)経由の予約では、まだ事前決済が一般的ではなく、直前キャンセルが当たり前になっている現状です。観光立国を目指すなら、事前決済の徹底が不可欠だと思います。
さらに、私は入国審査時に生体認証を活用し、カードなどを持たずに決済や交通利用ができる仕組みを導入すべきだと考えています。顔認証や生体認証の技術が進化すれば、ホテルや鉄道などの現場でも人手を減らしつつ、サービスの質を維持できるはずです。
中国のAlipayやWeChatPayのように、徹底したデジタル化が進めば、日本もDXによる効率化が一層進むでしょう。二重投資を避けるためにも、国全体で一気に整備していくことが望ましいと考えています。
鉄道では、自動改札のデータが全てJRのシステムに上がってしまう課題もありますが、今後は顧客データ活用や連携も重要になってきます。ホテル業界でも、AIやロボットの導入による業務効率化や、顧客対応の自動化、多言語対応、顔認証によるチェックインなど、さまざまなテクノロジーがすでに実用段階に入っています。こうした技術を積極的に取り入れ、スタッフが本来注力すべきサービスやおもてなしに集中できる環境を整えていきたいと考えています。
タッチ決済普及とデータ活用が変える観光インフラ
――顧客データの外販は、JR東日本が2013年に実施しようとしたところ、大きな批判を浴びました。
データを他社と共有化しようとしたところ、その問題が発生しました。その後、匿名データに切り替えることによって販売できる仕組みに変わってきました。今その状況を大きく動かそうとしているのが、タッチ決済を手掛けるカード会社です。
近年では、自動改札もクレジットカードのタッチ決済に対応しようとしています。これまでPASMOのような交通系ICカードを使えば、購買データなども自社グループに上がってきていたのですが、タッチ決済の普及によって、そのデータの流れが変わりつつあります。
唯一、Suicaの他社データを受け取れたのは、消費税還元の時期でした。あの時は「このカードで還元します」という仕組みだったので、他社での利用情報も返ってきて、JRがデータを開示してくれました。あの時だけは「こんなデータが取れるのか」と驚きましたね。
――それに伴って、自動改札機などハードの更新も必要になりますね。
鉄道会社は運賃を安く抑えるよう求められる一方で、設備投資も必要です。例えば駅のエスカレーターやエレベーターの設置時には国や自治体から3分の1ずつ補助があります。ですが、その後のランニングコストや更新費用は全額自己負担になります。そうした中で、唯一活路を見いだせるのが自動改札のデータです。
定期券についても、以前は「この区間をこの期間内で使えます」という情報しか取っていませんでしたが、4〜5年前からは「どこで降りたか」などの詳細なデータも営業部門に取らせるようにしました。これにより、利用者がどこで降りて寄り道をして帰るのかなど、行動様式が分かるようになり、マーケティングにも活用できるようになりました。
しかし、ちょうどそのタイミングでコロナ禍となり、さらにタッチ決済の波が押し寄せてきました。2024年11月には熊本で全国交通系ICカードから離脱する動きがあり、全国組織としてインフラを民間で維持するのは非常に大変な状況です。駅名の変更や新駅の設置にも多大なコストがかかりますし、その費用は各社が自前で負担する仕組みになっているからです。
インバウンド対応の面でも、VISAなど国際ブランドのクレジットカードが使えないと困るという声が多くなっています。PASMOやSuicaを購入しても、FeliCa(フェリカ)の種類やアプリの違いで海外の方が利用しにくい現状があります。
そのため、クレジットカードでそのままタッチ決済できるようにしようという流れが強まっています。VISAはこの流れを追い風にして、非常に積極的に攻勢をかけています。今や、データを独占している会社が最も強い時代です。どの業界でも、データをいかに管理・活用できるかが勝負になってきていると感じています。
生体認証の一元管理が切り拓く観光の利便性
――日本全体の利便性をより良くしていきたいというお気持ちは強いのでしょうか。
本当にそう思っています。例えば生体認証の仕組み一つを取っても、現状では1カ所で登録すれば済むわけではなく、さまざまな場所で何度も登録を求められるのではないかという危惧です。当ホテルで登録したからといって、他では使えない。こうした仕組みを効率化するためには、登録情報を一元的に管理するデータバンクのような存在が必要だと考えています。そうでなければ、利用者は何度も同じ手続きを繰り返すことになってしまうからです。
――東武グループでは、日立製作所と共同で生体認証サービス「SAKULaLa」(サクララ)の導入を進めていますよね。
はい、当社でも顔認証や生体認証を活用したシステムを導入しています。システム自体はどちらの認証方式にも対応できるように設計してもらっています。今後はこうした仕組みが社会全体に広がっていくべきだと考えています。
ただ、そのためにはデータ管理の在り方が非常に重要です。必要なときに照合できるようにしつつ、個別に管理されてセキュリティが過度にかかると、利便性が損なわれてしまいます。こうした仕組みの整備は、やはり国が主導する必要があると感じています。
――2023年6月の社長就任から2年になります。ホテル業界を見て、どんなことを感じていますか。
この2年あまり、ホテル業界に身を置いてみて、さまざまな可能性を感じています。例えば、インバウンド料金と国内料金を分けるという話もありました。海外ではそうした運用をしている国もありますが、日本でやろうとするとすぐに批判されてしまうのが現実です。
そのような中、国がマイナンバーカードを配布していた時期に、当社の「トブポ」アプリを活用して、クーポンや割引券を発行する仕組みを考えました。料金はインバウンド料金に統一し、国内のお客さまにはマイナカードやアプリを使って実質的な割引やポイントを還元する。外国の方にはマイナカードがありませんし、アプリもダウンロードできません。ですから、国内のお客さまだけに特典を付与できる仕組みができたらと考えておりました。
さらに、トブポの加盟店をホテル周辺の飲食店にも広げ、地元経済にもインバウンドの恩恵が波及するよう工夫しています。浅草などの古い町では、インバウンドは歓迎される一方で、実際に来店されると現場は戸惑うことも多いです。そこで、英語を話せる社員がアテンドとして同行し、一緒に食事をするなど、地元とインバウンドをつなぐ役割も考えています。これを副業として社員に経験させることも検討しています。
このように、ポイント還元など従来の仕組みにとらわれず、もっと合理的で地元にもメリットがある仕組みを模索しています。鉄道時代は投資の回収期間が長く、変化を好まない部分もありましたが、ホテル業界に来てからは、日々新しいことに挑戦できてとても楽しいと感じています。新たな職場で、さまざまな取り組みを通じて社会に貢献できることにやりがいを感じています。
基幹産業重視とサービス業の本質を見据える
――三輪社長の話を聞くと、自社がどう勝つかよりも、地元や周囲、全体を見据えた広い視野を持っていると感じます。その点についてはいかがでしょうか。
私たちサービス業は、実業があってこそ成り立つものだと思っています。国の基幹産業や生産物がしっかり評価されているからこそ、国が回り、安心して働ける環境が生まれるのだと感じています。もしも紛争やパンデミックのような事態が起きれば、サービス業は一気に立ち行かなくなります。だからこそ、本当に基幹産業を徹底して強化してもらいたいと考えています。
また、私たちの仕事はデイトレーダーのような短期的な利益追求とは違い、サービスという商品をきちんと提供し、利用者から評価をいただき、その対価としてお代をいただくものです。社員にとっても、その評価や報酬がやりがいや働くインセンティブにつながります。私自身もそうした形で働いていたいと思いますし、一緒に働く社員にもそうあってほしいと願っています。
――三輪社長がマネジメントにおいて大切にしていることや、座右の銘はありますか。
まず「諦めたら終わりだ」という気持ちを大切にしています。何事もやってみようという姿勢で臨んでいます。また、国鉄総裁だった石田禮助さんの「粗にして野だが卑ではない」という言葉を座右の銘にしています。粗野で荒々しい部分があっても、決して卑しいやり方はしたくない。石田さんは赤字の時に、自分の報酬を返上して改革に取り組みました。小さい頃その姿勢に共感したのを覚えています。経営には緻密さと大胆さの両方が必要だと思っています。私も、人とのつながりをとても大切にしています。
この記事を読んだ方に AI活用、先進企業の実践知を学ぶ
ディップは、小さく生成AI導入を開始。今では全従業員のうち、月間90%超が利用する月もあるほどに浸透、新たに「AIエージェント」事業も立ち上げました。自社の実体験をもとに「生成AIのいちばんやさしいはじめ方」を紹介します。
- 講演「従業員の生成AI利用率90%超のリアル! いちばんやさしい生成AIのはじめかた」
- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏」
- 2025年7月9日(水)〜8月6日(水)
- こちらから無料登録してご視聴ください
- 主催:ITmedia ビジネスオンライン
関連記事
 インバウンド好調も“内外価格差”に課題 東武ホテル社長に聞く経営改革
インバウンド好調も“内外価格差”に課題 東武ホテル社長に聞く経営改革
観光業界は今、かつてないインバウンド需要の高まりにわいている。急激な環境変化の中で、ホテル経営の現場はどのような課題と向き合っているのか。東武ホテルマネジメントの三輪裕章社長に、コロナ禍後のホテル業界の現状と展望を聞いた。 AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
米国のテック系人気ユーチューバーの何人かが、こぞって「AI開発競争はGoogleが勝利した」という見出しの動画をアップしている。これでGoogleの勝利が決定したのかどうか分からないが、少なくともOpenAIの首位独走の時代は終わったのかもしれない。 観光3社が見いだした「オフシーズンの需要喚起策」 宮古島の成功事例となるか?
観光3社が見いだした「オフシーズンの需要喚起策」 宮古島の成功事例となるか?
なぜ今、宮古島ではしご旅の需要が高まっているのか。その背景と可能性を探る。 インバウンド消費「8.1兆円」をどう生かす? Mastercardが提案する「日本企業が取るべき対策」
インバウンド消費「8.1兆円」をどう生かす? Mastercardが提案する「日本企業が取るべき対策」
日本の訪日外国人旅行消費額は2024年に8.1兆円に達し、日本の実質GDP成長率の半分以上を占める大きな成長要因となっている。日本政府や企業は、どのように対処していけばいいのだろうか。米Mastercardのアジア太平洋地域チーフエコノミストに聞いた。 なぜ今、ホテル経営にAIが不可欠なのか “泊まる”を超える宿泊拠点の未来像
なぜ今、ホテル経営にAIが不可欠なのか “泊まる”を超える宿泊拠点の未来像
テクノロジーと共創の力で“宿泊”の概念を再構築しようとする取り組みと、地域と連動して価値を創出する新たなまちづくりについて探る。 「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
NECが、オープンイノベーションに本腰を入れている。NEC Open Innovation Nightには富士通の社員も登壇。同社の取り組みの真意に迫る。 『スマブラ』『カービィ』生みの親に聞く ヒット作を生み出し続けるマネジメント
『スマブラ』『カービィ』生みの親に聞く ヒット作を生み出し続けるマネジメント
『星のカービィ』『大乱闘スマッシュブラザーズ(スマブラ)』の「生みの親」、ゲームクリエイターの桜井政博さんに、ゲーム作りにおけるノウハウや、ヒット作を生み出し続けるマネジメントについて聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング