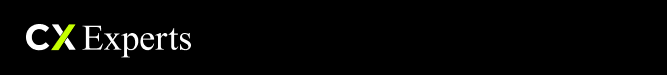“生で食べない魚”が定番ネタに 「サーモン寿司」普及の立役者に聞く「逆転のマーケ戦略」
回転寿司の定番ネタとなったサーモン。人気ネタランキングで14年連続1位(2025年マルハニチロ調べ)に選ばれ続けている。だが、ほんの数十年前まで、日本人の中に「サーモンを生で食べる」という発想はなかった。そう、多くの日本人の認識では、「サーモン=シャケ」として捉えていたのだ。
サーモン寿司の誕生の裏には、40年前のノルウェー政府と水産業界、そして研究機関が一体となったノルウェーの国家プロジェクト「プロジェクト・ジャパン」があった。日本へのサーモン輸出量を3年間で倍増させるという明確な目標のもと、プロジェクトは動き出したのだ。だが、日本で待ち受けていたのは、「こんな魚、寿司には向かない」「シャケを生で食べるなんて非常識だ」といった食文化の壁と業界の反発だった。
今、日本の消費者の多くが当たり前のようにサーモンを口にしている。シャケではないサーモンという名を根付かせ、日本の食文化の常識を覆した食のイノベーションの舞台裏を「サーモン寿司の父」とも称される旧ノルウェー貿易審議会 プロジェクト・ジャパン 市場調査担当者のビョーン・エイリク・オルセン氏に聞いた。
 ビヨーン・エイリク・オルセン 旧ノルウェー貿易審議会 プロジェクト・ジャパン 市場調査担当者。1986年から1990年にかけてノルウェー政府の水産輸出事業「プロジェクト・ジャパン」のメンバーとして活動し、1991年から1994年、東京の駐日ノルウェー大使館に水産参事官として勤務。日本に「サーモン寿司」を普及させた「サーモン寿司の父」。当時から日本にあったシャケと差別化し、「ノルウェーサーモン」としてブランディングしたことで、ノルウェーサーモン寿司を一般に浸透させた(アイティメディア撮影)
ビヨーン・エイリク・オルセン 旧ノルウェー貿易審議会 プロジェクト・ジャパン 市場調査担当者。1986年から1990年にかけてノルウェー政府の水産輸出事業「プロジェクト・ジャパン」のメンバーとして活動し、1991年から1994年、東京の駐日ノルウェー大使館に水産参事官として勤務。日本に「サーモン寿司」を普及させた「サーモン寿司の父」。当時から日本にあったシャケと差別化し、「ノルウェーサーモン」としてブランディングしたことで、ノルウェーサーモン寿司を一般に浸透させた(アイティメディア撮影)シャケではないサーモン 新しい価値観を植え付けるには?
1980年代、日本の食卓に「サーモン」は存在しなかった。寿司や刺身といえば、マグロやイカが主流。「シャケ」は主に焼き鮭を指していた。そんな保守的な日本市場に全く新しい価値を持ち込もうとしたのがノルウェーだったといえる。
「当時、日本に輸出されていたのは、スモークサーモンや魚卵ぐらい。市場はごくわずかでした。私たちは寿司・刺身という新たなカテゴリーに活路を見いだしていたのです」
プロジェクトの中心となったオルセン氏は、日本に長く住み、日本語と文化を理解していた。その目には、日本の「焼きシャケ文化」と、それに根ざした消費者意識の壁がはっきりと映っていた。
だが日本人の抵抗感は想像以上だった。「サーモン=シャケ」という認識が強い日本人にとっては、生食のサーモンは「寄生虫がいるのでは」「おいしくない」との声が挙がり、業界関係者からも否定的な意見が相次ぐ結果に。そこでサーモンを訴求する突破口となったのが、日本の有名料理人たちとのコラボレーションだった。
「当時、人気があった料理番組『料理の鉄人』の出演者を始め、革新的なシェフたちが協力してくれました。新しいものに挑戦する料理人の発信力は、まさに今でいうインフルエンサーでした」
寿司や刺身だけでなく、さまざまな調理法でサーモンを紹介。店舗、雑誌、テレビなど、生活者の接点に少しずつ入り込んでいった。一方で、日本的な「関係性」の構築も欠かせない。加工業者、輸入業者、メディア、業界団体、その一つ一つに「信頼できる人」との接点をつくり、地道に関係を築いていったという。
「日本では、信頼のネットワークを築くのが何より重要でした。リーダーと呼ばれる存在と対話を重ね、ノルウェーにも招いて、現場を見てもらう。その積み重ねが“義理と信頼”となり関係を築き上げました」
危機がチャンスに変わった日
1991年、ノルウェーの養殖業界を大きな危機が襲った。サーモンの供給過多によって価格が下落。業界団体は破綻し、養殖業者の半数、銀行すらも倒産した。
「政府は、余剰になったサーモン3万トンを『日本でシャケとして売ればいい』と言ってきました。ですが、それではシャケの市場と競合して、今までサーモンとして売り込もうとしていた業界との信頼を失ってしまう。私は断りました」
窮地に立たされた時、手を差し伸べたのが、日本の大手冷凍食品会社だった。同社は外交ルートを通じて5000トンを寿司・刺身用として買い取り、キャンペーンを展開。これが日本市場での転換点となった。
「日本では信頼も厚く評判も良い会社でしたので、日本の消費者も受け入れてくれました。そこから販売量が徐々に伸びていったのです」
時を同じくして、バブル経済の崩壊が訪れた。高級寿司店に人が入らなくなる一方、回転寿司チェーンは急成長。低価格で手軽に楽しめるこの新しい形態が、家族連れの支持を得ていく。そこでサーモンの鮮やかな色に子どもたちが引かれ、好んで食べるようになる。子どもたちには、「サーモンは焼くもの」「生で食べるのはおかしい」といった固定観念がなかったのだ。その子どもたちの素直な反応が、食文化に変化をもたらしていく。子どもの反応が家族全体へと広がり、結果として回転寿司がサーモン定着の大きな後押しになったのだ。
「子どもたちがサーモンの鮮やかな色に引かれて食べてくれました。すると母親も『食べてみようか』となり、家族を通じて味の受容が広がっていきました」
1995年、オルセン氏が再び日本を訪れた際、回転寿司店で「ノルウェーサーモン」と書かれた品名を目にする。
「感動しました。サーモンが定着したと実感した瞬間でした」
商品を根付かせるためのイノベーションの本質とは
サーモンを日本に根付かせたのは、製品のイノベーションというより、マーケティングのイノベーションだ。
「魚をご飯にのせるだけなら簡単ですが、『それを食べたい』『おいしい』と思ってもらうには、人々の考え方や食習慣を変えなければなりません。ただ、日本では今でも『サーモンは生で食べない』と言う年配の人が少なくありません。そのような人たちの長年の食習慣を変えるよりも、むしろ若い世代の習慣にアプローチする方が、時間的にも効果的だと考えました」
忍耐強くあること、そして一貫した努力を続けることが不可欠であり、そこに影響力を持つ料理人や子どもたちをインフルエンサーとして巻き込み、社会全体の価値観を少しずつ動かしていったのだ。
オルセン氏は「日本では信頼関係が全てです」と話す。その言葉通り、日本文化の中では、ただ製品を売るだけではなく、人と人の関係性が最終的な鍵となった。イノベーションには、すばらしいアイデアも必要である一方、忍耐や関係構築、そして一貫したブランド戦略も必要となる。それらが組み合わさったからこそ、サーモンは寿司の定番になったのだ。
日本市場で成功するには、信頼を積み上げる力こそが鍵である。その教訓は、食品のみならず、あらゆる異文化ビジネスに通じるものではないだろうか。
関連記事
 キリン「晴れ風」が絶好調 “ビール好き”以外をどうやって取り込んだ?
キリン「晴れ風」が絶好調 “ビール好き”以外をどうやって取り込んだ?
キリンビールが4月に発売した17年ぶりのスタンダードビールの新ブランド「晴れ風」の勢いが止まらない。11月13日には年間販売が500万ケースを突破した。なぜここまで売れたのか。同社ビール類カテゴリー戦略担当の小澤啓介氏に話を聞いた。 キリンビールの「本麒麟」が好調 敏腕マーケターに聞く「売れ続ける理由」
キリンビールの「本麒麟」が好調 敏腕マーケターに聞く「売れ続ける理由」
キリンビールのビール類の販売量が減っている中、気を吐いているのが新ジャンル(第3のビール)の「本麒麟」だ。マーケティング本部の松村孝弘ブランドマネージャーに開発コンセプトを聞いた。 苦戦のコーヒー業界で黒字転換 「豆で勝負した」タリーズが狙うのは“在宅需要”
苦戦のコーヒー業界で黒字転換 「豆で勝負した」タリーズが狙うのは“在宅需要”
伊藤園の2021年5〜22年1月期の連結決算ではタリーズコーヒー事業の営業損益は8億2200万円の黒字へ転換し、苦戦が続く飲食業界のなかで光明を見いだしている。黒字転換の要因は何なのか。タリーズコーヒージャパンのマーケティング本部でグループ長に、国内のコーヒー市場の変化に対するタリーズコーヒーの戦略を聞いた。 緑茶リニューアル対決 シェアトップの伊藤園が、"定番"でも変化し続ける理由
緑茶リニューアル対決 シェアトップの伊藤園が、"定番"でも変化し続ける理由
お〜いお茶』に15年以上に携わってきた伊藤園マーケティング本部 緑茶飲料ブランドマネジャーの安田哲也氏に、緑茶界の”横綱”伊藤園『お〜いお茶』のマーケティング戦略と、22年の新たな挑戦を聞いた。 オリオンビール、発売1年未満で缶チューハイをリブランド リピート率が高かったのに、なぜ?
オリオンビール、発売1年未満で缶チューハイをリブランド リピート率が高かったのに、なぜ?
オリオンビールのnatura WATTAは、沖縄県産の果実で、かつ防腐剤およびワックス不使用のものだけを原材料として活用。消費者のウケは悪くなかったものの、ビジネス上の課題もあってなかなか売り上げ拡大につながらなかった。そうした反省を踏まえて、発売から1年もたたない今年7月に商品のリブランドに踏み切ったのである。その背景を取材した。 午後7時閉店でも店長年収1000万円超え! 愛知県「地元密着スーパー」絶好調の秘密
午後7時閉店でも店長年収1000万円超え! 愛知県「地元密着スーパー」絶好調の秘密
愛知県東三河地方だけに5店舗しか展開していない「絶好調」のスーパーがある。「社員第一主義」を掲げ午後7時には閉店しているのに、店長の年収は1000万円を超える。その秘密に迫った。 「ふらのワイン」の販売不振をどう解決する? 北大博士課程の学生が奮闘
「ふらのワイン」の販売不振をどう解決する? 北大博士課程の学生が奮闘
4年連続で赤字になる見通しで、なんとか売り上げを伸ばしていきたい「ふらのワイン」。販売不振に北大の博士課程の学生が奮闘した。彼らはリピーターの購入商品に着目し、ある提案をしたのだが……。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング