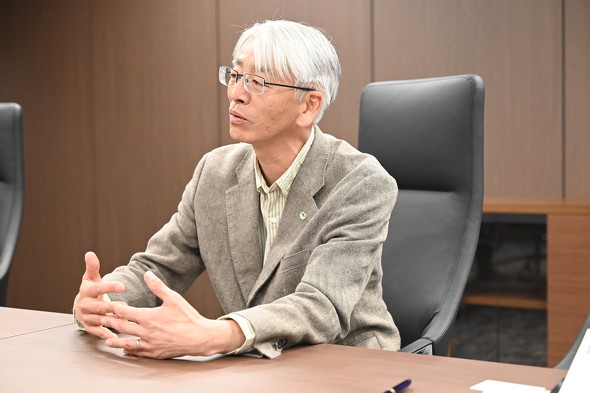日立のクラウド部門新トップは異組織出身 2万人を束ねるキーパーソンに展望を聞いた:進む組織再編
日立製作所のクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCEOに新しく就任したのが、社会ビジネスユニット出身の細矢良智氏だ。
日立製作所が組織再編を進めている。
2023年11月には米シリコンバレーに本社を置く、ストレージを中心としたデータインフラストラクチャやクラウド、IoTサービスを展開してきた「Hitachi Vantara」のデジタルソリューション事業を分社化し、新たに「Hitachi Digital Services」を設立した。ここには、急速に進化する生成AIの活用を通じた全社のデジタル変革を進める狙いがある。
この4月には経営陣が新しくなった。東原敏昭会長、小島啓二社長の体制は変わらない一方、副社長には阿部淳前専務が昇格。同じく副社長には、日立ヨーロッパ社取締役会長を務めたブリス・コッホ氏が就任した。専務には植田達郎氏と加藤知巳氏が常務から昇格した。
これに伴い、常務レベルでもさまざまな昇任や配置転換がなされている。4月の人事変更の筆頭に挙げられる阿部新副社長の後任として、新たにクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットCEOに就任したのが、社会ビジネスユニット出身の細矢良智氏だ。
クラウドサービスプラットフォームビジネスユニットは、30万人のグループ社員を抱える日立の中で2万人を擁する部門だ。クラウドサービスからミドルウェアやプラットフォームソフトウェア、ストレージソリューションなどの事業を展開していて、日立グループのDXや、日立が標榜(ひょうぼう)する「IT×OT(Operational Technology)」を推進する部門として名高い。
まさに日立の組織再編を担う部門ともいえる。そのトップとして新しくCEOに就任した細矢氏にインタビューした。
日立のDXを担うキーパーソン 経歴は?
細矢氏は1988年に日立に入社した。官公庁、自治体系のシステムを中心に、フロントのSEとして技術畑を歩んできた。業務の遂行やサービスに必要不可欠であり、障害や誤作動などが許されない「ミッションクリティカル」な公共分野の社会インフラを中心に担当。入社して10年ほどは自治体文書のデータベース構築など、情報検索を担当してきた。細矢氏は往時をこう振り返る。
「メインに担当していたのが特許庁で、主に特許の文献検索を整備していました。特許の審査は新規性があるかどうか、つまり過去と同じものがないかを調べることが中心になります。過去の事例全てを参照する必要がありますので、インターネット黎明期でもあった90年代は、その構築をしていました」
2000年以降も、特許周りのシステム構築を担当した。官公庁だけでなく、民間企業からの特許申請周りにも担当が拡大。民間企業側のシステムと、特許庁側のシステムをどう統合していくか、全体の特許管理システムの整備を進めていった。
「当時は、特許の審査官が申請に対してデータベースですぐに調べられたり、申請する企業側も同様に調べられたりするデータベースの構築が求められていました。各企業で作っていたデータベースを日立がクラウドサーバで統合するようなサービスを10年くらいまで担当していました」
10年代以降は、特許に限らず、郵政関係や放送関係をはじめ、公共系のシステムを担当してきた。
「基本的にはデータベースを作りながら、検索をより早く、容量の問題への対処や、通信速度の向上など、改善を続けてきました。90年代当時はインターネット上で検索できるデータベース自体が黎明期でもありましたので、クライアントと一緒にチャレンジングに作り上げていきました。ミッションクリティカルとはいえども、失敗が許されない今とは、やや時代背景が異なりますね」
一方で当時は通信環境も今と比べて格段に遅く、その通信速度を考慮に入れて、ユーザーが快適に操作できるかも考えなければいけなかった。
「例えば特許の場合ですと、審査官が膨大な類似特許件数のページを素早く切り替えながら、見ることのできる必要があります。これを200人以上いる審査官が同じ場所で同時にできるようにしなければなりませんでした。当時の通信速度は10Mbpsほどでしたので、1ページあたりの容量を30キロバイト以内に収めるなどの工夫が必要でした」
今ではデータの場所もクラウド上にあるのが当たり前になり、こうした時代の技術革新に合わせたサービスを開発していった。
21年からは、Chief Lumada Business Officer(CLBO)に就任する。これは日立が16年から進めている顧客データから新事業など価値を創出する「ルマーダ」を統括する役職で、日立社内の各部門に設置しているものだ。ルマーダは部門を超えて、顧客が抱える課題を解決できることを謳っていて、日立が進めるDX事業だ。言うなれば細矢氏は日立全体のDXを担う人材だといえる。
CLBOとしての役職はどういったものなのか。細矢氏が説明する。
「顧客の課題解決をどのように進めていけば良いのか、部門の垣根を越えて調整する役職になります。例えばマテリアルズ・インフォマティクス(情報科学を用いて材料開発を効率化する取り組み)の技術で言えば、どういった技術で、どんなふうにデータベースを作ったらいいのか、われわれが持っている技術と、顧客の知財とを組み合わせながら新たなものを作っていく、その橋渡しをする役割になります」
こうした課題解決は「日立の1カ所ではできない」と言い、細矢氏は社会ビジネスユニットを統括する立場として、他のビジネスユニットと調整しながら新事業を進めていった。
23年度からはクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットに移り、COOに就任。社会・公共系の顧客と接する立場から、提供価値の礎となる「プラットフォーム」そのものを開発・改善する立場へと転身しつつ、顧客のDXを支援してきた。
新体制によって日立はどう変わるのか? 細矢氏の決意
そんなバックグラウンドを持つ細矢氏がクラウドサービスプラットフォームビジネスユニットのCEOとなり、日立はどう変わるのか。
「23年度は組織体制を大きく変えたので、24年度はこれをきちんと実行して完遂していくのが、一つの大きな目標です。あとはどう顧客と一緒に課題解決をしていけるかですね。今までは社内のフロント担当しか接してこなかった顧客の課題解決に、横断的に取り組んでいきます。顧客の課題にどうリーチできるのかというところから進めていきたいですね。私たちには技術はありますが、それをどう役立てられるのか。そのビジネスの価値を理解しきれていない部分もありますので、そこから変えていきたいと思います」
日立の強みは、鉄道からエネルギー、そして産業機器から最先端のクラウドまで全て社内で技術開発できる点だ。ここまで幅広い技術を一社で持つ企業は世界でもあまり例がない。一方で幅広いがゆえに、各ビジネスユニットの独立性もあり、今までうまく連携を取れてこなかった面もある。
こうした反省から進めているDXがルマーダ事業と言える。さらに21年に日立傘下になった米シリコンバレーのデジタルソリューション企業・GlobalLogic社とも連携し、顧客課題の聞き取りから提案・改善までのサイクルを加速させている。
23年に大きく世の中を変えたものとして、生成AIの実用化が挙げられる。日立に限らず、さまざまなITベンダーが生成AIを生かしたソリューション開発を進めている。細矢氏も生成AIの活用に期待を寄せる。
「われわれがLLM(大規模言語モデル)を作るわけではないのですが、どのように社会に役立てていけるのか。顧客が持つ課題とノウハウと、われわれ日立が自前で持つ幅広いノウハウを守りつつ、組み合わせて提案していきたいと思います。いずれにしても生成AIの活用は、ビジネス向けのセキュアなものが必要で、複数のクラウドサービスを組み合わせたハイブリッドなものになると思われます。自分たちもトランスフォーメーションしつつ、顧客にも提案していく2本柱で考えています」
究極の“自前主義”を可能にしてきた企業がルマーダを通じ、どのようにグループ内外と連携して変わるのか。“唯一無二”の革新を遂げようとしている日立の今後に注目だ。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 “日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い
“日立流”生成AI時代の組織再編 「ルマーダ売上2.65兆円」につなげる狙い
日立製作所が組織再編を進めている。米シリコンバレーに本社を置く「Hitachi Vantara」のデジタルソリューション事業を分社化し、新たに「Hitachi Digital Services」を設立する。その狙いは? 日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立の責任者に聞く生成AIの“勢力予想図” 「来年、かなりの差がつく」
日立はどのように生成AIを利活用しようとしているのか。Generative AIセンターの吉田順センター長に話を聞いた。 日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?
日立社長「生成AIは歴史上のブレークスルー」 “電力需要6倍”にどう対処する?
日立製作所の小島啓二社長兼CEOは生成AIに対する日立の考え方を明示した。日立が生成AI開発にどのようなビジョンを抱いているのか。筆者がレポートする。 ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT創業者が慶大生に明かした「ブレイクスルーの起こし方」
ChatGPT開発企業の米OpenAIのCEOが来日し、慶應義塾大学の学生達と対話した。いま世界に革命をもたらしているアルトマンCEOであっても、かつては昼まで寝て、あとはビデオゲームにいそしむ生活をしていた時期もあったという。そこから得た気付きが、ビジネスをする上での原動力にもなっていることとは? 松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が明かす 日本企業が「ChatGPTでDX」すべき理由
松尾豊東大教授が「生成AIの現状と活用可能性」「国内外の動きと日本のAI戦略」について講演した。 和製ChatGPTで「戦いに参入すべき」 松尾豊東大教授が鳴らす“警鐘”とは?
和製ChatGPTで「戦いに参入すべき」 松尾豊東大教授が鳴らす“警鐘”とは?
経営者層がいま、最も注目しているビジネストピックが「ChatGPT」などの生成AIだろう。日本ディープラーニング協会理事長で、東大院の松尾豊教授の登壇内容をレポート。ChatGPTをはじめとする生成AIを組織内でどのように活用していくべきなのか。ビジネスで活用する上で、どんな点に注意すべきかをお伝えする。