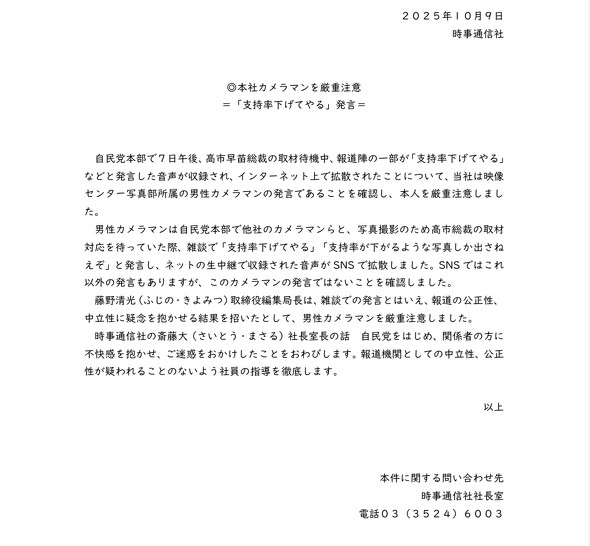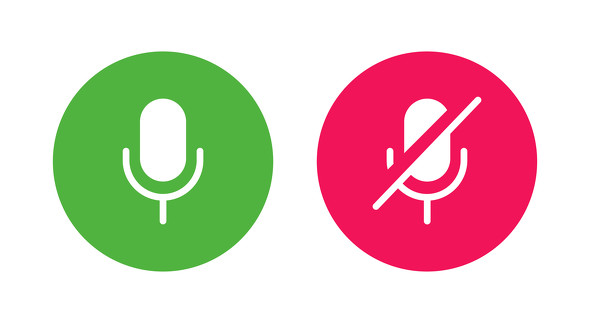時事通信社カメラマン「支持率下げてやる」騒動 社員の不適切発言を防ぐ方法は?
時事通信社の男性カメラマンによる「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねぇぞ」との音声が、生配信の映像に入ってしまった。社員の不適切発言を防ぐために経営層が取るべき方策とは?
気付かれずにオンになっているマイク、いわゆる「ホットマイク」(hot mic)。本来オフになっているはずのマイクが、オンのままになっている状態で不用意な発言が拾われてしまうことを指します。いまや会見、ウェビナー、ライブ配信、社内会議。“オフレコ”という言葉が存在しないほど、私たちの発言は簡単に可視化されます。
音声やカメラの切り忘れ、チャット誤送信など、「ちょっとした油断」が拡散する――。そして今回、そのリスクを象徴する事件が起きました。他社の事例も踏まえ、経営層がこうした不適切発言を防ぐ方策を考えます。
時事通信社「支持率下げてやる」 他社事例から考える「防ぎ方」とは?
10月7日。自民党総裁に就任した高市早苗氏の会見準備中、報道陣エリアで拾われた音声が全国を駆け巡りました。男性カメラマンが雑談中にこう言ったのです。「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねぇぞ」――。
その音声は、生配信の映像に偶然入っていました。数分後にはXで切り抜かれ、瞬く間に拡散。「報道機関が中立性を放棄した」「政治的偏向だ」と炎上。Yahoo!リアルタイム検索の上位には関連語が並び、ニュースサイトやテレビでも相次いで取り上げられました。
事実通信社の対応とその後
10月9日、時事通信社は公式サイトで事実を認めました。「雑談での発言とはいえ、公正性・中立性に疑念を抱かせる結果を招いた」として、発言者を厳重注意処分に。さらに、編集局長名で再発防止策の徹底と謝罪を発表しました。
対応自体は迅速でしたが、多くの人が感じたのは、「一社員の失言」以上のものでした。つまり「こうした発言が平気で出る業界の空気」への違和感でした。発言は個人の口から出ましたが、世間は企業の持つ価値観が露呈したことにより、メディア不信を増幅させました。
他社でも起きているホットマイクの“構造的事故”
実は、マイクの切り忘れによる“露出”は国も業界も問わず起きています。
ブループロトコル公式配信の炎上(2025年7月)
バンダイナムコのオンラインゲーム「BLUE PROTOCOL」(ブループロトコル)の中国版配信中、休憩に入ったスタッフがマイクを切り忘れました。 配信中のコメントに対して、出演者が「文句ばっかり言いやがって」などの暴言を吐き、そのまま全世界に配信されたのです。
SNS上では「運営がユーザーを侮辱している」と非難が殺到。動画が拡散され、ゲーム評価は暴落。
テンセント(運営側)とバンダイナムコは即日謝罪し、担当者が涙ながらに説明する映像を公開しました。しかし、ダメージは深刻でした。ユーザーからは「言葉に出たのは本音」「前からそう思ってたんだろう」といった声が多く、暴言そのものよりも、“普段の態度が出ただけ”と受け取られました。
結局、配信体制を全面見直し。マイクとカメラの二重チェック体制、休憩時のスタジオ退室ルール、社内ガイドラインの再整備が行われました。再開までに3週間を要し、コストは大幅に膨らんだといわれています。
ESPN「差別発言」ホットマイク事件(2021年・米国)
次にご紹介するのは、コロナ禍のリモート会議中に起きた事例です。
米スポーツメディアESPNの人気キャスター、Rachel Nichols氏が、同僚のMaria Taylor氏について「ダイバーシティ枠で選ばれた」と差別的に中傷する発言をしてしまいました。
本人はプライベートな雑談のつもりでしたが、会議ツールが録音状態のままだったため、発言が社内サーバに残り、後に外部へ流出。ニューヨーク・タイムズが報じると、社内の人種問題が一気に表面化しました。Nichols氏は番組降板、ESPNの多様性方針も再検討されます。これらのケースも共通しているのは、「社員個人の発言が組織文化の象徴として受け止められた」という点です。
では、企業はどう防げばいいのか?
こうした発言を「完全に」なくすことはできません。人は疲れ、ミスをし、油断します。しかし、“事故”を“組織の恥”にしない設計はできます。つまり、言葉のリスクを個人任せにしない文化づくりです。
組織が取り組むべき第一歩は、トップの明言です。
経営層が「舞台裏も含めて誇れる会社でありたい」と明示することで、現場の意識は変わります。配信チェック、社内ミーティング、雑談にいたるまで、「誰が聞いても恥ずかしくないか」を意識するようになります。
トップが動けば、ガイドライン策定、ミュート手順の標準化、インシデント報告の迅速化など――いずれもスピード感を持って制度化できます。しかし、現実はトップダウンで動ける企業ばかりではありません。
「うちの上は危機感が薄い」「炎上なんて他人事」――そんな悩みを抱える読者も少なくないのではないでしょうか。ここからは、ボトムアップからのアプローチを共有したいと思います。
まずは事例を共有することです。ニュースをプリントして、「これが他社で起きたんです」と定期的に伝える。“他山の石”として見せることで、危機の想像力を刺激できます。
次に、自部署だけでも試すこと。例えば定例会の冒頭に「マイク・カメラ確認」「一言チェック」を入れるだけでも違います。そして、提案の言葉を変えてみる。「リスク対策」ではなく「時間とお金の節約になります」と伝える。謝罪や火消しにかかるコストを数値化して示すと、経営層は動いてくれるかもしれません。
マイクが拾うのは、言葉ではなく“組織の無意識”
今回話題になった時事通信社の件も、ブループロトコルも、ESPNも。そこに共通していたのは「発言そのもの」ではなく、発言が出るまでの“空気”でした。無意識に生まれた上下関係、軽口、慣れ合い、慢心。それを“緩み”と呼ぶなら、緩みそのものが悪いわけではありません。問題は、それが可視化されていないことだと考えます。
ホットマイクとは、単なる配信事故ではなく、組織の無意識を映す鏡です。発言を管理するのではなく、空気を整える。技術ではなく文化で防ぐ。その視点さえあれば、「うっかり炎上」は学びの機会に変わります。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 サントリー新浪前会長は、なぜ「無罪推定」の段階で辞任したのか?
サントリー新浪前会長は、なぜ「無罪推定」の段階で辞任したのか?
サントリーの新浪剛史前会長が突然の辞任を発表した。捜査はまだ進行中。起訴も判決も下っていない。刑事法の原則でいえば「無罪推定」の段階だ。それでもなぜ、経営トップは早々に職を退いたのか? 日テレの「何も話さない」会見は必要だった? 国分太一氏降板に見る企業のリスク判断軸
日テレの「何も話さない」会見は必要だった? 国分太一氏降板に見る企業のリスク判断軸
6月20日に日本テレビが開いた記者会見。こうした会見の在り方が企業にとってどのような意味を持つのか、記者会見の設計において“語らない”という選択がどう受け止められ、実務にどう生かせるかを、危機管理広報の視点から掘り下げる。 フジテレビの「3つの判断ミス」 信頼回復への新セオリー
フジテレビの「3つの判断ミス」 信頼回復への新セオリー
フジテレビ問題は、社会に深く根付いた「人権リスク」の存在を、図らずも白日の下にさらけ出した。危機管理の観点から一連の出来事と対応を検証する。 フジテレビの「ガバナンス不全」 日枝久氏の「影響力」の本質とは?
フジテレビの「ガバナンス不全」 日枝久氏の「影響力」の本質とは?
フジテレビ問題の今後の焦点は日枝久氏の去就だ。フジテレビのガバナンスに焦点を当てて検討してみたい。 フジ新社長はアニメ畑出身 「異色だが期待大」な、決定的な理由
フジ新社長はアニメ畑出身 「異色だが期待大」な、決定的な理由
フジテレビジョンの清水賢治新社長は『ドラゴンボール』『ちびまる子ちゃん』『ONE PIECE』など国民的なメガヒットアニメを企画・プロデュースしてきた。これまでフジテレビの社長とどう違うのか? アニメ業界のビジネスモデルからひも解いてみたい。 フジテレビの余波で放送局の“ガバナンス”は強化されるか?
フジテレビの余波で放送局の“ガバナンス”は強化されるか?
フジテレビの問題が同社の経営にどこまで影響を与えるのか。今後はどうなるのか。現状では見通せない。スポンサー企業だけでなく、株主や視聴者といったステークホルダーが同社のコーポレートガバナンスに疑義を抱いていることが根本的な問題だ。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。 フジテレビの女子アナ“ステマ”疑惑が突き付ける「※ツイートは個人の見解です。」のウソ
フジテレビの女子アナ“ステマ”疑惑が突き付ける「※ツイートは個人の見解です。」のウソ
『週刊文春』4月22日号で発覚した、8人のフジテレビ女性アナウンサーの“ステマ”疑惑。そもそも何が問題だったのか。そして、フジテレビ以外の企業にもそのような問題が発生する芽はないのか、考えてみたい。 「ちょっと怖い選挙シーズン」──企業SNSが踏む地雷とは?
「ちょっと怖い選挙シーズン」──企業SNSが踏む地雷とは?
実は選挙の時期、企業にとっては“少し怖い時期”だ。過去の事例をもとに、企業の発信に潜むリスクと備えを整理してみたい。