「Web3で日本経済を成長させる」 AWAJ設立の目的と新たな取り組み2つを紹介
生成AIに注目が集まる中で、Web3もユースケース創出に向けて進展しているようだ。本稿は新たに設立されたAWAJが何を目指しているのか。今後どのような取り組みを進めていくのか紹介する。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
Asia Web3 Alliance 日本(以下、AWAJ)は2023年12月9日、同アライアンスの発足の目的と今後の取り組みに関する説明会を実施した。AWAJはWeb3に関する新たな協会で、2023年11月1日に設立された。
同説明会にはAWAJの代表取締役社長を務めるアセフ・ヒンザ氏(NFTStudio24 - ICP BLOCKCHAIN 共同創業者)に加え、理事会メンバーの中西威人氏(CROSS Value Chain 共同創業者)、谷本祐真氏(CROSS Value Chain 共同創業者)も登壇した。
日本と世界のWeb3エコシステムの差は歴然 改善には海外との協力が一番?
ヒンザ氏は説明会の冒頭で「AWAJは日本におけるWeb3と海外の機会損失を解消し、日本企業のグローバル展開を支援しながら日本経済を活性化することを目的に設立されました。海外の多くの政府機関や外交官、民間企業などは、日本におけるWeb3市場の参入障壁が高いと感じています。彼らはシンガポールや香港のように、Web3プロジェクトから利益を得られる機会を求めているのです」と、自身の経験に基づいて話した。
同氏によれば、日本はWeb3で世界をけん引できる可能性を持つ一方で「国際市場を巻き込む」ということが苦手だという。ヒンザ氏はこれを「グレーゾーン」と呼び、AWAJはこのグレーゾーンを海外と協力しながら解消するという。
「AWAJの使命は、日本のWeb3産業をグローバルに推進し、海外の投資家や企業に日本でのビジネス誘致を呼び掛けることです」(ヒンザ氏)
このような取り組みを推進するために、AWAJはWeb3に関する政策立案者や学者、専門家などと連携することを目指しており、そのために「コラボレーション」「倫理的革新」「包括性」という目標を掲げている。
AWAJの理事会メンバーは56人(本稿執筆時点)で構成されており、40人が外国人メンバー、16人が日本人メンバーだ。AWAJには他にも、日本投資家小委員会やグローバル投資家小委員会などをはじめとする16以上の小委員会が含まれており、ヒンザ氏は「理事会メンバーはAWAJと協力しながら、Web3技術の発展や日本経済の価値向上を目指します」と語った。
AWAJが進める新たな取り組み ステーブルコインのユースケース創出と人材育成
続いて登壇した中西氏はAWAJ参画の理由として「Web3ビジネス拡大に伴い海外を回る中で、日本人の存在感のなさを実感していました。そのような背景から、AWAJの理念に興味をそそられました」と語る。
同氏は理事会メンバーとして「公的機関や民間企業をもっと巻き込む」ということを掲げており、そのために金融庁や日本ブロックチェーン協会、全国銀行協会、各都道府県などと連携拡大を図っているという。
「AWAJは世界中のWeb3コミュニティーを結び付けようとしています。そのためには国際市場はもちろんさまざまな組織とネットワークを構築し、それを拡大していく必要があります。日本政府やWeb3に関して、これまでも開発者やクリエイターを支援してきましたが、海外からの投資や会社設立にも取り組まないと日本が“Web大国”になることはありません」(中西氏)
中西氏に続いて登壇した谷本氏は、AWAJについて「まずは日本企業や国内の開発者に外資の重要性を理解してもらえるように尽力するつもりです。グローバルなWeb3企業が歓迎されるようになれば、サービスの開発や改善、導入がより迅速に行われる可能性が高まるからです」と話す。同氏はアラブ・アフリカ地域を中心にブロックチェーンプロジェクトを拡大しており、AWAJではステーブルコインのユースケース創出に積極的に取り組んでいく。
説明会ではAWAJの設立目的の開設に加え、ステーブルコイン小委員会の発足と学生交流プログラムの構想が発表された。
ステーブルコイン小委員会の発足に関して、ヒンザ氏は「DeFi(分散型金融)やステーブルコインによって、企業や個人の国境を越えた取引コストの削減が可能になります」と話し、今後はユースケースの創出に取り組んでいくという。
学生交流プログラムは日本の学生を対象として2024年から始まる。ヒンザ氏によれば、各都道府県の48の大学から学生が参加する予定だ。詳しい詳細に関しては執筆時点でまだ発表されていないが、ヒンザ氏は「同プログラムに参加する学生にWeb3の世界を探求する機会を提供します」としている。
ヒンザ氏は最後に「日本政府もWeb3の普及に取り組んでいます。AWAJはその取り組みの輪を拡大し、実用化することを目指します」と話し、講演を終えた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
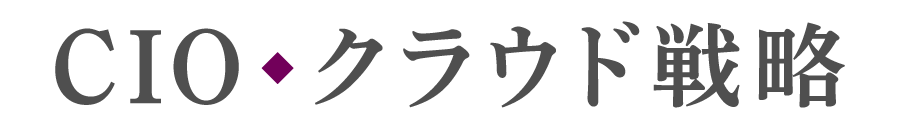
 アセフ・ヒンザ氏
アセフ・ヒンザ氏 中西威人氏
中西威人氏 谷本祐真氏
谷本祐真氏
