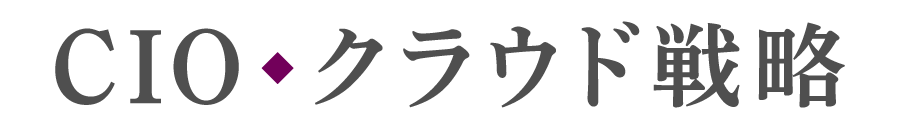職場の隠れた病? 「強さを競う文化」が与える弊害
リクルートマネジメントソリューションズの調査により、職場に根付く「強さを競う文化」がストレスや不公平感を生み、多様性の低下にもつながる実態が浮き彫りになった。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
リクルートマネジメントソリューションズは2025年5月19日、職場における「強さを競う文化」に関する調査結果を発表した。
従業員の働き方や意識が多様化する中で、企業の中に根強く残る「弱みを見せない」「仕事を最優先する」といった価値観が職場にどのような影響を与えているのかを明らかにした。
職場における「強さを競う文化」の実態
調査は従業員規模50人以上の企業に所属する20〜59歳までの正社員に実施された。主な結果は次の通りだ。
- 職場における「強さを競う文化」について、「困難があっても平然とすべき」との項目に対し、全体の約7割が肯定的に回答。「弱みを見せないこと」「力強さ・スタミナがあること」についても、それぞれ過半数が肯定的に回答した
- 回答者の71.3%が、「強さを競う文化」が従業員のストレスや精神的負担を増大させると考えている
- 「強さを競う文化」の4要素のうち、最も過剰と感じられているのは「仕事を最優先すること」(22.1%)
- この文化は、成長やモチベーション、パフォーマンスの向上といった肯定的な影響がある一方で、疲弊、公平性の低下、パフォーマンスの低下、多様性の低下といった否定的な影響もあるとされている
- 「総合職、地域総合職、一般職などの区分がある」企業に勤める人は、「強さを競う文化」の程度や過剰感についての平均値が高い傾向にある
- 一般社員と比較して、管理職は「強さを競う文化」に対して自身の過剰感や周囲の過剰感の認識が高い。さらに職種区分がある企業では、昇進意欲の高い層は昇進意欲の低い層よりも過剰感や周囲の過剰感の認識が統計的に有意に高い傾向がみられた
調査では組織心理学者のBerdahl氏らの提唱するMasculinity Contest Culture(MCC)の概念を基に、日本の職場環境に即した独自の設問を設定。「強さを競う文化」の4つの特徴《1》弱みを見せない、《2》力強さ・スタミナを持つ、《3》仕事を最優先、《4》競争に勝つ)がどの程度見られるかを検証した。
多くの肯定的回答を得たのは「プライベートで困難があっても職場では平然としていなければならない」で、67.4%が当てはまると回答した。「弱みを見せない」「力強さやスタミナがある」といった特徴についても過半数が肯定的だった一方で、「仕事を最優先する」「競争に勝つことが望ましいとされる」は肯定率が50%を下回った。
また、「強さを競う文化」が職場に悪影響を与えていると感じている人が71.3%を占めた。特に仕事を最優先することは過剰だと感じる人が多い。プライベートな時間も仕事のための自己研鑚に費やすべきだという風潮があるなどの事象が生じていると指摘された。
一方で「強さを競う文化」が成長意欲やパフォーマンスの向上に寄与しているという意見も存在する。しかし、「疲弊感(がある)」「公平性の低下」「パフォーマンスの低下」「多様性の低下」など悪い影響を職場に与えるとする自由記述も確認された。
さらに総合職、地域総合職、一般職など職種区分のある企業では、「総合職なのだから高い成果を出して当然」といった期待や同調圧力が「強さを競う文化」の認識を強めている傾向があるという。
管理職層では部下への配慮や成果責任の重圧などから、「強さを競う文化」に対する過剰感が高く、加えて周囲の過剰感にも敏感であることが示されている。昇進意欲の高い一般社員でも、同様に「強さを競う文化」に対して高い過剰感を持っている。昇進を目指す過程で、自身の意志に関係なく強さを示すことが求められる場面が多い可能性がある。
本調査により、「強さを競う文化」は職場で一定程度見られ、ポジティブな側面とともにストレスや不公平感といった課題を感じる人も多いことが明らかになった。職場の包摂性やマネジメントの在り方を再考するうえで、本調査は重要な示唆を提供している。
関連記事
 2028年、単純作業者の9割がAIに代替? 「AI時代に職を守る」戦略とは
2028年、単純作業者の9割がAIに代替? 「AI時代に職を守る」戦略とは
Gartnerは、AIやヒューマノイドの台頭によって、作業中心の職務に従事する人の90%が2028年までに業務を奪われるリスクがあると予測する。この転換期に、従業員はどう職を守り、企業はどう従業員と共に成長すべきか。 Microsoft、Googleが作ったAIエージェント間通信プロトコル「A2A」に対応する方針を示す
Microsoft、Googleが作ったAIエージェント間通信プロトコル「A2A」に対応する方針を示す
Microsoftは、AIエージェント同士の連携を実現するオープンプロトコル「A2A」の導入計画を発表した。Azure AI FoundryやMicrosoft Copilot Studioへの実装を通じ、企業は異なる環境間でも安全にマルチエージェント連携を構築できるようになる。 「97%が重要と答えたのに」 日本企業の"脆弱性対応"が進まない本当の理由
「97%が重要と答えたのに」 日本企業の"脆弱性対応"が進まない本当の理由
自社が利用している機器やOS、アプリケーションに脆弱性が発見された場合、うまく対応できているだろうか。脆弱性対応に関する調査報告を紹介する。 オンプレミスで「非仮想化」を選択する中小企業が6割にのぼる理由
オンプレミスで「非仮想化」を選択する中小企業が6割にのぼる理由
中小企業の約75%がオンプレミスを採用しており、そのうち非仮想化の物理サーバが全体の6割を占める。その理由は。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
- SMBC日興証券が「パスキー」で口座乗っ取り対策 約5カ月で実現したのはなぜ?
- 生成AIの記憶機能を悪用して特定企業を優遇 50件超の事例を確認
- 日本IBMのAI戦略“3つの柱” 「制御できるAI」でレガシー資産をモダナイズ
- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路
- 人材水準を4段階で評価 「サイバー人材フレームワーク」案の意見公募を開始
- 富士通、ソブリンAIサーバを国内製造開始 自社開発プロセッサー搭載版も
- 「身近な上司」を再現する専用ディープフェイク動画を作成 KnowBe4が新トレーニング
- 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新
- 「AI前提」の国家戦略と「思考停止」の現場 大半の企業で“何も起きない”未来を予見