仮想化で、強く問われる「ITで何をするか」:仮想化インタビュー(4)(1/3 ページ)
コスト削減や既存資産の保守を目的に、着実に利用が進みつつある仮想化技術。しかし真のメリットは、ITの可用性を飛躍的に高められる点にある。IDCジャパンの入谷氏は「競争力向上のために、仮想化技術をどう活用していくかが問題」といい切る。
ITインフラの物理的制約を解消
IDCジャパンの調べによると、仮想マシンソフトウェア市場は2006年から2011年にかけて、年間平均成長率(CAGR)39.8%で成長し、2011年には311億8100万円に達すると見込まれている。同社が2331社を対象に行ったアンケート調査「2007年度?2008年度の予算で導入を検討するソリューション」でも、「SaaS」や「グリーンIT」ではなく、「サーバ仮想化」と答えた企業が最も多かったという。
事実、安価なx86サーバが登場して以降、サーバ台数の増加に伴い、運用管理費も年々上昇し続けている。ハードウェアの数を大幅に削減できるサーバ仮想化に多くの企業が関心を示したのも当然だろう。IDCジャパン ソフトウェアリサーチアナリストの入谷光浩氏は、「特に米ヴイエムウェアがハイパーバイザ型の仮想化ソフトウェアを開発したことが、サーバ仮想化を加速させる大きなターニングポイントとなった」と語る。
「そもそも仮想化は、メインフレームで使われてきた技術。それが米ヴイエムウェアのホストOS型仮想化ソフトウェアによって、x86サーバでも利用可能となり、さらにハイパーバイザ型の仮想化ソフトウェアによって、複数のゲストOSをより手軽に1台のサーバに集約できるようになった。常にトータルコスト削減を求められる企業にとって、まさしく渡りに船だったということだろう」(入谷氏)
一方、サーバ仮想化には既存資産の保守というメリットもある。Windows NTやWindows 2000といったサポート期間が終了している古いOSが、いまも多くの企業で使われている。
その上では日々の業務を支えるアプリケーションが稼働している。特に製造業では自社独自の業務プロセスを反映した“競争力の源泉”ともいえる自社開発アプリケーションを使っている例も珍しくない。
それが万一、物理サーバやOSの不具合で使えなくなれば、業務がストップして大きな損失を招く。かといって、最新のOSにアップグレードしようとすれば、OSに合わせてアプリケーションも調整しなければならない。この点で、リスクを自覚しながらも手をこまねいているケースが多かった。
「しかし、ハイパーバイザ型の仮想化ソフトウェアを使えば、物理サーバとOSを切り離すことができる。既存システムの延命措置についても、新しい物理サーバにハイパーバイザを載せ、その上でWindows NT、Windows2000を動かす仕組みとすれば、アプリケーションを調整する手間もかからない。しかもVMware ESXiなど無償提供されるハイパーバイザも登場しており、OSのアップグレードにかかるコストを、従来より大幅に抑えることができる」(入谷氏)。
ソフトウェア開発・テストの効率化にも貢献する。従来は開発用のサーバを用意し、テストを行ってから本番サーバに移行していたが、これを仮想サーバ上で行えば、専用のサーバを用意する必要がないうえ、デスクトップ上のファイル移動と同じ感覚で本番環境に適用できる。パッチ当ての検証についても、本番サーバと同じ仮想サーバを立てれば、より手軽・確実に行える。
「従来、OSはハードウェアと密接につながっていたが、ハイパーバイザによって両者が切り離されたことで、あらゆる物理的制約が解消された。これによって、ハードウェアの削減、省電力・省スペースをはじめ、あらゆるメリットを享受できるようになった。サーバ仮想化の波は、今後もいっそう進展していくことだろう」(入谷氏)
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 知らない番号でも一瞬で正体判明? 警察庁推奨アプリの実力を検証
- ZIPファイルの“ちょっとした細工”で検知停止 EDRも見逃す可能性
- M365版「Cowork」登場 Anthropicとの連携が生んだ「新しい仕事の進め方」
- 生成AIで消えるのは仕事、それとも新人枠? 800職種のデータから分かったこと
- 偽のTeamsサポートで新型バックドアを設置 巧妙な手口に要注意
- AD DSにSYSTEM権限取得の脆弱性 Microsoftが修正プログラムを配布
- もはやAIは内部脅威? 企業の73%が「最大リスク」と回答
- 政府職員向けAI基盤「源内」、18万人対象の実証開始 選定された国産LLMは?
- 本職プログラマーから見た素人のバイブコーディングのリアル AIビジネス活用の現在地
- .NETにサービス停止の脆弱性 広範なアプリケーションに影響
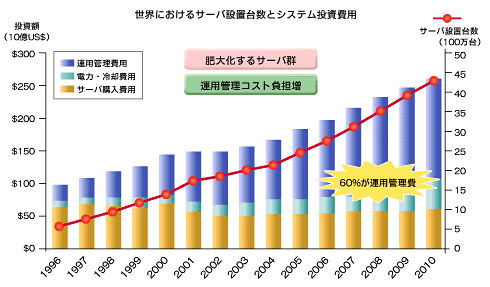 図1 サーバ台数と運用管理費の増加は世界的な傾向となっている(IDC調べ)
図1 サーバ台数と運用管理費の増加は世界的な傾向となっている(IDC調べ) IDCジャパン ソフトウェアリサーチアナリストの入谷光浩氏
IDCジャパン ソフトウェアリサーチアナリストの入谷光浩氏