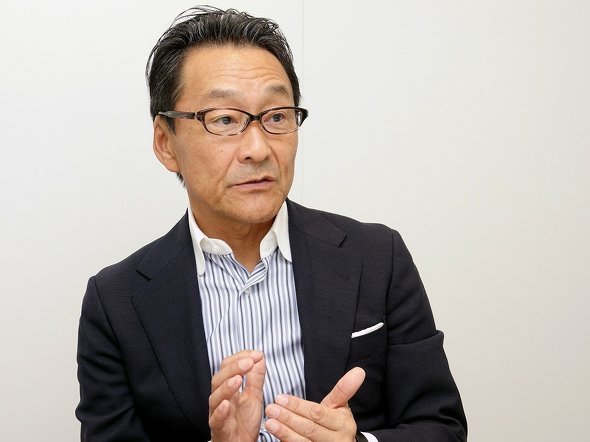人気なのに「Xperia」のシェアが急落した背景 それでもソニーがスマホをやめないのはなぜ?(1/3 ページ)
ソニーの「Xperia」は、日本ではよく知られたスマートフォンのブランド。新しいモデルが出るたびに注目されている。だが、シェアが落ち込んでいるのはなぜだろうか。
ソニーの「Xperia」は、日本ではよく知られたスマートフォンブランドで、新しいモデルが出るたびに注目される。
ITmedia Mobileが2024年4月に実施した読者アンケートでは、2024年4月〜5月に発表されたハイエンドスマートフォンの中で、Xperia 1 VIを選ぶと回答した人が最多だった。それ以前のモデルも、記事の反響を見る限り、端末としての人気は高いと感じることが多い。
しかし実際には、Xperiaの販売数は日本国内でも海外でも落ち込んでおり、スマートフォン市場でのシェア(出荷台数の割合)は大きく下がっている。市場調査会社のデータでも、Xperiaは上位5社から姿を消してしまっているのが現状だ(後述)。
なぜ、注目されているにもかかわらず、販売が落ちているのか。ここではその理由を、Xperiaの歴史を振り返りながら見ていく。
ソニー・エリクソンから生まれたXperia
Xperiaはもともと「ソニー・エリクソン」という、ソニーとスウェーデンのエリクソンが2001年に設立した合弁会社から2008年に誕生した。同年10月に発売の「Xperia X1」は、欧米諸国向けのモデルで、スライド式のキーボードとWindows Mobile 6.1を搭載していた。
2009年には、OSにAndroidを採用した「Xperia X10」を投入し、2010年には日本向けモデルとして「Xperia SO-01B」がNTTドコモから発売された。当時はスマートフォン黎明(れいめい)期で、XperiaはSO-01Bがヒットし、その後、ブランドが徐々に定着していった。
その後、2012年に合弁が解消されたことに伴い、ソニーモバイルコミュニケーションズが発足。Xperiaは高級モデル「Zシリーズ」などが人気を集め、特に2013年には、ドコモがGalaxyと並んで「ツートップ」と銘打ち、Xperiaを優遇した形での販売を行ったことで、Xperiaの人気はますます高まった。

2013年、ドコモが「ツートップ」戦略と銘打ち、当時人気のあるモデルだった「Xperia A SO-04E」「GALAXY S4 SC-04E」を優遇した形で値引き販売していた。Web広告やテレビCMには、他社製品は一切登場しない
悪化するソニーモバイルの経営 スマホ事業は縮小へ
しかし、2014年に事態が一変する。ソニーモバイルが大赤字になり、ソニー本体の経営にも影響が出るほどだった。
この時期、世界ではHuaweiやOPPOといった中国メーカーが、安価でコストパフォーマンスを武器にしたスマートフォンを市場に投入し、価格競争が激しくなっていた。こうした中、Microsoftがスマートフォン事業から撤退。HTCはVRにシフトしていき、LG Electronicsは赤字が続き、2021年にスマートフォン事業から撤退している。
一方でソニーは、赤字でもスマートフォン事業を継続したものの、利益を生むためにスマートフォン事業を大きく縮小した。その決断を下したのが、ソニーモバイルの十時裕樹社長(当時)だった。高価格のモデルに絞り、販売する国や地域も減らし、主に日本市場に集中した結果、世界での存在感はほとんどなくなった。日本でも、シャープのAQUOSなどに抜かれてシェアが落ちていった。
2018年には、岸田光哉氏(現:ニデック社長)がソニーモバイルの社長に就任し、製品ラインアップを刷新。クリエイターやゲーマー向けに特化した「Xperia 1」シリーズと「好きを極める」という新たなコンセプトを打ち出し、特にクリエイターから高い評価を得るようになる。
しかし、2017〜2019年度のモバイル・コミュニケーション(スマートフォンと固定通信)事業は、減収減益に加えて赤字に見舞われ、グループ全体でも足を引っ張る格好となっていた。一方、2020年度は減収だったが、オペレーション費用を削減することで、エレクトロニクス・プロダクツ&ソリューションは519億円の大幅増益となり、モバイル・コミュニケーションも赤字を脱却して277億円の営業利益を上げた。
2019年には、ミッドレンジモデルのてこ入れを行った。国内で投入した「Xperia Ace」と「Xperia 8」を皮切りに、2020年には「Xperia 10 II」「Xperia 8 Lite」を、2021年には「Xperia 10 III」「Xperia 10 III Lite」「Xperia Ace II」を投入した。
Xperia 1シリーズやミッドレンジが好調でシェア上位に復活
こうしたてこ入れが功を奏して、MM総研が2021年11月11日に発表した調査では、2021年度上期における国内スマートフォンの出荷台数シェアでソニーがAppleに次ぐ2位に躍り出た。ソニーのスマホシェアは10.7%で出荷台数は157.1万台となり、前年同期比で51.8%もの増加となった。Androidスマートフォンに限っていえばシェア1位となる。
苦戦していたスマートフォン事業が好転した理由について、ソニーは「Xperia 10 IIIやXperia Ace IIといったミッドレンジ、エントリーモデルの販売が非常に好調で、フィーチャーフォンや他社からの買い替えでもお選びいただけたことが大きな要因」としている。
当初からハイエンドモデル中心のXperia。ミッドレンジモデルにも力を入れるようになったことで、落ち込みから好転したわけだが、2021年にはソニーモバイルが再編でソニー本体に吸収され、スマートフォン部門はソニーの一部門になった。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応
「Xperia 1 VII」発表 目玉は被写体を逃さない動画撮影機能、ウォークマンのDNAで高音質化 Geminiや編集マジックにも対応
ソニーは5月13日、スマートフォンXperiaのハイエンドモデル「Xperia 1 VII(マーク7)」を発表した。発売時期はキャリアモデルとソニー直販モデルともに6月上旬以降を予定する。ソニーは動画撮影を強化するなど、体験重視のアップデートを図っている。 Xperiaが国内Androidシェア1位に躍進した理由 「ミッドレンジが好調」だけにあらず
Xperiaが国内Androidシェア1位に躍進した理由 「ミッドレンジが好調」だけにあらず
2021年度上期の国内スマートフォンシェアでソニーが2位に上昇した。「Xperia 10 III」「Xperia Ace II」といったミッドレンジモデルの販売が非常に好調であることが大きな要因だという。赤字続きだったモバイル・コミュニケーション事業も2020年度は黒字に転換している。 データで振り返る“スマホシェア”の5年間、Google躍進で国内メーカーに衝撃
データで振り返る“スマホシェア”の5年間、Google躍進で国内メーカーに衝撃
スマートフォンの出荷台数データを参照しながら、5年間を振り返る。Apple一強はますます強まる中、2023年にはPixelの躍進という大きな変化が生じた。 「Xperia 1 VI」が大きな変貌を遂げたワケ 実機に触れて感じた「進化」と「足りないところ」
「Xperia 1 VI」が大きな変貌を遂げたワケ 実機に触れて感じた「進化」と「足りないところ」
ソニーは5月17日、スマートフォンのハイエンドモデル「Xperia 1 VI(マーク6)」と、ミッドレンジモデル「Xperia 10 VI(マーク6)」の実機を報道関係者に披露。カメラ、ディスプレイ、オーディオのデモンストレーションを行った。Xperia 1 VIの光学7倍ズームや、ディスプレイのアスペクト比など、実機に触れて分かったことをまとめる。 ソニーモバイルが“SIMフリーのXperia”を本格投入する狙いは? カギはミッドレンジにあり
ソニーモバイルが“SIMフリーのXperia”を本格投入する狙いは? カギはミッドレンジにあり
ソニーモバイルが、SIMロックフリースマートフォンのラインアップを大幅に拡充する。発売されるのは、「Xperia 1」「Xperia 5」「Xperia 1 II」の3機種。Xperiaにとって大きな転換点になる可能性もある。そのインパクトを読み解いていきたい。