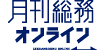【番外編】「新型インフルエンザ」今できる対策は?:医者要らずでできるインフルエンザ対策
潜伏期間も死亡率も分からない、未知数だらけのH5N1型ウイルス。新型インフルエンザに対して、今個人ができる対策は?
インフルエンザ対策を紹介する師走のインフルエンザ対策特集。「新型インフルザ」って何?に引き続き、国立感染症研究所ウイルス第三部部長の田代眞人(たしろ・まさと)さんに聞いた。
新型インフルエンザが落とす、健康被害と社会生活の影
H5N1型ウイルスによる新型インフルエンザに感染すると、具体的にどんな症状になるのだろう。
| 項目 | 通常のインフルエンザ | 新型インフルエンザ |
|---|---|---|
| 発病 | 急激 | 急激 |
| 症状(典型例) | 38℃以上の発熱 ・咳、くしゃみ等の呼吸気症状 ・頭痛、関節痛、前身倦怠感など |
未確定(発生後に確定) |
| 潜伏期間 | 2〜5日 | 未確定(発生後に確定) |
| ヒト―ヒト感染性 | あり(風邪より強い) | 強い |
| 発生状況 | 流行性 | 大流行(パンデミック) |
| 死亡率 | 0.1%以下 | 未確定(発生後に確定) ※アジア・インフルエンザ 0.5% スペイン・インフルエンザ 2% |
「名前は“インフルエンザ”ですが、今までとはまったく別物と思ってもらっていいでしょう」と田代さん。通常のインフルエンザは、鼻やのどなど局所的に感染する。しかしH5N1型は、ウイルスが肺の奥深くに入り、肺を侵す。さらに血液に入り込み、全身に広がっていく。こうして脳炎を起こしたり、心臓や肝臓、腸など、あらゆるところに病気をもたらす。
またインフルエンザには、発熱や倦怠(けんたい)感、節々の痛みといった症状がよく知られている。これはインターフェロンに代表される、細胞が生み出すたんぱく質サイトカインが、防御反応をしている表れだ。
一方、H5N1型インフルエンザの場合は、サイトカインが過剰になる“サイトカインストーム”になる。本来はウイルスから体を守るものが、反応が強過ぎるためにかえって体を痛めつけてしまうというのだ。そのため、免疫活性が低い年配者より、活性が高い若い年齢層の方が痛手が大きくなる。
「H5N1型ウイルスに感染すると、ほとんどの場合、サイトカインストームが起き、臓器や血管にダメージを与えてしまいます。その結果、多臓器不全になってしまうのです。これは従来のインフルエンザでは、考えられないことです」
最後は肺機能が低下。酸素のガス交換ができなくなり、死に至るケースが予測されている。
スペイン・インフルエンザやSARSより大被害に
過去にもウイルスが世界的に大流行したことがある。
その代表が、1918年のスペイン・インフルエンザ(風邪)だろう。弱毒性の鳥ウイルスに由来しているが、ヒトに感染するものの中では非常に強力だった。発生地については諸説あるが、アメリカのカンザス州というのが有力だ。ここから7〜8か月で世界を駆け回った。当時の世界人口は約18億人。そのうち感染者が6億人、死者は5000万人とも1億人ともいわれている。日本でも本土の人口5500万人のうち、45万〜48万人が犠牲になった。
現在、世界の総人口は約67億人。スペイン・インフルエンザが流行した頃に比べ、交通機関の発達が目覚ましく、人間の移動範囲も広いことから、H5N1型のインフルエンザが流行すれば、拡大のスピードは飛躍的だろう。
また、2003年に中国広東省を起点に大流行したSARSの場合、感染者と同じホテルに泊まった人たちが2次感染した。この人たちがさらに旅行で飛行機に乗り、ウイルスを遠くまで運んでしまった。その結果、約1週間で世界中に蔓延(まんえん)。新型インフルエンザについても、同様のことが心配される。
「実は、SARSと比較して、インフルエンザが広がる可能性は格段に高いと考えられています」と田代さん。これはSARSの潜伏期間が1週間くらいあるため。その間は、ほかの人に感染させないので、発熱した段階で隔離すれば、感染拡大を防ぐことができる。そして患者が行った場所、接触した人間を調べれば、その人たちも発症する前に隔離でき、2次感染を防止できるはずだ。にもかかわらず、ウイルスは拡散してしまった。
これに対して、インフルエンザは発熱の1日前からウイルスを排出する。熱が出てから隔離しても、間に合わないのだ。患者は自覚症状がないので、乗物を利用したり、人の集まる場所へ行くだろう。そうなればSARS以上のスピードで世界に広がる可能性は高い。専門家の試算によると、新型インフルエンザが大流行すれば、世界で死者は1億5000万人、日本でも200万人に上るだろうと見られている。
「同時に大量の重症患者が出ると、病院のベッドも人手も不足して、治療が十分にできません。医療従事者が感染する危険性も高い。医療サービスをどう確保するかは、重要で深刻な問題です」と田代さんは話す。さらに、大勢の人が無差別にウイルスに侵されれば、それぞれが担っている社会的な責任や仕事が停滞し、社会生活に大きな弊害が出ることも指摘する。
パンデミックに備えて個人ができることは?
いつ発生しても不思議ではない新型インフルエンザに備え、私たちは何ができるだろう。睡眠や栄養バランスに気を配り、体調を整えておくこと。そしてうがいや手洗いといった、基本的なことを守ることも重要だ。マスクは、機能性の高いもの(N95※)を選ぶようにしたい。
いざというときのために、食品や日用品を備蓄しておくのもおすすめだ。2週間分以上は確保しておくと安心だろう。ウイルスがヒトからヒトへと感染するので、外出しないのがもっとも効果的な防御策になるため、そのときに備えてだ。ショッピングストアや医療施設など、人の集まる場所は感染する危険が高くなる。
また日ごろから、関連機関のWebサイトなどを見て、正しい知識と情報を収集するのも大切なことだ。
田代眞人さんプロフィール
医学博士。20年以上前から鳥インフルエンザの研究に携わるエキスパートで、現在、国立感染症研究所ウイルス第三部部長、WHOインフルエンザ協力センター長を務めている。専門はウイルス学、感染症学。共著書に『新型インフルエンザH5N1』(岩波書店刊)、『鳥インフルエンザの脅威』(河出書房新社刊)など多数ある。
関連記事
 インフルをインフルと見抜けないと(年末を乗り切るのは)難しい
インフルをインフルと見抜けないと(年末を乗り切るのは)難しい
12月の総務特集は「医者要らずでできるインフルエンザ対策」。そもそもインフルエンザと風邪の違いって? 予防するにはどんなことに気をつければいいの? 個人でできる感染予防策と、企業が取るべき対策を見ていこう。- 医者要らずでできるインフルエンザ対策
ゴホゴホという咳の音が電車、オフィス、人混みで聞こえるこの季節。どこでインフルエンザウイルスをもらうか分からない。しかも新型ウイルスの大流行も懸念されている。医者にかからなくても個人、企業で今すぐ始められるインフルエンザ対策を紹介しよう。  3人に2人が「風邪なら約束キャンセルすべき」
3人に2人が「風邪なら約束キャンセルすべき」
風邪をひいたら、相手にうつさないように約束を早めにキャンセルするのがマナー――。3人に2人がそう考えていることが、グラクソ・スミスクラインの「風邪のスマート・マナー意識調査」で分かった。 風邪で仕事がはかどらない」の損失は? コンタック研究所が発表
風邪で仕事がはかどらない」の損失は? コンタック研究所が発表
「風邪で仕事がはかどらない」の損失は5日で4万4270円──。コンタック研究所は9月20日、「ビジネスパーソンの風邪に関する意識調査」を発表した。男女別では男性が5万6400円、女性が3万2100円と2万円以上の差がついている。 新人たちの「免疫力低下」現象を見過ごしていないか【個人編】
新人たちの「免疫力低下」現象を見過ごしていないか【個人編】
初々しかった新人たちも配属後半年ほどで落ち着いてくる。ここで見逃してならないのは、新人たちが入社時や配属時に持っていた“自己免疫力”を失っているのではないか――ということだ。
関連リンク
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 初期侵入口は“またVPN” 日本医大武蔵小杉病院にランサムウェア攻撃
- 「2027年1月12日」は運命の日? サポート切れOSを使い続ける会社の末路
- NTTデータ、仮想化基盤「Prossione Virtualization 2.0」発表 日立との協業の狙いは
- SOMPOグループCEOをAIで再現 本人とのガチンコ対談で見えた「人間の役割」
- AIエージェント普及はリスクの転換点 OpenClawを例に防御ポイントを解説
- Apple、「macOS」や「iOS」に影響するゼロデイ脆弱性を修正 悪用確認済み
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- Palo Alto Networks製品にDoS脆弱性 再起動やサービス停止の恐れ
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選