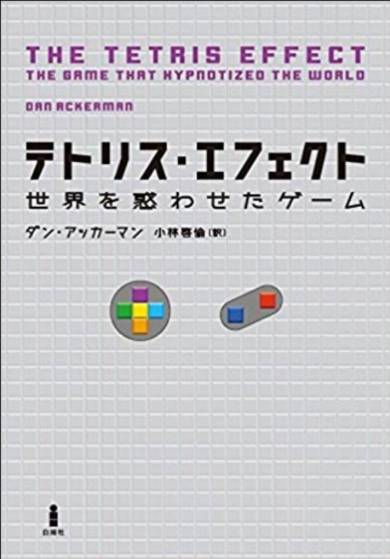誰もが知る「テトリス」の知られざるヒミツ:「テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム」
「テトリス」というゲームを知らない人はほとんどいないだろう。上から降ってくるカラフルなブロックを落として組み合わせる。一列そろったら消える。それを繰り返す――という非常にシンプルなパズルゲームだ。しかしそのシンプルさとは裏腹に(もしくはシンプルさゆえに)、「テトリス」は世界中の人々を熱狂させ、「落ち物ゲーム」というジャンルを作り上げた。しかし、あなたはテトリスがいつどこで生まれたゲームか知っているだろうか?
答えは1984年のソビエト連邦。日本にやってきたのは88年だ。ゲーム好きならさらりと答えられる質問だろうが、「えっ、米国製じゃないんだ」「『スペースインベーダー』(78年)と同時代のゲームだと思ってた」という人もいるのでは。社会主義の“壁”の向こうで、どのようにして作品が生まれ、どのようにして世界中に広がっていったのか? それを教えてくれるノンフィクションが「テトリス・エフェクト 世界を惑わせたゲーム」(白揚社/税別2300円)だ。
テトリスは当時のソ連にとって、外貨をもたらす貴重な知的財産だった。しかしソ連にはコンテンツ輸出のノウハウを持った人材がおらず、版権の契約は混迷を極めた。「誰もテトリスのライセンスの全容を把握できていない」という、現代では信じられないような状況で、テトリスは急速に世界に広がっていく。
混乱の中で、テトリスの関係者はタイトルの通り“惑わせ”られた。テトリスの生みの親でありながら、長らくゲームに関する権利をほとんど持てなかったアレクセイ・パジトノフ。日本初と言われるファンタジーRPG「ザ・ブラックオニキス」の作者であり、任天堂と手を組んでテトリスを日本に広げようとしたヘンク・ロジャース。ソ連側といち早く契約を進め、テトリスの権利を握ろうとしていたロバート・スタインやケヴィン・マクスウェル……それぞれの思惑が群像劇のように描かれる。
群像劇のクライマックスは、ヘンク・ロジャースと任天堂チームがライセンス契約を結び、携帯機「ゲームボーイ」のソフトとしてテトリスがやってくる一幕だ。その契約や交渉の様子はさながらスパイ映画。本書はたびたびネット上で「最強」と賞される任天堂法務部の「伝説」を味わえる1冊でもある。
関連記事
 任天堂、コロプラを提訴 特許侵害で「白猫プロジェクト」差し止め求める
任天堂、コロプラを提訴 特許侵害で「白猫プロジェクト」差し止め求める
任天堂がコロプラを提訴。「白猫プロジェクト」の配信差し止めと損害賠償44億円の支払いを求める。 アイドルが登場するのは「ガンダムファンが嫌いそうだから」 「マクロス」河森監督の企画論
アイドルが登場するのは「ガンダムファンが嫌いそうだから」 「マクロス」河森監督の企画論
「アイドル×ロボット×戦争」で“ロボットアニメ観”に風穴を開けた「マクロス」シリーズ。河森正治監督はいかにしてマクロスを生み出したのか? キーワードは「ガンダムじゃないもの」だ。 任天堂、7年ぶり売上高1兆円突破へ 「Switch」好調、通期1500万台に
任天堂、7年ぶり売上高1兆円突破へ 「Switch」好調、通期1500万台に
任天堂は、2018年3月期の連結業績予想を上方修正し、売上高が1兆200億円になる見通しだと発表した。 「最後の希望の光」モンストと歩んだミクシィの4年間
「最後の希望の光」モンストと歩んだミクシィの4年間
4周年を迎えたスマホゲーム「モンスターストライク」は、ミクシィという会社を救ったタイトルとしても知られている。モンストのヒットで、ミクシィはどのように変わったのか? 「モンスト」に立ち上げから関わるミクシィ森田仁基社長インタビュー。 「アズールレーン」席巻 大躍進「中華ゲーム」のヒミツ
「アズールレーン」席巻 大躍進「中華ゲーム」のヒミツ
艦船擬人化スマホゲーム「アズールレーン」が注目されている。実はこのゲーム、日本国内でヒットしているものの、開発元は中国企業だ。続々と上陸する中華圏発のゲームアプリに迫る。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング