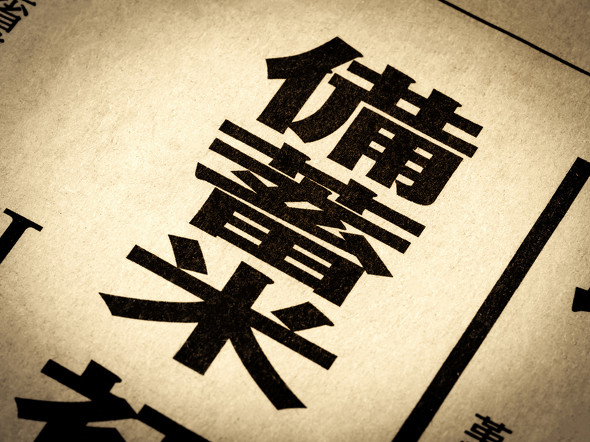まさかの「備蓄米ブーム」到来…… 米の価格は下落するのか? 各社の「仕入れ量」「取り組み」総まとめ(1/4 ページ)
著者プロフィール
山口伸
経済・テクノロジー・不動産分野のライター。企業分析や都市開発の記事を執筆する。取得した資格は簿記、ファイナンシャルプランナー。趣味は経済関係の本や決算書を読むこと。 X:@shin_yamaguchi_
政府と小売店業者間の随意契約に基づく備蓄米の供給が始まった。当初、備蓄米は入札方式で放出したが、高騰に歯止めがかからず、随意契約に切り替えた。大手小売チェーンが仕入れ、既に店頭に並んでいる。
随意契約ではないが、市場から調達した古米をそのまま売るのではなく、おにぎりとして販売するコンビニも現れた。各社はどのように販売しており、そして価格への影響は出ているのか。小売各社の仕入状況と販売額を比較していく。
2024年から上昇し始め……
もともと、スーパーにおける米5キロ当たりの価格は2000円未満で推移していた。2024年5月辺りから2000円強となるも、緩やかな上昇だった。
2024年後半から急にペースが早まり、8月に2500円、9月には3000円を超えた。直近では4000円台となっている。
日本の農業はJA(農業協同組合)が全てを左右するという極論も聞かれるが、米の全生産量に占めるJAの集荷割合は4割程度。残りは農家から卸売業者や外食事業者等への直売で、市場の原理が働く。昨今の高騰で卸売業者に流れる米の量は増えており、2024年産に至ってはJAの集荷率がさらに1割減少するといわれる。
価格高騰が収まらない状況で政府は3月以降、入札方式による備蓄米の放出を決めた。備蓄米は政府が凶作に備えて用意するものであり、1993年の大凶作をふまえて1995年から備蓄している。計3回の入札で31万トンが落札されたが、3月中に落札された21万トンのうち、小売業者に回ったのはわずか13%で2.7万トンしかない。国内における主食用米の需要は年間700万トンであり、焼け石に水となった。
流通が滞っている現状を踏まえ、政府は入札方式から小売業者との随意契約に切り替えた形だ。5月26日に契約申請の受け付けを開始し、早くも31日から一部スーパーの店頭に並び始めた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング