改革を迫られる企業の人事システム:特集:ヒューマンリソースマネジメントの現状と課題
変化の激しい経営環境の中にあって、いまあらためて注目されているのが人材の有効活用だ。これを実現するためには、人事制度の改革や、経営戦略と密接にリンクした人材活用戦略が不可欠だ。そのために多くの企業はいま、新たな人事システムの構築に取り組んでいる。本特集では3回にわたり、企業が競争優位に立つためのヒューマンリソースマネジメントの現状や課題を探る
なぜ改革が必要なのか
なぜ人事管理の改革が必要なのか。集約すれば、最も重要なリソースである人材を有効活用しないと、激しい経営環境の変化に対応できず企業は競争力を失ってしまう、ということに尽きる。
製造業を例に取ると、いまモノ作りは、製品の企画・設計から開発・生産、販売に至る一連の過程でリードタイムの短縮化が至上命題になっている。コンカレント・エンジニアリングやPLM(Product Lifecycle Management)などが注目されるのもそのためだ。そしてこれを実現するには優秀なプロジェクトマネージャや技術者、IT活用ノウハウが欠かせない。
ところが現実には、マネージャは旧来の年功序列型の人事制度に基づいて管理職になっているため、プロジェクトを管理するトレーニングを受けていない。従って、そうした管理能力に欠けるマネージャの下でプロジェクトが進み、思うような効果が得られていないといったケースが少なくない。
コスト競争力も製造業では最重要課題の1つで、それを実現するにはCAD/CAM/CAEを駆使する能力は不可欠だ。そこで、例えば液晶で世界トップに立った韓国のサムスン電子では、CAD/CAM/CAEの活用能力を高めるため、それらの研修への参加や資格取得を人事考課と結び付けるといった方法を用いて社員のスキルアップを図っている。つまり、研修に参加し資格を取得しないと、昇給や昇格の対象から外すといった人事評価制度を導入することによって企業競争力を高めているのである。
日本の製造業がコスト競争力を高めるには、中国に代表される労働賃金の安い地域での生産も求められる。この際には、当該地域の言語に堪能であったり、交渉能力やコミュニケーション能力の高い社員が必要だ。あるいはSARS(重症急性呼吸器症候群)で浮き彫りになったが、現地に担当者や管理者を持つか否かで、事業のスピードに差が生まれる。SARSの場合は、中国への渡航が禁止されたため、日本から担当者や管理者を派遣できず、事業をスピーディに展開できなかったケースも報道されている。
こうした経営戦略を実行に移す際、現在の人事制度の多くは、社内のだれが必要な知識やスキルを持っているのかということをスピーディに把握できる仕組みができていない。あるいは、個々の社員が望む自己啓発やスキル向上に柔軟に対応できるような仕組みが不十分だ。逆にいえば、そうした仕組みが出来上がっていれば他社に対して競争優位に立てることになる。従って人事改革が必要なのである。
現状の人事管理の課題
その人事管理の問題点や課題はどこにあるのか。人事コンサルタントでティーオージー・ジャパンの遠藤仁氏は、以下の4点を指摘する。
- 現状、景気低迷が続く中で社員に対する動機付け策が難しくなっている
- 成果主義人事制度が正しく運用できていない
- 教育投資が制限され自己啓発やOJTに頼らざるを得なくなっている
- キャリアパスを示すことが難しくなってきている
それぞれについて補足すると次のようになる。まず社員に対する動機付けの困難さだが、これは端的にいえば、右肩上がり時代のような定期昇給が困難になってきたことが背景にある。その結果、社員の士気を鼓舞するのが困難になってきたというわけだ。
成果主義人事制度の運用に関しては「成果主義」のとらえ方に問題があるとして、遠藤氏は次のように指摘する。
「成果主義人事の本来の在り方は、成果配分主義であるべき。つまり会社がもうかった分は社員に配分する。あるいは逆に、もうからなかった場合は社員にもそれ相応の責任を取ってもらうのが本来の成果主義。だが実際は、会社の業績とは無関係に単に賃金の上げ下げをしている。従って、日本の成果主義の場合は、企業経営と個人の評価が分断されており、社員の理解は得られない構造になっている」
成果主義人事制度のもう1つの問題は、評価者自体の問題だ。つまり、正しい成果主義人事制度で育ってこなかった上司が、部下を評価している点である。
教育投資の問題は、企業の収益が悪化しており、十分な投資をする余裕がなくなってきているということが背景にある。従って個々の社員は自己啓発に励む必要がある。
キャリアパスに関しては、企業側が社員にどういった道筋を示すかが難しくなっている。これは市場の変化が激しく、景気低迷で将来が不透明という事情もある。
人事システムの問題点
人事管理制度の抱える問題点は、当然ながら人事システムにも影響する。大手企業向け人事システム「COMPANYシリーズ」で注目されているITベンダのワークスアプリケーションズは、ほとんどの企業が抱える人事システムの問題点として、1. 変更要求に対する柔軟性のなさ、2. 運用コストの削減の2点を指摘する。
まずシステム変更に対する柔軟性のなさに関しては、例えば企業の人事制度が変わったり、法制度が変更された場合、現状の人事系レガシーシステムでは柔軟に対応できない。人事系システムは企業規模が大きいほど導入率が高いわけだが、そのシステム変更には莫大な手間とコストが掛かる。これを何とか解消できないかというわけだ。
運用コストに関しては、従来のレガシーシステムは当該企業の要求仕様に基づいて独自に構築しているためコストが掛かり過ぎる。そこでパッケージソフトを導入することによって運用コストを削減し、コストメリットを得ようとの判断だ。
そこでワークスアプリケーションズでは、人事・給与、Web Service、就労・プロジェクト管理、Knowledge information Portalといった一連の人事パッケージソフトによって、企業の抱える問題解決に乗り出した。同社は1996年7月設立と比較的社歴の浅いITベンダだが、東証1部上場の大手企業が相次いで導入するなど、人事パッケージソフトの分野ではトップクラス。企業が抱える人事システムの問題点解決に貢献しているといえそうだ。
一方、ERPベンダの中で人事系に強いとされる日本ピープルソフトのHCMプロダクトマーケティングマネジャー 横井クリスティーヌ由美子氏は、企業が人事システムに関連して抱える問題点を以下のように指摘する。
「個々の企業によって抱えている問題点は異なるが、どの企業にも共通しているのは、人事情報が分散していること。つまり、レガシーシステムには従業員情報や履歴情報などは入っているが、スキル管理のために新たなシステムを開発したり、教育用システムも別に存在している。給与計算のようなコアシステムや勤怠システムもあり、組織再編や企業合併を背景に、さらに別のシステムも存在する。要は、人事情報が統合化した形態で活用できない状況にあることだ」
最近は、正社員を必要最小人数にとどめ、契約社員や派遣社員を活用するケースも非常に多い。そうした正社員以外の社員はスプレッドシートで管理していたり、派遣元の企業のデータに頼っていたりするケースも少なくない。こうした場合、例えばグループ企業だとシェアードサービスの形にしたいので、統合されたビューが必要になる。
ピープルソフトのようなERPは統一データベースが基幹なので、個人情報や扶養家族情報、職務履歴、社員の前職歴なども管理している。だが顧客企業は「スキルやコンピテンシー情報、今後のキャリアの目標、マネージャから見た人事考課情報を統合的に管理したいニーズがある。また、正社員以外の情報を管理可能なシステム構築や人材の有効活用、従業員をよりモチベートできる報酬システムの構築へのニーズも高い」と横井氏は語る。
これを実現するにはセルフサービスシステムが必要になる。それによって正社員か契約・派遣社員かを問わず、各種の申請関連作業を本人ができるようになり、人事部の負担を軽減し、従業員自身も自分の情報確認や研修情報検索や申し込みなどが可能になる。スキル履歴の更新などもでき、従業員にとってもメリットがあるので活力も生まれる。
見方を変えれば、現行の人事システムの多くは、こうした戦略的な人材活用ができるようにはなっていないということになる。そこが問題点であり、これを実現することによって企業はこれまでとは違った人材活用が可能になる。
人材活用の潮流
前出の遠藤氏によると現在、企業の人材活用の潮流には以下の7つのものがあるという。
それぞれについて補足しよう。
コンピテンシーの導入
まず、成果主義人事の前段階としての「コンピテンシー」の導入。コンピテンシーは、高い業績を上げるための行動特性をいう。遠藤氏によれば、コンピテンシーの導入はかなり進んでいるが、よく理解しないまま導入を進めているのがかなり多いのが実情だ。
コンピテンシーの考え方は1970年代、米国で生まれた。米国はもともと成果主義の国で、結果がすべてで能力を評価することはなかった。しかしそれだけでは企業の中長期の成長のための施策が活かされないことから、コンピテンシーという考え方を受け入れていった。遠藤氏は、コンピテンシーは日本でいう“能力”の要素を含んでいる。従って「コンピテンシーを導入した日本の企業は、能力主義と変わらないのではないか」ととらえる場合が多いが、それは海外のものをそのまま導入した結果だからだと指摘する。
「日本のコンピテンシーはもともと能力主義だった。これは潜在能力の評価で、実質的には年功序列だった。そのため日本の企業は一足飛びに成果主義に行こうとし、それで失敗した。理由は成果というものの定義を明確にせず、かつ年功序列できた上司が成果を評価できなかったからだ。この中間にコンピテンシーがある。これを理解しているとうまくいく。すなわち、能力が発揮された行動を評価していく。その行動が成果に結び付くということだ」(遠藤氏)
コンピテンシーの導入は、ベンチャー系のIT企業や流通業が成功しており、重厚長大企業ではうまくいっていない。理由は、コンピテンシーは行動に評価の視点を置いて業績を上げるという手法なので、営業や流通系企業は好業績との関係が明確になりやすく、効果を得られやすいからだ。一方、重厚長大企業は難しい行動を求められるので、簡単には結果が得られにくいというわけである。
多面評価(360度評価)の導入
多面評価は、公正な評価やOJTの一環として導入されるもの。多面評価は上司が部下を正しく評価できない場合、部下や同僚、顧客先など、ほかからの評価を入れる手法である。サテライトオフィスなどで上司が部下の勤務状況を直接的に見ることができないといった場合にも活用される。
人事評価期間の短縮化
評価期間の短縮化は、従来は半期ごとの評価だったのを四半期ごとに短期間で評価していこうという取り組みだ。理由は、評価期間が長いと、能力や適性のない社員を長期に雇用し続けたままになるという反省がある。これでは人材投資が無駄になるし、能力や適性の優れた社員が、そうではない社員と同列に評価されることになり、できる社員の士気をそぐことにもつながる。それを改善しようというわけである。
ただし、短期評価といっても1カ月単位では、今度は評価作業に追われることになるので、四半期(3カ月)単位が有効というわけである。この短期評価は、ITを活用することによって日常の行動を自動的に評価するといった仕組みとの連携で導入されるケースが多いといわれる。
バランスト・スコアカードの導入
企業の業績評価と個人評価を連動する仕組みとして、バランスト・スコアカード(BSC)の導入も始まった。
「BSCは管理会計の研究者が考案したことから会計や経営戦略に適用されることが多いが、例えば米国では人事評価のツールとしてとらえられれている。いままでは企業の目標と個人の目標はファジーな関係だったが、この関係を明確にしたのがBSCであり、その意味で画期的な手法といえる」(遠藤氏)
eラーニングによる効率的な人材教育
eラーニングは、いうまでもなくインターネットを活用した人材教育方法。HRMの eラーニング専業であるスマートリンクの代表取締役CEO 北澤淳一氏は「eラーニングは2002年度下期から変わってきた。つまり、案件数、企業内研修が増え、eラーニングの新規事業者も立ち上がってきた2003年はeラーニングのターニングポイントになる」と指摘する。
同氏によれば、HRMに関するeラーニングの導入効果はこれからだが、目標にすべきは企業人がどういう方向に自分を伸ばしたいのか、それには何を学べばいいのかをナビゲートするようなラーニングポータルを与えることが重要という。そうすることによって個人を成長させるための学習の場を創出し、かつ、それを学習者にだけ提供するのではなく、学習の管理者としていかにマネジメントするかも不可欠だ。
それには各人の学習の進ちょく状況を管理するのではなく、BPRによって業務プロセスを革新したように、教育によって企業価値を高めることが重要となる。スマートリンクではこれを「EPR(Education Process Reengineering)」と呼ぶ。ITを活用することによって「PDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクル」を回し、イノベーションを起こすこと、それがeラーニングというとらえ方である。
「eラーニングは研修環境全体のイノベーション。ネット上での教育も、集合教育もOJTもラーニングオブジェクトであり、それらをeラーニングのラーニングマネジメントシステムで統合的に管理(ブレンディング)していくのが理想」と北澤氏は語る。
アウトソーシングの活用
アウトソーシングはかなり進んでいる。企業の営業事務などだれでもできる業務は積極的に外部に委託し、社員は企業の収益に貢献できる業務を遂行していくという考え方。人事部の場合も、給与計算や新入社員教育といった定型的な業務と、非定型業務がある。定型的な業務は積極的にアウトソーシングする傾向が少なくない。「人事評価など非定型業務も含めてアウトソーシングしたいというニーズも多いが、人にかかわる部分は企業の将来の成長に左右することであり、外部がすべてを理解できるわけではないので、それはやるべきではないと思う」と、遠藤氏は指摘する。
インセンティブ制度の導入
インセンティブ(歩合制度)は今後の潮流の1つ。日本の場合、インセンティブは賞与払いというケースが少なくないが、賞与は実質的には生活給に組み込まれており、あまり賃金格差が付けられていない。だが米国の場合は非常に多い。賞与はコストと見込む必要があるが、インセンティブは達成されなければ支払う必要がない、つまり、当初から見込む必要のない経費である。
日本人の意識として、歩合やコミッションには悪い印象があり、企業もあまり積極的に採用してこなかった。しかし、今後は右肩下がりで成長があまり期待できない。となればインセンティブを採用すべきだし、実際、日本の企業でも採用して成功しているケースが増えつつある。
ただし注意しなければならないのは、個人単位のインセンティブは足の引っ張り合いになり、避けるべきだということだ。そうではなく、組織単位のインセンティブを採用するのが有効だという。これは情報の共有化を推進する場合にも有効だ。こうした組織単位のインセンティブは米国でも注目されており、日本でも今後増えるとみられる。インセンティブは、先に紹介した短期評価との連携という点でも有効だ。
Profile
日高 俊明(ひだか としあき)
1952年1月生まれ、長崎県出身。OA、コンピュータ関連の雑誌、新聞記者を経て1987年からフリー。コンピュータ、科学技術関連、経営関連雑誌などに多数寄稿。著書:『ソフトウォーズ!』『続ソフトウォーズ!』(以上、コンピュータ・ニュース社)、『オラクルマスター・オフィシャルガイド』(IDGジャパン)、『VR革命』(オーム社)編著、『AIビジネスの布石』(コンピュータ・ニュース社)、『トコトンやさしいパーソナルロボットの本』(日刊工業新聞社)
メールアドレスはhidaka27@mb.infoweb.ne.jp
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 住信SBIネット銀行、勘定系システムのクラウド移行にDatadogを採用
- 2025年、話題となったセキュリティ事故12社の事例に見る「致命的なミス」とは?
- 3800超のWordPressサイトを改ざん 大規模マルウェア配布基盤が82カ国で暗躍
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
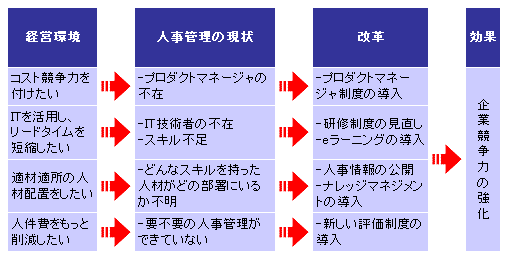 表1 人事改革の必要性の例
表1 人事改革の必要性の例 ティーオージー・ジャパン 代表取締役 遠藤仁氏
ティーオージー・ジャパン 代表取締役 遠藤仁氏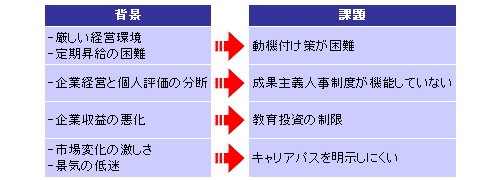 表2 いま企業抱える人事管理の課題
表2 いま企業抱える人事管理の課題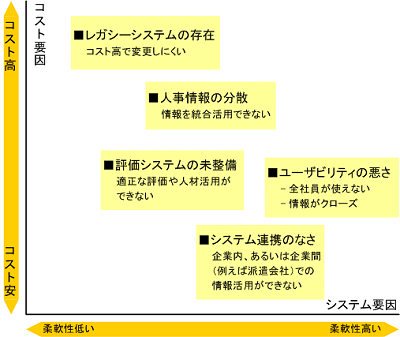 図3 人事システムの問題点
図3 人事システムの問題点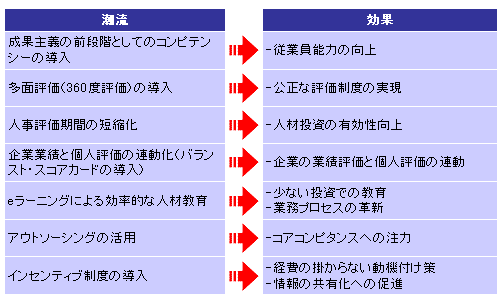 表4 人材活用のための7大潮流と効果
表4 人材活用のための7大潮流と効果