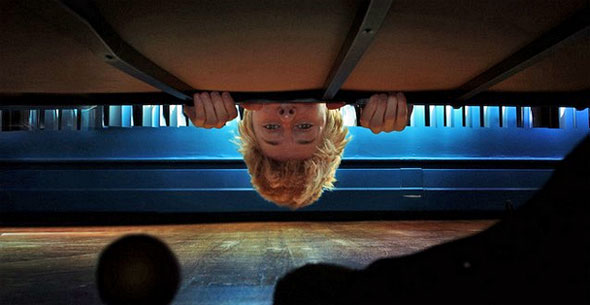ぜんぶ妖怪のせい? 正しく使おう「妖怪ウォッチ教育法」:問題の外在化(1/4 ページ)
もしもあなたに、子どもがいたら「金曜日の6時半といえば?」と聞いてみてください。そうすると、目を輝かせ、こう返してくるでしょう。「妖怪ウォッチの時間!」
月刊情報誌、日経トレンディが発表した2014年のヒット商品ランキング第2位は、「妖怪ウォッチ」でした(ちなみに、第1位はアナと雪の女王)。子ども向け商品のヒットには、大人も引きずり回されるもの。
休みの日に街を歩いていると、妖怪ウォッチグッズを求める親子連れの長蛇の列を見かけることも、もはや不思議な光景ではなくなりました。子どもたちは、目をキラキラとさせ、大人たちの眼は、どんよりと疲れ切っていましたが……。
以前、なぜ妖怪ウォッチがこれほどまでに流行ったのかについて、経済学的に分析をしましたが(関連記事)、今回は、妖怪ウォッチが引き起こした「何でも妖怪のせい」現象を心理学的に解明してみたいと思います。
「なんでも妖怪のせい」現象
妖怪ウォッチのブームによって、子どもたちが「なんでも妖怪のせいにする」ことが問題視されています(なんでも「妖怪のせい」にする子どもが増えているみたい)。番組のエンディングテーマとして使用された「ようかい体操第一」の歌詞の中では、「寝坊したこと」や「イケメンなのにフラれたこと」などが妖怪のせいとして描かれています。
これくらいだったらかわいいものですが、「部屋の片づけができない」とか「勉強する気にならない」とか「お母さんの言うこと聞きたくない」といったことまで全部「妖怪のせい」にしてしまう子どももいるそうです。「妖怪のせい」で親は納得するはずがありません。
しかし、「妖怪のせい」にすることで、心が落ち着く子どもだっているでしょう。本稿では心理学の視点にたって、一概に良いとも悪いとも言えない「妖怪のせい」現象のメカニズムを説明していこうと思います。
関連記事
 「妖怪ウォッチ」クロスメディア戦略の功と罪
「妖怪ウォッチ」クロスメディア戦略の功と罪
アニメや漫画だけでなく、ゲームソフトやグッズの売れ行きも好調な、子どもに大人気の「妖怪ウォッチ」。なぜ、妖怪ウォッチはここまでのヒット作となったのか。今回は、ヒットの裏を探ります。 「秋葉原に負けない聖地に」――JR高架下に「阿佐ヶ谷アニメストリート」が生まれるワケ
「秋葉原に負けない聖地に」――JR高架下に「阿佐ヶ谷アニメストリート」が生まれるワケ
2014年3月29日にオープンする「阿佐ヶ谷アニメストリート」。なぜ阿佐ヶ谷にアニメをテーマにした商店街を作るのだろうか。2人のキーパーソンに聞いた。 なぜ空洞化でアニメーターが足りないという声が生まれるのか
なぜ空洞化でアニメーターが足りないという声が生まれるのか
アニメ業界では「動画が海外にアウトソーシングされると、国内で原画を育てる機会がなくなるので空洞化してアニメーターが足りなくなる」と言われつつも、足元では若手アニメーターがある程度育っている。どうして、そのような懸念が生まれるのだろうか。 悪人を倒せば世界が平和になるという映画は作らない――宮崎駿監督、映画哲学を語る(前編)
悪人を倒せば世界が平和になるという映画は作らない――宮崎駿監督、映画哲学を語る(前編)
『風の谷のナウシカ』『となりのトトロ』『千と千尋の神隠し』など数々の映画で、国内外から高い評価を受けている宮崎駿監督。アニメーション界の巨匠が何を思って映画を作っているのか、どんなことを憂いているのかを語った。
関連リンク
Copyright © Credo All rights reserved.
Special
PR注目記事ランキング