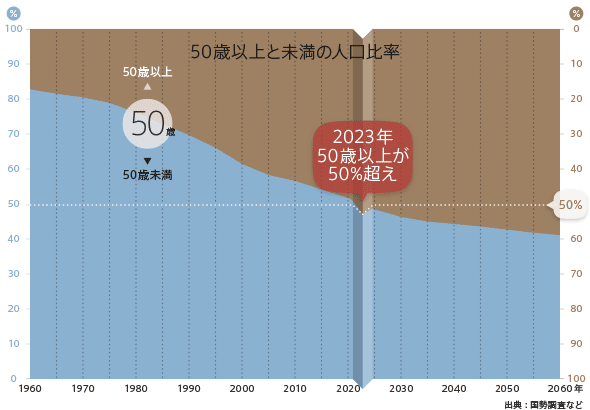え? 「過半数が50歳以上」に──2023年のニッポン、一体どうなる?:博報堂生活総研・吉川昌孝の「常識の変わり目」(1/2 ページ)
「昔はこうだったのに」──。これまでの常識とは違うことが常識になりつつあると感じる事象はありませんか。データで読み解くと、常識の変わり目が見えてきます。今回は、「過半数が50歳以上」になると予測される日本の人口分布についての変わり目を探ります。
博報堂生活総研・吉川昌孝の「常識の変わり目」
30年以上にわたり生活者を研究し続けてきた「博報堂生活総合研究所(生活総研)」。同研究所の主席研究員である吉川昌孝氏が、さまざまなデータを独自の視点で分析し「常識の変わり目」を可視化していくコラムです。世の中の変化をつかみたいビジネスパーソンに新たなモノの見方を提供します。
先日(9月15日)の敬老の日、「日本は、65歳以上が全人口の4分の1」になり、「75歳以上は、8人に1人」であると統計値を伝える報道を多く見かけました。高齢化がこのまま進むと、2023年──これから9年後に、日本は「全人口の過半数が50歳以上になる」と予想されています。
その後も、この比率はどんどん高まります。2033年には55%を超え、2060年には6割弱にまで拡大すると予測されています。
「人間五十年」、かの武将 織田信長の言葉があります。戦後間もない1947年の男女別平均寿命は、男性が50.06歳、女性が53.96歳。確かに日本人の寿命はつい最近まで、この言葉通り50年くらいでした。ちなみに、明治や大正時代までさかのぼるとそれは40歳代でした。
それがもう、過半数が50歳以上に。飛躍的な速度で日本人は長生きになったことになります。平均寿命が50歳のころにできた年金制度が現状と合わないのも、仕方ないことかもしれません。
ちなみに、平均寿命が男女とも60歳を超えたのは1951年。70歳を超えたのが1971年。そして昨年2013年、日本人は男女ともに80歳を超える長寿国になりました。
このように高齢化が急激に進むと、社会での主役の座も交代していくのでしょう。私たち(博報堂生活総研)が隔年で実施している「生活定点」調査で、「若者が主役の世の中だと思う」と答えた割合がどう変わったと思いますか? 1998年の20.4%から、2014年は12.6%と、なんと約8ポイントも落ちました。以後も低落傾向にあるとみています。
本当に、高齢者の存在感は大きくなっているのでしょうか。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 10軒に1軒以上が「空き家」──空き家率の上昇は、いいこと? 悪いこと?
10軒に1軒以上が「空き家」──空き家率の上昇は、いいこと? 悪いこと?
「昔はこうだったのに」──。これまでの常識とは違うことが常識になりつつあると感じる事象はありませんか。データで読み解くと、常識の変わり目が見えてきます。今回は、13.5%に達した空き家から「新しい住まい方」の変わり目を探ります。 多死社会の入口で感じた「悲しくて楽しい」こと
多死社会の入口で感じた「悲しくて楽しい」こと
最近、「生老病死(しょうろうびょうし)」を考える機会があった。「生まれる、老いる、病む、死ぬ」の4つ、必ずやってくる苦悩。今後増える「死」を楽しく語り合えることが大切なのだ。 少子高齢化の切り札? 独身男を襲う「カニばさみ」の恐怖
少子高齢化の切り札? 独身男を襲う「カニばさみ」の恐怖
厚労省の調査によると、独身女性の3人に1人は「専業主婦になりたい」だったが、独身男性の5人に1人は「専業主婦になってほしい」。今の若い男は甲斐性なしね、といった声が聞こえてきそうだが、男女間の経済感覚の“ギャップ”を解消しなければ、大衆は踊らないだろう。 ヨン様からおひとり参加限定の旅まで……高齢者向けビジネスあれこれ
ヨン様からおひとり参加限定の旅まで……高齢者向けビジネスあれこれ
日本の金融資産のうちの多くを持っている高齢者たち。その財布を狙ったビジネスが近年、静かに増えてきているようです。 「リバースモーゲージ」は高齢化社会の救世主になれるか?
「リバースモーゲージ」は高齢化社会の救世主になれるか?
最近よく見聞きする「リバースモーゲージ」。リバースモーゲージとは、自宅などの不動産を担保に入れ、その評価相当額を一括、もしくは毎月一定額を年金のように受け取るローンのこと。年金不安の中、高齢化社会の救世主となれるのでしょうか? その課題と留意点を考えてみました。 今の50歳代が、不幸な高齢者になるかもしれない理由
今の50歳代が、不幸な高齢者になるかもしれない理由
「老いの工学研究所」の研究員も務める筆者。5人の高齢者を招いた座談会で最も印象に残ったのは、ある80歳代前半の女性が語った内容だった。 博報堂生活総研・吉川昌孝の「常識の変わり目」:「少子化」を子どもの目から見てみると……
博報堂生活総研・吉川昌孝の「常識の変わり目」:「少子化」を子どもの目から見てみると……
「昔はこうだったのに」──。これまでの常識とは違うことが常識になりつつあると感じる事象はありませんか。データで読み解くと、常識の変わり目が見えてきます。連載1回目の今回は「少子化の変わり目」を取り上げます。- 博報堂生活総研・吉川昌孝の「常識の変わり目」 バックナンバー