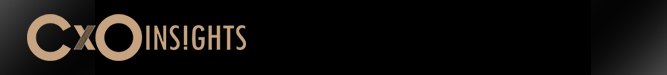三井化学のCTOは「サステナビリティ経営」をどう実現するのか 研究者育成の壁
本記事はサステナブル・ブランド ジャパンの「化学技術から実現するカーボンニュートラル、研究者育成が課題――三井化学」(2024年2月26日掲載)を、ITmedia ビジネスオンライン編集部で一部編集の上、転載したものです。
産業部門で見ると鉄鋼に次いで二酸化炭素(CO2)排出量が多い化学産業。脱炭素化の時流に先駆け、三井化学は2020年に「2050年カーボンニュートラル」を宣言し、自らを変革していく決意を表明した。
さらにその取り組みを加速するため、4月にCTO室を正式に設置。社内事業の技術開発に関わる案件に横串を刺し、開発を活性化する。そのトップに立つのが、代表取締役専務執行役員 CTO(最高技術責任者)の芳野正氏だ。
 芳野正氏。三井化学 代表取締役専務執行役員 CTO(最高技術責任者)。1987年三井東圧化学入社。2003年三井化学基礎化学品本部企画管理部、09年PT. PETNESIA RESINDO(インドネシア)社長、12年三井化学工業薬品事業部長、16年執行役員基盤素材事業本部副本部長、18年常務執行役員基盤素材事業本部長、21年取締役専務執行役員基盤素材事業本部長、22年より現職(撮影:以下、松島香織、サステナブル・ブランド ジャパン)
芳野正氏。三井化学 代表取締役専務執行役員 CTO(最高技術責任者)。1987年三井東圧化学入社。2003年三井化学基礎化学品本部企画管理部、09年PT. PETNESIA RESINDO(インドネシア)社長、12年三井化学工業薬品事業部長、16年執行役員基盤素材事業本部副本部長、18年常務執行役員基盤素材事業本部長、21年取締役専務執行役員基盤素材事業本部長、22年より現職(撮影:以下、松島香織、サステナブル・ブランド ジャパン)企業を取り巻く環境が目まぐるしく変化する中で、同社は15〜20年先の「目指すべき企業グループ像」を再定義し、21年6月に新長期経営計画「VISION 2030」を策定。「VISION 2030」では、パーパスとして「社会課題の解決」を再認識し、化学の力で社会課題を解決していく姿勢を明確にした。
こうした同社の方針に沿って、化学工学の技術者として新しい製造プロセスの開発などに携わってきた芳野氏は「三井化学の中で一番伸ばさないといけないのは技術経営。化学技術の革新こそが、サーキュラーエコノミーやカーボンニュートラル実現に不可欠だ」と話す。
これまで成長分野の見極めや事業の方向性などは戦略的にできていたが、技術面から全社を俯瞰(ふかん)して決定し、事業を動かす部署はなかった。芳野氏は「技術経営という立場でコントロールする部署が必要ではないかとずっと考えていた」という。そこで、1年ほど前からそういった役割を担う「CTO室」を準備して、今年の4月に正式に組織化されることが決まった。
同社は製品分野ごとに組織分けされているため、これまでA本部とB本部がお互いの研究開発を共有することがほぼなかった。その間にCTO室が入ることで、別々に開発していた共通技術を融合させ、もう一段上の事業につなげることができるようになる。芳野氏は「それこそが、三井化学のやるべき技術経営」だと強調する。
同時に「サステナビリティ」は経営の中心にあると考えており、「あらゆる製品のリサイクルや社会のバイオマス化から、さらにその先にあるサーキュラーエコノミーやカーボンニュートラルにつながるソリューションの創出といったように、私たちが成すべきことは非常に広い範囲を含んでいる。化学素材のメーカーだからこそ、サステナビリティを中心に経営していかないと、会社自体が成り立たたず、社会にも受け入れられない」と話す。
CO2を排出するということは、炭素の酸化反応、つまり化学反応が起きたことを示す。CO2と水素を反応させてメタノールを作るということも、化学反応の一つである。「化学産業が貢献していかないとCO2は減らない。ある意味、われわれの活躍の場が増える可能性もあるし、われわれがいないと達成できない目標ともいえる」と、グリーンマテリアルに結び付けていくような化学産業であるべきだという芳野氏の思いは強い。
プラスチックの価値を上げる「リジェネラティブ」
プラスチックが抱える課題は大きく2つある。1つはCO2排出の問題、もう1つはプラスチックごみの問題だ。この2つの問題にバイオマス化とリサイクルの両輪で取り組むことで、「バイオ・サーキュラー」な世界観、つまり、より再生的な社会(リジェネラティブ)の実現を目指している。
プラスチックのリサイクルでは、主に物理的処理を経て再び製品の原料として再利用する「マテリアルリサイクル(メカニカルリサイクル)」と、化学的・熱的に処理・分解し化学原料や分解油などに転換して再利用する「ケミカルリサイクル」の2種類の手法がある。
前者は比較的容易に行えるが、リサイクルをするたびに再生原料の品質劣化が進んでしまう。そのため、主に元の製品よりも低い品質の製品に再利用され、荷役台のパレットや路盤材、プランターなどに成形されることが多い。品質が劣化するため、価値が低くなってしまうのだ。リサイクルしているので資源は循環しているが、製品そのものの価値がどんどん下がっていく状況では「サーキュラーエコノミーとしてのレベルは下がっている」と芳野氏は懸念を示す。
ここで重要になるのが「リジェネラティブ」という考えだ。芳野氏は「集めたものでまたさらに別の価値を創出し、もっと高く売ったり利用価値を広げたりすること。最低でも水平リサイクルができなければならない」と説明する。
ペットボトルのキャップから、キャップにリサイクルすることは比較的難しくないと考えられがちだが、芳野氏によると「非常に難しい」という。まず色で考えると、白だけでなく、緑、赤など、ブランドを表すさまざまな色が使われている。それらを集めて再びキャップにしても、グレーや黒などの色になってしまい、また同じ商品としてリサイクルできない。国や業界に対してもキャップを白に統一する制度を検討するよう働きかけるなど社会システムの提案も必要になる。
一方で進めているのが、リサイクルしても性能の落ちない製品にする添加剤の開発だ。「落ちてしまった性能を補い、添加すれば性能が元に戻るような価値のある化学品の開発は、まさにリジェネラティブにつながる」と芳野氏。さらに、化学的・熱的に処理・分解する「ケミカルリサイクル」では従来の石油由来原料と同品質の製品を製造できるため、この手法によるリサイクルの取り組みも本格化させようとしている。
また、芳野氏はバイオマスナフサ(※)から作られたバイオマスプラスチック製の黒い食器を見せてくれた。バイオマスプラスチックと間伐材の削りかすを混錬し、微妙に自然な模様が残るよう、建築家の隈研吾氏がデザインした。同社が取り組む社会のバイオマス化を目指した「BePLAYER®」の一事例でもある。帝国ホテルやホテルオークラなどのレストランで使用されているが、赤いトマトや黄色いカボチャが非常に映えて好評だという。
「隈研吾氏のデザインでブランド力を高め、バイオマス素材や食べ物の価値、あるいはレストランの価値も高めていくようなものになった」と芳野氏のお気に入りだ。
(※)再生可能なバイオマス(植物など生物由来の有機性資源)から生成された炭化水素混合物のことで、バイオディーゼルやSAF(バイオジェット燃料)をつくるときの副産物として得られる。そこから得られるバイオマスプラスチックの物性は石油ナフサ由来のプラスチックと同等
だが、こうしたリジェネラティブな製品はコストがかかる。例えば、炭素は燃えた後にCO2となるが、リサイクルする場合にCO2からO2を剥(は)がしてC(炭素)だけにしようとすると、必然的に新たなエネルギーが必要になる。「コストは上がるが、リサイクルでき、リサイクルしたことによって価値が上がる。価値に見合うモノであることを社会に認めてもらわなければならない」と芳野氏は強調する。
こうしたコストを含んだカーボンニュートラルの考え方を理解してもらう方法として、学校教育がある。同社は先ほどの食器と同様、隈氏デザインのバイオマスプラスチックの筆箱を工場のある千葉県市原市の中学校に寄付。生徒たちが1年間使った後回収し、リサイクルしてベンチなどにするプロジェクトを進行中だ。
「若い人たちにプラスチックはリサイクルできることを体感してもらうことには大きな意義がある。体感して得た経験は、必ずより良いリジェネラティブな未来につながっている」という。
社会貢献度を測る「Blue Value®」と「Rose Value®」
同社では、カーボンニュートラル達成のため、CO2の発生量をスコープ1、2で定量的に捉えている。素材はさまざまな用途に展開されるためスコープ3まで定量化することは困難だが、PCF(Product Carbon Footprintプロダクトカーボンフットプリント)を顧客と共有することで、サプライチェーンのc-LCA(carbon Life Cycle Analysis:カーボンライフサイクル分析)の算出に取り組んでいる。
一方で、CO2排出量以外で定量的に社会への貢献を見える化することは難しいが、把握できなければ企業として方向性も打ち出せない。
そこで、社会貢献度を測る自社内の尺度として「Blue Value®」と「Rose Value®」を設定。「Blue Value®」は環境に貢献するもの、「Rose Value®」は生活の質の向上に貢献するものだ。第三者による審議委員会で製品を審査し、該当するかを決定しているという。年次単位でその製品を取りまとめ、「VISION 2030」に非財務KPIや目標として設定している。
「全製品の売上比率の40%を30年までにBlue Value®やRose Value®製品にするのが目標。あと6年後だが、達成できると思っている」と芳野氏は自信を見せた。
化学メーカーの動きが世の中の大きな流れに
「今後、化学メーカーの動きが世の中の大きな流れになる」と芳野氏は持論を展開する。同社は23年2月に、京葉臨海コンビナートに拠点がある住友化学、丸善石油化学と企業連合を結成。共同でカーボンニュートラルの実現を促進する覚書を締結した。また、千葉県が主導する「京葉臨海コンビナートカーボンニュートラル推進協議会」に参画するなど、産学官、自治体を含めた連携に積極的だ。
そうした他社や地域との連携のほか、芳野氏が特に重要視しているのは、社内研究者の育成だ。同社は21年10月に、九州大学内に三井化学カーボンニュートラル研究センターを設置し、共同運営を開始した。もし、研究センターでの研究が成功して実用できるようになれば、「ノーベル賞が取れるくらいの研究」と芳野氏は自負している。
一方で、研究開発担当役員としての悩みは尽きない。芳野氏は研究所に行くたびに若い研究者を集めて「アドレナリンが出るような研究をしよう」と鼓舞しているという。「ある意味の大企業病。研究者がサラリーマン化している。世の中のためにこの研究をするべきだ! と議論するのが研究者なのだ」と熱く語る。
「研究者がパーパスや目的意識、やりがいなどと結びつけて研究できるのかどうか」。そのためには、組織としてモチベーションを上げるガバナンスも必要だ。現在、さまざまな試みをしている最中だという。また、研究者の育成の他に芳野氏が考えているのは、スタートアップ企業との連携だ。資金提供だけでなく、場合によっては技術を一緒に開発したり、営業担当者を付けたり、新たなプロジェクトを計画しているという。
CTOとしてサステナビリティの推進で大切にしていることを尋ねると、芳野氏から「必要十分条件(※)」という言葉が返ってきた。
「生産技術の面から言えば安全管理が非常に大事になるが、安全をおろそかにして企業が存続することはできない。環境保全、従業員の労働・人権問題、そしてサステナビリティもその中の非常に大きな必要十分条件の一つ。なかったら、企業は存続できなくなる」
(※)ある事柄が成立するための必要にして十分な条件。 命題「AならばB」と命題「BならばA」が同時に成り立つとき、BはA(またはAはB)の必要十分条件という
関連記事
 アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略
アップルウォッチの脱炭素化、徹底ぶりがすごい BYDや白い恋人も“一石二鳥”の脱炭素×企業戦略
脱炭素化の実現に向け、各社が知恵を絞っている。アップルは最新のアップルウォッチで脱炭素化を図り、すでにCO2排出を8割近く減らすことに成功した。最先端企業の取り組みを見ていこう。 企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘
企業のサステナビリティ戦略、2024年のリスクと機会はどこにある? 4大コンサルファームが指摘
2024年、サステナビリティ経営をめぐる動向はどうなるか? 4大コンサルファームが、企業のサステナビリティ戦略の「リスクと機会」を分析した。 欧州の新サステナビリティ規制「CSRD」 日本の対象企業は約800社、今後の対応は?
欧州の新サステナビリティ規制「CSRD」 日本の対象企業は約800社、今後の対応は?
2024年1月1日から、欧州の大手上場企業およそ1万2000社を対象にサステナビリティ規制「CSRD」の運用が開始される。これは欧州に限った話ではない。日本企業にはどのような影響があるのか、解説する。 米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」
米国のイチゴ工場、200億円の資金調達 NTTや安川電機が認めた「日本人経営者」
米国で「イチゴ工場」を運営する日本人経営者が、シリーズBで200億円を調達した。投資家の期待の大きさが数字に表れている。世界初となる「植物工場でのイチゴの量産化」に成功したOishii Farmの古賀大貴CEOに話を聞いた。 パタゴニアが味噌や日本酒を売る真意 農業は脱炭素の切り札になるか
パタゴニアが味噌や日本酒を売る真意 農業は脱炭素の切り札になるか
© Hakuten Corporation All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング