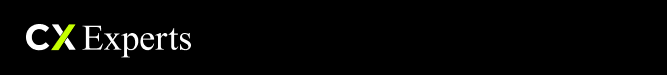なぜ「猫ミーム」は流行り続けているのか? ネットの最強コンテンツを分析:電通デジタルが読み解く、SNSマーケの最旬トピックス(2/2 ページ)
そもそも「ミーム」とは?
猫ミームは「猫+ミーム」なわけですが、そもそもミームとはなんでしょうか?
厳密には、リチャード・ドーキンス(進化生物学者)などが論じた「生物間で複製的に伝達される文化的な情報」ですが、そこから転じてインターネットミームは「ユーザー間で話題になり、さまざまなバリエーションを生み出すバズネタ」といったものを指すようになりました。
特にTikTokはミームを「ネット上でユーザーが真似やアレンジを重ねて楽しみながら広がっていくコンテンツ」と定義し、それが多様なUGCを生み出すことを強調しています。
まさに、猫のかわいらしくおもしろいシーンがグリーンバック素材化され、さまざまな動画に貼り付けられるコンテンツとなった結果、多くのユーザーが自分なりにアレンジして模倣的に広げていく余地を獲得したことで、世の中ごと化したミームへと育っていったわけです。
数年前に「いらすとや」が流行ったことの反復とも捉えられるでしょう。投稿数は本記事執筆時点で約10万件ほど。規模としても十分に大きいといえます。
猫ミームの素材をまとめてくれる下記のような動画も存在しています。
企業の活用事例も散見されます。例えばその会社の紹介を猫ミームでつくったり、猫ミームの素材を「中の人」が模して、それを動画にしたりしたものが見られました(おそらく、後者は著作権上の配慮から企業としてそのまま使うことは避けたものと推察されます)。堅苦しくないかたちで発信できるので、より興味関心を持ってもらいやすくなるというわけです。
企業・ブランドのコンテンツ発信の切り口として、SNSで話題になっているネタに便乗するという定石がありますが、まさにその考え方を応用したものだといえるでしょう。
猫ミーム以前の猫コンテンツたち
今日の話題コンテンツと言えば「猫ミーム」が上位にきますが、これまでも「猫」はネットの最強コンテンツでした。
2000年前後のギコ猫(アスキーアート)に始まり、2010年代にはニャンキャットや宇宙猫が流行り、仕事猫/現場猫も広くミーム化。スコティッシュフォールドの日常を配信する「もちまる日記」はYouTubeの登録者数が約215万人で、書籍も出版されるほどの人気ぶりです。
猫はその時代のメディア環境に適応するかたちで、常に最強のコンテンツとして君臨していることが分かります。日本ではペットとしての猫の飼育頭数は約906万頭で、犬(約684万頭)よりも圧倒的に多いです(「令和5年 全国犬猫飼育実態調査」PDFより)。身近にいる存在としての感情移入のしやすさがSNSの時代にフィットしているとも考えられそうです。
なお、私が以前に携わった調査では、自分のペットをSNSに投稿する「ペット好きさん」は全体の5%ほどを占めることが分かりました。もちろんペットとして飼っていない人であっても猫や犬のコンテンツをつくって発信することはできますが、ボリューム感を確かめる一助にはなるのではないでしょうか。
ネコノミクスは経済効果から私たちのマインドシェアまで
さまざまな社会現象の経済効果を試算してきた宮本勝浩氏(関西大学名誉教授)によれば、2024年の「ネコノミクス(猫にまつわる経済効果)」は約2兆4941億円に上るとのこと。
その額の大きさに驚くとともに、ネコノミクス=経済効果はもちろん、「猫のミーム」=SNSの話題化&ユーザーのマインドシェアを底上げする効果にも、いまいちど注目する必要があるのではないでしょうか。
本稿で見てきたように、猫コンテンツが定期的に(特に新しいメディアや表現形式が定着してきたときに)バイラルすることは歴史が証明しています。受け手としてはそれを期待し楽しむとともに、発信する側としては、次の山を狙ってみるのもよいかもしれません。
著者紹介:天野 彬(あまの あきら)
1986年生まれ。東京大学大学院学際情報学府修了(M.A.)。SNSのトレンドやマーケティング活用に関するリサーチ・コンサルティングが専門。電通デジタル プラットフォーム部門ソーシャルプラットフォーム部 兼 ソーシャルコネクトグループ所属。日経Think! エキスパートコメンテーター、明治学院大学社会学部非常勤講師。TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category審査員。主著に『新世代のビジネスはスマホの中から生まれる―ショートムービー時代のSNSマーケティング―』(2022年、世界文化社)。その他、『情報メディア白書』(共著)、『広告白書』(共著)など。
関連記事
 コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意
コンビニの25倍も売れる コカ・コーラも期待するドリンクが「銭湯」を主戦場に選んだ真意
コンビニよりも銭湯で売れるドリンクがあるのをご存じだろうか? 日本コカ・コーラが出資したリラクゼーションドリンク「CHILL OUT」だ。なぜあえて「銭湯」を主戦場に選んだのか、その真意を取材した。 5500円もするシャーペン、なぜ即完売? 三菱鉛筆「クルトガダイブ」の画期性
5500円もするシャーペン、なぜ即完売? 三菱鉛筆「クルトガダイブ」の画期性
三菱鉛筆のシャープペンシル「クルトガダイブ」が人気だ。店頭に並んだ瞬間、すぐに売り切れるという。ただ、価格は5500円と強気だ。シャープペンシルにしては高価だが、なぜこんなに売れているのか? リプトン ミルクティー、わずか1年で「元の味に戻します」 なぜ、異例の判断をしたのか?
リプトン ミルクティー、わずか1年で「元の味に戻します」 なぜ、異例の判断をしたのか?
2023年3月、森永乳業は1年前に刷新した「リプトン ミルクティー」を元の味に戻すという異例の判断をした。その背景にはどのような出来事や葛藤があったのか? 森永乳業の担当者に取材した。 レジ袋有料化の“二の舞”か プラ削減のために導入した「紙ストロー」が別の環境問題を引き起こすジレンマ
レジ袋有料化の“二の舞”か プラ削減のために導入した「紙ストロー」が別の環境問題を引き起こすジレンマ
2022年は「プラスチック削減元年」と言っても過言ではないほどに紙ストローが普及した。環境に配慮した取り組みのようだが、レジ袋有料化同様に紙のほうが本当に環境負荷が小さいのか? という疑問が消費者の中で渦巻いているように感じる。紙ストロー移行は本当に意味があるのかというと……
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング