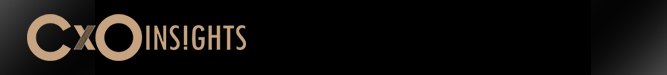なぜIT多重下請けは起こるのか? 日米“外注構造”とDXの違いから考える:クレディセゾンCTOとSHIFT技術顧問に聞く(1/2 ページ)
ITmedia デジタル戦略EXPO 2025冬
KDDIが経理のオペレーション改革にAIを活用し、得た成果とは。従来の業務プロセスから脱却を図る中で直面した課題、失敗と成功、今後の展望を語る。
GAFAなど米国の企業がITを駆使して成長を遂げてきたことを受け、多くの日本企業がそのノウハウを取り入れようとDXを推進してきた。米国の成功事例を見習おうとする取り組みといえる一方、日本と米国では、IT業界の成り立ちや発展してきた歴史に違いもある。
日米では、ITやDXに対する考え方がどのように違うのか。ソフトウェアの品質保証を軸にさまざまなDX事業を展開するSHIFTが2024年9月、同社の技術顧問を務める川口耕介氏と、クレディセゾンの小野和俊CTOが対談するイベント「SHIFT EVOLVE エンプラ企業DXの成功事例」を開催。日米のIT業界の違いや、DXの課題について議論した。
両氏はサン・マイクロシステムズ(現オラクル)に在籍していた共通点がある。川口氏は今でも米シリコンバレーを拠点に、CI/CDプラットフォームを開発するCloudBeesのco-head of AIを務めている。
日米のIT業界の違いは何か。DXなど技術部門への考え方の違いについて、川口氏と小野氏に聞いた。
 小野和俊(おの・かずとし)1999年サン・マイクロシステムズ株式会社に入社。米国 Sun Microsystems, Incでの開発などを経て2000年に株式会社アプレッソを起業、データ連携ミドルウェアDataSpiderを開発し、SOFTICより年間最優秀ソフトウェア賞を受賞。 2013年にセゾンテクノロジー HULFT事業CTO、2014年 他事業部も含めたCTO、2015年取締役 CTO、2016年常務取締役 CTOを務め、2019年に株式会社クレディセゾンへ入社。取締役 CTOなどを経て、2023年3月より現職
小野和俊(おの・かずとし)1999年サン・マイクロシステムズ株式会社に入社。米国 Sun Microsystems, Incでの開発などを経て2000年に株式会社アプレッソを起業、データ連携ミドルウェアDataSpiderを開発し、SOFTICより年間最優秀ソフトウェア賞を受賞。 2013年にセゾンテクノロジー HULFT事業CTO、2014年 他事業部も含めたCTO、2015年取締役 CTO、2016年常務取締役 CTOを務め、2019年に株式会社クレディセゾンへ入社。取締役 CTOなどを経て、2023年3月より現職 川口 耕介(かわぐち・こうすけ)Sun Microsystems, Inc.在籍中にCIツールの草分けJenkinsを開発。2019年、米CloudBeesにてCTOとして就任し、Jenkinsや関連サービス・製品の発展・普及を推進。同年、株式会社SHIFTの技術顧問に就任。2020年、AIを使って自動テストの効果を改善するサービスLaunchableを米国で立ち上げ、同サービスの日本法人Launchable Japanを設立。2024年、CloudBeesのLaunchable買収に伴い、CloudBeesの co-head of AIに就任
川口 耕介(かわぐち・こうすけ)Sun Microsystems, Inc.在籍中にCIツールの草分けJenkinsを開発。2019年、米CloudBeesにてCTOとして就任し、Jenkinsや関連サービス・製品の発展・普及を推進。同年、株式会社SHIFTの技術顧問に就任。2020年、AIを使って自動テストの効果を改善するサービスLaunchableを米国で立ち上げ、同サービスの日本法人Launchable Japanを設立。2024年、CloudBeesのLaunchable買収に伴い、CloudBeesの co-head of AIに就任日米IT産業構造の違い なぜ日本企業は内製化できなかった?
――日本企業は米国を見習う形でDXを推進している部分が大きいと思います。一方で、米国とはIT業界の産業構造が異なる部分もあります。この違いについてどのように見ていますか。
小野: 僕はサン・マイクロシステムズの米国本社に半年ほどいただけで、現地の事業会社にいたことはありません。ただ、よく指摘される違いとしては、IT技術者がいる場所にまず違いがある点があります。
米国の場合、7割のIT技術者が事業会社にいるといわれています。GoogleやAppleなどのテクノロジー企業はもちろん、金融や医療、小売などの企業も含めてです。これが日本だと、7割の技術者がNECや富士通などといったSIerにいるといわれています。
日本の事業会社では多くの場合、IT部門の社員はプログラミングのコードを直接書いているわけではありません。企業が外部の業者にシステム開発や運用などの業務を委託する際に、その業務全体の品質やコスト、納期やリスクなどを管理・監督するベンダーコントロールや、ユーザーとの対応、要件調整が業務になります。
プログラマーが事業会社の中におらず、その部分はSIerと協業することによって、システムを構築してきた経緯があります。
――ITに対して、日米には、内製と外注といった考え方の違いがあるということですね。
小野: このIT部門への考え方の違いが、1990年代以降の日米の、経営変革のスピードの違いを生んでいるようにも思います。日本企業は1989年の世界時価総額50社のうち、30社以上を占めていました。ところが約30年後の2018年になると、トヨタ自動車が20位台に入るだけになっています。
日本の「失われた30年」の背景には、やはりデジタルの変革をうまく取り入れられなかったことがあると思います。ITの力を事業にうまく使っていくことができなかったからだと思うんですよね。ERP(企業資源計画)の導入のような大型の取り組みにしても、コーポレート部門の仕事の一つという感覚でしか見ていなかったという話も聞きます。
その構造は、2000年代にインターネット社会が到来しても、2010年代にスマートフォン社会が到来しても、あまり大きく変わっていません。だから競争力が落ちているのだと思います。米国は7割のIT技術者が事業会社の中にいて、ビジネスの意思決定をしていますから、変革できているのだと思います。
クレディセゾンでは、この内製のIT技術者の数を増やすことによってDXを推進しています。
――日本の経営者はなぜ、IT技術者たちを社内に取り入れられなかったのでしょうか。
小野: 経営層が決してITを軽視していたわけではなく、社内でその変革を提案できる素地がなかったからではないかと思います。日本企業の人事制度は、総合職採用でいろいろな部門をローテーションするのが一般的です。総合職制度自体は一時代を築いたやり方なのでリスペクトすべきですが、一方でITに特化した技術者が社内で育たず、社内から提案がなかなか上がってこなかった背景が考えられます。
――近年ではCTOやCDOなど、上場企業の中でも経営層にIT関連のポジションを置く動きが盛んです。
小野: 企業内のボトムアップではなく、「デジタル担当役員が設置されているかどうか」ということがDX進捗を測る指標の一つになってきていることが外圧となり、トップダウンの動きとして加速してきていると感じます。ただ、その結果、今では「DXは待ったなし」になっていますから、変わってきているとはいえると思います。
川口: CTOなどの役職を設置しようとしても、結局はみんな手作りですから、何をすればいいか分からない部分もあると思います。うまく回っている成功例が広まることで変わっていくのではないでしょうか。
――日本ではITを外注する向きが強く、多重下請け構造にもつながっています。
川口: 米国では、目につく範囲だと多重下請け構造はあまりないですね。ないと言い切れるわけではないのですが。
小野: 多重下請け構造は、調達能力などの面で利点もあるとは思いますが、コードを書く人が二次請け三次請け、場合によっては六次請けとかになってしまっています。ダルマ落としに例えるなら、全体の設計をする人とコードを書く人の、ダルマの頭と下だけでも回るものが、間に企業が多く入っている構造になっているのです。そのため、発注する側の企業にとっては、本来なら最低限で済む金額と、実際に払う金額との間に、大きな乖離がある原因にもなっています。ただ一方で、日本のIT業界がそれで成り立ってきた現実も、受け止めるべきではあります。
こうなってしまった原因は明確にあって、企業がITに関する仕事の実体的な部分を(他社に)丸投げしてきたからです。ITのことがあまり分からないクライアントが、そのシステムの企画、設計、開発や運用までを全て外注し、SIer側も「承知しました」と言って全部やってくれる。企業側にとってみたら全部やってくれるから楽、ということになりますから、この構造を変えようという力が働きにくい状況が続いたのだと思います。
関連記事
 「ITの多重下請け構造は最悪」 エンジニアの“報酬中抜き”が許せないと考えた理由
「ITの多重下請け構造は最悪」 エンジニアの“報酬中抜き”が許せないと考えた理由
PE-BANKは日本でフリーランスの働き方が一般的ではない時代から、ITフリーランスエンジニアの働き方を支援するエージェント事業に取り組んできた。今回、所属するエンジニアのキャリア自律を支援する福利厚生サービス「Pe-BANKカレッジ」の提供を始めた。その理由を社長に聞いた。 「IT多重下請け」が生まれた背景 フリーランスを守る、共同受注の強みとは?
「IT多重下請け」が生まれた背景 フリーランスを守る、共同受注の強みとは?
フリーランスのITエンジニアと企業をつなぐエージェント事業を手掛ける1989年創業のPE-BANK(東京・港)の髙田幹也社長に、多重下請け構造が発生した背景や生成AIとエンジニアの関係について聞いた。 IT業界の「多重下請け地獄」が横行し続ける真の理由
IT業界の「多重下請け地獄」が横行し続ける真の理由
IT業界の多重下請け構造にはさまざまな問題があるとして、構造改革に取り組んでいるのが情報戦略テクノロジーだ。ソフトウェアの開発において、1次請けから3次請けまでのビジネスを経験してキャリアを築いてきた高井淳社長に日本のIT業界の課題と、同社が取り組む改革について前後編の2回にわたって聞いた。前編ではソフトウェア業界やシステム開発の問題点について聞いた。 IT業界の「多重下請け問題」を変える真の方法とは? 1次請けから3次請けまで経験した社長が提唱する「0次請け」
IT業界の「多重下請け問題」を変える真の方法とは? 1次請けから3次請けまで経験した社長が提唱する「0次請け」
IT業界で常態化している多重下請けが、日本のソフトウェア開発を米国や中国よりも遅れさせ、かつ、優秀なエンジニアが育たない状況を作り出している――。こんな危機感を持って、業界の構造改革に向けて取り組んでいるのが、東京都渋谷区に本社がある情報戦略テクノロジー。高井社長はIT業界で1次請けから3次請けまで経験している。その経験から、業界の構造改革のためには、企業の事業部門と直接ビジネスをする「0次請け」と、エンジニアのスキルシートの統一化が必要だと訴えている。 「IT多重下請け」の構造と解決策 やりがい搾取と「報酬中抜き」はなくなるか?
「IT多重下請け」の構造と解決策 やりがい搾取と「報酬中抜き」はなくなるか?
ITエンジニアやアニメ制作者らが抱えている「多重下請け構造」。この課題が社会問題となって久しい。発注者と受注者という立場の差が生み出した事象だ。TECH PLAY Company代表に多重下請け構造の課題を聞いた。 7pay問題に潜む病巣――日本のIT業界で是正されない「多重下請け構造」
7pay問題に潜む病巣――日本のIT業界で是正されない「多重下請け構造」
7pay問題は必ずまた起きる――。日本のIT業界の根本的課題である「多重下請け構造」という病巣に迫った。 ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと
ひろゆきが斬る「ここがマズいよ働き方改革!」――「年収2000万円以下の会社員」が目指すべきこと
平成のネット史の最重要人物「ひろゆき」への独占インタビュー。ひろゆきの仕事観・仕事哲学を3回に分けて余すことなくお届けする。中編のテーマは「働き方」――。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング