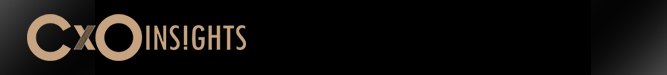講師も親も巻き込む「学研のDX」 AIは“教育事業の脅威”となるか?:学研の変貌(3)
学研HDは2021年12月、グループのDX推進を担う新会社「Gakken LEAP」(学研リープ)を設立した。背景には、従来の教育・福祉事業の枠組みを越え、デジタルやグローバル領域の専門人材・ノウハウを結集し、学研グループ全体の成長を加速させる狙いがある。
LEAPは設立から3年でエンジニアやマーケターなど50人以上を採用し、2025年までに200億円規模のデジタル投資を計画。学研教室の20万人規模の顧客基盤を生かしたDXや、社会人向けオンライン学習「Shikaku Pass」(資格パス)の開発、オンライン英会話のレアジョブとの資本業務提携など、次世代EdTechサービスを次々と展開している。
生成AI活用やデータベース一元化も積極的に進め、現場の業務効率化と新たな価値創出を両立。教育現場のデジタル化とAI活用によって、学研は「全世代・全領域」対応の新たな企業グループ像を描き始めている。
学研のDXや生成AI活用はどのように進むのか。教育業界特有の課題について、Gakken LEAP社長で、学研HDの細谷仁詩・取締役上席執行役員に聞いた。
 細谷仁詩(ほそや ひとし)株式会社学研ホールディングス 取締役/株式会社Gakken LEAP 代表取締役CEO。1986年生まれ。2008年にJPモルガン証券に入社し、株式調査部でアナリストとしての業務を経験。2013年にマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社、2020年同社パートナー就任。2021年に学研ホールディングス執行役員に就任、2022年に上席執行役員、2023年に取締役就任(現任)。2021年にはGakken LEAPを設立し、代表取締役CEOを務める(現任)。以下、撮影は河嶌太郎
細谷仁詩(ほそや ひとし)株式会社学研ホールディングス 取締役/株式会社Gakken LEAP 代表取締役CEO。1986年生まれ。2008年にJPモルガン証券に入社し、株式調査部でアナリストとしての業務を経験。2013年にマッキンゼー・アンド・カンパニーに入社、2020年同社パートナー就任。2021年に学研ホールディングス執行役員に就任、2022年に上席執行役員、2023年に取締役就任(現任)。2021年にはGakken LEAPを設立し、代表取締役CEOを務める(現任)。以下、撮影は河嶌太郎Gakken LEAP設立の背景とデジタル新会社の狙い
――Gakken LEAPはどのように設立したのですか? 新規事業やデジタル化を進めてきたのでしょうか。
Gakken LEAP設立の背景としては、やはりグループ内にデジタルやグローバル領域を専門的に担う組織や、それを牽(けん)引する人材がいなかったという課題がありました。そこで私が社長となり、2021年12月に新会社として立ち上げました。
当初は「DX」「AI」といったキーワードが先行し、各社が個別にDXを推進しようとしました。しかし、DXが目的化してしまい「コストばかりかかる」「現場で十分に活用されない」といった課題が目立ちました。
そこでLEAPでは、サービス化のアウトプットが明確で、実際に顧客につながる分野に注力する方針に切り替えました。例えば、学研教室の子どもや保護者向けのDXには特に力を入れています。学研教室は20万人規模の顧客基盤があり、ここでのデジタル化はグループ全体のDX推進の象徴的な取り組みとなっています。
学研グループの事業はこれまで子ども向け教育が中心でしたが、リカレント教育や社会人向けサービスにも本格的に参入し始めました。その代表例が「Shikaku Pass」(資格パス)です。社会人向けのオンライン資格学習サービスを自社開発し、学研が大人の学びにも本気で取り組んでいることを世の中に示したい狙いがありました。
――Gakken LEAPの人材戦略についてお聞かせください。
人材戦略は、LEAP設立以降、エンジニアやマーケターなど50人以上を採用しています。特徴的なのは、教育業界出身者がほとんどおらず、デジタルや経営の素養を持つ人材を積極的に採用している点です。この多様な人材が、教育業界の常識にとらわれず、新しいサービスや価値を生み出す原動力になっています。また、LEAPで活躍した人材を学研教室や経営戦略室などグループ内に派遣し、グループ横断的な人材交流・知見共有も進めています。
採用においては、教育業界や事業会社への転職にハードルを感じるプロフェッショナル人材でも、LEAPを経由することで安心感を持ってもらえるような仕組みづくりを意識しました。今後も、教育×プロフェッショナル領域の人材が、学研グループ全体の経営やデジタル変革を牽引していくことを期待しています。
最終的には、LEAPで培った人材やノウハウをグループ全体に還元し、教育業界や社会全体に貢献できる経営人材がどんどん増えていくことが理想です。学研グループとしても、子どもから大人まで、そして教育から福祉まで、全世代・全領域で価値を提供できる企業グループを目指していきます。
「学研出身」経営者こそ最大のブランディング
――Gakken LEAPのような組織に集まる人材は、まさにキャリアの掛け算を体現している印象です。教育と他分野の掛け算によって新しい価値を生み出す、そうした人材がこれからさらに増えていきそうですね。
その通りです。例えばマッキンゼー・アンド・カンパニーのブランドがなぜ強いかというと、現役コンサルタントの実像を知らなくても、「東大首席クラスしか入れない」といった入口のブランディングと、南場智子さん(ディー・エヌ・エー会長)や茂木敏充さん(自民党前幹事長)のような活躍している卒業生を多数輩出している出口のブランディングの両方を確立しているからです。
企業として本当に重要なのは、優秀な人材を社会に輩出し続けることだと考えています。ですから、Gakken LEAPや学研出身の経営者が社会で活躍し、「学研出身」と経歴に書かれること自体が誇りになるような、そんな存在になってほしいと強く思っています。むしろ卒業して、外で成功してくれることこそ、企業としての最大のブランディングだと考えています。
――現在の「資格パス」や学研IDを中心とした顧客接点の状況についてはいかがですか。
事業としては順調に伸びています。学研IDの成長に伴い、資格パスも利用者が増えていますし、市場全体もアナログからデジタルへの転換が進んでいるため、その流れに乗っている部分も大きいです。特に2024年11月に発表したレアジョブとの資本業務提携は大きな転機でした。
レアジョブは英語だけでなく資格分野にも強みがあり、今後はオンライン資格取得でナンバーワンを目指す明確な目標を掲げています。これまで関係がなかった領域とも連携できるようになったのは、資格パスを立ち上げた大きな成果の一つだと感じています。
デジタイゼーションから始める教育現場の変革
――グループ全体のDX推進について、特に難しさを感じる部分はどこでしょうか。
DXを「目的化」してしまうと、現場はなかなか動いてくれません。例えば「このアプリを使ってください」「進捗管理をしてください」と言っても、現場の講師やスタッフは使いません。自分の授業や仕事がある中で、余計な手間が増えることを、本音として避けたいのです。実際、オンライン学習サービスや外部システムを導入しても、現場で活用されないことが多々ありました。
この経験から、グループ戦略や本社主導の“自己満足型DX”はやめました。現場や顧客目線で「本当に必要とされるDX」に集中することが大切だと痛感しています。例えば、学研教室では「今、子どもが教室に来ているかどうか」「どんなプリントをやっているか」といった情報を電子化し、保護者と先生の間のブラックボックスを解消するシンプルな仕組みを導入しました。これにより、保護者は「今来ました」「今帰りました」といった情報がすぐに分かるようになりました。
また、先生との面談予約もアプリで完結できるようにし、保護者の利便性を高めています。さらに、週2回の通塾が難しい家庭には、Zoomを使ったオンライン学習も選択肢として提供しています。こうした現場の課題や顧客の声に寄り添ったDXが、最も効果的で持続的だと考えています。今後も、現場・顧客の視点を最優先に、グループ全体のDXを推進していきたいと思います。
――現状は業務の電子化の「デジタイゼーション」が中心で、本来的な意味でのDXはまだ道半ばといった感じでしょうか。
その通りです。まずはデジタイゼーションを進めないと、その先の本格的なDXには到達できません。特に教育分野では、なぜ勉強するのかという目的が明確で、例えば小学校高学年以降は受験が主目的になります。しかし、受験の仕組み自体が大きく変わらない限り、デジタイゼーションやDXの意義を保護者や子どもたちに納得してもらうのは難しい部分があります。
仮に中学受験が完全にCBT(Computer Based Testing)になり、AIを活用した問題解決が当たり前の世の中になれば状況は変わるかもしれませんが、現状では私たちが解いてきた国語や算数とほぼ同じ内容です。だからこそ、DXを目的化しても意味がない。むしろ講師の手間を省く、業務を簡素化するという観点で、まずはデジタイゼーションを進めているというのが実態です。
AIエージェント活用と競争力強化のための環境整備
――AI活用について、どのようにお考えですか。
AIについては、人によって見方や期待値が大きく異なる分野だと思います。私は教育業界における第1次DXブームを肌で経験してきましたが、やはりAIも「目的化」してしまうと現場には浸透せず、コストばかりかかると実感しました。ですから、AIを導入すること自体をゴールにするのではなく、「社員一人一人がAIを自分の業務効率化のために自然に使いこなせるようになること」こそが、まずは最低限の第一ステップだと考えています。むしろ、それが達成できれば十分だと思うくらいです。
今やソフトウェア開発やアプリ開発の現場では、エンジニアが当たり前のようにAIを活用していますし、社内でもChatGPTやGeminiなどを使って業務の効率化を図っています。AIを使っているからといって、急に頭が良くなるわけではありません。
大切なのは、AIを「自分の秘書」のように使えるかどうか。例えば、会議の録音データをAIで整理して論点ごとにまとめる、塾講師が宿題や問題作成、採点などにAIを使って業務時間を短縮する。こうした「現場で本当に楽になる」使い方が一番のゴールだと考えています。
また、「AIエージェント」としての活用が、社員全員に浸透することが理想です。顧客の方がむしろ早くAIを使いこなす時代が来るでしょうから、社員がいち早くAIを使いこなせるようになることが、今後の競争力の源泉になるはずです。実際、当社でもOpenAIのサービスを使い、クローズドな環境で「GENESYS」(ジェネシス)というAI活用基盤を構築し、全社員がAIを使える環境づくりを進めています。
もう1つ重要なのは、グループ全体のデータベース一元化です。現在、出版は4社、塾は10数社、教材開発は出版社の文理などが独自に手掛けています。教材やコンテンツのデータが一つに集約されることで、著作権を管理しながら二次・三次利用が可能になります。例えば「小学3年生の5月に出す算数の練習問題10問を作って」とAIに指示すれば、一瞬で生成できるような世界です。今までは講師が自分で数字を変えたり工夫したりして作っていましたが、AIとデータベースの活用によって、こうした業務も大きく効率化できると考えています。
最終的には、まず自分たちの社員がAIを自然に活用できる環境を整え、その上で業界や社会の進化についていくことが、今後の学研グループの成長にとって非常に重要だと考えています。
「現場最適と全体最適化」のジレンマ デジタル活用の課題
――学研の現場ではデジタル活用が進んでいても、現場ごとの部分最適にとどまってしまい、全体最適やナレッジの横展開が難しいという課題もあるのではないでしょうか。
その通りです。今は現場ごとにデジタルリテラシーも高く、Slackなども現場で工夫しながらどんどん使っています。しかし、テクノロジーの進化が速すぎて、中央で「この使い方をしなさい」と指示しても現場のスピードに追いつきません。むしろ現場が自発的に使うのが一番良いのですが、そうすると部分最適にとどまり、ナレッジが全社に広がりません。結果として、あるプロセスだけが良くなっても、全体のスループット(一定期間における処理能力)は変わらないジレンマがあります。
また、例えば介護士がAIやデジタルによって介護日誌作成の時間が1時間から3分に短縮できたとしても、その分早く帰れるわけではありません。むしろ空いた時間で他の仕事をしてもらうことになる。人手が足りているわけではないので、業務効率化が即コスト削減には直結しません。
むしろ、離職率が下がる、働きやすくなるといった副次的な効果の方が大きいと感じています。KPIとして「コストが下がったか」「合格実績が上がったか」といった成果を直接求めるのは、現実的ではないと思います。
――逆に、AIが事業の脅威となる懸念はありますか。
それは十分にあり得ると思っています。これまで生徒を惹きつけてきたのは、やはり講師の人間的な魅力やモチベーションアップの力が大きいです。しかし、もし子どもたちがオンライン上で自分に合ったAI講師を見つけ、しかもそのAIが人間と同等の指導力を持つようになれば、リアルな塾に通う価値観自体が変わってしまうかもしれません。
そのため、私たちは「学研オンエア」という100%オンラインのサービスも展開しています。今は人間の講師が担当していますが、将来的にはアバターやAI講師が担当することも十分に想定しています。どんな価値観を持つ子どもが現れるか分からない時代ですから、そうした多様なニーズに応えられる場を用意しておくことが重要だと考えています。
AIとの対話が当たり前になる時代の「人間の役割」
――AIとの対話やアバターによるコミュニケーションが一般化した場合、人間の役割はどう変わると思いますか。
私自身はまだ人間味を大事にしていますが、人によってはアニメキャラクターと対話するのが心地よいという人もいます。子どもたちの中にも、学校で友達と話すのが苦手な子や、アバターから勉強を教わる方が安心できる子もいるでしょう。そうした多様な価値観や学び方に対応できる教育サービスを提供することが、今後ますます重要になると感じています。
――こうしたAIとの関係性や新しい学びの形が広がる中で、今後の教育サービスの在り方についてはどう考えていますか?
AIやアバター的なサービスを批判するつもりはありません。むしろ、そうしたニーズが生まれてきたこと自体を肯定的に捉えています。今のオンライン英会話業界のように、新しいプレーヤーがどんどん登場するでしょうし、われわれもそうした動きに柔軟に対応していく必要があります。時代のトレンドやニーズに抗うことなく、対応できる範囲で自分たちのポートフォリオを広げていくことが自然体だと思っています。
――YouTubeやSNSなどを駆使して、若い世代が自ら学びに向かう動きも活発です。こうした無料コンテンツとの競合についてはどう考えますか。
結局、EdTechやデジタルサービスを突き詰めていくと、最大の競合はYouTubeやSNSといった無料コンテンツになると思っています。どれだけ資金調達しても、SNSや無料の動画コンテンツには勝てない部分があります。リアルの場も依然として重要ですし、両方の強みを生かす必要があります。実際、塾に通いながら帰り道でYouTubeを見るなど、フリーコンテンツとリアルな学びを使い分けている子どもがほとんどです。
ですから、当社もフリーコンテンツを作り、リアルの場も強化し、その中間に位置するアバター型サービスやAIを活用した新しい学びの形にも積極的に取り組んでいきます。子どもたちの学び方は一つではなく、気分や時間によってさまざまなサービスを使い分けています。だからこそ、どんなニーズにも対応できる柔軟なサービス展開が必要だと考えています。
――AIとの共感や双方向性、無料コンテンツとの競争など、教育の現場は大きく変わってきていますね。
はい。AIが「共感」や「承認」を与える存在になりつつあり、教育現場でもAIを前提とした新しい評価基準や学びの形を模索しています。われわれも、時代の変化や多様なニーズに自然体で対応しつつ、リアルとデジタル、無料と有料、あらゆる学びの選択肢を提供できる存在でありたいと思っています。
連載「学研の変貌」1回目は【学研、介護事業が「30%成長」の原動力に 「M&Aの成否」を分けるのは?】、2回目は【学研HD新体制の舞台裏 コンサル出身経営者が挑んだ「ブランド統合とDX」】からお読みいただけます。
この記事を読んだ方に AI活用、先進企業の実践知を学ぶ
ディップは、小さく生成AI導入を開始。今では全従業員のうち、月間90%超が利用する月もあるほどに浸透、新たに「AIエージェント」事業も立ち上げました。自社の実体験をもとに「生成AIのいちばんやさしいはじめ方」を紹介します。
- 講演「従業員の生成AI利用率90%超のリアル! いちばんやさしい生成AIのはじめかた」
- イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2025夏」
- 2025年7月9日(水)〜8月6日(水)
- こちらから無料登録してご視聴ください
- 主催:ITmedia ビジネスオンライン
関連記事
 学研、介護事業が「30%成長」の原動力に 「M&Aの成否」を分けるのは?
学研、介護事業が「30%成長」の原動力に 「M&Aの成否」を分けるのは?
学研グループの2024年度のグループ売上高は1855億円に達し、そのうち医療福祉分野が約900億円と全体の半分弱を占めるまでに成長した。この急成長の背景には、積極的なM&A戦略の展開がある。M&Aを牽引する学研HDの細谷仁詩・取締役上席執行役員にインタビューした。 学研HD新体制の舞台裏 コンサル出身経営者が挑んだ「ブランド統合とDX」
学研HD新体制の舞台裏 コンサル出身経営者が挑んだ「ブランド統合とDX」
学研ホールディングスでも2021年4月、マッキンゼー・アンド・カンパニー出身の細谷仁詩氏が取締役上席執行役員に就任した。コンサル出身経営者が、なぜ学研の現場で新たな挑戦をしようと考えたのか。 「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
「NECのイベント」に富士通社員も登壇 オープンイノベーションに本腰を入れたワケ
NECが、オープンイノベーションに本腰を入れている。NEC Open Innovation Nightには富士通の社員も登壇。同社の取り組みの真意に迫る。 孫正義「SBGで10億のAIエージェントを作る」 生成AIが「自己増殖する仕組み」構築へ
孫正義「SBGで10億のAIエージェントを作る」 生成AIが「自己増殖する仕組み」構築へ
ソフトバンクグループ(SBG)会長兼社長でソフトバンク取締役創業者の孫正義氏は7月16日、ソフトバンクが都内で開いた法人向けのイベントで「グループ全体で年内に10億のAIエージェントを作る」と宣言した。 「SaaSが終わる? 興味ない」 ラクス社長が語るAIの「真の脅威」
「SaaSが終わる? 興味ない」 ラクス社長が語るAIの「真の脅威」
国内SaaS業界トップランナーのラクス。「SaaSが死ぬかどうかってそんなに興味ない」と明かす中村崇則社長が、本当に恐れているものとは何なのか。業界トップが明かすAI時代の生存戦略を聞いた。 AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
AI競争は「Googleの圧勝」で終わるのか? Gemini 2.5 Proの衝撃
米国のテック系人気ユーチューバーの何人かが、こぞって「AI開発競争はGoogleが勝利した」という見出しの動画をアップしている。これでGoogleの勝利が決定したのかどうか分からないが、少なくともOpenAIの首位独走の時代は終わったのかもしれない。 なぜ日立はDXブランドの“老舗”になれたのか? Lumada担当者が真相を明かす
なぜ日立はDXブランドの“老舗”になれたのか? Lumada担当者が真相を明かす
連載「変革の旗手たち〜DXが描く未来像〜」では、各社のDXのキーマンに展望を聞いていく。初回は日立製作所。なぜ日立は2016年の段階で、ブランドを立ち上げられたのか。Lumadaの推進に関わる、デジタル事業開発統括本部の重田幸生さんと、Lumada戦略担当部長の江口智也さんに聞いた。 なぜ富士通「Uvance」は生まれたのか サステナビリティに注力する強みに迫る
なぜ富士通「Uvance」は生まれたのか サステナビリティに注力する強みに迫る
DXブランドが乱立する中、DXだけでなくSX(サステナビリティ・トランスフォーメーション)も打ち出し、着実に成長してきたのが、富士通が2021年に立ち上げた「Fujitsu Uvance」だ。なぜSXを掲げ続けているのか。ユーバンスの事業戦略責任者に聞いた。 NEC「ブルーステラ」誕生の舞台裏 コンサル人材を自社で育成する強みとは?
NEC「ブルーステラ」誕生の舞台裏 コンサル人材を自社で育成する強みとは?
NECが5月、新たなDXブランドとして価値創造モデル「BluStellar」(ブルーステラ)を立ち上げた。なぜ新たにブランドを設立したのか。その強みは? NECマーケティング&アライアンス推進部門長の帯刀繭子さんに聞いた。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング