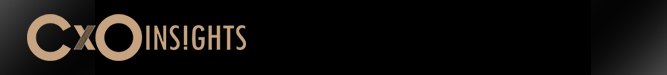「貧乏人の食べ物だ」 “スープの巨人”キャンベル社が防げなかった「顧客蔑視」の末路
【注目】ITmedia デジタル戦略EXPO 2026冬 開催決定!
学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ
【開催期間】2026年1月27日(火)〜2月25日(水)
【視聴】無料
【視聴方法】こちらより事前登録
【概要】学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。
「通報者は守られる」という言葉を、果たしてどこまで信じていいものだろう。
2025年、誰もが知る大企業で、内部通報をきっかけに解雇されたとする元従業員が裁判を起こした。このニュースは瞬く間に全米を駆け巡った。問題は、単なる解雇の不当性だけではない。訴状に記された、耳を疑うような幹部の発言だった。
「貧乏人のためのクソみたいな食べ物」
これは、注目を集めたいインフルエンサーが放った毒舌でも、ライバル会社が裏で流した中傷でもない。赤と白のラベルでおなじみの「スープの代名詞」、ザ・キャンベルズ・カンパニー(The Campbell's Company)の副社長(当時)であるマーティン・バリー氏が口にしたとされる言葉である。
事の始まりは2025年11月、キャンベル社の元社員ロバート・ガルザ氏が裁判所に提出した訴状だった。
給与の相談のために行われた面談の中で、当時の副社長マーティン・バリー氏は、自社製品を「誰がこんなクソを買うんだ」と嘲笑ったとされる。さらに、製品の中身についても「3Dプリンターで作られた鶏肉だ」などとうそぶき、自分はほとんど口にしないと語った。さらに、インド系の従業員に対する差別的な言葉や、仕事中にマリファナ入りの食品を食べてハイになっているという自慢話までされたという。
ガルザ氏は、この耐えがたい状況を会社に報告し、正そうとした。しかし、彼を待っていたのは解決の手差しではなかった。具体的な対応は何一つ取られず、通報からわずか20日後に会社を解雇されたのである。
ガルザ氏は一連の発言を録音していた。一方、キャンベル社は訴訟によって初めてその録音データの存在を知ることになる。ここから始まる同社の対応は、有事における企業対応のケーススタディとして極めて示唆に富んでいる。時系列で追ってみよう。
揺れ動く巨大企業の、迷える「7日間」
11月20日 訴訟提起と第一報
ガルザ氏が裁判所に訴状を提出し、これをテレビ局がスクープとして報じた。報道が出ると、同社は「もし報道が正確であれば、録音されたコメントは容認できないものだ。現在、積極的に調査を行っている」と第一報となる声明を出した。
11月24日 メディアへの防衛的なコメント
同社の広報担当者がメディアに対し、「念頭に置いてほしいのは、問題の発言をしたのはIT担当者であり、当社の食品製造には一切関わっていないことだ」とコメント。
11月25日 反論と「3D鶏肉」への対応
同社の広報担当者がメディアに対し、告発者であるガルザ氏の解雇について「正当な理由があって解雇された」とコメント。問題発言をしたマーティン・バリー副社長が同社を退職した(解雇された)ことが確認される。
Webサイトに「鶏肉についての真実」(The Facts About Our Chicken)という特設ページを公開し、「私たちは3Dプリンターで作られた鶏肉は使用していません」と製品の品質に関する噂(うわさ)を否定した。
11月26日 声明の更新とSNS発信
Webサイト上の声明を更新し、録音の声がバリー氏のものであると認めた上で、「コメントは野卑で不快かつ虚偽であり、引き起こされた苦痛に対して謝罪する」と表明。同時にFacebook、Instagram、TikTokに全て同一の定型文のコピペでメッセージを投稿した。
11月27日 CEOによる直接謝罪
ミック・ビークハイゼンCEOが84秒間のビデオメッセージを公開。バリー氏の発言について「私たちの食品、顧客、従業員に対する誤った攻撃的なコメント」とし、「キャンベルの視点や価値観、そして私自身の考えを代表するものではない。このような行為は容認しない」と断言。「これらのコメントが引き起こしたあらゆる傷に対して謝罪したい」と述べた。
冷ややかだった市場の反応 対応の何がいけなかったのか?
対応の初動(最初の4日間)において、同社は元社員の解雇の正当性を主張したり、発言者がIT部門であることを強調したりするなど、防衛的な姿勢が目立った。その後、製品に関するデマ(3Dプリンター肉など)の否定に注力し、最終的にCEOが登場して包括的な謝罪をするまでに問題の発生から1週間を要した結果になる。
謝罪ビデオに対する市場の反応は冷ややかだった。
内容は適切だが、タイミングが遅すぎるという評価が大半となった。PR専門メディア「PR Daily」は、「謝罪の内容はよかったが、タイミングがあまりにも遅すぎた」と評した。
特に問題視されたのは、ブルームバーグのコラムニスト、ベス・コウィット氏も指摘するように、会社が当初「食品の防衛」(製品の正当性)に力を入れすぎた点にある。
ここで、同社の置かれている経営環境はどうだったか見てみたい。
2026年度の見通しについて、ビークハイゼンCEOは、消費者の食品選びの慎重化、インフレ、関税によるコスト増への懸念を表明していた。経営陣は「プレミアム化」や「家庭料理への回帰」を成長戦略に掲げていたが、足元では販売数量が落ち込んでいた。また、同社の株価は長期的に低迷しており、今回のスキャンダル発生時には5年来の安値水準で取引されていた。
つまり、インフレに苦しみ、安いものを求める消費者の支持を取り戻すことが喫緊の課題だったのである。その矢先に飛び出した「貧乏人のための〜」という発言は、同社の顧客層の矜持(きょうじ)を傷つける好ましくないタイミングでの失言だった。
こうした状況下で、同社は結果として「技術的な正しさ」(製品の品質)の防衛に終始し、「感情的な信頼」(顧客への敬意)の回復を後回しにしてしまったように世間から見えた。
コミュニケーション戦略に生かす「3つの教訓」
では、今回の事案から、企業のコミュニケーション戦略に携わる者は何を学ぶべきか。実践に生かせる3つの柱でまとめたい。
1. オンラインという「主戦場」を直視する
ピュー・リサーチ・センターが2025年9月25日に発表した「Social Media and News Fact Sheet」によると、米国の成人の約半数(53%)が、少なくとも時々はソーシャルメディアからニュースを得ていると回答している。にもかかわらず、キャンベル社のSNSは炎上の最中活用されなかった。特に拡散力の高いX(旧Twitter)に至っては、2023年6月以来、投稿が止まっていたことが指摘されている。
情報の拡散スピードが極めて速い現代では、SNSこそが情報の主戦場となる。今回のキャンベル社の対応を振り返ると、オンライン上での初動の鈍さが、結果として事態の深刻化を招いた一因と言わざるを得ない。企業が沈黙している間に、SNS上では独自の解釈や批判が固定化されてしまうため、公式な見解を迅速に発信することが、負の連鎖を止める手段となる。
2. 事実(スペック)以上に、誠実さ(バリュー)を示す
危機に陥った際、企業は往々にして「手続きに不備はなかった」「法律的には問題ない」といった論理的整合性、いわば「スペック」の正当性を主張しがちだ。しかし、世論が注目しているのは、その企業の「姿勢や価値観」である。
事実として正しくても、不誠実だという感情的な印象を与えてしまえば、ブランドへの信頼は失墜する。具体的には、事実関係の調査を待たずに「まずは懸念を抱かせたことへの謝罪」を表明し、企業の倫理観を前面に出して対話に臨むことが、感情的な対立を鎮める。
キャンベル社は、「3Dプリンター肉」という事実無根のデマに対しては、迅速に反論の証拠を集めた。しかし、最も深刻だった「顧客蔑視」に対する謝罪とフォローは、製品の弁護に比べて希薄だった。危機発生時、「事実に反論すること」と「感情をケアすること」を完全に切り分ける。ブランドの核となる顧客層が侮辱された場合、必要なのはスペック表の提示ではなく、「私たちはあなたたちを誇りに思っている」という価値観の再表明である。
3. 内部通報制度の「実効性」を文化として根付かせる
裁判沙汰になるような事態は、制度の形骸化が招くものがある。「通報窓口がある」という形式的な事実だけでは不十分であり、通報者が報復を恐れずに声を上げられる文化があるかどうかが問われる。これを実現するためには、通報があった際、経営層が自ら「この問題は真摯に受け止めるべき課題である」という明確なメッセージを社内外に発信し続ける必要がある。
通報内容を単なる「火種」として処理するのではなく、組織を改善するための「資産」と捉え直すことが、結果として法的リスクを最小限に抑えることにつながると考える。
誰に寄り添い、何を最優先に守ろうとしているか
問題が発生した際、「何が正しいか」という事実を証明することは不可欠。しかし、それ以上に重要なのは、「企業が誰に寄り添い、何を最優先に守ろうとしているか」という姿勢を世に示すことだと考える。
今回のケースにおいて、キャンベル社は自社製品の正当性を主張することに終始してしまったように見受けられた。本来であれば、不安を感じている「顧客」や、組織の改善を願って声を上げた「人」に寄り添う姿勢を見せる方が賢明だったかもしれない。
通報者を守れなかったという事実が本当なら、組織が「人」よりも「保身や体制」を優先したとして、社会に記憶されるリスクがある。危機の渦中にあるときほど、企業は「この発信は世間にどう映るのか」という第三者視点を持ち、自社の倫理性がどこを向いているかを常に自問自答したい。
【イベント情報】学研が挑む"真のDX"
学研グループは、DXを目的化するのではなく、現場と顧客にとって“本当に使われるデジタル”を出発点に教育価値のアップデートに挑戦しています。本講演では、現場で浮き彫りになった課題や、実際に行ってきた改善や仕組みづくり、そこで得られた知見がどのように学研のDX推進を形づくんできたのかをお伝えします。既存のデジタル活用の成果と学びを振り返りながら、学研が目指す“真のDX”の姿をご紹介します。
- 講演「学研が挑む"真のDX"──「本当に使われるデジタル」で目指す教育価値のバリューアップ」・イベント「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 冬」
- 2026年1月27日(火)〜2月25日(水)
- こちらから無料登録してご視聴ください
- 主催:ITmedia ビジネスオンライン
関連記事
 アサヒ、アスクルに学ぶ サイバー攻撃後に「信頼を落とさない会社」がやっていること
アサヒ、アスクルに学ぶ サイバー攻撃後に「信頼を落とさない会社」がやっていること
アサヒグループホールディングスやアスクルを事例に、サーバ攻撃後に「信頼を落とさない会社」がやっていることを分析してみた。 サントリー新浪前会長は、なぜ「無罪推定」の段階で辞任したのか?
サントリー新浪前会長は、なぜ「無罪推定」の段階で辞任したのか?
サントリーの新浪剛史前会長が突然の辞任を発表した。捜査はまだ進行中。起訴も判決も下っていない。刑事法の原則でいえば「無罪推定」の段階だ。それでもなぜ、経営トップは早々に職を退いたのか? 日テレの「何も話さない」会見は必要だった? 国分太一氏降板に見る企業のリスク判断軸
日テレの「何も話さない」会見は必要だった? 国分太一氏降板に見る企業のリスク判断軸
6月20日に日本テレビが開いた記者会見。こうした会見の在り方が企業にとってどのような意味を持つのか、記者会見の設計において“語らない”という選択がどう受け止められ、実務にどう生かせるかを、危機管理広報の視点から掘り下げる。 フジテレビの「3つの判断ミス」 信頼回復への新セオリー
フジテレビの「3つの判断ミス」 信頼回復への新セオリー
フジテレビ問題は、社会に深く根付いた「人権リスク」の存在を、図らずも白日の下にさらけ出した。危機管理の観点から一連の出来事と対応を検証する。 時事通信社カメラマン「支持率下げてやる」騒動 社員の不適切発言を防ぐ方法は?
時事通信社カメラマン「支持率下げてやる」騒動 社員の不適切発言を防ぐ方法は?
時事通信社の男性カメラマンによる「支持率下げてやる」「支持率が下がるような写真しか出さねぇぞ」との音声が、生配信の映像に入ってしまった。社員の不適切発言を防ぐために経営層が取るべき方策とは? フジテレビの「ガバナンス不全」 日枝久氏の「影響力」の本質とは?
フジテレビの「ガバナンス不全」 日枝久氏の「影響力」の本質とは?
フジテレビ問題の今後の焦点は日枝久氏の去就だ。フジテレビのガバナンスに焦点を当てて検討してみたい。 「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
「これさぁ、悪いんだけど、捨ててくれる?」――『ジャンプ』伝説の編集長が、数億円を費やした『ドラゴンボールのゲーム事業』を容赦なく“ボツ”にした真相
鳥山明氏の『DRAGON BALL(ドラゴンボール)』の担当編集者だったマシリトこと鳥嶋和彦氏はかつて、同作のビデオゲームを開発していたバンダイに対して、数億円の予算を投じたゲーム開発をいったん中止させた。それはいったいなぜなのか。そしてそのとき、ゲーム会社と原作元の間にはどのような考え方の違いがあったのか。“ボツ”にした経緯と真相をお届けする。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR注目記事ランキング