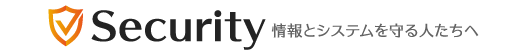VMware vSphere環境を狙うバックドア「BRICKSTORM」の脅威とは?:セキュリティニュースアラート
中国が支援する脅威アクターが使うバックドア型マルウェア「BRICKSTORM」に関する分析報告をCISAらが公開した。VMware vSphere環境を標的に長期潜伏し、高度な暗号化通信や横移動機能を備える実態が示されている。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
米国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁(CISA)は2025年12月4日(現地時間)、「BRICKSTORM」と呼ばれるバックドア型マルウェアに関する分析報告を公開した。
報告はCISAや米国家安全保障局(NSA)、カナダサイバーセキュリティセンター(CCCS)らが共同で作成しており、中華人民共和国の国家支援を受けた脅威アクターが長期間にわたって被害組織のシステムに潜伏する手段としてBRICKSTORMを活用しているという。
高度な秘匿通信と持続性を持つ「BRICKSTORM」バックドアの実態
BRICKSTORMはプログラミング言語Goで作成されたカスタムELF形式のバックドアで、今回分析したサンプルはいずれも「VMware vSphere」環境(「vCenter」サーバおよびESXi)を対象にしていた。
分析によると、各サンプルはステルス性の高い持続的アクセスや初期化処理、環境設定、暗号化通信による指令送信などの機能を備えていた。コマンド&コントロール(C2)サーバとの通信にはHTTPS、WebSocket、ネスト化したTLS、DNS-over-HTTPS(DoH)など複数の暗号化手法が使われており、正規通信に溶け込む構造が確認されている。リモートシステム制御としてはインタラクティブシェルの提供やファイル操作などを提供し、一部のサンプルではSOCKSプロキシによる横移動支援などが実施されていた。
CISAが対応したある被害組織では、2024年4月に中国支援の脅威アクターによる内部ネットワークへの不正アクセスが始まり、内部のvCenterサーバにBRICKSTORMが配置された事例が確認されている。攻撃者はその後、ドメインコントローラー2台およびADFSサーバに不正アクセスし、暗号鍵の取得までしていた。これらのアクセスは2025年9月初旬まで継続した形跡が示されている。
報告では侵入直後にDMZのWebサーバに設置したWebシェルを足掛かりに、RDPやSMBを利用して複数の内部サーバに横移動を進めた背景を説明している。サービスアカウントの認証情報を悪用した動きも複数確認されているが、その一部は入手経路が不明とされている。vCenter到達後は権限昇格をし、/etc/sysconfig/配下にBRICKSTORMを投入した上で初期化スクリプトを改変し、起動プロセスに組み込んでいた。
分析された複数のサンプルにおいて、自己監視機能によって稼働状態が途切れた際に自動的に再インストールや再起動をする仕組みが確認されている。環境変数を使った親子プロセスの判定や、正規の格納パスから実行されているかどうかを判断する仕組みも共通しており、削除や妨害が起きても動作を保持できる設計となっていた。
通信の確立方法はサンプルごとに差異があるが、DoHを使ったC2アドレスの秘匿解決、WebSocket Secure接続、TLSの多層利用、トンネリングの多重化などが共通点として挙げられている。特定のサンプルでは仮想環境用にVSOCKによる通信機能が実装され、仮想マシン間で秘匿経路を形成し、データ流出や内部移動を容易にしていた。
CISAとNSA、CCCSは、レポートに含まれるセキュリティ侵害インジケーター(IoC)や検知ルール(YARAおよびSigma)を活用し、不審な挙動が確認されている場合、速やかに関係当局に通報するよう求めている。加えて、VMware vSphereの更新やネットワーク境界装置の把握、DMZから内部への不要な接続遮断、サービスアカウントの最小権限化、DoH通信の制御など、複数の防御策を提示している。
関連記事
 サイバー攻撃よりシンプルな脅威 北大で起きた“アナログ侵入”の教訓
サイバー攻撃よりシンプルな脅威 北大で起きた“アナログ侵入”の教訓
「また情報漏えいか」と思った人ほど見過ごしてはいけないインシデントが起きました。なんと犯行はネット経由ではなく“目の前のPCを直接操作された”という極めてアナログな手口。原因を踏まえつつ教訓を探しましょう。 ランサム被害の8割超が復旧失敗 浮き彫りになったバックアップ運用の欠陥
ランサム被害の8割超が復旧失敗 浮き彫りになったバックアップ運用の欠陥
ランサムウェア被害の深刻化を受け、バックアップの実効性が事業継続の要として再び注目されている。ガートナーは形式的な運用だけでなく、復旧力と連携を重視した戦略的見直しが不可欠と警鐘を鳴らしている。 復旧できない「7割の企業」で何が起きている? ランサムウェア被害からの“復旧力”を考える
復旧できない「7割の企業」で何が起きている? ランサムウェア被害からの“復旧力”を考える
ランサムウェアが猛威を振るっています。被害を受けた企業のシステム停止はなぜ長引くのでしょうか。侵入を前提とせざるを得ない時代に入った今、企業に求められる“復旧力”の構成要件とは。 「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新
「英数・記号の混在」はもう古い NISTがパスワードポリシーの要件を刷新
NISTはパスワードポリシーに関するガイドラインSP800-63Bを更新した。従来のパスワード設定で“常識”とされていた大文字と小文字、数字、記号の混在を明確に禁止し、新たな基準を設けた。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- ドローンいらず? 飛行動画作成できる「Google Earth Studio」登場
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- NTTグループは「AIがSI事業にもたらす影響」をどう見ている? 決算会見から探る
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい