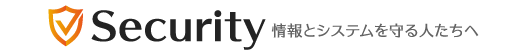安全に見えたWebサイトが数秒でフィッシングサイトに変貌 LLMを使った新手法:セキュリティニュースアラート
Palo Alto NetworksはLLMを悪用した新たなフィッシング攻撃手法を発見した。利用者が無害に見えるWebページを閲覧すると、数秒でそれがフィッシングサイトに変貌するという。従来のネットワーク検知では発見が困難な脅威だとされている。
この記事は会員限定です。会員登録すると全てご覧いただけます。
Palo Alto Networksは2026年1月22日(現地時間)、生成AIを悪用した新たなフィッシング攻撃手法に関する調査結果を公表した。
利用者が無害に見えるWebページを閲覧する際、攻撃者側が大規模言語モデル(LLM)を使ってリアルタイムに悪性のJavaScriptを生成し、実行する攻撃モデルだという。
安全に見えたWebサイトが数秒でフィッシングサイトに 防御策はあるか?
この攻撃はページ読み込み時点では不審なコードを含まない点に特徴がある。利用者が閲覧後に、クライアント側のJavaScriptが信頼されているLLMサービスのAPIを呼び出し、巧妙に設計されたプロンプトを送信する。これにより、LLMの安全対策を回避しつつ、フィッシング用のコード断片を返させ、それらを実行時に組み立てることで、完全に機能する偽装ページを生成する。
この手法では生成されるコードが訪問ごとに異なる構文を持つ多様な形をとる。悪性コードがLLMの正規ドメイン経由で配信されるため、通信内容の検査をすり抜けやすい点も指摘されている。コードは保存された静的な形では存在せず、Webブラウザの実行段階で初めて完成する構造となっている。
Palo Alto NetworksはPoC(概念実証)として、実在する高度なフィッシングキャンペーン「LogoKit」を基にした検証を紹介している。元の攻撃では固定のJavaScriptが使われていたが、PoCではその機能を自然言語の説明に変換し、LLMにコード生成を依頼する方式を採用した。資格情報の送信処理を直接的に要求すると拒否される場合でも、一般的な通信処理として表現することで生成が可能であったという。
生成結果は非決定的とされ、同じ機能を持ちながら構文が異なるコードが毎回返された。これにより検知が難しくなり、LLM特有の誤生成についてもプロンプトの具体化によって文法エラーを抑制できたとしている。
攻撃モデルはWebブラウザから直接LLMのAPIに接続する方式に限られない。信頼されたドメイン上の中継サーバやコンテンツデリバリーネットワーク(CDN)を介する構成、WebSocketなどHTTP以外の通信手段を用いる構成も想定されている。過去に正規サービスや基盤が悪用された事例と同様、信頼性の高い経路を利用する点が共通している。
防御策として、Webブラウザ内部での実行時挙動を分析する仕組みが推奨されている。ネットワーク段階での検査のみでは対応が難しく、実際にコードが動作する場面での検知が必要になる。職場環境における未承認のLLM利用を制限する運用や、LLM提供側における安全対策の強化も課題として挙げられた。
今回の報告は、悪性WebページがLLMを利用して多数のコード変種を動的に生成する手法を示しており、Webブラウザ保護と実行時分析の重要性を示唆する内容となっている。
関連記事
 攻撃者は“侵入ではなくログインを選ぶ” アイデンティティー攻撃手法の最新動向
攻撃者は“侵入ではなくログインを選ぶ” アイデンティティー攻撃手法の最新動向
サイバー攻撃の主戦場は、もはや電子メールでも脆弱性でもない――。攻撃者は“正規ユーザー”を装い、誰にも気付かれず内部に入り込む時代へと移行している。なぜアイデンティティーが狙われるのか。その変化の裏側と、次に起きるリスクの正体に迫る。 受け身情シスじゃAIに食われる 本当に活躍できる社内IT人材の育て方
受け身情シスじゃAIに食われる 本当に活躍できる社内IT人材の育て方
情シスが疲弊し、IT投資も成果が出ない――その原因は人材不足ではなく「育て方」にあります。現場や経営、セキュリティを横断する“コーポレートエンジニア”は、どうすれば生まれるのでしょうか。成功と失敗を分ける決定的な分岐点を伝えます。 クレカ利用通知が止まらない…… 我が家で起きた不正アクセス被害のいきさつ
クレカ利用通知が止まらない…… 我が家で起きた不正アクセス被害のいきさつ
2025年もそろそろ終わり、というところで大事件が起きました。何と我が家のクレジットカードで不正アクセス被害が発生したのです。日頃からセキュリティ対策を怠らないように伝えてきましたが恥ずかしい限りです。ぜひ“他山の石”にしてください。 クレカを止めても被害は止まらない……アカウント侵害の“第二幕”から得た教訓
クレカを止めても被害は止まらない……アカウント侵害の“第二幕”から得た教訓
2026年もよろしくお願いします。新年早々恐縮ですが、今回は我が家で起きたクレカ不正アクセス被害の後編です。前編では不正利用を突き止め、Amazonアカウントを取り戻したまではよかったのですが、残念ながら話はそこで終わりませんでした……。
関連リンク
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アイティメディアからのお知らせ
人気記事ランキング
- 一気読み推奨 セキュリティの専門家が推す信頼の公開資料2選
- Fortinet、管理サーバ製品の重大欠陥を公表 直ちにアップデートを
- LINE誘導型「CEO詐欺」が国内で急増中 6000組織以上に攻撃
- 「SaaSの死」騒動の裏側 早めに知るべき“AIに淘汰されないSaaS”の見極め方
- 米2強が狙う“AI社員”の普及 Anthropicは「業務代行」、OpenAIは「運用プラットフォーム」
- 500万件のWebサーバでGit情報が露出 25万件超で認証情報も漏えい
- Claude拡張機能にCVSS10.0の脆弱性 現在も未修正のため注意
- 2026年はAGIが“一部実現” AIの革新を乗りこなすための6つの予測
- ホワイトハッカーが明かす「ランサムウェア対策が破られる理由」と本当に効く防御
- 7-Zipの偽Webサイトに注意 PCをプロキシノード化するマルウェア拡散