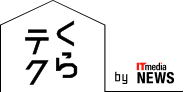3Dテレビの進化と分化――「2011 International CES」総括(2):麻倉怜士のデジタル閻魔帳(1/3 ページ)
米国ラスベガスで開催された世界最大級の家電ショー「2011 International CES」では、参考展示を含めて多くの3Dテレビが出品された。今年はAndroid端末に代表されるモバイル機器に主役の座を奪われたという見方もあったようだが、AV評論家・麻倉怜士氏の目にはどう映ったのか。詳しく話を聞いた。
――3Dテレビについて、今年は主役の座をモバイル機器に奪われたという見方もありましたが、実際には注目の展示が多かったようですね
麻倉氏: そうですね。業界全体が一様にBlu-ray 3Dに向かっていた昨年とはまったく異なる様相で、むしろ話題は非常に多かった。とくに大きく違うのは、“グラスレス”の裸眼立体視テレビが多く見られたことでしょう。
“グラスレス”は東芝のフレーズですが、展示会場ではLGエレクトロニクスも“グラスレス3D”をうたっていました。ほかに小型ディスプレイまでを含めると、サムスンとパナソニックを除くほとんどの大手メーカーが裸眼立体視の展示を行っていました。“グラスレス”を推進している東芝が展示に力を入れたのは当然ですが、意外だったのは、液晶シャッターメガネを推進しているソニーです。
ソニーは、24.5インチの有機ELパネル、56インチの4K2K液晶パネル、それからBlu-ray Discドライブ内蔵のポータブルタイプ、さらに3D対応のヘッドマウントディスプレイまで展示していました。関係者に話を聞いたところ、研究中のものまで引っ張り出してきたそうです。「東芝さんの術中にはまりました」と笑っていましたが、要は「ソニーもここまでやる」と世間に見せつけたわけです。
もう1つの傾向として、3D表示方式が多様化してきたという点が挙げられるでしょう。振り返ってみると、2009年はパナソニックだけがフルHDのフレームシーケンシャル方式で、他社は「Xpol」(円偏光フィルター)を使ったものが大半でした。2010年は、アクティブシャッターメガネを使用するフレームシーケンシャル方式に全メーカーが動いたのは周知の通りです。
そして今年は、裸眼、液晶シャッター、偏光と、それぞれのグループに分かれました。さらにいえば、偏光方式でもアクティブとパッシブに分かれています。これが良い兆候なのか、あるいは(規格乱立などの)悪い兆候なのか、現時点では分かりません。
液晶シャッターの進化
麻倉氏: まず、裸眼3Dには目もくれず液晶シャッター方式にこだわったのがパナソニックで、3Dの画質改善を積極的にアピールしていました。もともとプラズマパネルを使う同社の「3D VIERA」はクロストークが少ないのですが、それでも全くないわけではありません。とくにコントラストの強いシーンでは散見されていました。今回のCESでは、自発光のプラズマパネルが持つ階調性のリソースをクロストーク対策に集中させていました。
もう1つがアクティブシャッターメガネのクロストーク対策。CESの後にハリウッドのPHL(パナソニック・ハリウッド研究所)を訪ねた際に聞いたのですが、第2世代のアクティブシャッターメガネは、シャッターを閉じるときの精度を向上させ、クロストーク抑制に効果が大きいそうです。つまり、より“光を遮断する”性能が高いということです。
また、サムスンも展示ではクロストーク対策や黒の再現性に触れたりと、液晶とプラズマの違いはありますが、液晶シャッター方式の画質を向上させるという方向性ではパナソニックと一致していました。
一方のグラスレスは、東芝が積極的な展示を行いましたね。CEATEC JAPANでも展示していた56V型は、視野角や輝度が上がっていました。初披露の64V型は、56V型に比べるとまだ完成度が低い印象ですが、さらなる大型化にも期待が持てます。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR