AVアンプに新風を吹き込むか? NuForceの3製品を試す:潮晴男の「旬感オーディオ」(1/2 ページ)
「変化はチャンス」とばかりにアンプのデジタル化がムーブメントになった2000年代前半、米国から彗星のごとく、NuForce(ニューフォース)は現れた。オーディオの世界への新規参入は珍しいことではないが、ビジネスモデルとしてはなかなか成立しにくい状況が続くだけに、よほどの趣味人かお金持ちのバックアップがなければ起業は難しい。しかしながらこの企業は2002年、3人の青年だけでシリコンバレーにおいて設立されたのである。
後にメンバーの1人が退職してしまったので、現在はジェイソン・リムとケーシー・アンの2人が中心になって運営を行っている。ともにシンガポール出身だが米国留学からそのまま国籍を取得した、アメリカン・ドリームの体現者でもある。
2005年1月、米国のラスベガスで開催された「International CES」(国際家電見本市)で、ニューフォースは初の製品となるモノーラルのパワーアンプ「Reference 8」を発表する。この時点ではぼくはまだ彼らの存在を知らなかったが、翌年に発売されたプリメインアンプ「IA-7」が日本でもお披露目され、ついにその名前に出会った。今から7年前のことだ。
お弁当箱のような小さな筺体(きょうたい)に、立錐の余地がないほどのパーツを詰め込んだ作りにも驚ろかされたが、サイズからは想像もつかないパワフルなサウンドが出てくることにも大きな衝撃を受けた。アナログオーディオの世界からスタートしたエンジニアには考えられないような大胆な設計にはぼくも唸ってしまったのである。
そしてAVアンプに打って出た
コンパクトでスマートな製品が彼らのレゾンデートルになっているといってもいいが、ここで紹介するAV用のプリアンプも基本的にはその延長線上にあるように思う。今AVアンプは日本の独壇場である。進化するサウンド・フォーマットや4Kを初めとするハイレゾリューションの映像信号に対応するためには、膨大な信号を処理するための回路が必要になるため、弱小のメーカーではマンパワーと開発コストが追いつかないからだ。
音は出るのか、絵は出るのか、DLNAやAirPlayはちゃんと動作するのか、はたまたUSBメモリーやネットワークオーディオは機能しているのか、などなど……。HDオーディオの解凍に加えて、増殖する複雑多岐な機能についても総てを検証しなくてはならないからだ。一般的にAVアンプを設計する場合、マイコンの開発に係るエンジニアだけで50人近くの人員を投入しなくてはならない。だから海外の製品は一気に減った。
ところがである、そんな状況の中、ニューフォースからAVプリアンプ「AVP-18」と、HDMI端子を装備せず、アナログ入力だけで構成したマルチチャンネル・プリアンプの「MCP-18」、そしてマルチチャンネル・パワーアンプ「MCA-20」が登場したのである。しかもAVプリアンプとマルチチャンネル・プリアンプは超リーズナブルなプライス。これにもまた驚かされた。
アナログ方式のマルチチャンネル・プリアンプとパワーアンプは、その気になれば海外のメーカーでも作れなくはないと思う。しかしAVプリアンプとなると最前にも触れたように話は別だ。ニューフォースの場合、デジタルアンプ作りで培ったノウハウがここに生かされたということだろう、充実した内容に加えシンプルできれいな形にまとまっている様は、昨日今日から始めたメーカーにはとても真似のできることではない。
AVP-18には、マイクロホンを使ってスピーカー・コンフィギュレーションやレベルバランスを調整する自動音場測定機能が内蔵されている。そしてここに採用されているアプリケーションまで、なんと自社製のオリジナルという点に再びびっくり。時間と労力を惜しまない彼らならではの物づくりの一端を観た気がする。機能の1つとしてフロントチャンネルのバイアンプ駆動をおこなう場合、クロスオーバー周波数の分割を行うこともできるが、ここにもニューフォース流のアレンジが施されている。
使用パーツについては、オーディオ・グレードのものを用いて、このクラスで出来る最大限の可能性を求めていることも特長だ。HDMI端子は4入力1出力。アナログ音声出力はアンバランスの7.1チャンネルが一系統用意されている。この他にはSPDIFの同軸デジタル入力と光入力、さらにはUSB端子を装備してハイレゾ音源やネットワークオーディオの再生を可能にしているが、アナログ入力端子は一切ない。
「AVP-18」とペアになる8チャンネル構成の「MCA-20」は、PWM方式のアナログ・スイッチング方式によるクラスDアンプを採用し、チャンネルあたり4オーム負荷で278ワット、8オーム負荷でも150ワットの出力を叩き出す。このパワーアンプのベースとなったモデルは「リファレンスV3」シリーズだが、このシリーズと同様に独自のNFB技術を投入してリアルタイムでスイッチング周波数や電流、スピーカーに対するインピーダンスの変動を適正にコントロールすることにも成功している。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
Special
PR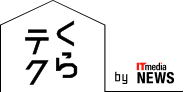
 2007年に国内で販売されたNuForceのプリメインアンプ「IA-7E」
2007年に国内で販売されたNuForceのプリメインアンプ「IA-7E」


